ここは小さな読書ブログですが、ページをめくるたびに世界の見え方が変わる瞬間を残しています。
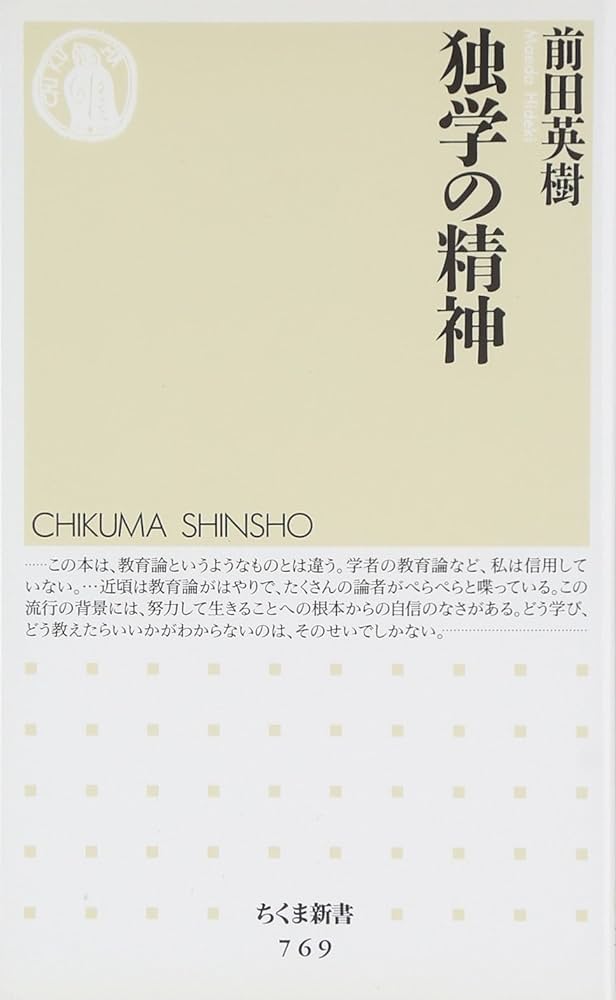
つづきを読みすすめた。
今日読んだ部分ではパスカルや本居宣長についてかかれていた。
パスカルといえば『パンセ』の「人は考える葦である」が有名である。
学を究めれば究めるほど、その限界が見えてくる。
著者は、あたかも世界を理解したかのように論破しにかかる学者を嫌悪する。
パスカル、本居宣長、二宮金次郎は独学を通して学を究めた。
今日の学者と対比させる形で独学の精神について著者は語る。
少子化に伴い大学全入時代をむかえ、大学生の学力が低下する。
下位の大学では高校までの範囲を復習させる。
なんでこんなことになったのか。
著者によれば、高校まで学んできたことは空虚なものであったからだという。
つまり、教育で行われていることは知識詰め込みで、忘却曲線に従って忘れていく定めにある。
それを再び大学で、忘れ物を取りに行くように拾いはじめる。
こんなことがあっていいのか。
という具合である。
学問は何のためにあるのか。
考えさせられる。
読書とはなにか。
ただ、ひとつ言えることは、たとえアマチュアでディレッタントと言われようが、読書を究めて東京大学に客員教授として招かれている人物を僕は知っているということである。
何事も王道だけが全てではない。
つづく
公開日2022-01-24
こうして書き残すことは、私にとって読書ブログを続ける意味そのものです。