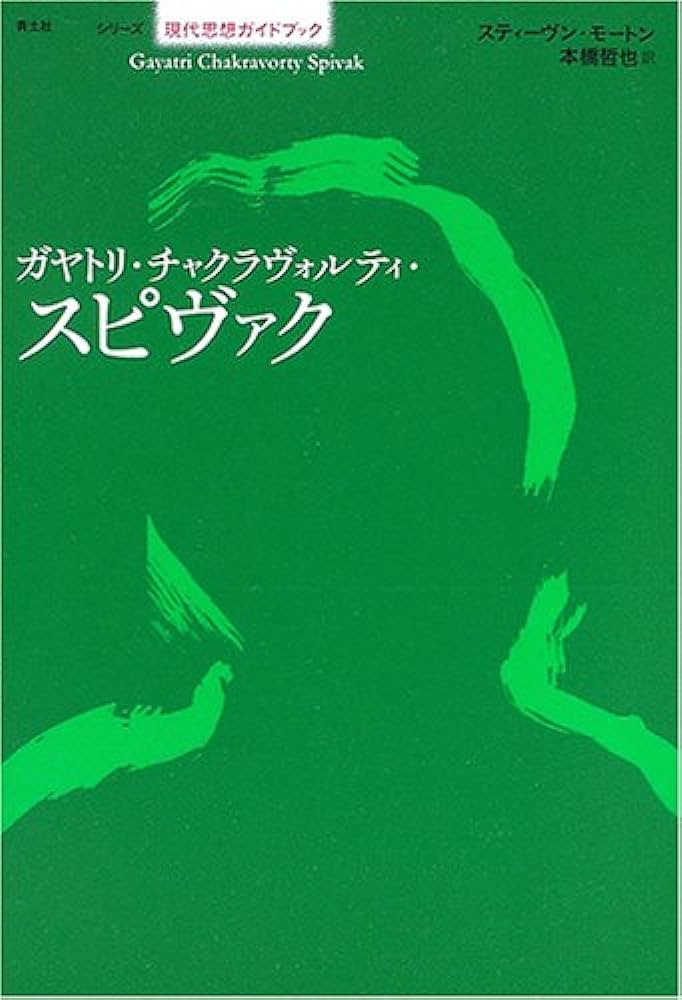
■株式会社青土社
公式HP:http://www.seidosha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/seidosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
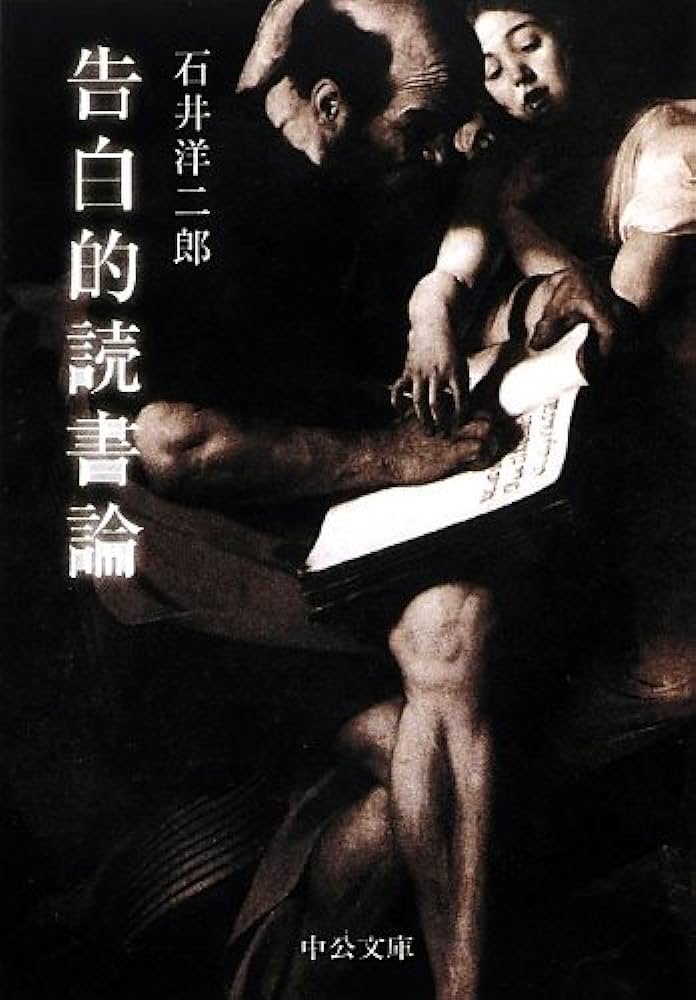
■株式会社中央公論新社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『告白的読書論』
「人はなぜ本を読むのか」という問いに対して、著者はひとつの理由として「自分を崩すこと」を挙げた。
ちょうど『忘れる読書』を読んだあとのタイミングでこの言葉に出会ったので、見事に著者の思考が落合氏と重なった。
なぜ自分を崩す必要があるのか。引用する。
“だが、成長することはつねに、硬直することと背中合わせである。” P186
人は年を重ねるごとに自分独自の意見が形成されていく。
人はそれを「成長」ともいえば、著者のように「硬直」とも言う。(悪く言えば頑固)
考えさせられた。
例えば自己啓発の本で、いつも同じような内容ばかり書いている作家というものは、一定数必ずいる。
良くも悪くも、同じことを何度も主張することは、それ相応の「自信」や経験に基づく「確信」があるからだと思われる。
しかし、「この人はいつも同じことを言っているな。成長を感じない」と思うことがなくはない。
固定性のなかの否定性。
それを取り除くための、「自己破壊衝動」としての読書欲。そういうものだろうと自分には思われた。
すると自然に思うことは、プラトン的な絶対主義(=善は相対的なものではなく形を変えない、不変なのも)にこの考えを接続させたときに何が言えるか、である。
池田晶子は「善い」という言葉を固定的で、不変なものとして語っているように見える。
固定的(=不変的)なものの、否定性をどう捉えていけばいいだろうか。
例えばカント主義も似ていて、「定言命法」という訳語から分かるように、原理としては「不変」である。
不変性に伴う否定性から絶えず逃れるような原理がこの中に含まれているだろうか。
そのようなことを考えながら今日はいろいろと本を読んだ。
また、本書では澁澤龍彦が訳したサドの『悪徳の栄え』で勃発した「サド裁判」について書かれていた。
規範から逸脱したただの告白文書に何の価値があるのか、という問いかけを著者は若いときにしたという。
その「無価値性」こそが文学的な価値をもたらしたのかもしれない、という逆説について語っていた。
なるほどと思った。
文学的な「価値」と、一般的な「価値」は対照関係にあるのかもしれない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『シリーズ 現代思想ガイドブック ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク』
スピヴァクの文体はあまりにも難解で、悪文とすら言われることがあるようである。
しかし自分はスピヴァクの、日本で行われた講演が本になったものを読んだが、語り口調はいたって普通で、ややこしい言い回しはなかった。
本書を読むと、その背景が理解できた。
敢えてスピヴァクは難解な言い回しを使っている。その理由は、あまりに政治的で、戦略的なものであった。
“(・・・)実は彼女がおこなっているのは、西洋の批判的思考の伝統的仕組みに従おうとしない仕方で、さまざまに異なる歴史や場所や方法論を注意深く結びつけようとすることだ。” P19
スピヴァクは簡素な文体を使わない理由として、次のように述べた。
“「私たちにはわかりやすい文はだますことがわかっています」” P19
自分はここまで読んで、何かから逃れたいという意図を感じた。
本書には、スピヴァクの指導教授が脱構築で有名なポール・ド・マンだったと書かれていた。
デリダの脱構築は、哲学の伝統を外側からではなく、内側から解体するものであった。
スピヴァクはこの戦略を政治に応用できると踏んだのかもしれない。
つまり、政治を外側からではなく内側から解体する。
このやり方にはサイードから批判があったりと、論争を生んだが、政治的な問題が多い今日、スピヴァクを読むことで何かしらのヒントや問いを引き出せたら幸いである。