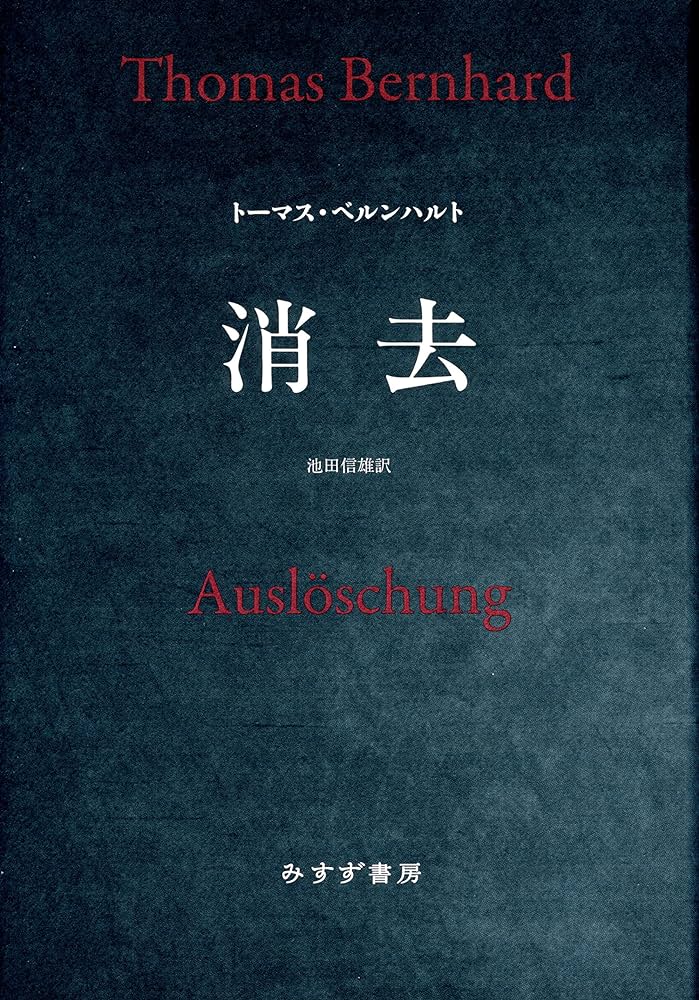
■株式会社 みすず書房
公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
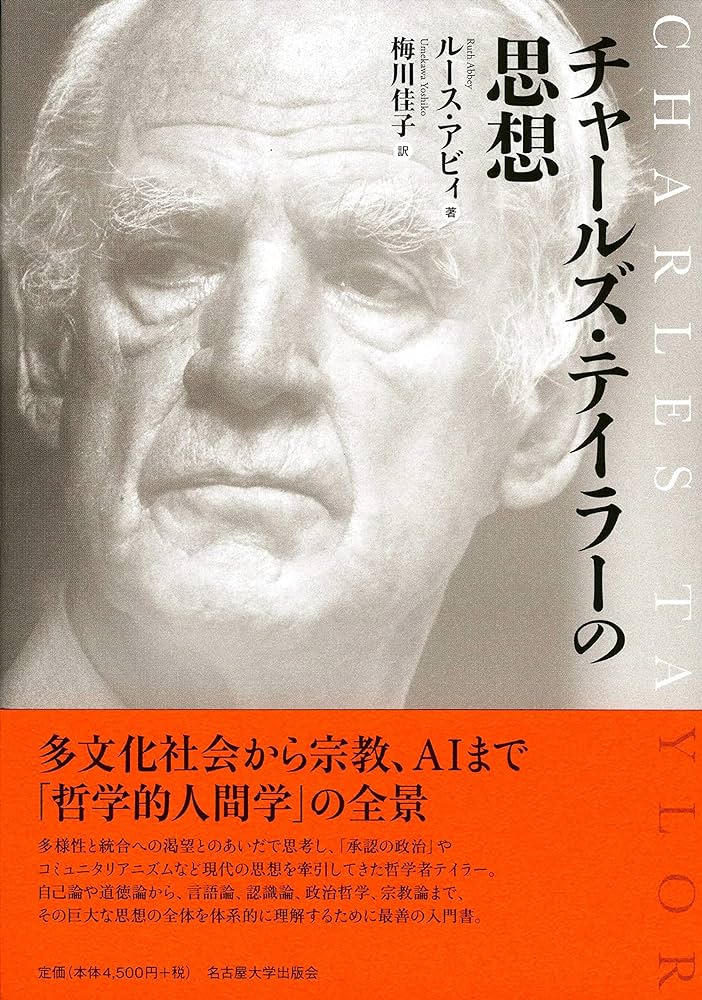
■名古屋大学出版会(国立大学法人名古屋大学)
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UN_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
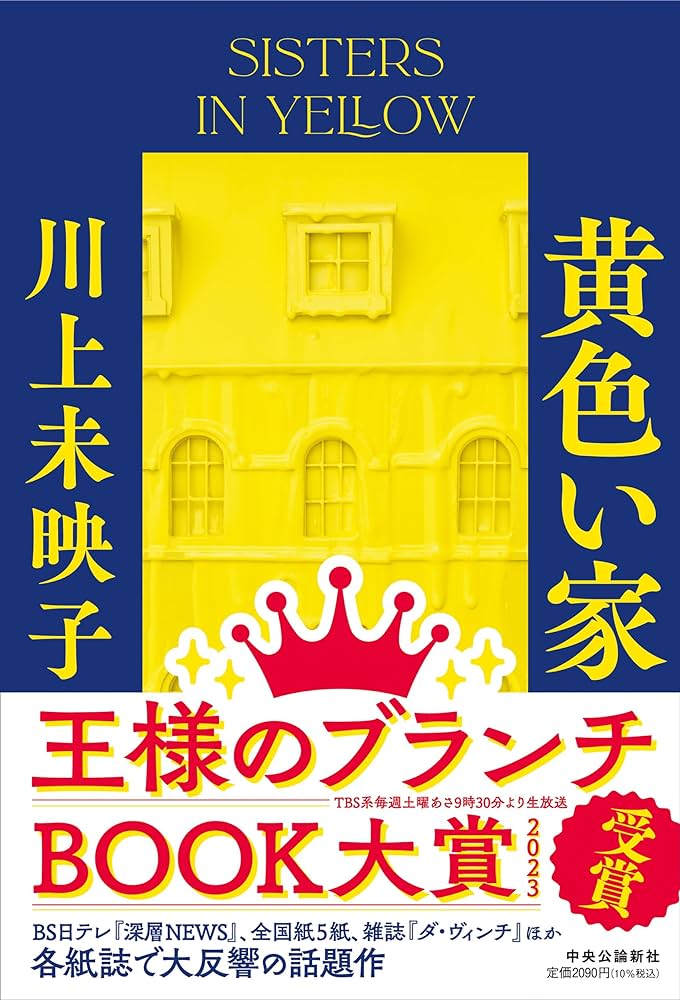
■株式会社中央公論新社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
その他数冊
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
明日の月曜日が雨になると、東京では五週連続の雨になるとのことである。
日曜日に雨もつらいが、月曜日の雨はもっとつらい。
今日は普段より多めの昼寝を取って心を休めることに集中した。
『黄色い家』やトーマス・ベルンハルト『消去』を読んだりと、今日は小説を多めに読んだ。
『消去』はただひらすら延々と悪口がつづく小説ではあるが、そのなかに若干のユーモアと普遍性が備わっていて、なぜ読まれるのかが少しだけ分かる気がする。
徹底した間接話法も個人的にはしっくりくる。
『消去』に埋め込まれている真理の重さは、全体を覆う雰囲気の暗さを凌駕する。そこにこの本の魅力がある。
・・・
『チャールズ・テイラーの思想』
X(旧 twitter)の自己啓発界隈(副業や起業を応援するアカウント及びそのフォロワーたち)の気持ち悪さはいったい何に起因するのだろうか。
あまりXを見ないようにしているが、Xは利用の仕方次第では非常に有益であるので今はやめるつもりはない。
しかしながら、時には不快なこともある。
全員がそうではないことは前提として、彼らは、往々にして自分に益のある人たちと仲間になろうとしていて、自分に益にならない、あるいは有害であると判断した人間は相手にしない。そういう心理があるのではないかと思えてならない。
「文句ばかり言う人とは関わらないようにしよう」
「不満ばかり感じていて成長しようとしない人とは関わらないようにしよう」
「成長できる人たちと仲間になろう」
このようなツイートが目に入ってきた。
ある種の排外主義、不寛容の象徴であり、「他者」という言葉が本屋でよく見かけるようになったのも納得できないでもない。
自分はこの空気があまりよくない気がしている。
3,4年前くらいにこのようなネオリベ的な発想をブログで批判し続けていた自分は、今では批判の回数は減ったにせよ、嫌悪感は相変わらず残っている。
資本主義を疑うという常識外れの思考を始めた理由のひとつに、自己啓発界隈の狂気が挙がるのは今でも変わらない。
チャールズ・テイラー、マイケル・サンデル、宮台真司教授、小室直樹。
自分はこの方たちの本に絶えず魅了され続けてきたわけであるが、『実力も運のうち』、『危機の構造』、『評伝 小室直樹』、『小室直樹の世界』などを読んで分かったのは、彼らが社会批判を痛烈に行っているのは、実は人間に対する期待値が相対的にかなり高い人だということの裏返しなのではないかということであった」。
つまり、彼らは共同体主義(=コミュニタリアニズム)の考えを共有している。そして自分も少なからず、その考えに賛同している。
ということで、チャールズ・テイラーについてはまだあまり思想の輪郭が捉えられていないので本書を読んでいる次第である。
・・・
今日はチャールズ・テイラーが人間と動物の違いについてどう考えているのかを理解した。
テイラーは、「自己言明」できるのは人間だけだとし、自分が持っている独自の「目標」を他者に伝えることは動物にはできないと述べていた、ということが書いてあった。
自分は「目標」よりも「無目的の合目的性」という言葉が好きであるが、自己啓発界隈は「目標」や「目的」という言葉が大好きなわけである。たしかに人間はそれを自己開示し、時には仲間と共有したがる生き物だと思われる。
動物はそこまでの言語コミュニケーションをしているとは思えない。それは、動物の行動様式において多義性があるとは考えにくいからである。
テイラーは『行動の説明』のなかで行動主義批判を行いった。テイラーがいうには、行動主義者は行動を動機づけるうえでの「目的の役割」を軽視しているようである。科学は形而上学的思考と問いを退ける。
自分はプラトンの「徳」が日本で一般的に理解されている「徳」の意味とは違った仕方で使っていることを鑑みて、翻訳書の言葉の意味を一度判断保留する癖がついた。
目的は自己啓発界隈のような、単純化された、「結果を達成するための行動」ではない。
アリストテレス『ニコマコス倫理学』のような最高善に向かう「過程」に近いかもしれない。
今日読んだ箇所をまとめるのはかなり難しい。
抽象度が高すぎる。
しかしあきらめてはいけない。ここで「ネガティブ・ケイパビリティ」が幅を利かせる。
すぐに答えを探そうとせず、テイラーの追求する「共同体的徳」について自分なりに考えてみようではないか。