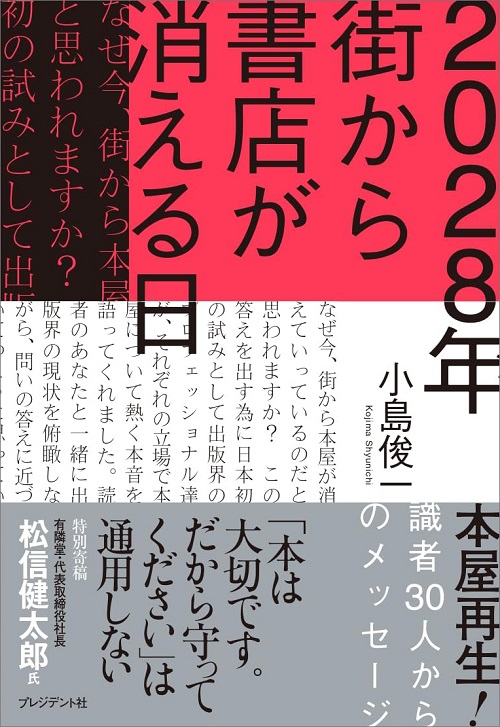
■株式会社プレジデント社
公式HP:https://www.president.co.jp/family/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/President_Books?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
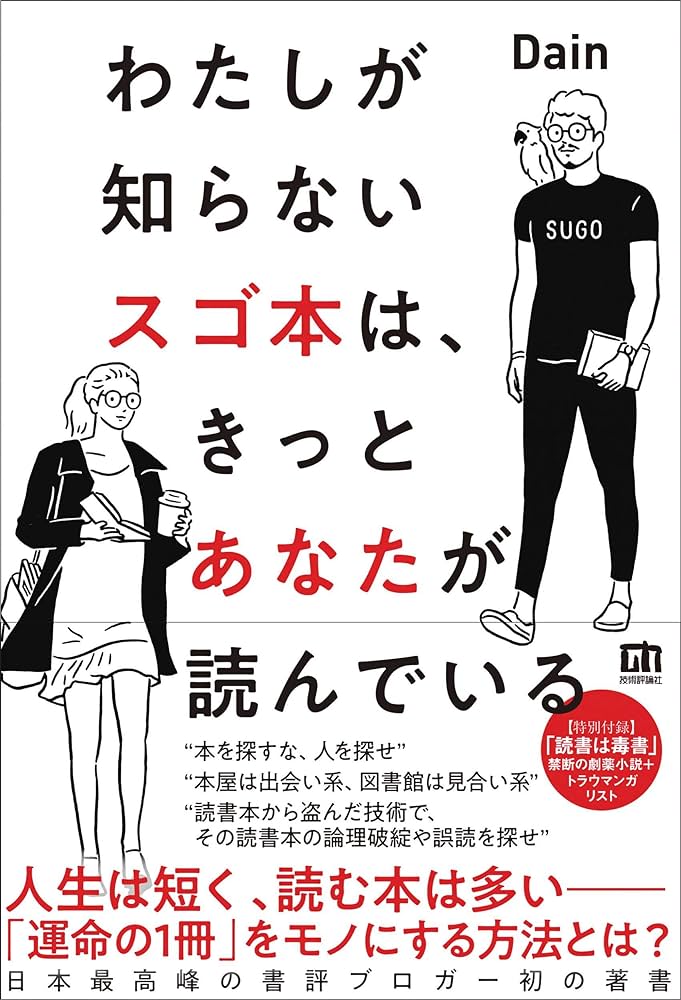
■株式会社技術評論社
公式X(旧 Twitter):https://x.com/gihyo_hansoku?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
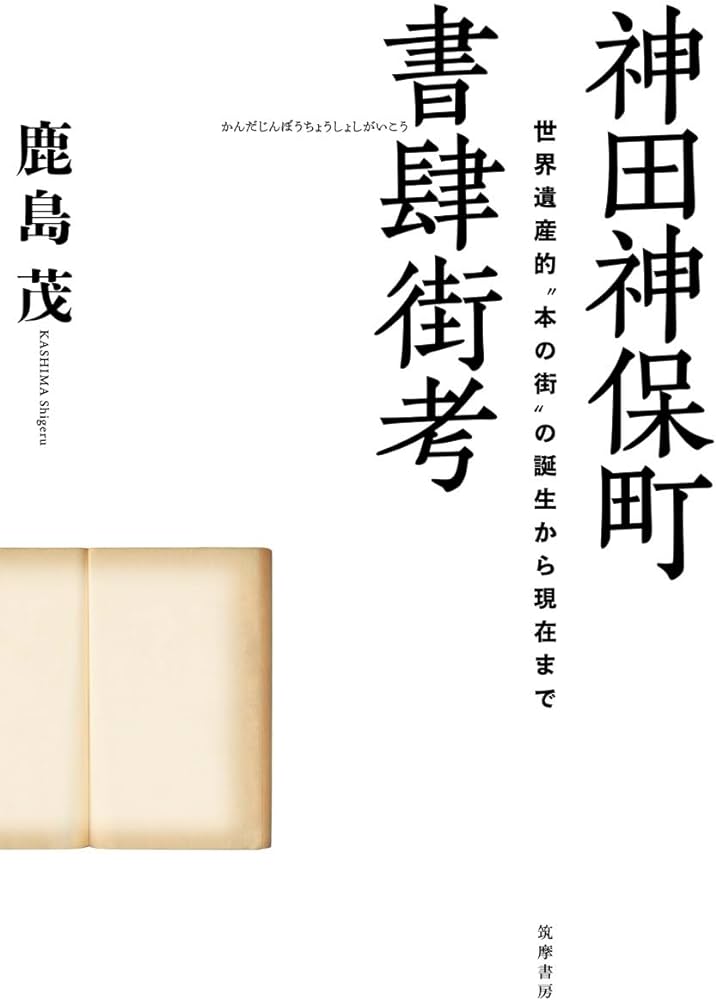
■株式会社筑摩書房
公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
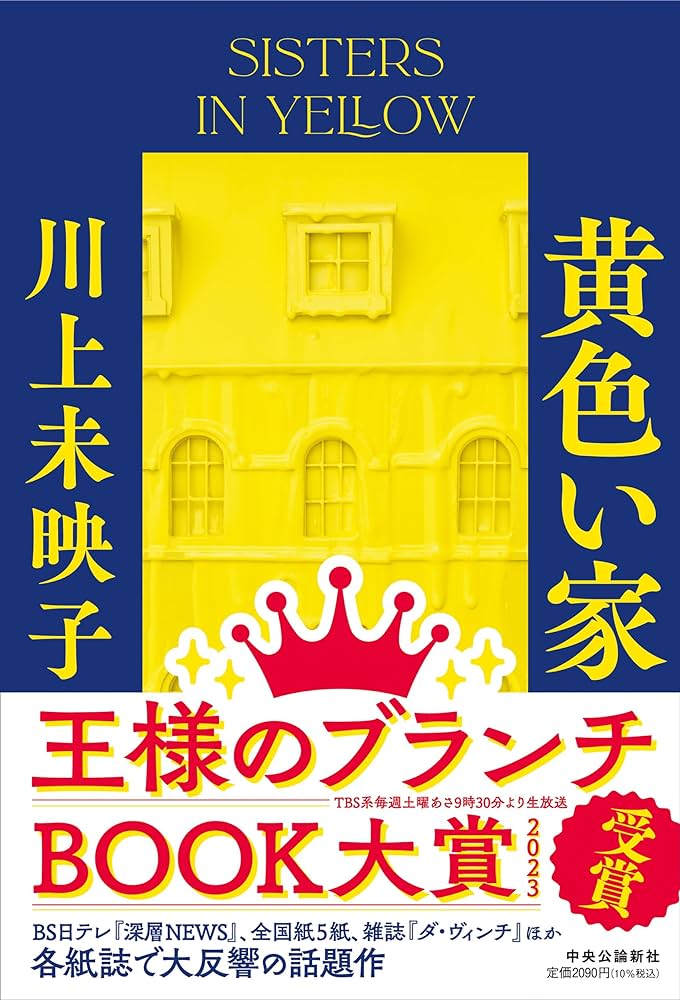
■株式会社中央公論新社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
「何のために本を読んでいるのか?」
と聞かれたとしたら、自分はどう答えるか。
「気分によります。無目的に、なんとなく読むこともあれば、調べるために読んだり、気分を紛らわせるために読んだり、研究の材料として読んだり、様々です」と答えるしかない。
本を書く人はどうだろうか。
「何のために本を書いているのか?」
「書きたいから書いています」といった答えが返ってきそうだ。
書くことにすべてを賭けている人の本に自分は感化され、情熱は連鎖し、自分はその情熱の次の人へ伝えるために何か行動を起こしたいと思いながらも、本があまりに売れなさ過ぎて、しまいには消滅してしまうらしい。
ビジネスとして成り立たなくなった本は、書く人の情熱と読む人の情熱をどこへ追いやるのだろうか。
私たちはどこへ向かって生きていくのか。
そんなことを漠然と思いながら、いろいろと読み漁った。
・・・
『2028年 街から書店が消える日 ~本屋再生!識者30人からのメッセージ』
書店の危機に関する本は沢山世に出ているが『2028年 街から書店が消える日 ~本屋再生!識者30人からのメッセージ』のタイトルはいつも以上にインパクトがあった。具体的に2028年に街から消えると言い切っている。
実際それは現実的で、2010年代以降、自分の地元では三省堂書店、紀伊国屋書店、文教堂書店などが次々と商業施設の中から消え去った。中小企業の書店はもっと多いかもしれない。そして古本屋も多く消え去った。逆に新しく生まれた店舗は明らかに指の数より少ない。
『2028年 街から書店が消える日 ~本屋再生!識者30人からのメッセージ』には有隣堂の社長からのメッセージも収録されているので、ひとまずそこを読んでみた。
社長は言う。自分を高め、自己実現するには自分の力で考える力が必要であり、そのためには経験、体験、知識、教養、疑似体験などが必要とされる。本は後者の3つ(知識、教養、疑似体験)をカバーできると社長は語った。
本には文化的な意義のある商品として認知されているが、だからといって「文化財なので守ってください」という主張は通用しないと社長は語る。
人が必要としなくなれば淘汰される。本も例外ではない。それだけ。
イノベーションを起こし、活性化せよというのが社長の主なメッセージであった。
『百年の孤独』のなかに独学の数学者がいるらしい。そしてその数学者は自力で二次方程式の解法を発見したあとに亡くなってしまうそうだ。Dain氏はショウペンハウアーの読書論を「半分正しい」としている理由に、自分で考えることの危うさをこの数学者に見出している。
『百年の孤独』は読んでいないので詳しくは分かりかねるが、その数学者は、二次方程式の解を見つけるために数学をやっていたのではないと自分は思う。もっと深い、より真理へ到達するために数学をやっていたのだと思われる。であれば巨人の肩に乗ったほうが明らかに人生を正しい方向に向けることができる。そのためには本が必要だ。
そういう意味では社長の言葉は間違っていない。本は勉強の道具ではないが、ひとつの機能として、知識と教養を提供してくれることは疑いない。
・・・
昔なにかの本で読んだが、本はもともと必要から生まれたらしい。
それが今では逆転し、必要とされるような本を作っている。これが現代の出版業界を傾かせている要因なのだと。
情報が氾濫している現代、そもそも自分は何を求めているのかすら分からない人は多いのではないだろうか。
だからその不安を煽るような製品、不安を解消させてくれる本が売れたりするのである。
自分はこの風潮がつづくと消滅に向かう気がしている。
情報だけの本は新聞のようにデジタル化されアーカイブ化されておしまいな気がしてくる。
商業的にそういう本しか残らないならいっそ書店は消えてしまっていい。
そうでない本が必ず残るわけであって、情報に埋もれた山の中から必要な本だけを取り出してくれる、そういう人が必ず現れる。
自分もそうなりたい。そしてそのような人を応援したい。
つづく