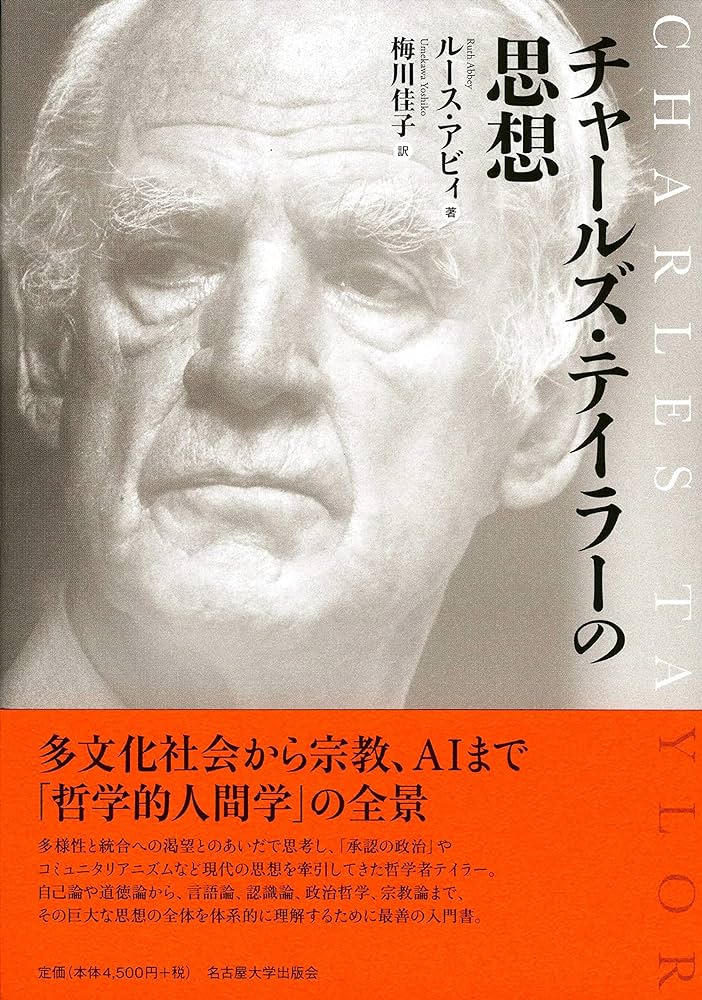
■名古屋大学出版会(国立大学法人名古屋大学)
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UN_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
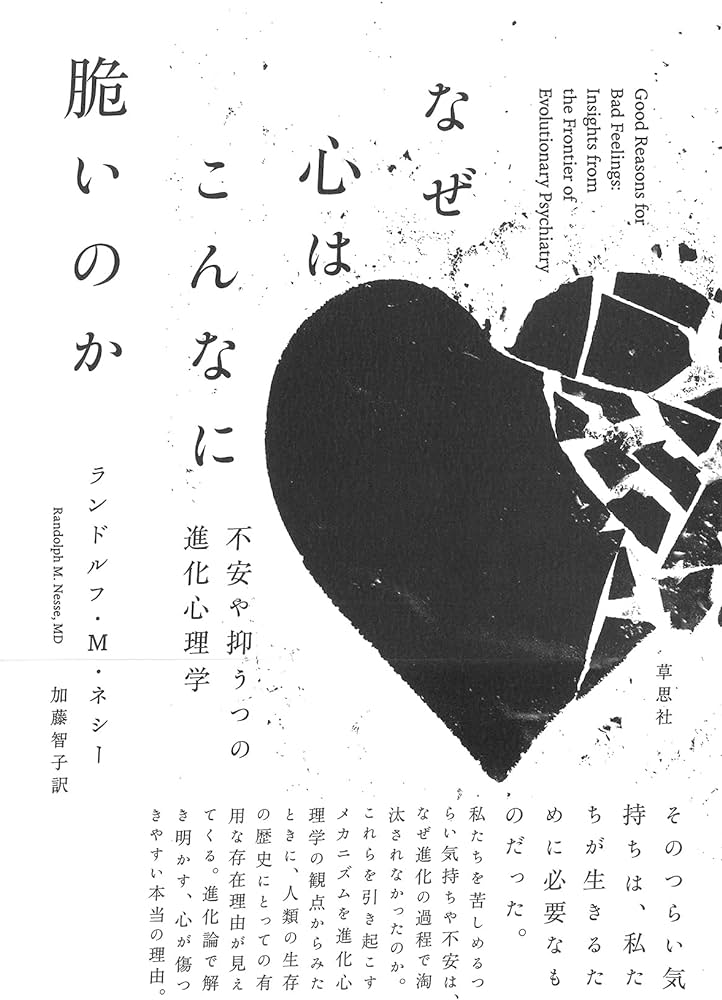
■株式会社草思社
公式HP:https://www.soshisha.com/
公式(旧 Twitter):https://twitter.com/soshisha_SCI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
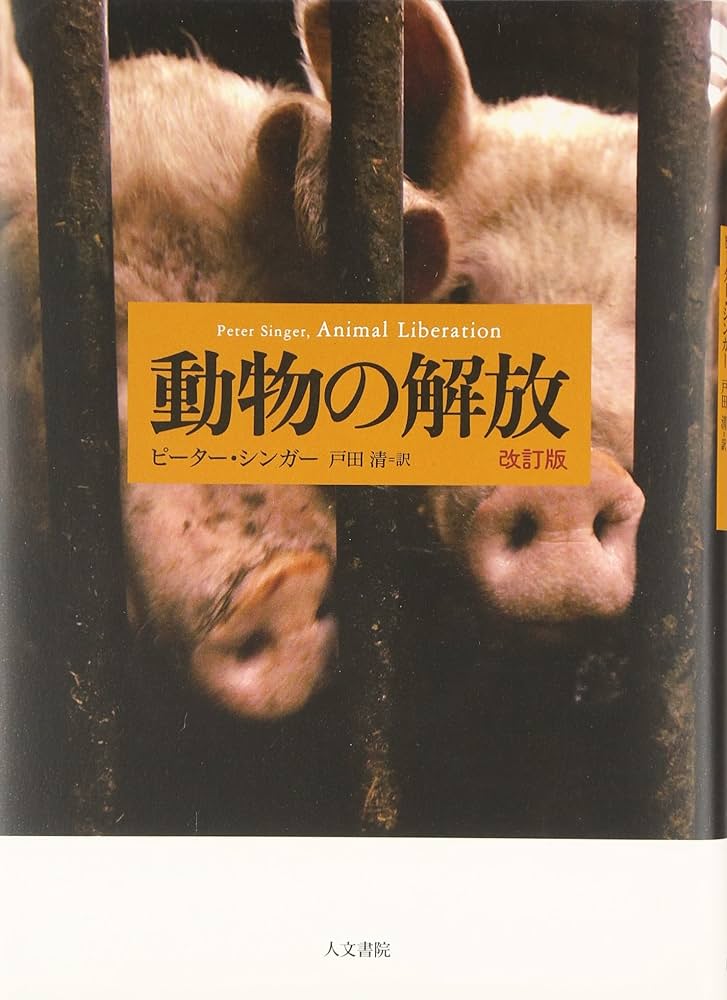
■株式会社人文書院
公式HP:http://www.jimbunshoin.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/jimbunshoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『動物の解放 改訂版』
第三章の終わりの手前まで読み進んだ。
ピーター・シンガーの言葉を信じ、第三章まで読めば今までの見方が変わるということが割と現実的になってきた。
ヴィーガンになりたいと思うほどの強烈な影響は受けてはいないが、自分で調べることの重要性に関しては今まで以上に強く意識させられた。
一昨日読んだ、有隣堂の社長の言葉は「自分の力で考え、そのために本は助力となる」というものであった。
思考と本が相乗効果を発揮することでより高い位置から物事を見ることができる。今日、この本を読んで改めて思った。
本屋が消えるという現象は、個人的にはあまり嬉しくはないが、これは裏を返せば、ネットが自分で考えたり、自分で資料を取って調べるということの肩代わりをしていくようになるということだ。
しかしながら、まとまった情報や信頼性についてはまだまだ紙が強い。この力関係が完全に逆転したとき、紙は敗北するのである。
・・・
今日も相変わらず、動物がいかに苦しんでいるのかについて読み進めた。
少し牛乳を飲む気が失せた。というのも、強制的に子供を隔離される苦しみは、想像を絶すると言える。
アドルノはアウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮であると述べたみたいだが、自分は「この世界において、倫理について語ること、書くことは可能か?」と問わざるを得なかった。
言うことと実際に行っていることを一致させるには、自分自身が完全に社会から隔離しなければならない。
全ての経済活動は、何らかのかたちで必ず動物の搾取と関係している。(飲み物、食べ物、服等)
メモ
“肉用仔飼育の本質は、監禁された貧血状態の仔牛に高タンパクのエサを与えて、高級レストランで食通たちに出される、やわらかい淡色の肉をつくるというものである。” P166
“大規模のフィードロットはいまや米国の牛肉の三分の一を占めている。それらは実質的に営利本位の事業で、しばしば税金の軽減を求める石油会社やウォール街の金融資本が出資している。” P178
・・・
『なぜ心はこんなに脆いのか: 不安や抑うつの進化心理学』
著者は「抑うつは何の役に立つのか?」という問いを展開させる。
その前提には、抑うつや不安には必ず「有用性」があるという想定である。
しかし自分は、この前提はおかしいのではないかと思い始めた。
というのも、『動物の開放』を読んで思うのは、明らかに苦痛に伴うネガティブな感情は度を越えると、むしろ有害ですらあるからである。
ストレスによって早死にする家畜の例がこれでもかというほど示されている。
であれば抑うつ気分や不安には何一つ有益性はないと考えて妥当ではないか。
仮に意味があるとしたら、それは「警告」としての、信号としての情動に過ぎない。
しかし抑うつはただの「警告」だとは思えない。それ自体が病気である。著者はそれ自体が病気とみなされがちであること(うつ、不安等)を否定しているが、とてもそうは思えない。
やや進化論にこだわり過ぎているのではないかと思えた。
根本的に治さなければならないのは不安や抑うつを誘発する背景である。
不安や抑うつの有用性に着眼していくのは、それほど意義のある問いだとは思えなかった。
ピーター・シンガーの本は射程範囲が広く、精神疾患の問題とも接続し得る。
メモ
“自然選択においては、私たちの幸福などどうでもいい。進化の計算式において重要なのは、繁殖の成功だけだ。” P88
・・・
『チャールズ・テイラーの思想』
チャールズ・テイラーの思想はピーター・シンガーのそれよりも高度に抽象的で、輪郭がまだ見えない。
わずかに見えたのは、歴史がいかに自我を形成するのかについて深い考察をしている、ということくらいであった。
しかし近代の成立と自我について考えだしたらキリがない。
このあたりは社会学の力を借りたほうがいいかもしれない。
時間があればタルコット・パーソンズも少し読んでみたい。コミュニタリアニズムの人道的な空気は嫌いではないが、どことなく抽象的すぎるきらいがある、自分はそう感じる。
メモ
“善の概念は、それらが実践され、実践が善の概念を表現し永続化するときのみ、実際に維持されるのである。(1978a : 139,153)。” P101
“人は内面に向かうによって、人を善性に導く自然の声をきくことができる。(・・・)生の自発的な流れは、自己の中を通って内的な自然の声に達する。” P112