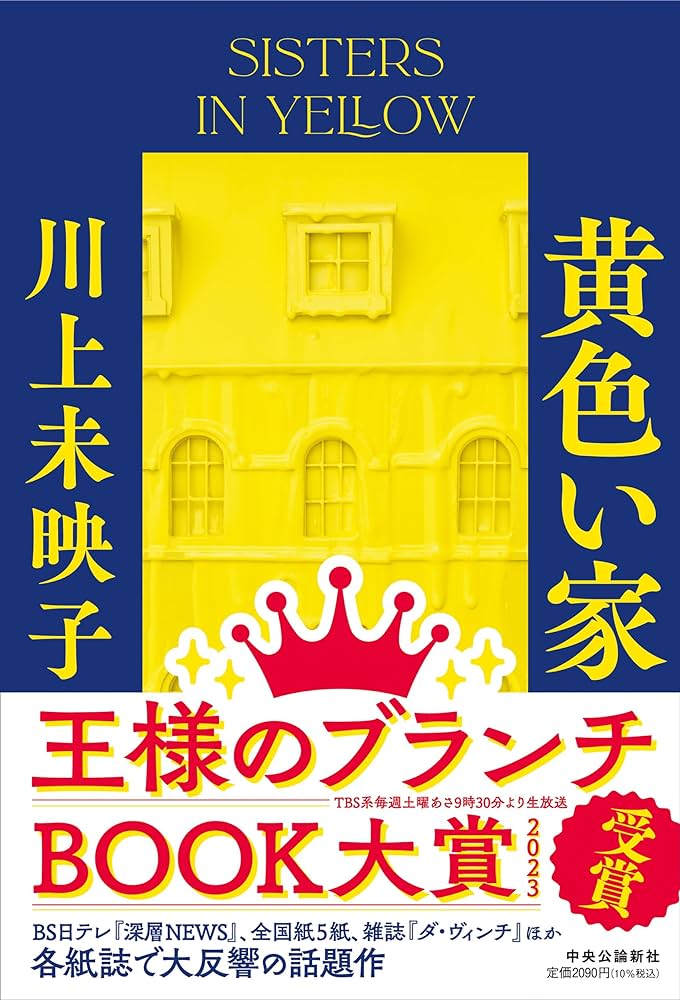
■株式会社中央公論新社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
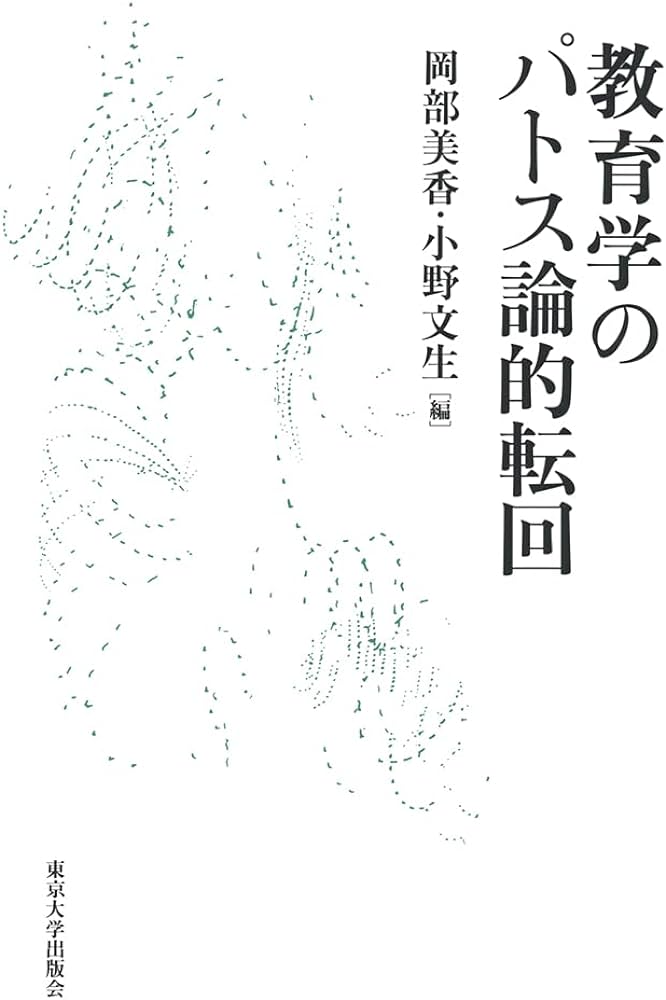
■一般財団法人東京大学出版会
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
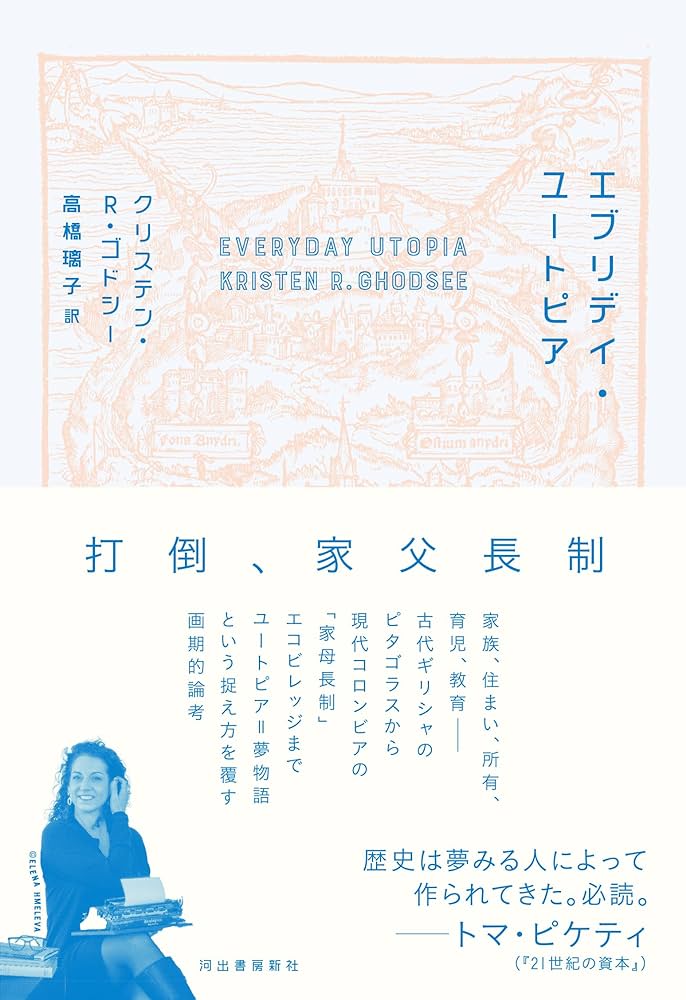
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
今日はほとんどの時間を『黄色い家』の読書に費やした。
320ページくらいまで進んだ。
伏線回収という言葉があるが、本書の最初にある出来事について書かれていて、その真相が少しずつ明らかになっていくという構造になっているので、謎解きのようなミステリな小説ではないが、展開が気になるようにさせてくれる小説となっている。
物語は非常に長く、時間もゆったりと流れるので、自分が生きているこの世界とパラレルの世界でこの本の物語が進んでいるような感覚を覚えた。
・・・
『エブリデイ・ユートピア』
共同生活によって家賃や家具の費用を抑えることができる。コリビング物件というものについて紹介され、言葉通りリビングやダイニングルームを共有して使う物件の実態について書かれていた。
そこで育った子供たちは一人でいるよりも集団でいることを好む傾向にあるという。子供たちは集団でいるほうが幸福度も高い。宮台真司『14歳からの社会学』では、グローバル化とともに「他者」というものの定義が変わっていき(昔は誰がどの辺に住んでいるのか知っていたが、今はプライバシーの重視とともに、分譲マンションもニーズに沿って増えていき、誰がどこに住んで言うのか見えにくくなっている)、となりに誰がいるのか分からなくなり、功利行為主義から規則功利主義へと移行していくストーリーについて書かれていた。
”スピード重視の多忙な社会のなかで、私たちはそれと気がつかないまま、便利のために人とのつながりを犠牲にしているのです。” P84
・・・
69ページに、プライバシーとコストについて書かれていた。
”またスターシティの共同創業者ジョン・ディショッキーは、ニューヨーク・タイムズ紙の取材で、過度のプライバシー確保はお金の無駄だと指摘しています。” P69
個室の多い、現代の日本の過程において、一家にエアコンが二台、三台が当たり前になっているのではないだろうか。エアコンに限らず、あらゆる家電商品がひとりひとりにあてがわれるのが今の主流となっている。
巨視的に見れば、このディショッキーという人物の発言にはうなずける。
家賃が高い、物価が高い、必要最低限の生活用品を揃えるにも工夫が強いられる。
新卒の新入社員の給料は、都心へ住めば贅沢はなかなかできない。
それは、部分的にお金の無駄遣いによるものだ。プライバシーは大事だが、たしかによく考えてみれば、節約や生活の工夫(今でいうポイ活など)が強いられる世の中はやや歪に見える。
・・・
『教育学のパトス論的転回』
普通に考えて、営利活動は合理性の所産である。
しかし近代以前はそうではなかった。
帳簿という仕組みが発生した瞬間、生活が営利という目的を達成するための仕事となり果てた。
人間の活動は概ねほぼ仕事の時間で占められる。よって日々の活動は合理的でなければならない。
そして合理性から外れていく人間は「使えない者」として排除されていく。
“(・・・)世間一般の平均から外れないことが人々にとって最も重要な懸案事項である。このため、おもて向きの合意のみが重んじられる世間話や、ただ知るための知識欲、ことの真偽がはっきりしない曖昧さといった現象が日常生活で幅を利かせる。(・・・)自己の固有の在り方から目を背けたありようのことを、ハイデッガーは、人間存在の非本来性(Uneigentlichkeit)と呼ぶのである” P237
池田晶子がいうには、世の中、生きるために食べる人と、食べるために生きる人がいる。
なんのために何をしているのか、深いことを括弧にいれ、ひとまず人の役に立つこと、すなわち利益になることを考える。むしろ、そうでないと平均から外れていく。
「なんで仕事してるかって?食ってくために決まってるじゃないか」
後者は「自己固有の在り方から目を背けた」人であろう。
ハイデガーの哲学はあまりに近づきがたく、『存在と時間』を読む気になれないが、ハイデガーも実はウェーバー問題を強く意識していたのではないだろうか。そのような疑問が浮かんだ。