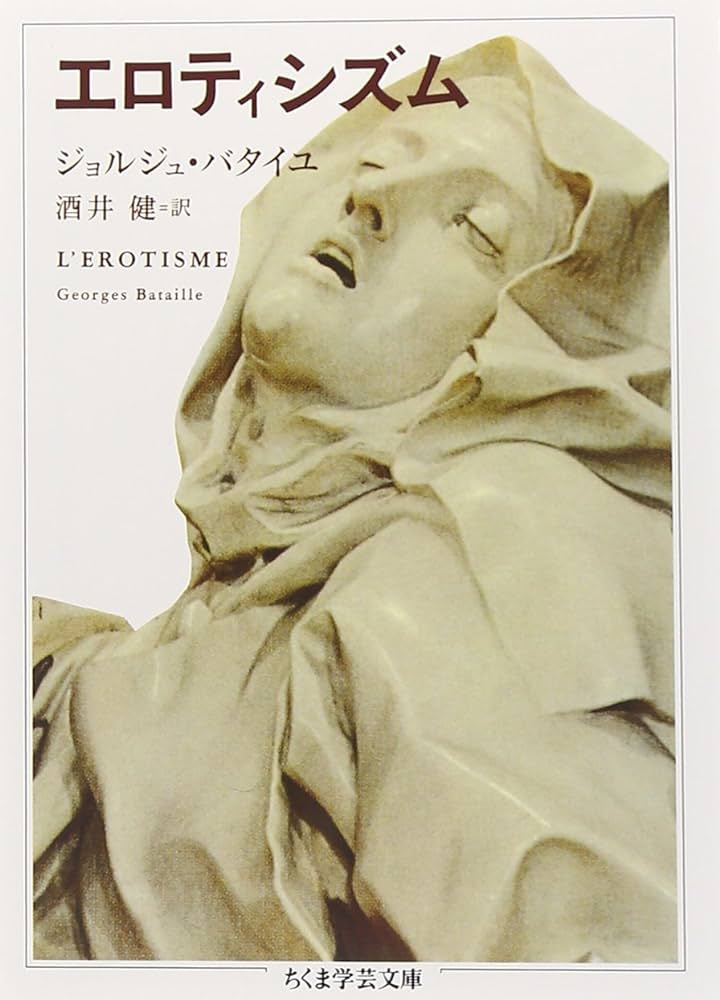
■株式会社筑摩書房
公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
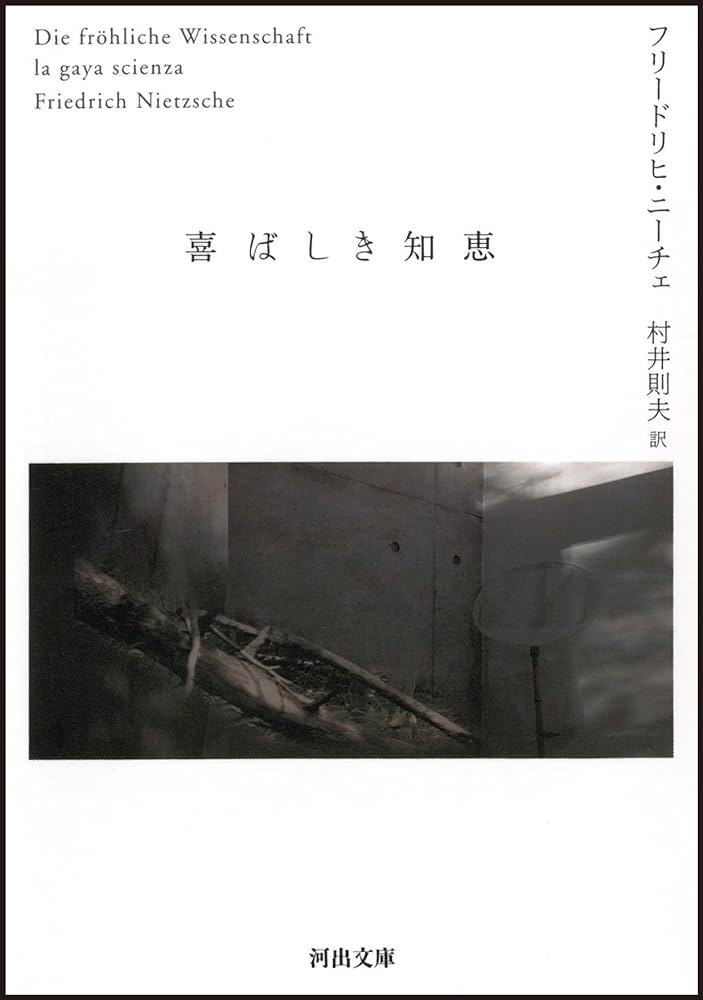
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
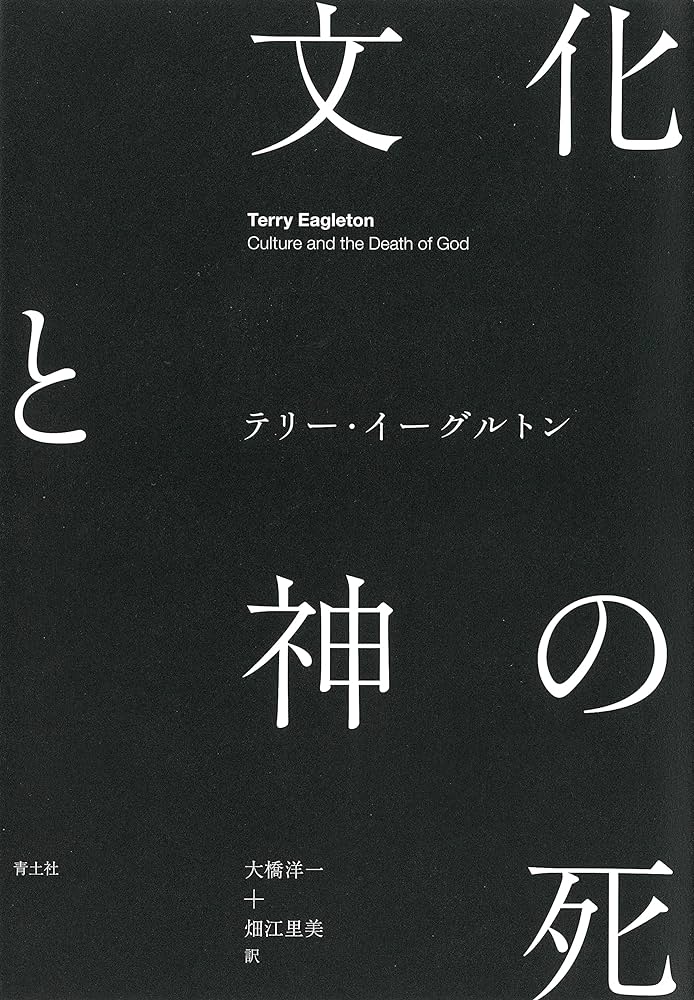
■株式会社青土社
公式HP:http://www.seidosha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/seidosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
メモ
“(・・・)しかし芸術は民衆を熱くさせないまま放置する傾向がある。芸術は宗教信仰におきかわるにはあまりにマイナーな事象であって、宗教信仰にように、無数の男女の日常的行動をもっとも崇高な真理へとつなげるなど望めそうもない。この点で、宗教とわずかながらでも肩を並べることのできた歴史上の象徴体系は存在しない。結局のところ、観念論は、ロマン派の著述家たちのなかからも反対の声があがったように、あまりに頭でっかちな原理となったのだ。” P91-92 『文化と神の死』
日記
ついこないだ、ひとつの仮説を立ててみた。
性に執着する傾向にある人間は、そうでない人間と比べて死への恐れが相対的に大きいような気もしないでもなかった。
性に執着するというと語弊があるので、別言すれば、性に対する関心が高く、審美主義の傾向がある人間としておく。
サンプルが少ないのでこの仮説にはあまり自信がない。
しかしながら、何人かの著述家の生死に関する考え方、性に対する考え方を俯瞰してるとそのような仮説が立ったのであった。
資本主義批判の延長線上でこのことを考えているわけであるが、深い地点にまで探究を進めればなにかヒントが得られるような気がしてくるのであった。
哲学者の中山元氏によれば、バタイユは3B(バタイユ、ベケット、ブランショ)と呼ばれる、難解な思想家のひとりとされるゆえに、やはり文章はじっくり読んでいかないと頭に入らない。
それでもところどころ、示唆的な表現が見受けられる。
人間の欲望は、その要因を内に持ちつつも対象は常に外部である。ということをバタイユは書いていた。
今更という感じはあるが、よくよく考えてみると不思議なものである。
自分が何を欲している分からない時はよくあることだ。
お腹がすいたとしても、具体的に何を欲しているのか曖昧な場合が多い。
どうしても「あれが食べたい」というときもあるにせよ。
この欲望が貨幣の空間に入ると話はさらに複雑になっていく。これをバタイユは『エロティシズム』のなかで経済と絡めて論じている。ちくま学芸文庫では経済と欲望に関するバタイユの論考が多い印象がある。
興味深いので、追える範囲で追っていきたい。
・・・
仲正昌樹教授は、ニーチェの文章をギリシアの歴史や神話などから読み解く必要性を『ニーチェ入門講義』(作品社)のなかで述べていた。
自分も、そろそろホメロスくらいは読んでおこうという気になってきた。
ニーチェの道徳批判、宗教批判はギリシアの歴史の知識なしには100%理解できないと今更感じ始めた。
テリー・イーグルトンの本も非常に興味深い。いっきに100項まで読み進めた。
仲正昌樹教授が修士論文で出したような内容と重なっているところがあるように思われた。
哲学と芸術の位置関係、芸術としての文学の今日における可能性。
そういうものをこれから考えていきたいと思う。