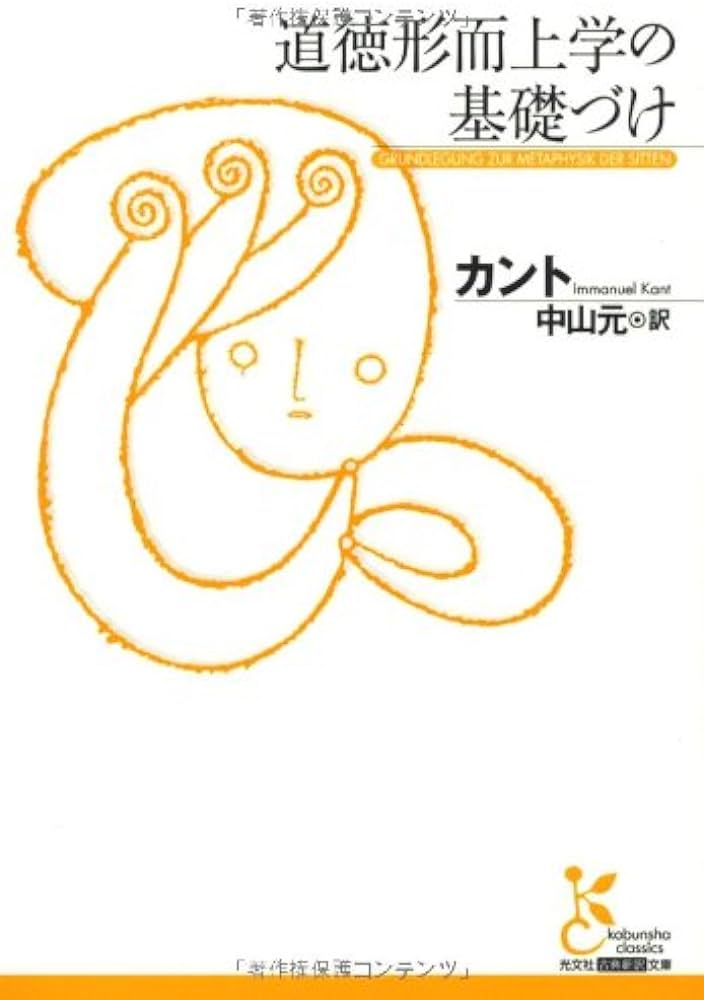
■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
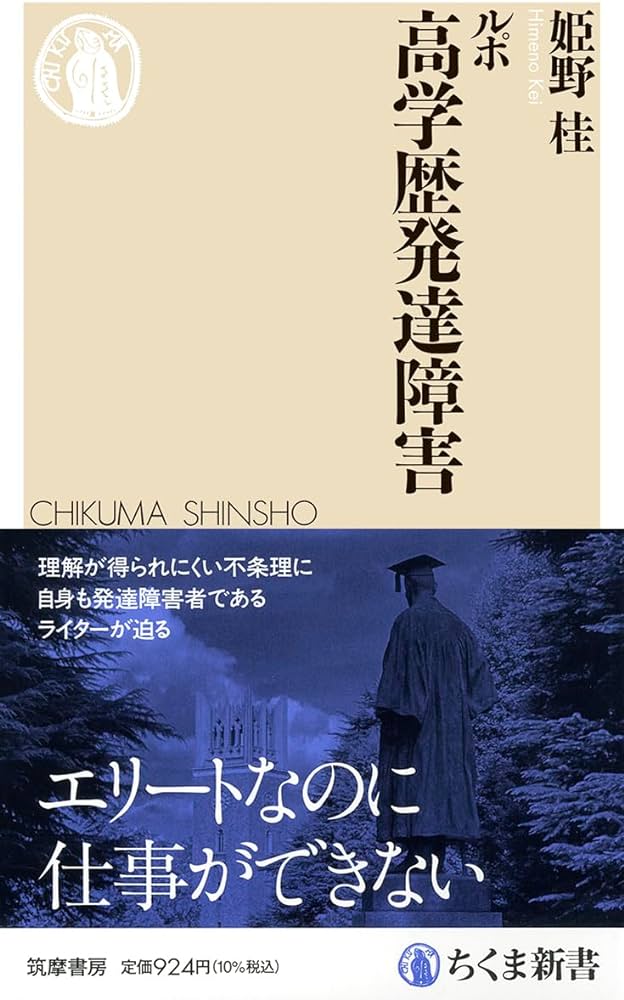
■株式会社筑摩書房
公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
メモ
『道徳形而上学の基礎づけ』
カントの定義する「義務」
“義務とは、行為の法則にたいする尊敬の念に基づいた行為の必然性であると表現しておこう。” P50
カントの定義する「尊敬」
“わたしは、直接自分にとって法則として妥当すると判断するすべてのものを尊敬する。尊敬するということは、外部からわたしの感覚能力に与えられる影響の媒介なしに、わたしの意志が直接に法則に服従するという意識をもつことである。だから意志が法則によって直接に規定されているという意識を、そして意志が法則によって直接に規定されているという意識が、尊敬なのである。” P54
日記
道徳法則(自由の法則)を、義務によって遂行すること。
「それ自体に価値のある行為の条件」について今日はいろいろと学びを得た。
義務というとどこか「責任」という言葉とセットで語られがちである。そして堅苦しく、説教臭い。
(カントは説教臭いと感じる人も多いかもしれないが、自分は自らの意志でカントを読んでいるのでそうは思わない)
それ自体価値のある行為を遂行するためには「義務」を行わなければならない。
義務には「尊敬」というフィルターを通過しなければならない。
そして尊敬とは、「意志が法則によって規定される意識」であるとカントは書いた。
まだ自分のなかで普遍妥当性のある法則というものの輪郭がつかめない。
極論をいえば、人間が成していること全てには必ず悪い部分も含まれるという、ある種のニヒリズムが自分の意識の根底にあるからである。
少しずつ吟味しながらじっくりと読み進めたい。
・・・
『ルポ 高学歴発達障害』
100ページほど読んでみた。
ペーパーテストだけできても意味がないというのは、薄々誰でも理解するようになると思われる。
大学教育は学問だけやればいいという意見もある。大学は勉学を行うところであって、大学は就職予備校ではない。
自分は発達障害という言葉はあまり好きではない。
ビジネスの現場に適応することだけが発達の目的ではない気がするのである。
発達の定義がなければ、適応の定義もない。
何をもって発達とみなせるのか。何をもって適応とみなせるのか。
それがビジネスの現場ですべて決まるのか。なんと狭い世界だろう。
このルポに載っている方は、適材適所を見つけるのが苦手だったのかは分からないが、最初につまづいてもいつかは必ずどこかの場所で落ち着くはずである。