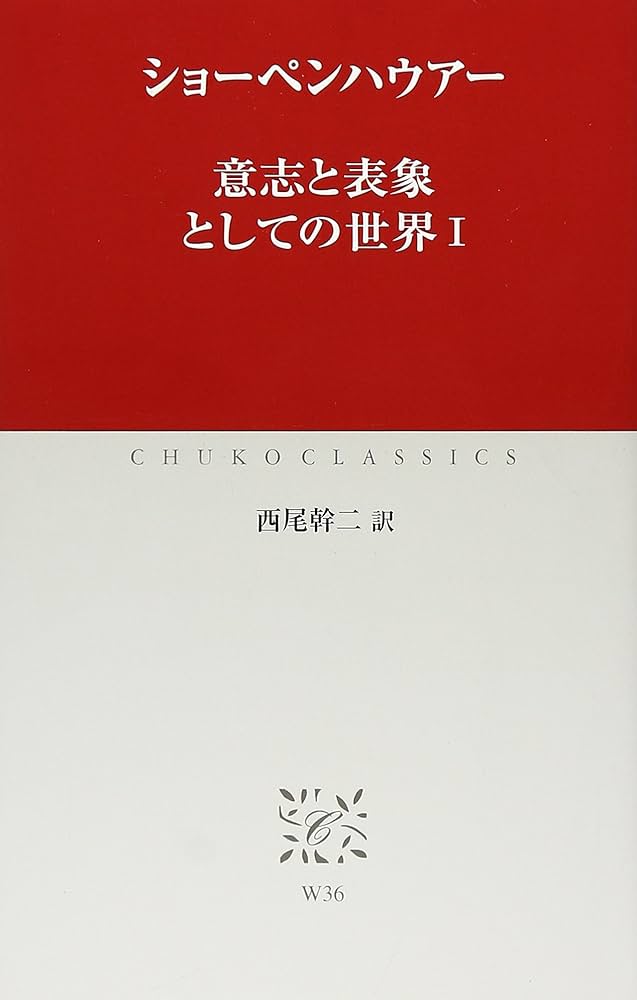
■株式会社中央公論新社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
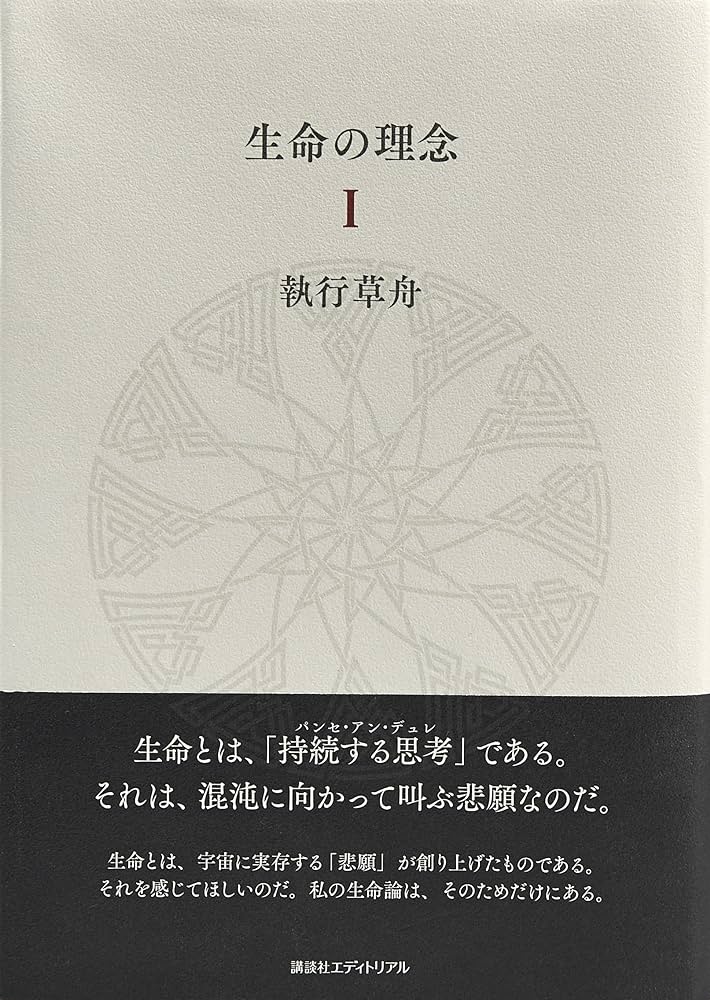
■株式会社講談社
公式HP:https://www.kodansha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
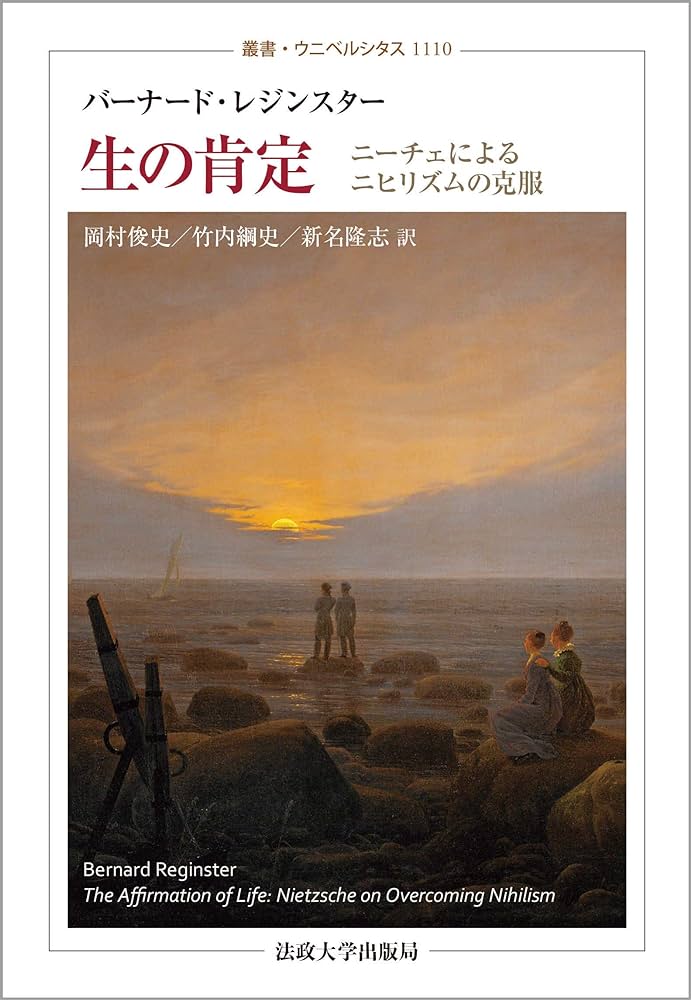
■一般財団法人 法政大学出版局
公式HP:https://www.h-up.com
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
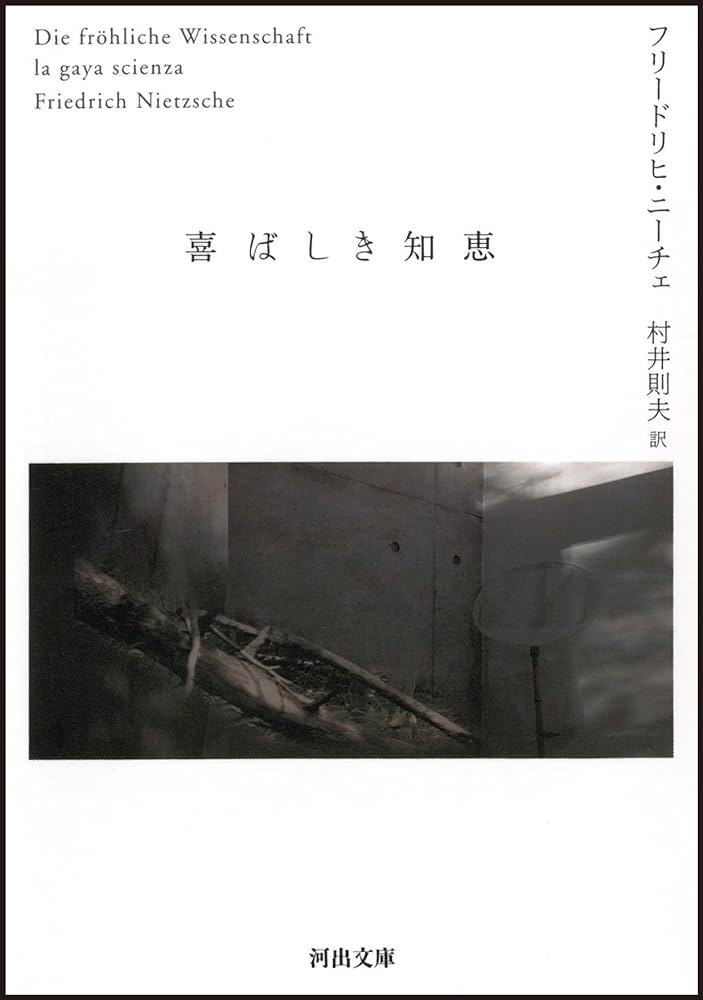
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
メモ
“プラトンは、人間はただ夢のなかに暮らし、哲学者だけが目醒める努力をする、としばしば語っている。” P41 『意志と表象としての世界Ⅰ』
”ローマ帝国も、古代ギリシアのポリスも、中国の古代社会も、そのすべてが家族制度の崩壊と共に文明としての「実体」が崩壊しています。” P94『生命の理念1』
“自分ひとりの人生で完成できるものなどは元々何もありません。みんな円環の一部分を担うだけなのです。” P117『生命の理念1』
⇒メルロ=ポンティ「生の未完結性」
“学者の書物はいつでも、歪んだ魂を反映している。いかなる専門職も魂を歪めてしまうのだ。” P416『喜ばしき知恵』
日記
今日は珍しく小難しいショーペンハウアーばかりを読んでいた。
誰かについて語るような、批評本を嫌うような傾向が出てきたのかもしれない。
批評にはオリジナリティがない。といいつつも、自分も似たようなことをしているのではあるが。
ニーチェの学者批判は何を問題にしているのかよく分からないが、哲学に関しては、誰かについての研究が多いイメージは否めない。
カント研究者の中島義道は、カントに関する論文がゴミのように生産されていくことを批判していた。
自分は哲学のアカデミアの世界は知らないが、修士課程、博士課程では誰かについての研究がメインに論文が作成されているのだろうか。
断言できるのは、池田晶子、執行草舟氏の二名に関しては単なる批評を超えているということだ。
それ以外の作家にはあまりオリジナリティを感じない。(自分が興味ある分野のなかにおいては)
いや、いるのだろうけれども、日本人の著述家に関しては今のところこの二名以外で面白い本は最近あまり見ない。
・・・
今日は、ショーペンハウアーが表象と意志なしに世界は存在し得ないという、観念論の立場をとっていることが読み取れた。
確かに、世界が存在しているのかどうかは人間の主観的な問題と思えなくもない。
意識がなくなれば世界が存在しているかどうか確かめようがない。
昔、『14歳からの哲学』のなかでこれと似たようなことを池田晶子が書いていたような記憶がある。
・・・
『生命の理念1』は相変わらず深い。そして、「そうだ」と、心のなかで返事をするような場面が何回もあった。自分の言いたいことを部分的に代弁してくれて、自分は本書と共振をする。
感化によって意志が次世代、その次の世代へと継がれていく。
また、健康至上主義社会(≒現代のヒューマニズム)の盲点をうまくついている。本書は生物・医学の勉強にもなる。
動物にはもともと病気など存在しない、という話は他の書物でも読んだ覚えがある。
全ては人間の文明による。社会病理やミシェル・フーコーの医学批判は陰謀論とも親和性があるのでこれ以上の話は控えておく。
生き切るという、執行草舟氏の定言命法は自分に大いに影響を与えている。
今日は哲学書に没頭できたという意味では充実した一日だったかもしれない。
その反面、文学作品への読書欲が少し下がっている。