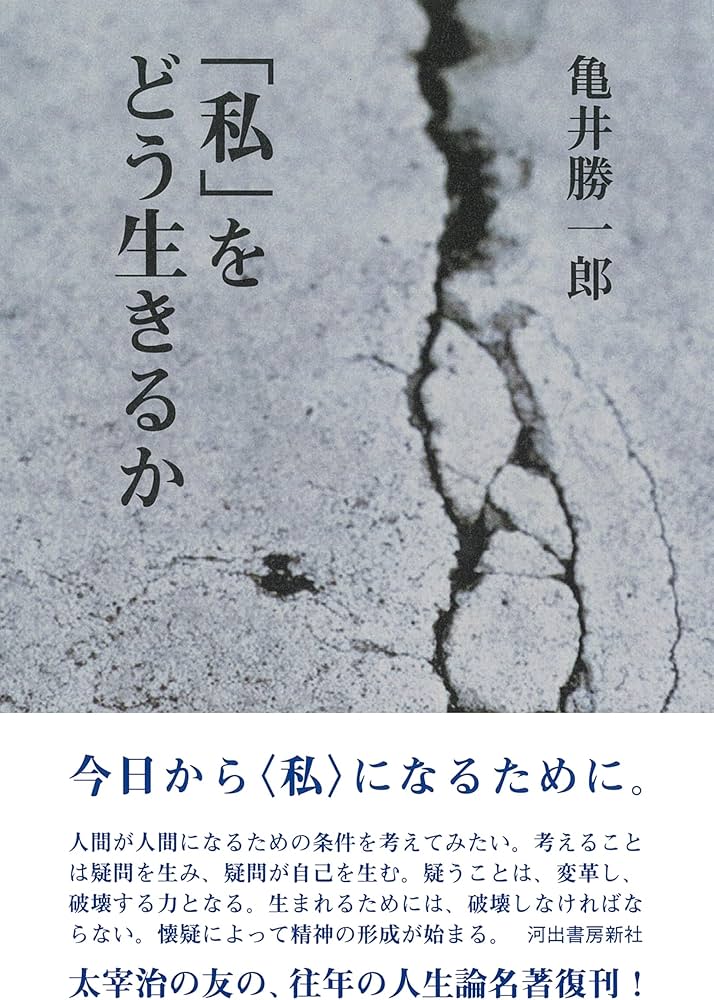
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

画像引用元:紀伊國屋書店 オンライン
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784061983403
■株式会社講談社
公式HP:https://www.kodansha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
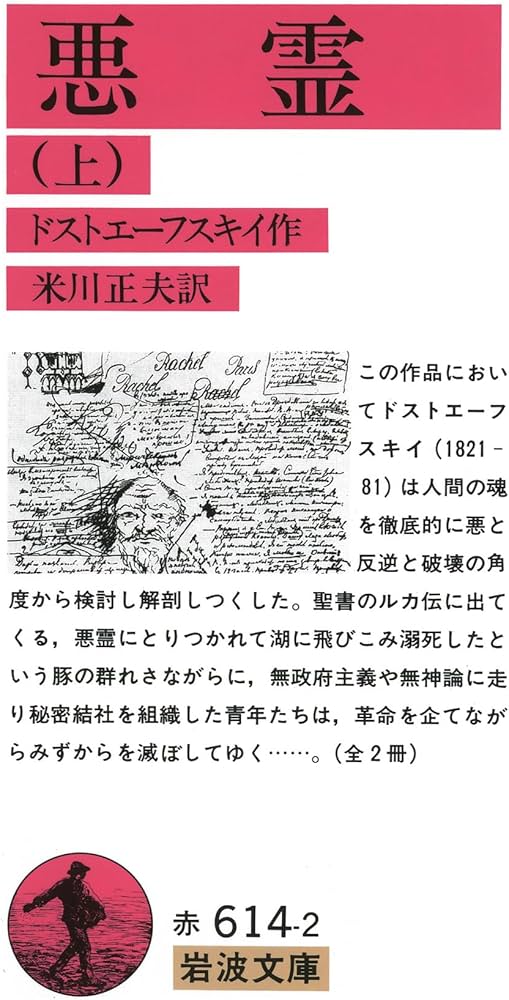
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
言い訳になってしまうが、カフェがうるさすぎたので読書が進まなかった。
イヤホンをしてなんとかごまかしたが、一度萎えた心を取り戻すのは容易ではない。
途中仮眠を取って少し回復したのでそのあとは少し読み進めた。
亀井勝一郎の本はかなり良かった。二日連続でパスカルが本の中に登場している。
昨日は松岡正剛から、今日は亀井勝一郎から。
松岡正剛はパスカルが編集工学の精神を宿していると絶賛していたが、亀井勝一郎は人間の条件をパスカルの有名な名言から語った。
意識があり思考できる理由を半ば「義務」としてパスカルは、正当に思考することを、人間の全品位であり全価値である、と書いていたパスカルを亀井勝一郎は引用した。
冒頭からいきなりパスカルの件になったので、昨日との連続性を感じずにはいられなかった。
ナボコフに絶望というタイトルの本があるが(勿論まだ読めていない)、絶望という概念をそれぞれの作家はどのように位置づけているのか、どの程度意味を共有しているのかは定かではないが、亀井勝一郎は絶望のことを「生まれかわるための陣痛」であると書いていた。
一部をここに書き残して頭に入れたい。
“青春は元来性急なものである。性急に結論を欲し、ないしは問題を切断する。この性急さは青春の美徳ともなれば、悪徳ともなるのである。どんな場合に、それは美徳となるか、性急さが絶望に変るときである。解きがたい難問を担って、しかも容易に解決が得られぬとき、しかも考えることを放棄しなかったとき、絶望する。(・・・)つまり自己に絶望し、自己否定をしながら、第二の自己を形成して行く。絶望とは、「生まれ変る」ための陣痛に他ならない。” P16-17
自分も約1500回、読書日記を書き続けたので理解ができる。このブログは絶望によってかたちづくられたと言っても間違いではない。どうしても納得がいかないことは徹底的に詰めてきた。完全な公理が数学に存在しないように、生き方や社会の在り方にも完全な公理というものは存在しないのではないかと不安になることが多くあった。
ふりかえると絶望は思考の源泉であった。
子供たちに読書嫌いが多いとすれば、それは良い意味でも悪い意味でもまだ絶望していないことを意味する。
言い変えると、大人になっても読書が嫌いな人は、ある意味、それは絶望していないことでもある。岡本太郎に言わせれば、かりに絶望していたとしてもごまかして、逃げているということある。
そう考えると、自分は部分的には正常な人間なのだろうと、少なくとも過去のプロレタリア文学者とは意を分かち合える存在なのだろうと思うところはあった。(亀井勝一郎は保田與重郎とプロレタリア文学の雑誌「日本浪漫派」の創刊に携わっている)
高橋和巳の小説を面白いと思えるのは、似たような傾向性を持っているところがあるからなのかもしれないと思えた。
しかしこう書いてみるとなんだか自分が恥ずかしくなるものである。彼らが絶望する理由と自分が絶望する理由はどの程度異なるのだろうか。彼らは何を理想としていたのだろうか。このあたりは彼らの書いた小説を読むほかない。しかし今そこまで元気が自分にはない。
・・・
『対談 人間と文学』
創作と虚構にまつわるパラドックスの話は印象的である。
現実というものを、徹底的に細かく描写をしていくと、最終的にはそれは創作(虚構)となってしまうということを二人は語っていた。私小説は素材が現実でありながら、完成したあかつきには「創作」としての小説が待っている。たしかにそのようなジレンマは想像できる。
自分はこのパラドクスにそこまで興味は持てなかったが、ヴァージニア・ウルフの言葉を思い出す。
どれだけ虚構でかたちづくられたとしても、小説の素材が現実世界である以上、少なくともなんらかの真実を含むもの、そういうものが文学であると語っていたのを覚えている。
自分は文学論ができるほどの頭と経験はないのでこれ以上の言及は避けたい。
もう一度亀井勝一郎に戻りたい。
まず、名著を新装というかたちで復権した河出書房新社には感謝である。
本は徐々に劣化していくものであるが、内容までは劣化しない。劣化する本もあるが、むしろ100年後にとんでもない価値を生み出す本もある。これが書物の唯一性である。
読み継がれるには、内容をそのままにして紙を新しくしてまた流通される。これは文化的に価値のある営みだと自分は端的に感じた。
古典新訳もその流れと方向を同じにしていると思われる。
本は読み継がれるべきであるとまでは言わないが、価値のある本は新装としてどんどん循環させていくべきだとは思えた。
つづく