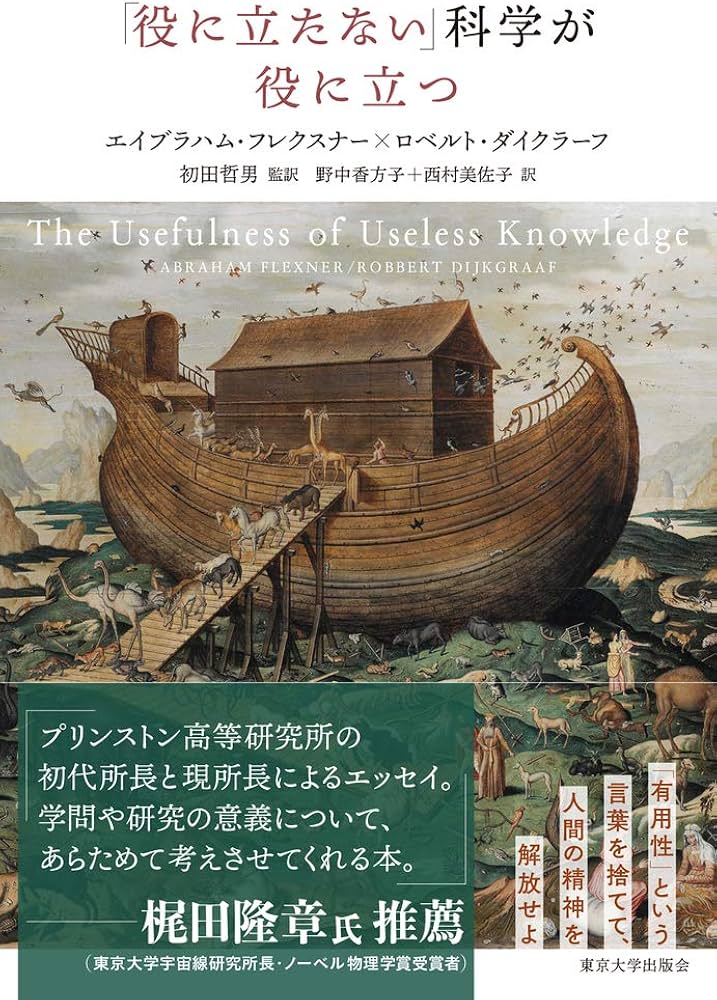
■一般財団法人東京大学出版会
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
感想
今日は心を打たれるような本が多かった。非常に意義のある読書時間だったように思う。
とてつもない残暑にはまいったが、読書に対する熱は残暑を上回った。
『「役に立たない」科学が役に立つ』を読み終わったあと、小室直樹のアノミーと結びつけて自分は考えたくなったところである。
某元知事はアカデミズムへの批判を「どうしてそう偉そうなんだ、対して役に立たないくせに」ということを述べていたのを自分はハッキリ覚えている。
実利的なものを追うばかりとなった日本は逆説的に貧困になっていやしないだろうか。
そういうことをいろいろと考えさせられた。
応用、応用へと傾いた先に何が待ち受けているか。自分はそのひとつに、薬害があるとみている。
他にも考察すれば多く見つかるはずである。例えば、手段が目的になってしまうような類の話だ。
人間にとって都合よく作られたものが、人間にとって完璧に都合の良いものになるかどうか。
逆説についていろいろと考えさせられた。逆説について今日学んだこと、思ったことは後述したい。
まずはメモを。
“アインシュタインの次の言葉はよく知られる。「想像力は知識よりも重要だ。なぜなら、知識は今わたしたちが知り、理解していることに限られるが、想像力は世界のすべてを包括し、わたしたちがこれから知ること、理解することまで含むからだ」。” P40
“(・・・)人類にとって有益だと判明する真に重要な発見のほとんどは、有用性を追う人々ではなく、単に自らの好奇心で満たそうとした人々によってなされた、ということです。” P70
“ここまでに述べてきた考察が強調するのはーーー強調するまでもないかもしれないがーーー精神と知性の自由こそ、圧倒的に重要だということだ。” P90
“大学は、特殊な政治、経済、人種的教義を奉じる人々の道具になろうとしている。(・・・)真の敵は、人間の精神を型にはめ、翼を広げさせないようにする人々なのだ。” P92
・・・
自分も内省しなければならないが、読書を頻繁にするようになったきっかけは好奇心も含まれていた。
『配色の教科書』、『絵とは何か』、『近代芸術の五つのパラドックス』という本に出会い、いままで考えることのなかった話が満載で芸術に興味を持つようになったことを覚えている。
他にも心理学、認知科学、哲学、文学などの刺激的な本が沢山世の中にあることが分かり、好奇心がかきたてられたことを記憶している。
ところが最近は好奇心が薄れていることは自覚している。
好奇心が生涯つづいた科学者は尊敬に値する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
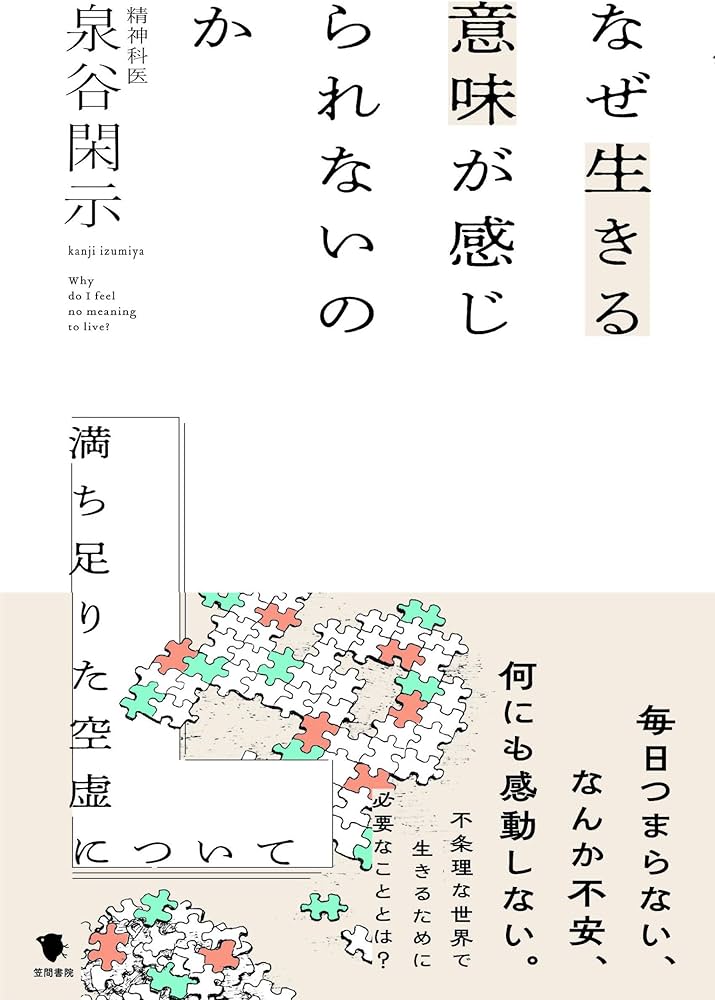
■有限会社笠間書院
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/kasamashoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
感想
本書は文学者の言葉が多く引用されていたのが個人的に良い点だと感じた。
この本もなかなか心を打つものがあり、また、多くの力強い言葉が散りばめられていた。
読み終わったあとは活気が戻ってきた感触がある。本書はこれからの自分にとっての活力の泉になることは間違いない。『「役に立たない」科学が役に立つ』もすばらしく、こちらも素晴らしい本であったので少し心を動かされた。
メモ
現代のおびただしい情報の洪水は、もはや留まるところを知らない勢いで加速し続けています。(・・・)しかし、情報を探しそれを次々に受け取っているのでは、人間は単に情報処理しているに過ぎず、それは真の意味で思考していることにはなりません。思考とは本来「空白の時間」があってこそ可能なものだからです。” P36
「空白の時間」≒真空
キルケゴール「信仰とは、自己自身を確保するために、自己自身を喪失することである」
=シモーヌ・ヴェイユ「心を真空にすること」
=不幸を厭わないこと
=松下幸之助「人間の崇高」
“お笑い芸人を起用すれば親しみやすくなると考えるステレオタイプな番組制作” P44
“教育とは単に知識の伝承を行うことではなく、憧れるに足る豊かな世界があるということを啓蒙するところにこそ本質がある” P76
・質へのフラストレーションについて
“代理満足とは、自分の求めるものを「質」的に妥協し他のもので満たそうとすることを指しますが、「質」を妥協したがために、その物足りなさを「量」的に補わざるを得なくなってしまいます。しかし、その「量」によるごまかしは一時的効果しかないので、どんどん「量」を増やすしかない泥沼状態に入っています。” P93
ロゴス・クラッシャー・・・・・目に見えるものしかわからない存在
≒唯物的発想
≒唯物主義
“・・・荒れ地の本質とはなんでしょう。それは、だれもがいいかげんな生活をしている場所です。だれもが他人の猿真似をし、他人から言われるままのことをし、自分の生活を築く勇気を持たない。それが荒れ地です。” P117
(オスカー・ワイルド)
「この世には二つの悲劇があるだけだ。ひとつは欲するものが得られないこと、もうひとつはそれを得ることだ。後者のほうがずっと悪い。真の悲劇だ。」
⇒これが究極の逆説と言える。オスカー・ワイルドはおそらく世界のあらゆる逆説を認知している。
“(・・・)あたかも思考停止することこそが健康なことだと言わんばかりの言葉が、真剣に悩み考える者に次々に投げつけられる” P162
ジャック・デリダはたしかに言語に対する異常なまでの執着をみせたが、それを「神経症」とまで言ってしまう『「社会正義」はいつも正しい』(早川書房)の著者はおそらくこの類の人間に違いない。
考えることが神経症と言われる時代である。著者はハッキリと物を言わせている。これが痛快であった。
ミヒャエル・エンデの言葉
(世間のいう「大人」とは)「魔法を喪失し凡庸で啓蒙された不愚の人間」
⇒これもまた痛烈な逆説である。大人になるということは均質化されてしまうことを意味する。
教育機関の怠慢・愚行。この批判・問いかけは『「役に立たない」科学が役に立つ』のなかで書かれていた、教育機関への批判と重なる。
ペシミスト・・・「不条理な世界の「お客さん」」
「お客さん」という言葉がユーモアとして、アイロニーとして素晴らしく効いている。
そのあと、話は合理性と脳の話にうつった。
心は論理的にはいかない。
“(・・・)信じるという行為は、「頭」の合理的判断を完全に超越した次のもので、「心」の働きによって成されるもの” P174
超越=超自然的なもの
“私たち人間が人間的であるためには、どこかに向かって「超自然の徳」のベクトルを出し続けることが欠かせません。” P191
超自然=論理ならざる意志=「にもかかららず」もう一度生きてみよう
要約することは意味がないので断片的なメモを心に刻む。そうすることで精神の栄養になる。
ニーチェの超人とは「論理ならざる意志を絶えず引き出す人間」のことを言うのだと自分は思うに至る。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新・読書日記170(読書日記1510)
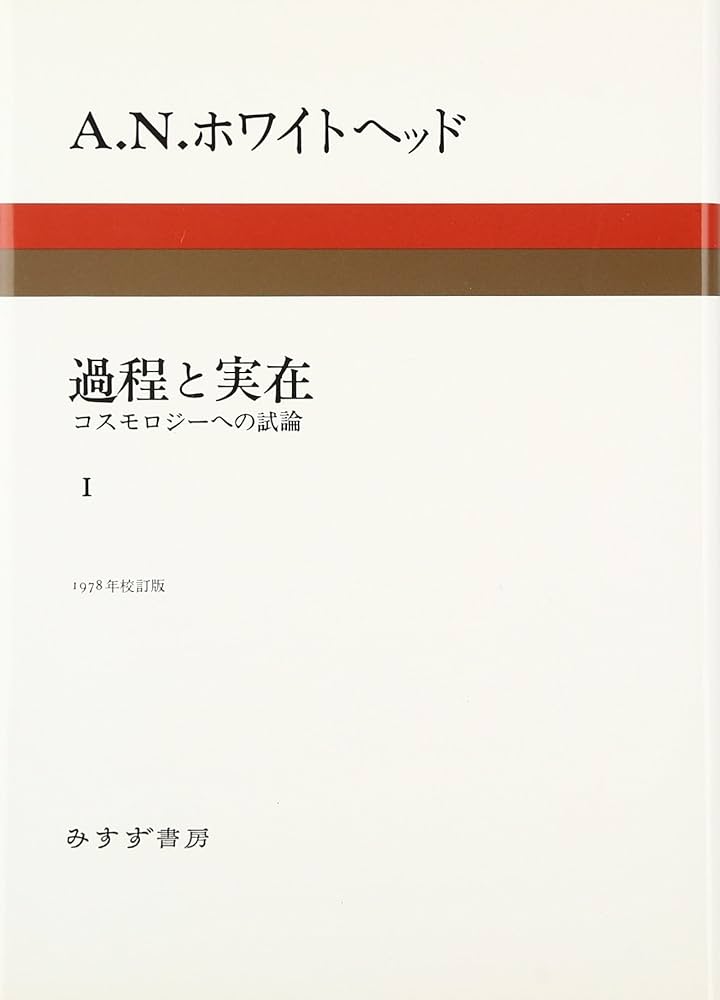
■株式会社 みすず書房
公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
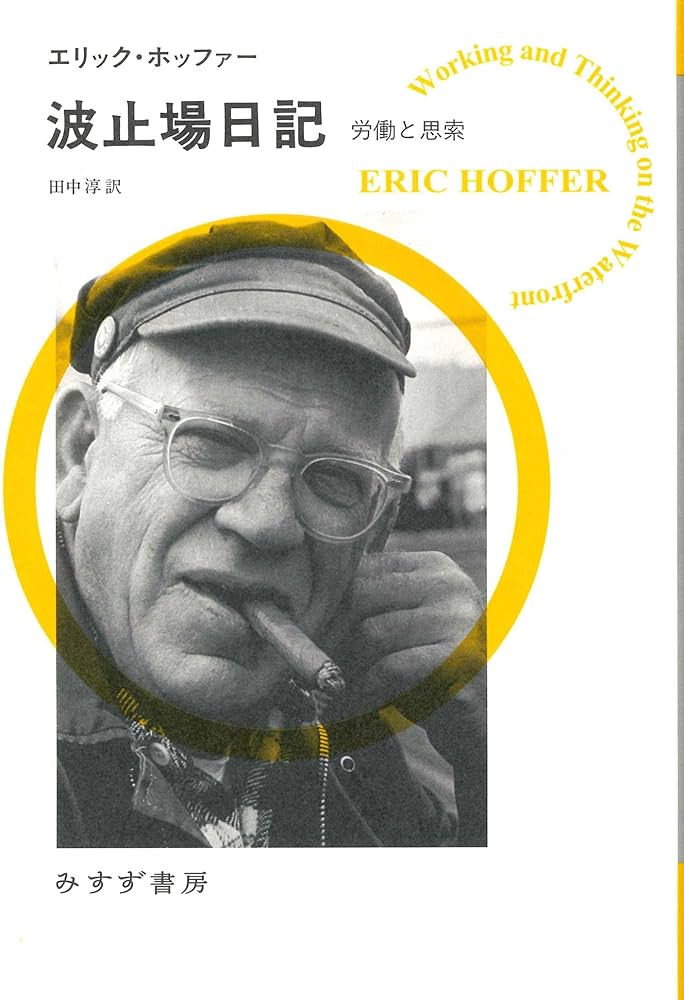
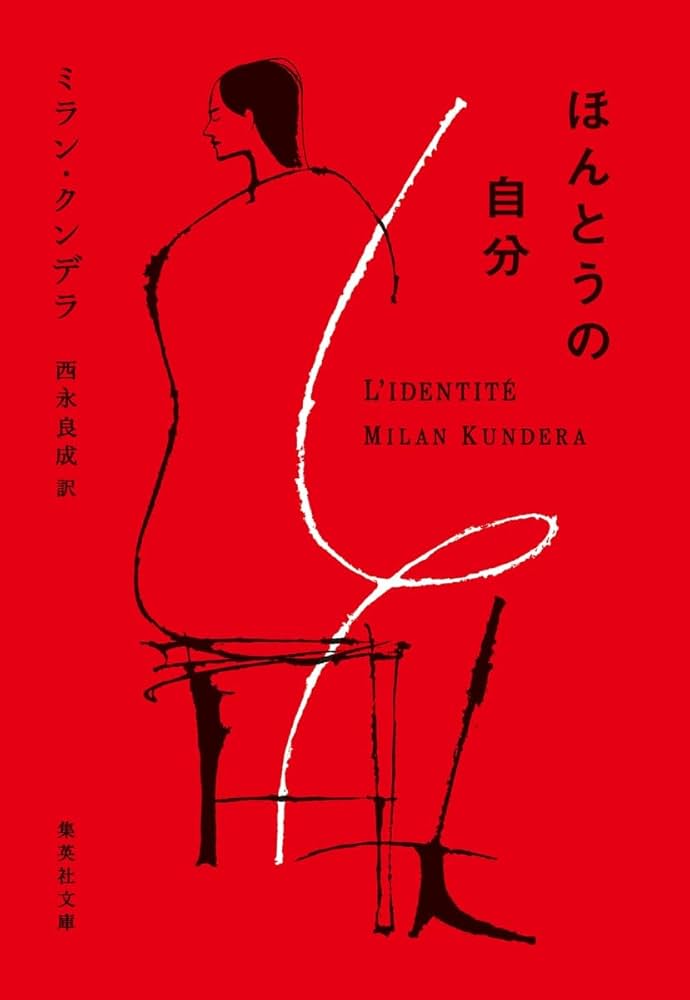
■株式会社集英社
公式HP:https://www.shueisha.co.jp/
公式X(集英社新書編集部)(旧 Twitter):https://twitter.com/Shueishashinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『過程と実在〈1〉コスモロジーへの試論』
メモ
“理性主義的図式の検証は、その全般的な成功に求められるべきであって、その主要な原理の特殊な確実性や最初の明晰性に求められるべきではない。これに関連して帰謬推理の誤用ということが注目されなければならない。多くの哲学上の推論が、この誤用によって堕落させられている。一連の推論から矛盾が現れる場合、そこで引き出されるべき唯一の論理的帰結は、その推理に含まれている少なくとも一つの前提が誤っているということに過ぎない。しかしその非ある前提が直ちに突き止められるということが、それ以上少しも問いかけることなしに、性急に仮定されているのである。” P11
『波止場日記』
メモ
“自分自身の幸福とか、将来にとって不可欠なものとがまったく念頭にないことに気づくと、うれしくなる。いつも感じているのだが、自己にとらわれるのは不健全である。” P7
“礼儀の正しさはある程度客観性と相互の妥協がなければ成り立たない。ある絶対的な真理に一生懸命かじりついている人間は悪魔以上に妥協を恐れる。そういう人間は自分と他人をしっかり結びつけ自分の非妥協的な構えをぼやかしそうな人当たりのよい礼儀の発見を抑える。したがって、ある信念がその力を失うと、しばしば無作法がそれにとって代るのである。” P18
“ベンサムの生涯を理解しなければならない。万視塔(パノプティコン)から、一般的福祉の促進へという彼の関心の移行は、知識人の理想主義とその心に秘められた強い監督願望との緊密な関係を示す例である。〔ヴィジョン(展望)とスーパーヴィジョン(監督)〕” P44
・・・
オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』を読み終わって以後、しっくりくる小説がない。
ミラン・クンデラの小説は、やはり自分にはしっくりこないかもしれない。
深淵な問いかけを感じない。勿論それはそれで、自分が求めすぎているのだけれども。
言い方が悪くなるかもしれないが、どことなくふにゃふにゃしている。
かといって三島由紀夫のような硬派な小説も合わなかったりする。
次は誰のものを読もう。