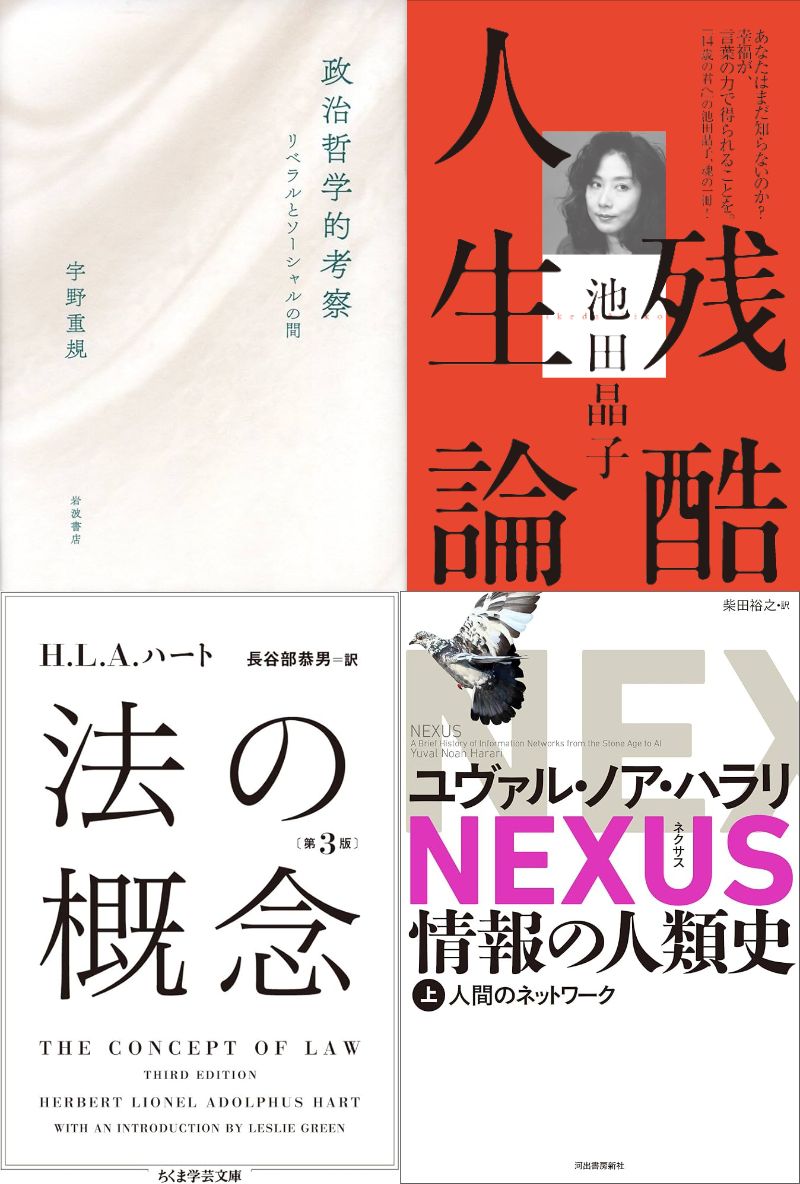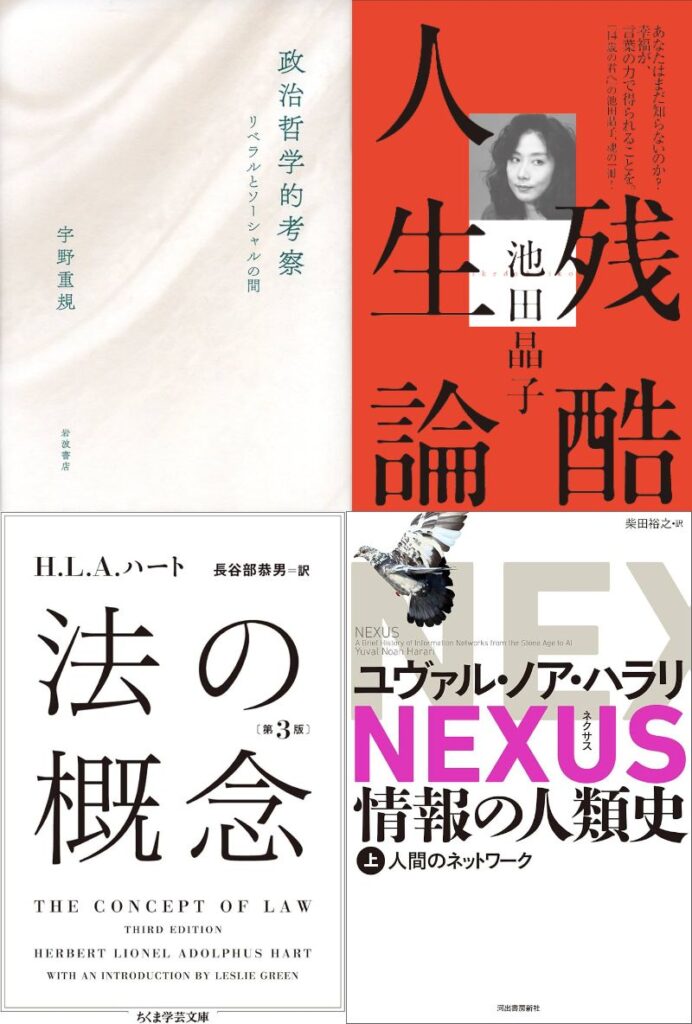
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
■毎日新聞出版株式会社
公式HP:https://mainichibooks.com/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/mai_shuppan
■株式会社筑摩書房
公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
最近は法律が人間の行動にどう影響を与えるのか、そのマクロ的な効果に興味がある。
トクヴィルの本を読みながらいろいろと考えさせられた。
池田晶子はロゴスによってそれが与える自由について語るが、法律の観点からも考えてみたいと思うようになってきた。
就労支援の現場で働いている自分が常に考えるのは、何を与えればいいのかということである。
進路や方向性を与えるだけでは全く効果がないのはすぐに分かった。
金銭もそうではない気がしている。
じゃあと、豊かな生活を与えることを意識すればいいのか。
しかし、そもそも豊さとは何か。
そう考えていくうちに、堂々巡りを繰り返しながらも、「自由の精神」を与えることが哲学的には(ロゴスとして)重要なのではないかと思うようになってきた。
ただ一時的な発見なので、日々こういった考えは変わっていくことだろう。
大事なのは考えて書くことであって、何もしないことが最大の愚行だと今の自分は考えている。
・・・
『政治学的考察』
メモ
“判断主体の多数性を否定する社会における同調圧力や、公的事柄に関心を失った市民をむしろ歓迎し各個人をその孤立の中に閉じ込めようとする中央集権的権力は、彼の最も忌避するものであった。” P16
“トクヴィルは、よく知られているように、自由の精神と宗教が相反するものではなく、むしろよく支え合うということを、生涯主張し続けた。” P16
カトリック教会が権威となり、自由の精神と宗教は敵対した背景があった
そうならないようにするための「政教分離」
トクヴィルは、アメリカはそのあたりがしっかりしていると評価した
“このアメリカは自由の精神が最も活発な国であると同時に、最も根強い宗教心が見出される国でもある。” P17
(トクヴィル)
“「専制に信仰は不可欠ではないが、自由にとっては不可欠である」” P17
「自由(意志)とは善を自発的に選択する能力のことである」
ツヴェタン・トドロフ「フランス・リベラリズムにおける自由とは、むしろ自律として理解するのがふさわしい」
・政治体の自律
(トクヴィル)
“「アメリカにおいて、社会は自らの力で、自らを決定している。権力はその社会のなかにしかない」” P23
(筆者)
“たしかに、宗教の力によって人間社会の脆弱性を克服することは、もはや不可能かもしれない。しかしながら、宗教があくまで信仰の領域にとどまって政治に関与しない限り、人間の内面における「知性の健全な枠」として、人間精神の不安定性に対する最低限の支えとしてなお機能するのではないか。” P26
・・・
『ネクサス』
ハラリ「秩序は虚構を通じて維持されることが多い」
“(・・・)私たちの情報テクノロジーの速度と効率を増すだけでは、世の中は必ずしもより良い場所にはならない。真実と秩序のバランスを取る必要性が、より切迫したものになるだけだ。” P80
“愛国心の本質は、母国の美しさについての感情的な詩を暗唱することではないし、外国人や少数派に対する憎しみに満ちた演説をすることでもけっしてない。むしろ愛国心は、同国人ならば自分とは縁もゆかりもない人々でさえ下水設備に加えて治安や教育や医療の恩恵を享受できるように、税金を払うことを意味する。” P84
・・・
『残酷人生論』
“狂気?我々らの正気の貫徹こそがそれであるということを、あなたはまだ知らないのか? ” P12
“考えることは、悩むことではない。(・・・)悩むのではなく考えるということが、いかほど人を自由に、強く、するものか。” P16