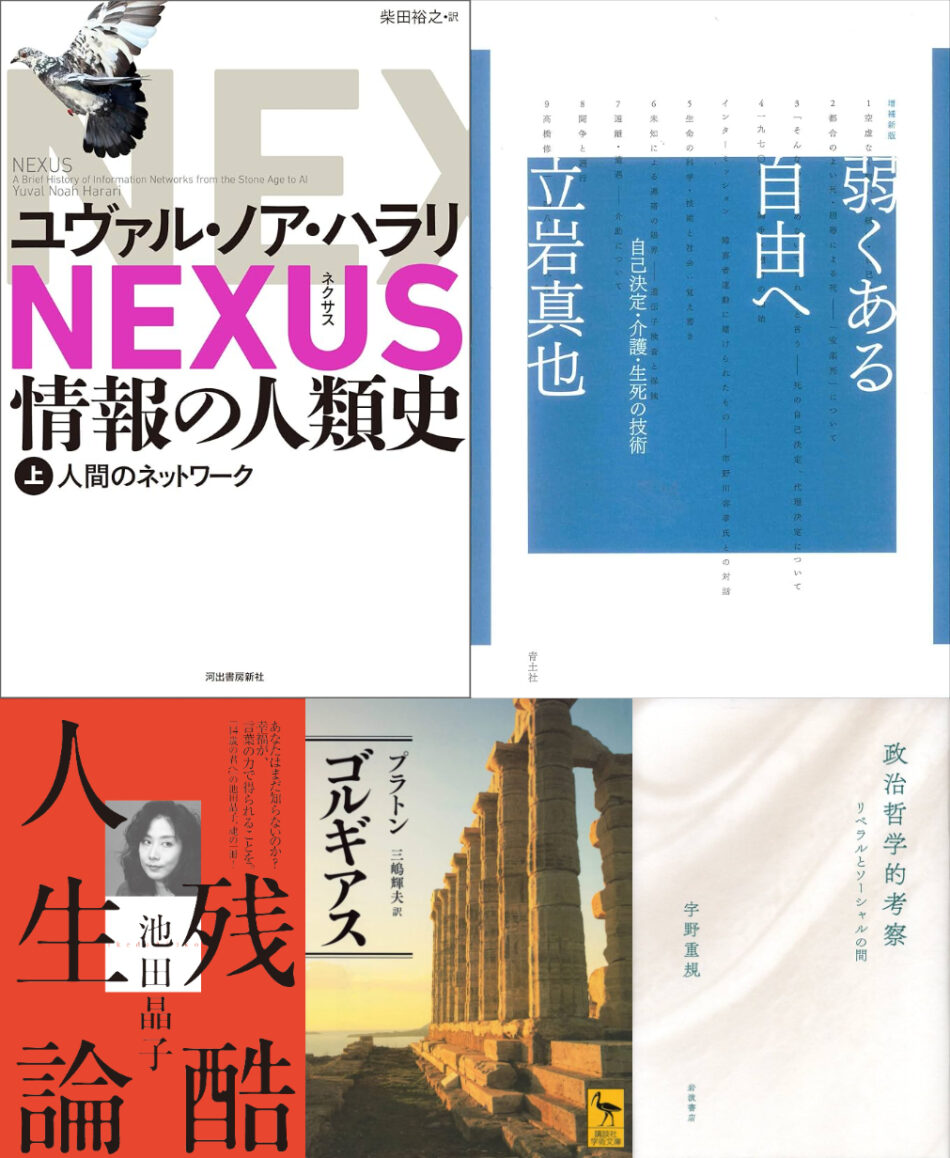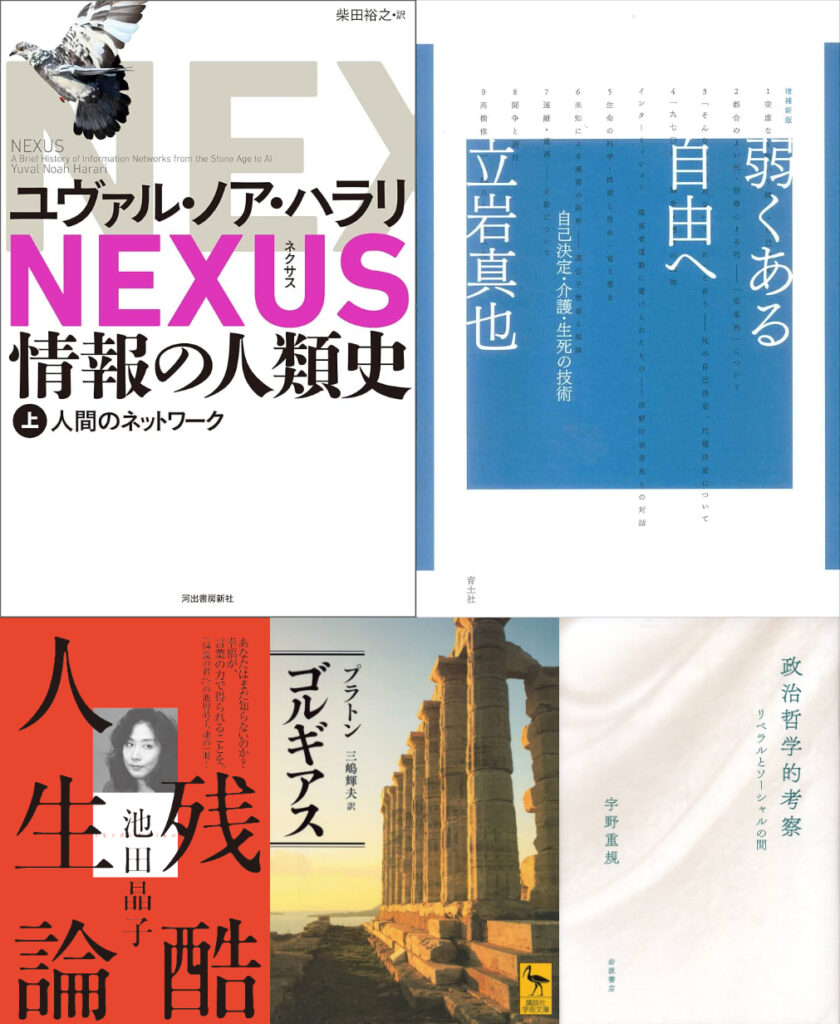
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■毎日新聞出版株式会社
公式HP:https://mainichibooks.com/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/mai_shuppan
■株式会社青土社
公式HP:http://www.seidosha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/seidosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社講談社
公式HP:https://www.kodansha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『ネクサス 上』を読み終えた。全体的には、歴史の中心を「情報」から見た時、そこには何が見えるか、そこにはどんな原理が働いたのか、というのが上巻の内容だった。全体主義は情報源が非常に狭く、民主制は非常に広い。情報の多様性が人類に何をもたらしたのか。そういう壮大なテーマを果敢に取り組むハラリ氏。終着点はどことなく見え始めた感じはある。AIが情報の多様性を担保できるかどうかがひとつの争点、というのが率直の感想。
メモ
“私たちは、古代アテナイやローマ帝国、アメリカ、ソ連のような歴史的システムにおける情報の政治学を理解して初めて、AIの台頭が持つ画期的意味合いを探る準備が整う。なぜなら、AIにまつわる重大な疑問の一つは、AIが民主的な自己修正メカニズムを助けるのか、それとも損なうか、だからだ。” P174
“ポピュリストは、人民の意志とされるものを、客観的な真実の名の下に退ける機関を胡散臭く思う。真実というのは、エリートたちが不法な権力を強引に手に入れるのを隠す名目にすぎないと、ポピュリストは見がちだ。そのせいで彼らは、真実の追求には疑いを抱き、プロローグで見たように、「力こそが唯一の現実だ」と主張する。” P192
“何が原子力発電所の事故を招いたかを説明してくれたウクライナ人ガイドの言葉が、今も頭から離れない。「アメリカ人は、質問は答えにつながると教わりながら育ちます。ところがソ連国民は、質問はトラブルにつながると教わりながら育ったのです」” P246
・・・
最近はトクヴィルが自分のなかでブームになっている。
家に帰ってから本棚をてきとうにいじって手に取って読んで、を少ししていた。
トドロフ『われわれと他者』にトクヴィルについての考察が書いてあった。
タイムリーであった。
これを後日、ゆっくり読んでみようと思う。
・・・
メモ
『残酷人生論』
池田晶子の精神分析批判 わかる/わからない
“患者は、医者にはわからない考えや感覚や感情をもっている。自分にはわからないそれらについて、なぜこの人はこんなふうに考えるのか、なぜこの人はこう感じざるを得ないのか、わかろう、わかってあげようとするのが医者の仕事だ。しかし、このとき医者の側が、自分のわかっているわかり方によってのみわかろうとする、すなわち「〇〇型」というわかり方によって、自分にはわかっていない人のそれをわかったことに、はたしてなるのだろうか。かくして患者は、オウムに走る。” P39
池田晶子の情報化社会批判
“情報によって動き出す知性とは、情報によらなければ動き出せない知性である。外からの情報なしでは考えられない知性が、ほんとに賢いことになるのだろうか。” P45
池田晶子のニューアカデミズム批判
“自分が本当に知りたいと希っていることだけを、まっすぐに問い、考え詰めてゆけばいいのだ。選ぶ必要も、競う必要もない。じつは情報にすぎないような知識の、新旧や多寡や出典を競い合うのは、自分の頭で考えられないまぎれもない証拠と、そう思っていればいい、気にすることはない、人生は短い。” P61
池田晶子の鋭いまなざし、尖った言葉は好きだ。本当に気持ちがいい。人は「世の中に絶対は無い」という。しかし、であるならば、その「絶対」という言葉はなぜ存在する。「絶対」ということが無ければ、そもそも言葉すら生まれなかったはずである。普遍性もしかり。普遍性を疑いながらも、「普遍性」という言葉の存在自体までは否定していない。このことを人はわかっていない。
・・・
『弱くある自由へ』
障がい者福祉、社会福祉、福祉国家に関する本を読み漁っていたときに、この本に遭遇した。
職業上、タイムリーなことが書いてあったので、しばらく読んでみることにした。
メモ
“(・・・)例えば医療という領域では特殊な知識が必要とされ、その分専門家の方が有利で、消費者側の情報入手によってはこの有利さを覆すことはできないという指摘がなされることがある。しかしこれはおかしい。どんな物についても、私達は、その製造法、内部の構造等々をほとんど何も知らない。けれどもそれを使うことはできる。だから知識の特殊性、専門性が問題なのではない。選択のための有用な知識が得られない構造が問題なのである。” P30
“次に、責任を押しつけられることについて。とにかくあなたが決めたその結果なのだから、文句はないだろうと言われる。自らも、選択の自由を認めるなら、その選択の結果を選択した人が引き受けなければならなくなるのではないか、と思ってしまう。実際、その通りに、文句を言えない現実がある。ただ、自己決定が尊重されるべきことと、その結果の全てをその当人が負わなければならないことはすぐにはつながらない。(・・・)気にいらない商品を返品できるのと同じように、思い通りの結果が得られなかったら、選び直せればよい。宝くじのように、結果に文句を言わないことが前提になって成り立っているものもある。しかし、そうである必要のないものもある。” P33
立岩さんは、誰しもが当たり前だと思っていて考えることがないことを真面目に考えているところが魅力的である。小難しい、理屈の連打でずっと読むのは気力がいるが、定期的に読むことにしている。
ミル『自由論』に書いてあったように、他人に危害を加えなければ自由は保障されるべきだという、ある意味当たり前の自由論は、実は突っ込みどころは意外と多い。危害の定義、迷惑の定義が実はハッキリしない。直接的な迷惑、間接的な迷惑、その強弱等、考察を進めればキリがない。裏を返せば考える余地がいくらでもある。たまにはこういうことを考えてみるのも悪くないと思う。
・・・
ゴルギアスを久しぶりに読んだ。
弁論術は説得を与えるという。医者の言うことを聞かない患者にいう事を聞かせることを弁論術は可能にしてみせる。しかし知識に関しては弁論家よりも格段に医者のほうが上である。つまり説得によって与えるのは知識ではなく信念である。(正しい)知識には真のみが存在するが、信念は基本的に偽と真の判別がつかない。弁論家は知識が正しいかどうかは問わず、とにかくイエスと言わせることを目的とする。ソクラテスの突っ込みが始まった。恐ろしいほどの質問攻めが始まる。70項あたりである。
池田晶子、立岩さん、プラトン、ハラリ氏等、今日は刺激的な本をいろいろと読むことができた一日であった。
やはり個人的には池田晶子の言葉が今日は一番記憶に残ったように思う。
情報によってのみ動かされる知性とは、換言すれば情報なしには発動しない。
情報というものは手段であって目的ではない。
いや、手段ですらないのかもしれない。
・・・
関連図書