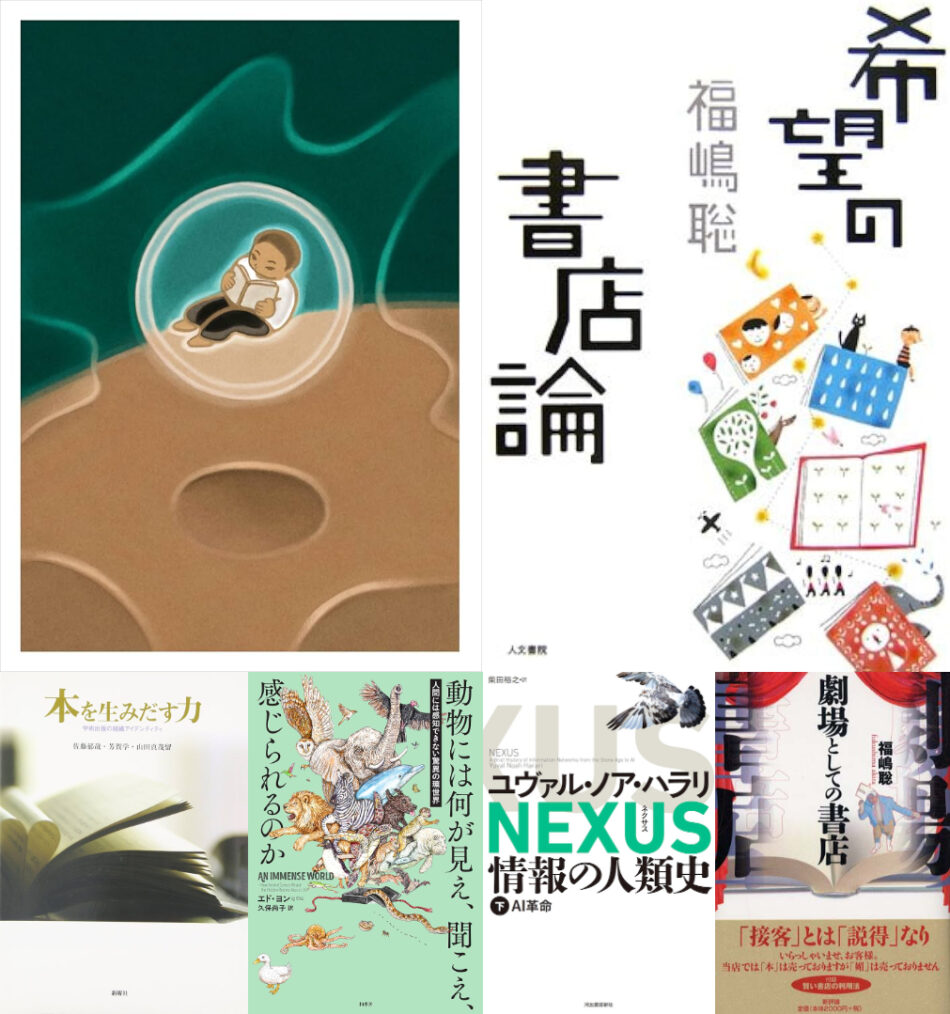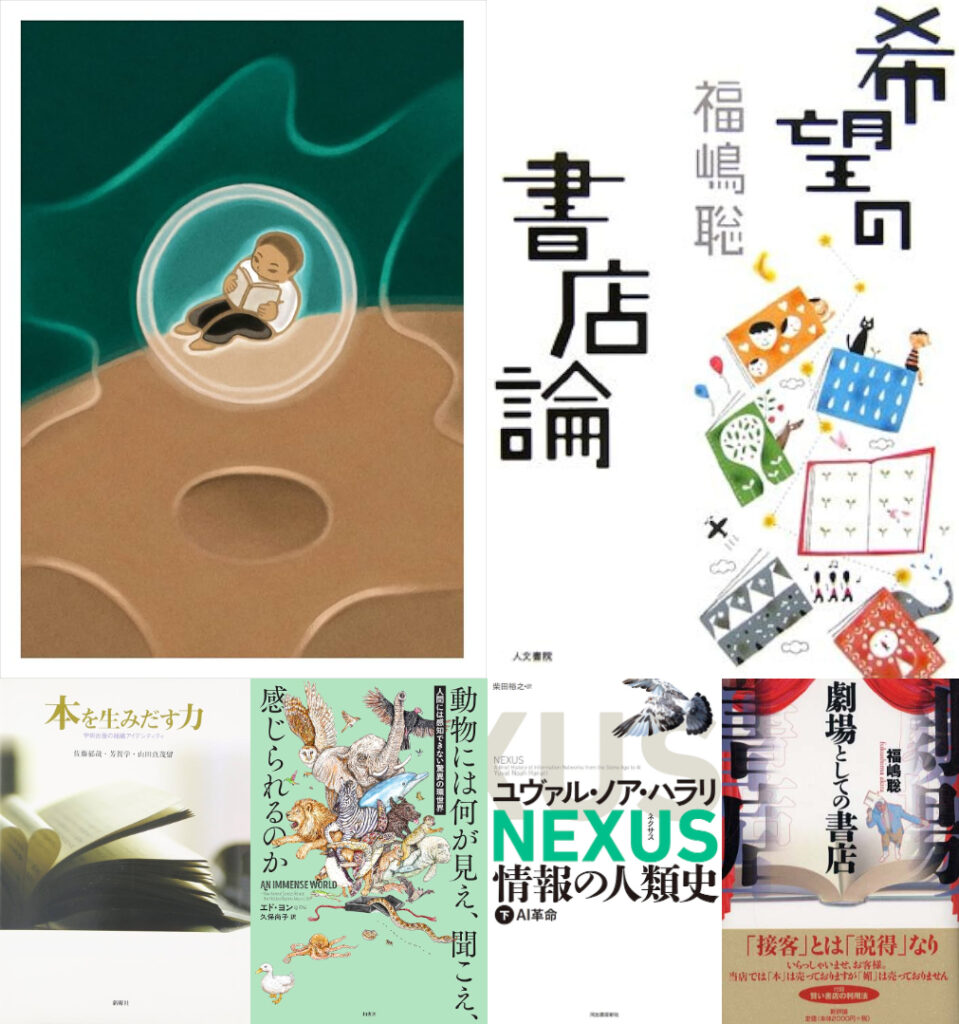
■NUMABOOKS
公式HP:https://numabooks.thebase.in/
公式X:https://x.com/numabooks?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社新評論
公式HP:https://www.shinhyoron.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/shin_hyoron
■株式会社人文書院
公式HP:http://www.jimbunshoin.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/jimbunshoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社原書房
公式HP:http://www.harashobo.co.jp/
公式X:https://x.com/harashobo_Japan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社河出書房新社
公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社新曜社
公式HP:https://www.shin-yo-sha.co.jp/
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/shin_yo_sha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
fuzkueの阿久津さんの日記を読みたかったので読んだ。
あとはジュンク堂の福嶋さんの本を二冊、ハラリ氏、メディア系の本をよく読む一日だった。
阿久津さんの文章は句読点がいつまでも見えず、持続する思考を延々となぞるような、不思議な文章であった。同じ、読書日記を書く人間としてはちょっと参考になるというか、勉強になる一冊だったように思う。
メモ
”パトロニズムの観点に立った時、文芸家協会VS図書館という図式で繰り広げられる「公共貸与権」についての議論にどうしても抱いてしまう違和感を、うまく説明できるように思われる。作家は図書館がそもそもみずからの著書を図書館利用者に貸与することによって、みずからの著作権が侵害されているという。これは、平ぺったく言うと、借りることができなかった図書館利用者は本を購入したであろうから、その際に支払われた代金の一部を印税として手に入れる権利を侵害された、という主張である。それに対して、図書館側は、借りることができなかった利用者が本を購入するとは限らない、むしろ図書館利用者こそ本を購入する習慣を併せ持っていると主張する。(・・・)ただ、自分が書いたものを誰かに読んでもらいたいという著者の気持ちは、印税を得たいという気持ちとは、(矛盾するわけではないにせよ)決して重ならないように思うのである。だからこそパトロニズムが成立するのではないか。” P50-51 (『希望の書店論』)
・・・
“歴史を通して何度となく私たちが目にしてきたように、情報の完全に自由な戦いでは、真実が敗れる傾向にある。” P101 (『NEXUS 下』)
“(・・・)その人が、本棚から6冊くらい本を取ってきて机に置いて(あとで4冊ほど追加された)、読んでいた、読んでいたというか、横に押しやって、次の本に行って、という感じだった、いや、そんなのは、多読というか、なんていうのかわからないけれども、読書のひとつのメソッドなのかもしれない、それこそ松岡正剛あたりが何か名前をつけているかもしれない、のだけど、だから、だからというか、それはなにか面白いことを発生させるメソッドなのかもしれないけれども、それを見ていると、というか、ただただ本の扱いが雑だったことがきっと全部だけど、本は雑に扱う、みたいな姿勢は、それは人それぞれで(・・・)高速で処理できているつもりなのかな、今、済んだと思ってかたわらに押しやった本、もう処理できたと思っているのかな、なにか判断できたと思っているのかな、と思ったというか、なにかを読んで、違うなとか、あるいは、もうわかったとか、思って、置いて、というところを見ていると、そんなの、自分のサイズでしかものを考えようとしていないじゃん、(以下省略)” P357-358 (『読書の日記』)
・・・
久しぶりに大型書店へ行った。
いろいろな人がいた。自分はカバンがでかいとよく言われる。そのせいか、最近本屋へいく度に人とぶつかる。というよりか、本屋が狭すぎるのではないか。それは一坪あたりの利益率と言われるものが低く、狭くして沢山陳列せざるを得ないのではないかと想像はつくのだけれども、ちょっとな、と思う。
とくに若い女性がいると気が滅入る。近づけない。一番行きたい本棚にぽつりと若い女性がいたら諦める。
本屋のなかの距離感って微妙だよな、と思う日々である。目の前がおじさんならまあいい。女性はちょっと厳しい。こういうのなんとかならんものか、と思う。
阿久津さんの文章とその内容が非常に印象に残ったので、一部だけめいっぱい引用した。(たぶん一回きりだと思っている、著作権とかうるさい世の中なので)
速読批判が正論すぎてこれは良い点をついていると思った。
自分サイズでしかものを考えない。これは自分もたまに当てはまっている。自分に都合のいい本ばかり読みたくなる日もある。
心理学、文学、科学、環境、エネルギー、生物、芸術、哲学といろいろまわった。
立岩真也さんについて語る本があったので購入。
仕事関係としては、障がいについて深く考える本を数冊購入。
まあ、久しぶりにいったのでやはり新陳代謝を感じた。知らない本がけっこう置いてあった。
今日も朝から晩まで本を読んでいたように思う。
さすがに残業の疲れか、朝の7時からカフェは無理だった。
・・・
紙のカバーをお願いした。
明らかにサイズがあっていないものが一冊あった。これで何回目か。
丸善はカバーが若干雑な印象を持ってしまう。有隣堂はいつも完璧だ。
カバーもしっかりできないで、いったい何をしっかりできるというのか、という、歪んだ正義感、仕事観が一瞬頭をよぎってしまった。
つづく