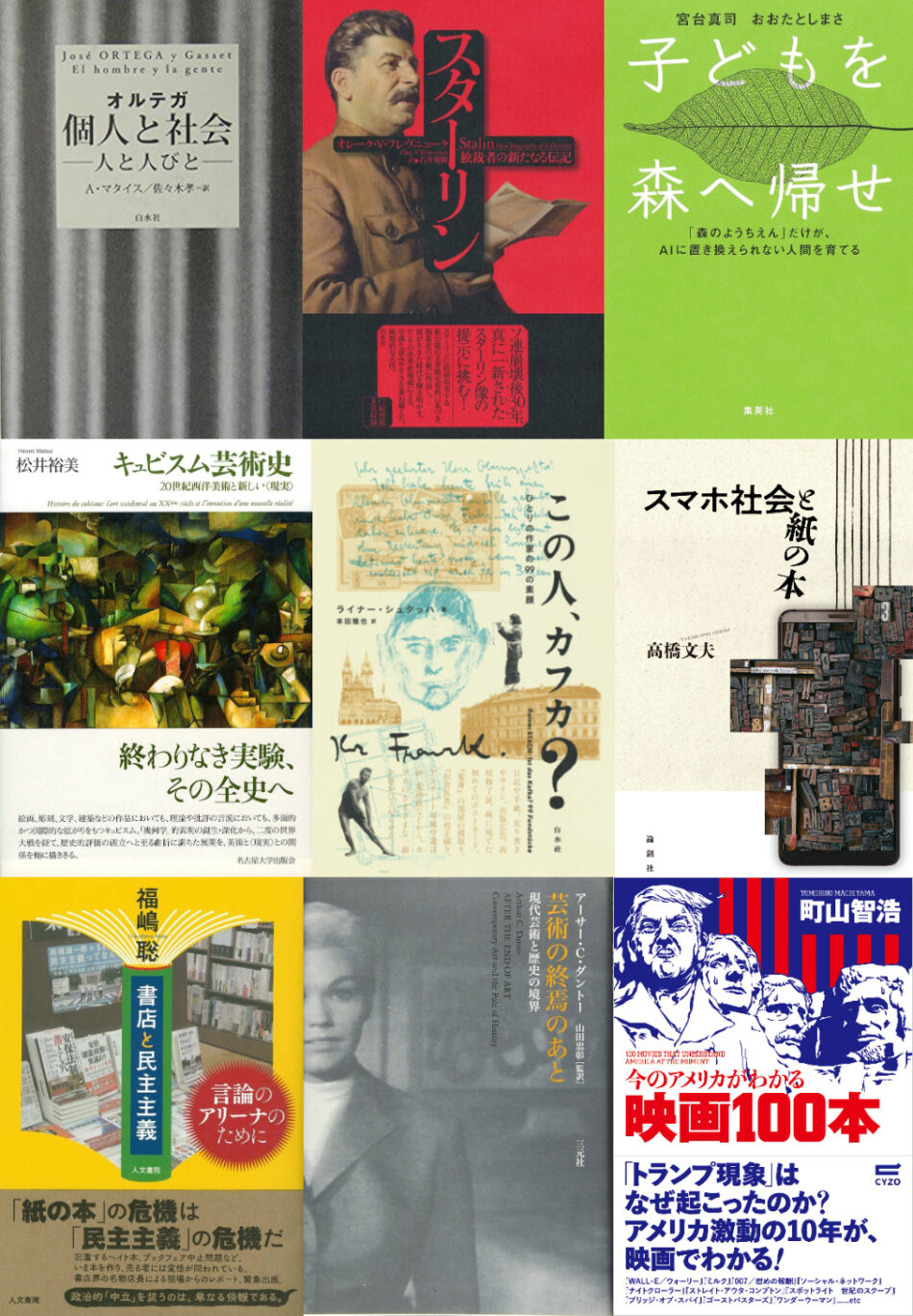■株式会社白水社
公式HP:https://www.hakusuisha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hakusuisha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社集英社
公式HP:https://www.shueisha.co.jp/
公式X(集英社新書編集部)(旧 Twitter):https://twitter.com/Shueishashinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■名古屋大学出版会(国立大学法人名古屋大学)
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UN_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社三元社
公式HP:http://www.sangensha.co.jp/
公式X:https://x.com/SangenshaP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社サイゾー
公式HP:https://cyzo.co.jp/
■有限会社論創社
公式HP:https://ronso.co.jp/
公式(旧 Twitter):https://twitter.com/ronsosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社人文書院
公式HP:http://www.jimbunshoin.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/jimbunshoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
電子書籍と紙では当たり前だけれども双方にメリットとデメリットがあり、自分はこの5年ほど両者のあいだを行ったり来たり(とは言いつつも99%は紙)しつつ、自分なりに見極めてきたつもりで、結局のところ紙が勝つという結論に辿りついたものの、恐らく長期的に見れば自分のような紙派はいずれマイノリティの中のマイノリティになっていくのだろうと、『スマホと紙の本』を読み終わったあとに思ったというよりか、感じたであったが、と言いつつもこうしてwebに向けて謎の記録を残し、誰かに語りかけながら文章を書いている気になっている自分というのも確かに存在していて、そこが僅かに残された電子の可能性というか、これから新しいことをやっていくには不可欠な存在なのかもしれないと、若干の悔しさを感じつつも、hontoであがってくる電子書籍のクーポンの数々を見ていると、そこまでして電子書籍を広めたいのかという、業界人の必死な思いも伝わってきて、正直なところ、本がただの売り物となって、広告で踊らされているように見えてきてしまい、複雑な気分が拭い去れないなか、さていよいよ『スマホと紙の本』の内容について少しだけ触れてみようという段になってきた。
「読書時間が長ければ長いほど想像力や共感力がそうでない人と比べて高かった」「読書時間が長ければ長いほどそうでない人と比べて読解能力が高かった」といった類の調査結果、言説というものを自分はあまり信用しないというか、むしろ当たり前のことであって、それは「筋トレを長く続けた人はそうでない人よりも筋肉量が多かった」くらい当たり前すぎて何を今更感が強くて逆に苛立ちを覚えたのであるが、自分は正直そんなことよりも大事な視点、観点があると思っていて、むしろ「読解能力が高い人ほど本が好き」「読解能力が高い人ほど本を楽しく読める」くらいの勢いで書いた方がインパクトが残るというか、真理を突いていると思うであるが、まあそんなことは軽く聞き流されてしまうか、信用してもらえないかのどちらかなのかもしれないが、自分はこの主張をさらさら譲る気にもなれないのは相応の理由があって、そもそもなぜ人は本を読むのか、読み始めるのかという原点に帰って考えることがやはり重要であって、それは結論から書いてしまえば自分が思っている世界とは違う世界は目の前に現われてくるからであって、言い換えれば自分が正だと思っていた価値体系、価値観、価値の世界がどうやら一般的なそれとはどうやらズレているようだと気が付いてからようやく人というものは他人の考えや感じていること、意見というものに耳を傾け始めるのではないだろうかと、それに尽きると思うのであるが、意外とそういうことを真面目に書いている本は少なく、まあそれは置いておいて、人間は最終的に自分と世界とのずれを認識することで普遍的な価値体系というものに初めて触れ、そこで思考は形をかえつつ丸くなっていくのであり、文字通り削れて削れて丸くなっていくことによってある程度普遍的な思考と自分の信念が共存できるようになって初めて読解力というものが正常になると思うのであるが、そういうことは確かに語られることは少ないかもしれないけれどもやはり池田晶子だとかヘーゲルだとかプラトンというのは大まじめにそういうことを昔から書いてきたのであって、なぜ今更こんなところでそれを強調せずにはいられないのかというこの自分の気持ちがいたたまれなく、ああ、だから出版業界も本も図書館も、よくわからない資格の本をメインに売りだし図書館は読書の時間ではなくもはや勉強の場所勉強をするところ勉強で成り上がるための踏み台にしかなっていないのではないかと、これを延々と語ればただの愚痴にしかならないだろうからそろそろここでこの『スマホと紙の本』の感想とさせて頂きたい。
・・・
メモ
インスタレーション・・・・展示空間そのものがひとつの作品となるような表現手法
絵画 ≒ ベッドルーム・インスタレーション
➡純粋なものの消滅
ベルディング
“「現代芸術は、なるほど芸術の歴史の自覚を表現しはするが、もはやその歴史を先に進めはしない」” P28
(『芸術の終焉』)
グリーンバーグ
“「私のみるところ、モダニズムの本質は、ある規律そのものを批判するためにーーーそれを破壊するためにではなく、その機能のおよぶ領域内で、それをより強固に確立するためにーーーその規律に独自の方法を用いることにある」” P31
(『芸術の終焉』)
『スマホと紙の本』
メモ
(ニューヨークタイムズに執筆しているバーカーソの言葉)
“「書物は・・・・・・コンピューターと直結しないデータ処理方法である『オフライン』でやる方法として、・・・・・・避難港とみなされるだろう。・・・・・・ある本に没入し、音楽を聴き、絵画の視覚領域に入りこむ。・・・・・・自我の時間は、深い時間、接続の時間、本質的に忘却可能だという特徴をもつ時間である」” P171
“(・・・)
“(・・・)「書物はページをめくる速度によって空間の中で経験を移動できる方法であり、人間と共通の分母で括ろうとする考え方からの逃走となる。・・・・・・この逃走は皆と違う顔の表情への逃走であり、分母から分子への、個人であることへの私的な存在であることへの逃走にほかなりません」” P171
読書で心に格納された言葉は免疫細胞に近いものを持っている。困難が訪れるとこの免疫細胞の迎撃システムが作動し、一斉にし言葉による反撃が始まる。この引き出しにしまいこまれた言葉の数々は、眠れる獅子のように、ひそかに眠り、その時を待っているのである。。。。。。