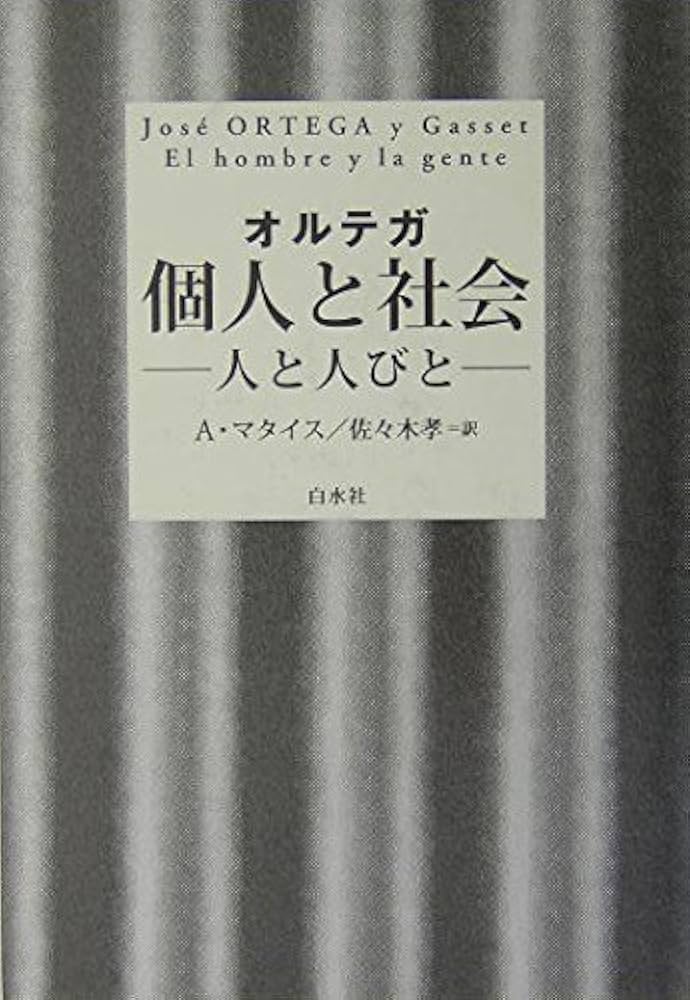■株式会社白水社
公式HP:https://www.hakusuisha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hakusuisha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
個人と社会という言葉を説明するために何故ここまでページを割いて説明しなければならないのか。当たり前だが当たり前に人は考えていないであろうことを今から書いてみようと思う。まず、単純な言葉ほどその意味を定めるには膨大な言葉が必要になる。それはなぜかと言うと、解釈に幅が生まれ、万人が納得するような定義をすることができないからである。幸福という言葉が端的にそれに該当する。よくある話ではあるが、それほど多くは語られていないであろうことを書いてみる。幸福には内的な幸福と外的な幸福があると考える。外的な幸福は受動的に行われるもの、享受するもの、消費するものであり、内的なものは創造的なこと、生産すること、能動的に行われるものと考える。お金持ちになれば幸せだという単純明快な発想は外的な幸福の典型的な例である。人はそれぞれ、内的な幸福と外的な幸福とを程よいバランスで、各々の感性に従って享受するものと自分は考える。なぜ働くのか。それは人を幸せにするためだと人はよく言うが、その場合、当人は与える側、消費者は与えられる側だとみなせるので、外的な幸福によって人々を幸せにできるという発想がそこには存在すると考えられる。ただ、働くことそれ自体が目的であるような、自分自身が目的であるような場合は、幸福を与えつつ自らも内的に幸せになれたりする。従って、なぜ働くかという問いに対して幸せのためだと答える場合、それは二重の意味が含まれていて、内的なものと外的なものがある比率で同時に存在することになる。話がそれてしまった。言葉の意味を定めるにはそれ相応の膨大な文章を必要とするのであった。それは解釈に幅が出るからであった。しかし逆説的に、解釈に幅が出にくいものが存在する。それは論文のような体系立った文章である。こういうものは、短い言葉とは逆に、相対的に短い文書で言い表せることができる。そういうものは人は要約と呼ぶ。ここでようやく、人はが普段あまり考えないこと、語らないことを言う準備ができた。短い言葉に対しては長文を、長文に対しては短い言葉で定義することがある程度可能だというこのことに自分が気づいたとき、なんだか非常に不思議な気分になった。またしても逆説というものがここで浮かび上がってきた。逆説。なんと不思議な、なんとも捉え難い存在。パラドックス。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
付録:AIとの対話
カントの義務論は幸福の価値を「自由」の度合いに依拠するものであって、精神性を最高の価値と置くものであり、功利主義はその対をなすものと私は考えます。このテーゼを端的に批判していただけませんか。500文字以内でお願いします。
ChatGPT:
あなたのテーゼはカント倫理と功利主義の対比を明確に打ち出していますが、いくつかの点で再考の余地があります。第一に、カントの義務論において幸福は道徳的価値の基準ではないものの、「自由」の度合いが幸福の価値を規定するというのは、やや曲解の可能性があります。カントにおいて自由とは理性に従う自己立法の能力であり、幸福の尺度とは直接的には結びつきません。第二に、「精神性を最高の価値と置く」とする点も、功利主義との対比を強調しすぎて、カント倫理の普遍性や義務の形式性を曖昧にしてしまっています。カントにとって重要なのは「善意志」であり、それは結果ではなく動機に根ざします。よって、幸福を自由や精神性と結びつけてカント倫理を捉えるのは、主観的価値観の導入であり、誤読の可能性があります。
あなた:
ありがとうございます。直接に結びつかないものの、幸福というものを前提としているのではありませんか。それとも、幸福というものを全く考慮せずにそのような体系を作ったのでしょうか。これに対して反論を手短にお願いします。400文字以内だと助かります。
ChatGPT:
確かにカントは幸福を完全に無視しているわけではありません。ただし、彼の倫理体系において幸福は道徳の基礎ではなく、理性によって導かれる「義務」に従うことが中心です。カントは人間が「幸福を求める存在」であることを認めつつも、それを道徳法則の根拠にはしません。むしろ、幸福の追求は個々人の主観的欲望に左右されるため、普遍的な道徳法則の根拠にはなり得ないとします。したがって、幸福は倫理体系の「前提」ではあっても、その「基礎」ではないのです。
あなた:
前提であり、基礎ではない。やや分かりにくいので、お手数ですが300文字程度で説明をお願いします。
ChatGPT:
カントにとって幸福は、人間が自然に求める目的であり、倫理を考える上で無視できない「前提」です。しかし、それは理性によって導かれる普遍的な道徳法則の「基礎」にはなりません。なぜなら、幸福は人それぞれ異なる内容を持ち、主観的で不確実だからです。道徳はそうした変動的なものに依存せず、自律的な理性に基づくべきだとカントは考えました。
あなた:
ありがとうございます。もう少し考えてみます。
ChatGPT:
どういたしまして。じっくり考える価値のあるテーマですね。カント倫理は一見厳格に見えますが、その背景には人間の尊厳や理性への深い信頼があります。もしまた考えを整理したり、他の視点を取り入れたくなったら、いつでもお声がけくださいね。考えるプロセス自体が哲学ですから。