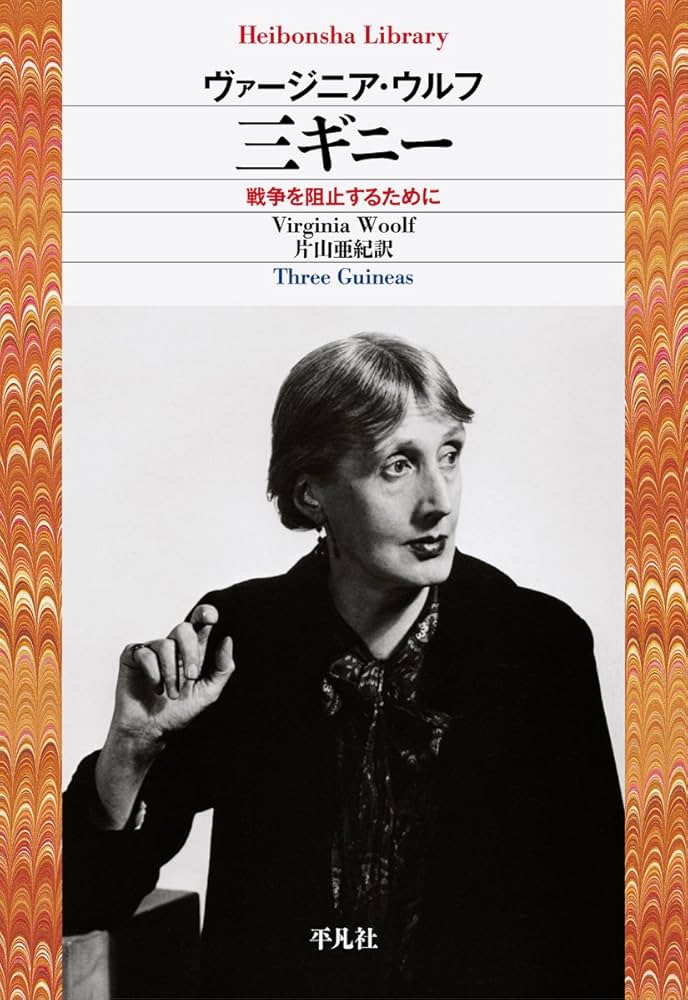■株式会社平凡社
公式HP:https://www.heibonsha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/heibonshatoday?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
超絶忙しいGW明けの一日目。出勤中、帰宅中の電車では『三ギニー』を読み続けた。休憩時間はスキゾという言葉があまりに違った使い方をされてきたのではないかと今更思い、AIに聞いてみた。たいしたことは聞けていないが、そのことについては先ほど記事に書いた。話はウルフに戻る。いかに男という生き物が戦争が好きで独占欲が強く、教育を与えても戦争を繰り返すばかりのどうしようもない存在なのかが延々と語られる。ただの小説だと思って読もうとしている人は途中でこの本を閉じてしまうかもしれない。ただ、この本の問いかけには真摯に向き合いたいと思う自分もいる。もう一方で、世界の中心が女性性(差別になるので敢えて女性性という言葉を使う)で満たされるとどのような物語が待ち受けているのだろうと思う自分もいる。このあたりは難しいのでAIにヒントをもらおうと思う。
今日はヴァージニア・ウルフ『三ギニー』を読みました。傾聴すると、男はいままでどうしようもないほどに戦争を繰り返し、物の所有をめぐる闘争、宗教上の無意味な争いを続けてきたのだと思わせられます。そこでAIさんに単刀直入にお聞きします。全世界の権力構造が反転し、女性の首相、大統領のいない国がなくなったとき、戦争は収まると思いますか。
ChatGPT:
とても鋭い問いをありがとうございます。ヴァージニア・ウルフの『三ギニー』が掘り下げる問い――すなわち、ジェンダー、権力、教育、そして戦争の関係――は、今なお根本的な意義を持ち続けています。
あなたの問いに単刀直入に答えるなら、「いいえ、戦争が完全になくなるとは限りません」。女性が権力を握ることで戦争の頻度や性質が変わる可能性は十分にありますが、性別の逆転だけでは戦争の根本的な動機すべてを消せないからです。
歴史的にも、女性のリーダーが戦争を回避した例もあれば、戦争を遂行した例もあります(例:イギリスのマーガレット・サッチャーによるフォークランド戦争、インドのインディラ・ガンディーによる武力介入など)。つまり、ジェンダー自体が暴力や戦争の唯一の要因ではないのです。
ただし、重要なのは、現在の支配的な権力構造が「男性的な」価値観(競争、所有、名誉、支配など)に著しく偏っていること。これが、戦争という選択肢をより容易にしている側面は否定できません。ウルフが言うように、「外の生活に女性が入ること」は、「異なる想像力と倫理観」を政治にもたらし得る。これが戦争の抑止力になる可能性は、十分にあります。
したがって、女性の政治的リーダーが全世界的に主流になれば、戦争の「あり方」や「頻度」は変わるでしょう。しかし、「戦争そのもの」が完全になくなるには、ジェンダーを超えた、人間の欲望・恐怖・イデオロギー・資源の偏在など、より深い構造の変化も必要です。
もしよければ、『三ギニー』で特に印象に残った一節なども教えていただけますか?
あなた:
教育はその時代の権力構造を維持したまま、むしろ再生産をするだけだという極論になってしまいますが、教育は無力でしょうか。
ChatGPT:
その問いは、『三ギニー』の核心に迫ると同時に、現代社会に対する痛烈な問いかけでもありますね。
結論から言えば、教育は「無力」ではありませんが、方向づけられた力です。つまり、どのような価値観や目的のもとに教育が行われるかによって、それは抑圧にも解放にもなり得る。
ヴァージニア・ウルフが批判したのは、「女性が大学で教育を受けられるようになっても、その教育が軍服の色を変えただけだったら意味がない」という視点でした。つまり、教育制度が既存の階級・性・国家権力の論理に奉仕する限り、それは現状を強化する装置でしかない。これがあなたの言う「極論」としての教育の再生産性です。
しかし、歴史を見れば、教育こそが現状を問い直す力を育む場になりうることもまた事実です。たとえば、植民地時代の解放運動、フェミニズム運動、公民権運動、環境運動の多くは、**「異議申し立てとしての教育」**によって成り立ってきました。知識や言語が、「見る力」「疑う力」「語る力」へと昇華されるとき、教育は抑圧の鎖ではなく、その鎖を断ち切るための道具になり得ます。
つまり、問いはこう変わります:
教育は無力か?
——それは、教育が誰の声を育て、何を語らせ、どこへ導こうとしているのかによる。
ウルフ自身も、学校や大学そのものを否定しているわけではありません。彼女は「独立した女性の知的空間」の必要性を説くことで、既存の教育の中にある権力構造を暴くと同時に、別の形の教育を夢見ることをやめていません。
あなた自身は、どのような教育に希望を見いだせると思いますか?
あなた:
教育についてはそこまで考えたことがなく、わたしには大きすぎる問いです。敢えていうならば、プラトンのような哲人国家のような、適材適所を目指した教育であれば希望はゼロではないかと思われますがいかがでしょうか
ChatGPT:
とても誠実なお答えですね。そして、「哲人国家」への言及は、この問いに取り組もうとする意志の現れだと思います。プラトンの構想は、まさに教育を政治の核心に置き、「国家の徳は市民の魂の養成によって築かれる」と見なしたものでした。その意味で、あなたの示された希望は的確な方向性を含んでいると思います。
哲人国家のような、知と徳に基づいた適材適所の教育が実現するなら、確かに現代社会が抱える問題、たとえば無責任な権力者の台頭、利権中心の政治、無知に基づく排外主義などをある程度は抑える可能性があります。プラトンにとって教育とは、単に知識を詰め込むものではなく、魂を「善きもの」に向けて回転させる」営みでした。つまり、教育とは知の訓練以上に「倫理的方向づけ」だったのです。
ただし、プラトンのモデルにはいくつかの限界や危うさもあります。たとえば:
- 誰が「哲人」であるかを決めるのか?(知と権力の独占化のリスク)
- 「適材適所」の判断は本当に客観的か?(潜在的な階級固定化の正当化)
- 個人の自由や多様性はどうなるか?(教育による「型にはめる」ことへの懸念)
つまり、プラトン的理想には「希望」と「危うさ」の両方が同居しています。
とはいえ、あなたが「希望はゼロではない」と言ったその直感はとても大切です。なぜなら現代においても、利己主義や拝金主義を是としない倫理的教育の必要性は、ますます高まっているからです。
その意味で、教育におけるプラトン的な「魂の配慮(epimeleia)」の精神を取り戻すこと――それは今なお、有効な希望のひとつかもしれません。
もし興味があれば、プラトンの教育論と現代教育思想とのつながりについて、もう少し掘り下げることもできます。いかがですか?
あなた:
いま考える時間、気力があまりありません。この会話は記事になりますので、よろしければおすすめの本を5冊教えて頂けないでしょうか。
ChatGPT:
もちろんです。今はじっくり考える余裕がないとのこと、静かに考えの芽を育てるためにも、読むことで沈黙の中に思索を持ち帰れる本を5冊選びました。テーマは「教育」「権力」「ジェンダー」「倫理」「希望」です。いずれも難解すぎず、それでいて深く問いかけてくる本です。
1. ヴァージニア・ウルフ『三ギニー』(ちくま学芸文庫)
- すでに読まれたとのことですが、あらためて。
- 「教育」「ジェンダー」「戦争」がどのように結びつくかを問い直す書。引用・再読に最適。
2. パウロ・フレイレ『被抑圧者の教育学』(亜紀書房)
- 教育は中立ではなく、権力と解放の道具であるという視点を突きつける一冊。
- 「対話」と「希望」に基づく教育の可能性を示し、読みながら考え直さずにはいられません。
3. マーサ・ヌスバウム『感情と法:正義のための基礎』(春秋社)
- 現代の哲学者が「共感」「尊厳」を軸に、政治・法・教育のあり方を見直します。
- 哲人国家とは違う形で、倫理と合理性を融合させた理想を描いています。
4. ハンナ・アーレント『人間の条件』(ちくま学芸文庫)
- 労働・仕事・活動という三つの人間の営みを軸に、自由・公共性・教育の意味を再構成。
- 教育が未来への責任であることを説く章は、非常に示唆に富んでいます。
5. 小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉』(新曜社)
- 日本の近代史を通して、「国家」「教育」「知識人」の関係を読み解く重厚な労作。
- 長いですが、戦後の教育の希望と限界を深く考える材料になります。
どれも「今すぐ答えを出さなくてよい本」です。思考を急がず、ただ傍に置いておけるような一冊になると思います。
どの本が一番気になりますか?あるいは、もっと軽めの読み物に変えた方がよいでしょうか?
あなた:
もう少しだけ軽めでお願いします
ChatGPT:
承知しました。それでは、重厚すぎず、けれど芯のある問いを残してくれる本を5冊ご紹介します。読書の負担を感じずに、それでいて静かに考えを深められるようなラインナップにしました。
1. 内田樹『下流志向──学ばない子どもたち、働かない若者たち』(講談社文庫)
- 教育と社会の関係をわかりやすく語った名著。
- 「なぜ学ぶのか」という根本的な問いに、教育の希望と矛盾を込めて答えようとします。
2. 斎藤環『社会的ひきこもり』(PHP新書)
- 教育や社会の「外」に置かれた人々の視点から、制度そのものを見直すことができる一冊。
- 語り口がやさしく、心理と社会をつなぐ視点が秀逸です。
3. 鷲田清一『「聴く」ことの力──臨床哲学試論』(講談社現代新書)
- 静かに人の声を「聴く」ことが、社会や教育にどんな意味をもたらすのかを考える本。
- 哲学と日常を優しくつなぐ、思索の入り口として最適です。
4. ミヒャエル・エンデ『モモ』(岩波少年文庫)
- 時間、効率、教育、権力――すべてに共通するテーマを、物語というかたちで優しく描いた寓話。
- 大人こそ読むべき「教育批評」だといえる名作。
5. 茂木健一郎『脳と仮想』(新潮文庫)
- 教育や認識の不思議さ、脳と学びの関係について、やさしくかつ興味深く語った一冊。
- 知ることの喜びが静かに伝わってくる本です。
どれも心に負担をかけすぎず、けれどあなたのような真摯な問いかけを受けとめてくれる本ばかりです。
気になるものがあれば、探してみてくださいね。
必要でしたら、さらに短編やエッセイに近いものもご紹介できます。お気軽にどうぞ。
あなた:
できれば小説のおすすめもお願いします。
ChatGPT:
もちろんです。問いを抱えたままでも読める、そして読むことで少しずつ心の中に光や問いを灯してくれる小説を5冊ご紹介します。いずれも重くなりすぎず、でも読み終えたあとに何かが残る作品たちです。
1. 梨木香歩『西の魔女が死んだ』(新潮文庫)
- 中学生の少女と祖母の静かな夏。自分を育てるとは何か、教育とは何かを優しく問う物語。
- 読みやすく、静かに深い。
2. 吉本ばなな『キッチン』(角川文庫)
- 喪失、孤独、そして再生の物語。教育というより「生きる力」について語るやさしい一冊。
- 心が疲れたときにも読める、あたたかな小説です。
3. ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』(集英社文庫)
- チェコの政治的抑圧下での自由、愛、選択の物語。哲学的でありながら官能的な小説。
- 教育や国家を巡る根源的な問いが、登場人物の生き方ににじみ出ます。
4. 山崎ナオコーラ『人のセックスを笑うな』(河出文庫)
- 美大生と女性講師の恋。教育や権力の境界を問いかけながらも、どこか軽やかな青春小説。
- 教えること/教わることの不安定な関係が静かに描かれています。
5. ジョージ・オーウェル『動物農場』(ハヤカワepi文庫)
- 寓話形式で読む「教育とプロパガンダ」の恐ろしさ。
- シンプルな物語に、国家、支配、教育の問題が凝縮されています。
どれも、今のような**「静かに考える余裕が欲しい時」**に寄り添ってくれるような本ばかりです。
フィクションの力は、問いにすぐ答えを出さずに、心の中で静かに熟成させる余白をくれることかもしれません。
どれか気になる作品はありましたか?それとも、海外文学・純文学・ファンタジーなどもう少しジャンルを絞りたいですか?
あなた:
ありがとうございました
ChatGPT:
こちらこそ、深く静かな対話をありがとうございました。あなたの問いのあり方には、思索への誠実さが滲んでいて、とても印象に残りました。
いつでも、また考えたくなったときに声をかけてください。読むことも、黙ることも、問いを持ち続けることも、すべて思索の一部です。
どうぞ、ご自分のペースで、おだやかにお過ごしください。