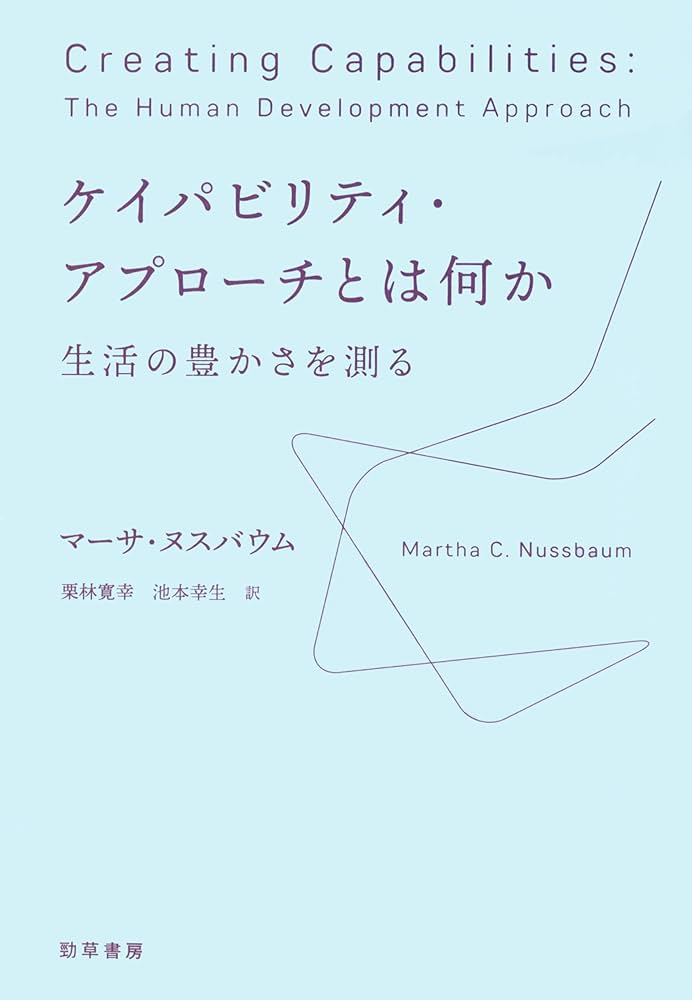■株式会社勁草書房
公式HP:https://www.keisoshobo.co.jp
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/keisoshobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
画像を結合させるサイトに入れなくなって一週間くらいがたつ。今日も駄目だった。しばらく一枚にしようと思う。なるべくその日に一番読んだ本を画像にあげようと思う。
・・・
メモ
『ケイパビリティ・アプローチとは何か 生活の豊かさを測る』
“これら一〇のケイパビリティをすべての市民に提供することが、社会正義の必要条件である。” P53
ChatGPTより↓↓↓
ヌスバウムは、人間の尊厳を支える「最低限備わるべき10のケイパビリティ」を提案し、どの社会でも保障すべき普遍的価値として主張しています。以下は代表的な整理です:
- 生命(Life)
– 通常の寿命を全うできること。早死や価値がないと感じるような生存状態を避けること スタンフォード哲学百科事典+10J-STAGE+10k-junshin.repo.nii.ac.jp+10。 - 身体的健康(Bodily Health)
– 十分な栄養・医療・避難所があり、リプロダクティブ・ヘルスも含む健康状態を維持できること iep.utm.edu+9changingminds.org+9CSL4D+9。 - 身体的完全性(Bodily Integrity)
– どこへでも安全に移動でき、暴力や性的搾取などから保護される身体の統制権があること ウィキペディア+5changingminds.org+5journals.law.harvard.edu+5。 - 感覚・想像力・思考(Senses, Imagination, Thought)
– 教育を受け、自ら考え、文化・宗教・芸術などを自由に体験・創造できる能力 ウィキペディア+7changingminds.org+7Ragged University+7。 - 感情(Emotions)
– 他者との愛着や悲しみ、怒りなど多様な感情を経験し、恐れや心的外傷に支配されないこと changingminds.orgウィキペディア。 - 実践理性(Practical Reason)
– 自己の人生を組み立てる上で、善悪を吟味し、良心に従える思考力を持つこと ウィキペディア+4changingminds.org+4ウィキペディア+4。 - 帰属・交わり(Affiliation)
– 他者との社会的交流、差別のない尊厳ある扱いを受ける能力 ウィキペディア+8千葉大学OPAC+8ritsumei-arsvi.org+8。 - 他の種との関係(Other Species)
– 動植物や自然との調和ある関係を築ける能力 さとかん・佐藤寛公式ホームページ+7ウィキペディア+7ウィキペディア+7。 - 遊び(Play)
– 笑ったり楽しんだりできる簡潔で自由な遊びの時間を持つこと ウィキペディアウィキペディア。 - 自らの環境に対する統制(Control over One’s Environment)
– 政治参加や発言の自由、平等な財産権、働く場での尊厳など、自分の社会環境を変える力を持つこと ウィキペディア+5ウィキペディア+5changingminds.org+5。
これらは、「国家や社会が最低限保障すべき自由」であり、文化や宗教などを問わず、普遍的な正義の基盤として提案されています iep.utm.eduウィキペディア。
🌐 アマルティア・センのケイパビリティ・アプローチ
一方、センは「ケイパビリティ」を以下のように捉えています:
- 単に行う「機能(functionings)」ではなく、「何を選んでできるか」という自由のあり方そのもの。
- 富や所得ではなく、この自由(real freedoms)こそが福祉を評価する根本指標であり、それらは個人ごとに異なる背景(環境・能力・好み)によって異なる 千葉大学OPAC+9ウィキペディア+9さとかん・佐藤寛公式ホームページ+9どさんこ北国の経済教室+2ウィキペディア+2ritsumei-arsvi.org+2。
そして重要な点は、センはヌスバウムのように固定的な「リスト化」を拒否しており、ケイパビリティの具体的内容は状況によって柔軟に設定すべきと考えています。 J-STAGEiep.utm.edu
“各国がケイパビリティの保証を促進するためによくとる方法の一つは、成文憲法を通じるものであるが、それは手間がかかり、超(圧倒的)多数による手続きを経なければ改正できない。” P57
・・・
『スタートアップの経済学』(有斐閣)
“スタートアップ企業を公的に支援することのより強い根拠は、市場の失敗(market failure)にあります。一般的には、社会の効率的な資源配分において市場は有効に機能します。しかし、独占、外部性、公共財、あるいは情報の非対称性などの特徴を持つ市場では、社会的に望ましい水準での取引が行われず、効率的な資源配分が達成できません。” P239
アントレナーシップ教育は創業に対し正の効果を持つとは限らないという結果を示した二つの研究
➡P257
具体例
J-Startupプログラム(経済産業省)
Tokyo Innovation Base 等
・コワーキングスペースとの違い
➡メンタリング、卒業制度などがコワーキングスペースにはない
・・・
楠木建『経営読書記録(裏)』
“奴隷が奴隷である理由は、自分以外の誰か(=主人)が決めた価値基準への従属を強制されていることにある。他者から与えられた価値基準から自由になる。そこにリベラルアーツの本質がある。” P256
リベラルアーツ⇔メカニカルアーツ
リベラルアーツ・・・・・・「思い通りにならない世の中を、思うがままに生きる力(技術)」
・・・
選挙が明日ということなので、自分なりに考えた。
執行さんは絶対に選挙に行かないということであるが、自分はとりあえず行く。
減税だとか、時給1500円だとか、そういうちょろい政策は自分にはなびかない。
実績を持ち、スタートアップを応援する政党に票を入れる。
スタートアップの負の側面(生存確率の低さ等)はいろいろあると重々承知しているが、SmartHRのような会社がどんどん生まれてくれば日本も明るくなるのではないか。
起業精神を応援してあげることが長期的には日本を物質的に豊かにする。物質的な豊かさが安定すればそのうち精神的な豊かさを醸成させる土台が生まれると自分は考える。
とりあえず明日もヌスバウムの本を読む。