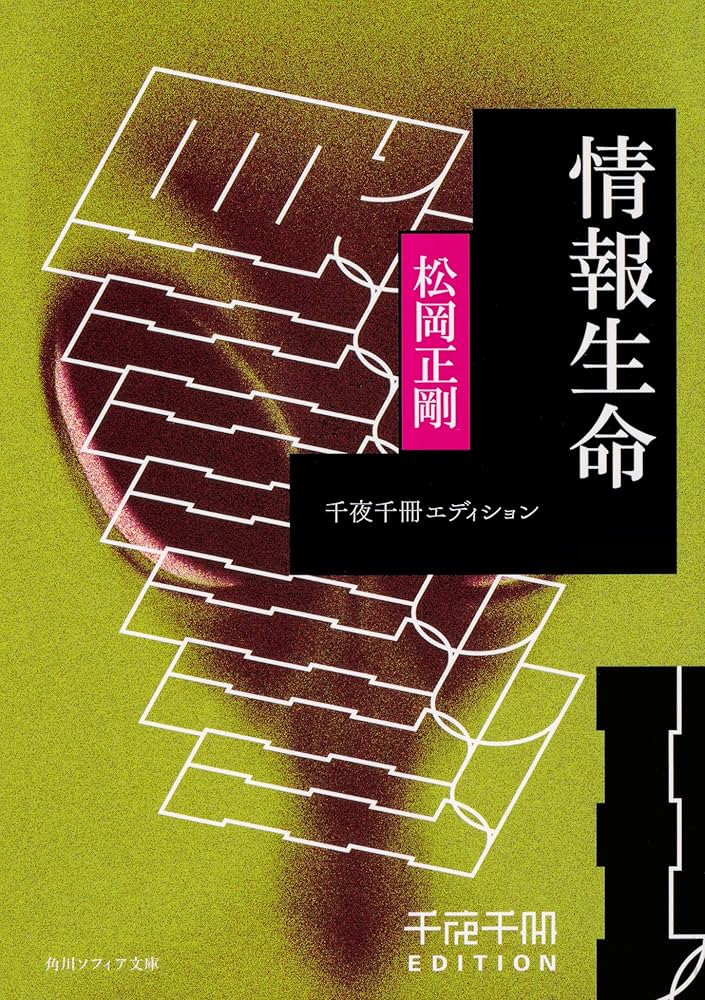■株式会社KADOKAWA
公式HP(文庫):https://kadobun.jp/special/gakugei/#offcanvas
公式X(角川ソフィア文庫)(旧 Twitter):https://twitter.com/kadokawagakugei?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
PCを新調した。あらゆるものが速くなった。気持ちがいい。
書くべきことがたまりすぎていた。ボロっちい2万円のノートパソコンはあまりに重すぎた。予め起動させておいて、しばらく放置してからいじる、という日々とさよなら。こんなに素晴らしいことはない。
ということで、たまりにたまっていた読書日記を延々と書いていこうと思う。
・・・
昨日、キケロが多読について批判している件に触れた。しかし冷静に考えてみてほしい。毎日毎日同じ本だけを読むように人間はできているだろうか。毎日同じルーティンだけで済むような仕事で満足するのが人間だろうか。そんなわけないだろうと思う。毎日ただひたすら流れ作業に満足できないのが人間なのであり、毎日大量の本に触れていたいのが私、読書梟なのである。
ということで、新・読書日記514では松岡正剛『情報生命』について触れてみようと思う。
昨日『デリダの遺言』を読み、エクリチュールとはプログラムのように、予め書き込まれたものであって、人間の言語能力は書き込まれたものによって作動している。よって、プログラム自身がプログラムについてなにひとつ知ることができないように、人間も書き込まれたものが何かを知ることができないという話についてここに書いた。
生命も文脈という比喩、アナロジーを使って捉えることができる。
日本語はそもそも誰がつくったのか、そんなこと誰も知らない。しかし、誰もが当たり前のように習得し、当たり前のように使用する。これがいま書いたプログラムと似ている。つまり、予め言語が人間に埋め込まれているということである。人類史という文脈の西暦2025年というプロットにただ立っているだけなのである。言語という観点からみると、生命とは文脈だ、と言っても突飛なことはない。
ここまでを前置きとして、ではベイトソンやモリス・バーマンは何を考えたのか。自分は両者の本を何回も読んだ本だけれども、読むたびに見方は当然変わる。今日はさきほど書いた文脈と言語について『情報生命』のなかで落とし込みながら読み進めてみた。
メモ
“バーマンは、魔術から科学への変容によって「ミメーシス」という世界観ががたがたち解体していったことに気が付いたのだ。” P71
バーマン「世界は新たな再魔術化が可能であるはずだ」
ベイトソン「事実と価値は分けることができない」
・・・
彼らの問題意識は近代の合理性と人間の在り方についてであった。
エクリチュールの話とはあまり関係ないように思えた。彼らはもっと先のことを、次元の高いところで考えていた。
言語はプログラムされているかもしれないが、文化まではプログラムされていない。
21世紀にChatGPTが生まれるように遺伝が組み込まれているわけではない。
突然変異のように、ひょこっと突然現れる。文化は言語・精神が体現されたものであるが、その法則についてまでは人間はとらえきれていない。ゆえに未来予測も困難。
ああ、なんという深さ。生命の奥深さ。