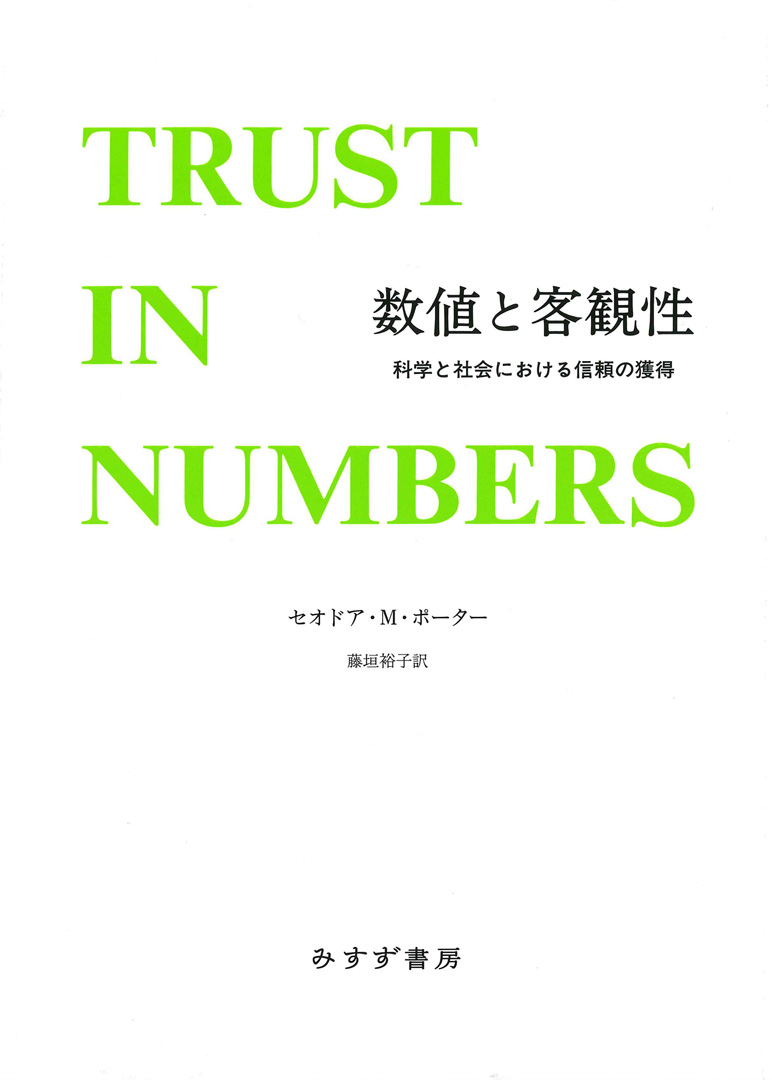■株式会社 みすず書房
公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
・・・忙しすぎる。敢えて自分で忙しくしてしまっていることは認める。
珍しく一冊しか読めていない。
『数値と客観性』は、客観性という概念の歴史を振り返ることから内容はスタートする。
ゲーテとニュートンの対立を思い出す。ゲーテはニュートンのような実験を批判した。
自然を狭い実験室という名の監獄に閉じ込めるのではなく、感性云々、、すべし。みたいな論争が「色」をめぐって繰り広げられた。のちに『色彩論』に発展する。
色は感性や心理に影響を与えるので、それをすべて排除して分析することになんの意味があるのだろうかといわんばかりのゲーテ。気持ちは分かるが最終的にはニュートンが勝ってしまう。そして現代物理学によって『色彩論』の欠点を暴露される。
自分は今「形式と内容のずれ」という、抽象的なテーマに関心がある。
宮台真司教授の「法内ー法外」のシンクロと問題意識をもちろん共有してている。むしろ共有しているからこそ生まれた問いなのである。
人はなぜ形式におどらされるのか?
例を述べる。
自分は「ありがとう」と明らかに言葉だけの感謝をされたことがある。
行動から合理的に推論すればその人物が明らかに本当に感謝していると思えない過去を自分は経験した。
ありがとうという言葉の建前と本音のずれに自分は苦悩したものである。
ありがとうと言えばなんでも済むと思っている輩がいる、そう実感した強烈な体験を自分は経験している。
もちろんこのように書く自分にバイアスがかかっているのは認める。
・・・と、語ればキリがない問いの連続によって私の思索は宮台教授の社会システム論と交差した、
あとでこの問題とモリス・バーマン、グレゴリー・ベイトソンをくっつけてみようと思う。
テーマは「参加しない意識=見物=非内発性」という構成。
つづく