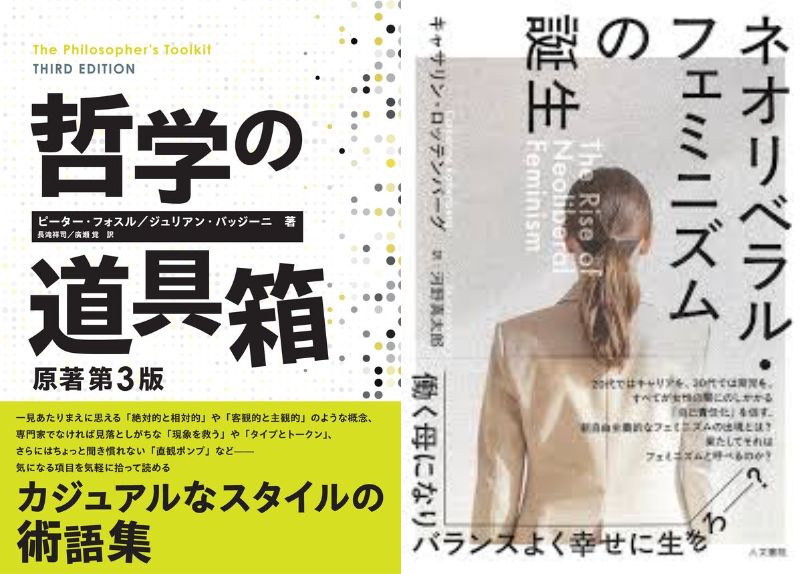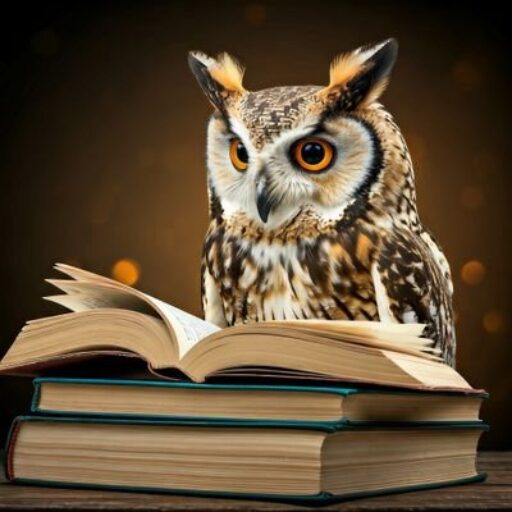■株式会社人文書院
公式HP:http://www.jimbunshoin.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/jimbunshoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■共立出版株式会社
公式HP:https://www.kyoritsu-pub.co.jp/company/c10097.html
公式X(旧 Twitter):https://x.com/kyoritsu_pub
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
ヒュームの法則は「ヒュームのギロチン」と呼ばれるらしい。初めて知った。
ヒュームのギロチンとはなんですか
ChatGPT:
思考時間: 9s
ヒュームのギロチンって何?
要点一行:
「事実(is)からだけでは、価値判断や義務(ought)は論理的に導けない」という原則。しばしば “no ought from an is” と言われます。
出どころ
デイヴィッド・ヒュームが『人間本性論』(Treatise)で、著者たちが説明(is)からいつのまにか規範(ought)へ飛んでいる、と注意した観察が由来。あとから「ヒュームの法則/ギロチン」と呼ばれるようになりました。
何が問題?
- 純粋に事実だけを前提にすると、
結論に「~すべき」が入ったら論理的には無効になります。 - 規範的前提がどこかに含まれていないと、ought は出てこない。
× 例:
① 多くの人がXをしている(事実)
② だから私たちもXをすべきだ(規範)
ーー> 規範前提が抜けていて飛躍。
どうすれば導けるの?
**橋渡し前提(bridging premise)**を明示すること。
- 例の修正版:
① 多くの人がXをしている(事実)
② 「多くの人がしていることは道徳的に正しい」(規範)
③ だからXをすべきだ
この②を出すと、少なくとも論理形式は整います(②自体が妥当かは別問題)。
よくある混同
- **自然主義的誤謬(ムーア)**と似て非なるもの。
- ヒューム:推論の形式に関する指摘(is→oughtの論理飛躍)。
- ムーア:「良い」を自然的性質で定義すること自体が誤りだという主張。
批判・再検討
- 価値判断にも事実記述が絡むという立場(プトナムなど)は、事実/価値の厳密な二分に疑問を投げます。ただしそれでも、規範結論には何らかの規範的前提が要る、というヒュームのポイント自体は多くの場合維持されます。
使いどころ(実務感)
政策議論や倫理議論で、「データ上こうなっている」→「だからこうすべき」という無意識の飛躍を検出するためのチェックツール。
→ 「その結論を支える規範前提は何?」と問い直せます。
必要なら、ヒュームの法則とプトナムの事実/価値二分法批判の関係ももう少し丁寧に整理します。どこから深掘りします?
あなた:
道徳実在論とは
ChatGPT:
思考時間: 5s
道徳実在論(moral realism)とは?
ひと言:
「人はどう思おうが、本当に正しい/間違っているという道徳的事実が(少なくともいくつか)客観的に存在する」という立場。
コア主張(3点セット)
- 真理性:道徳判断は真偽をもつ命題になりうる(cognitivism)。
- 心的独立性:その真偽は、個人や社会の態度・感情から独立した事実によって決まる。
- 認識可能性:私たちは推論・経験・直観などで、それらの事実にアクセス可能だ(どの経路かは学派で異なる)。
バリエーション(ざっくり地図)
- 自然主義的実在論(Cornell realism など):道徳的性質は、幸福や苦痛、協力の安定性等の自然的性質に還元/同定できる。
- 非自然主義的実在論(ムーア、シャーファー=ランドー等):道徳的性質は自然的性質に還元できない独自の規範的性質。
- 強固(robust)vs 省エネ(reductionist):規範の独立性をどれだけ強く守るかで強弱が分かれる。
主要な対立相手
- 誤謬理論(エラー・セオリー):道徳文は真偽を主張するが、全部ウソ(客観的道徳事実は存在しない)。
- 表出主義/非認知主義:道徳文は感情や態度の表明であって、真偽の話ではない。
- 相対主義/構成主義:真偽は文化・合意・手続きに相対的(独立した実在は措定しない)。
よく使われる論拠(超圧縮)
- 現象学的訴求:奴隷制は「本当に」悪い、という私たちの経験的感覚。
- 説明力:道徳的事実を認めた方が、道徳的進歩や非道の批判をうまく説明できる。
- 同伴者論法:知的・実践的理由(論理・認識規範)の客観性を認めるなら、道徳だけ特別扱いできるか?
代表的な反論の種
- クィアネス(奇妙さ)論証:客観的で規範的な性質なんて形而上学的に奇妙では?
- 不一致の事実:文化間で強い道徳的分岐がある。
- ヒュームのギロチン:事実だけから「~すべき」は導けない——> 実在論はこの橋渡しをどう確保するかが勝負所。
直感チェック
「もし世界中の人が“拷問はOK”と信じても、それでも間違いだと言えるか?」
→ イエスと答える人は、道徳実在論に親和的です。
・・・
道徳実在論についてもおさらいした。
客観的に、感情抜きで道徳は存在するという立場らしい。
しかし、、、
感情とはそもそも不合理で、非合理的ではないか。
非合理的なふわっとしたものから客観性をそなえた道徳のようなものが生まれえるのだろうか。
直感的にそうは思えない。いくら時代には時代の道徳が存在するにしても、その可変性のある道徳が法則として固定されるとは到底思えない。
・・・でも面白い命題ではある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ネオリベラルフェミニズムが少しずつ見えてきた。
卵子を凍結しておけばいつでも子供を産める。だから女性は地位を得るまでは子育ては保留にし、20代は男性と仕事で張り合おう、自己を啓発しようという呼びかけ。
技術が結婚観を変えつつあるという、まあアメリカにはよくある話だと思った。
まあ西洋人という感じの考えで、家族主義(だった)日本やその他、家庭を大切にするアジアではあまり流行しそうにない。でも調べると日本では普通に行われているらしい。
いろんなことがありすぎて、奇妙なことには思えなくなってきた。
全人類エンパワーメント化。
つづく