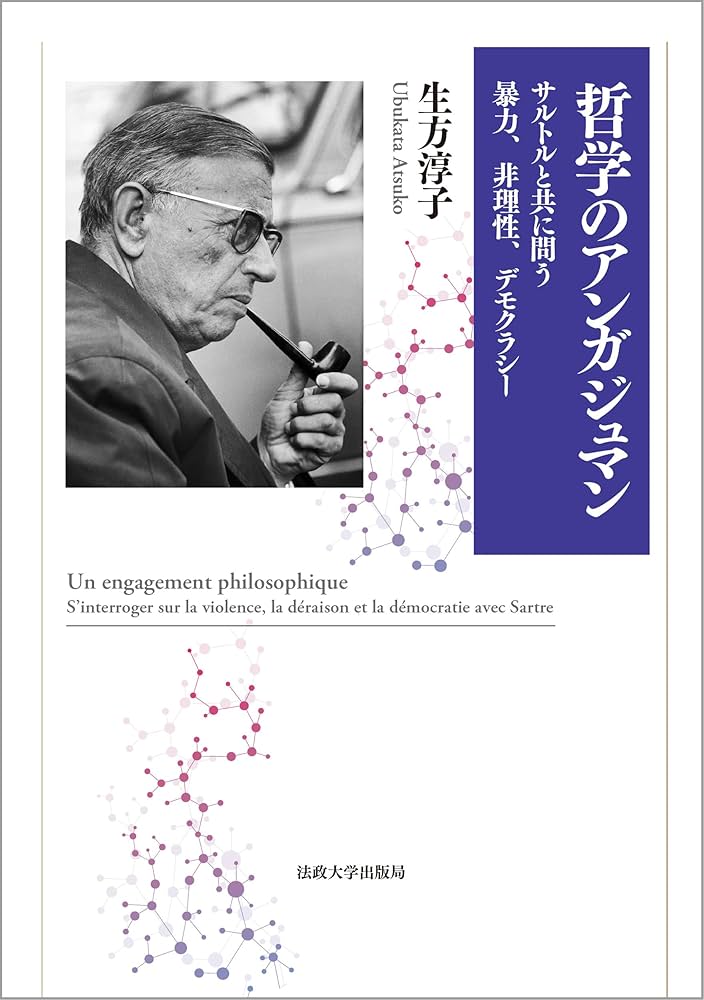本記事は「読書ブログシリーズ」第2部・文学と孤独の読書の一篇である。
サルトルといえば実存主義の旗手であり、『嘔吐』『存在と無』で有名だが、
もうひとつ見逃してはならない要素がある――それが「モテなさ」である。
サルトルの孤独と文学的欲望
サルトルはシモーヌ・ド・ボーヴォワールと契約関係を結び、
「自由な愛」の実験をしたことで知られる。
だが同時に、彼自身がモテる存在だったわけではない。
外見的な劣等感、孤独感を抱えながら、
哲学と文学にそのエネルギーを注ぎ込んだ。
「モテなさ」はサルトルの文学を理解するうえで、
決して無視できない心理的背景なのだ。
「眼差し」とモテなさの構造
サルトル哲学の核心にあるのは「眼差し」である。
他者の視線にさらされるとき、私は客体化され、自由を奪われる。
ここに「モテなさ」の構造が潜む。
モテるとは「他者の眼差しを欲望として返される」こと。
だがモテないとは「眼差しが返ってこない」状態にほかならない。
サルトルの描いた実存の苦悩は、まさにこの欠落から出発している。
読書日記アプローチからの示唆
「モテなさ」は笑い話のように思えるかもしれない。
だが、そこにこそ孤独の倫理がある。
- モテないことは、他者に欲望として承認されないこと。
- だが、それは同時に「自己を哲学として深める契機」となる。
- 孤独はサルトルを哲学者にし、作家にした。
読書日記アプローチとして言えば、
「モテなさ」を読むことは、存在の本質的な孤独を読むことでもある。
梟コメント
サルトルの「モテなさ文学」は、
自分の弱さや欠落をそのまま哲学へと変換していく点にこそ光る。
「モテなさ」を引き受けることは、
実はもっとも誠実な形で生きることなのかもしれない。
結び
サルトルの哲学は、高尚な実存主義の言葉に彩られているが、
その根底には「モテなさ」という切実で人間的な経験がある。
そこから「他者とともに生きるとは何か」という根源的問いが立ち上がるのだ。
■一般財団法人 法政大学出版局
公式HP:https://www.h-up.com
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor