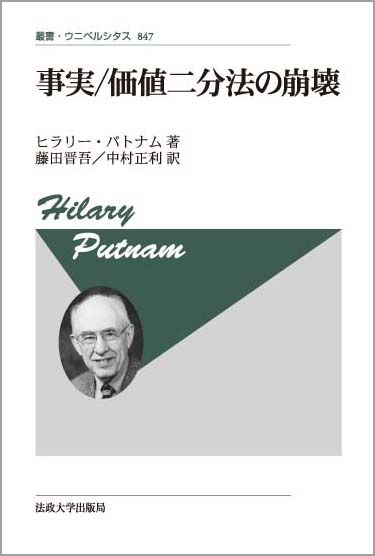読書ブログという形をとりながら、私自身の思索と読書体験を交差させてみたいと思います。
本記事は「読書ブログシリーズ」第2部・文学のズレの一篇である。
ここでは哲学者デイヴィッド・ヒュームとヒラリー・パトナムを対比させ、
「事実」と「価値」をめぐる議論を読書の実践に引き寄せて考える。
ヒュームの法則
18世紀の経験論哲学者ヒュームは、「事実」から「価値」を導くことはできないと主張した。
観察できる「ある (is)」と、規範的な「べき (ought)」のあいだには飛躍があるというのである。
「ある」から「べき」を導くことはできない。
梟コメント:
この区別は冷徹な合理性の象徴であると同時に、倫理の不確かさを突きつけるものでもある。
パトナムの挑戦
20世紀の哲学者パトナムは、この二分法を批判した。
科学的事実もまた価値判断に支えられており、完全に切り離すことはできないという立場を取った。
「事実と価値の二分法は、我々が世界を理解する仕方を貧困にする」
梟コメント:
パトナムは「事実もまた価値に浸されている」と言う。
この逆説は、読書における「解釈の重なり」と響き合う。
読書における事実と価値
一冊の本の「内容」は事実であり、その受け止め方は価値に属する。
だが両者は分離できず、むしろ相互に影響し合いながら「読書体験」を形づくる。
梟コメント:
事実と価値の交錯こそが、読書日記アプローチの核心だ。
本をどう読むかは、常に「解釈=価値づけ」の行為を伴っている。
ズレとしての「あいだ」
ヒュームとパトナムの議論は、相反するようでいて、むしろ「あいだ」にこそ意味がある。
事実を切り離す冷静さと、価値を引き受ける誠実さ——そのズレが、読書を豊かにする。
結び
事実と価値のあいだをどう渡るか。
それは読書の営みを、単なる情報消費から倫理的・解釈的実践へと変える問いである。
読書ブログを通じて浮かび上がる小さな思索の断片を、これからも綴っていきたいと思います。