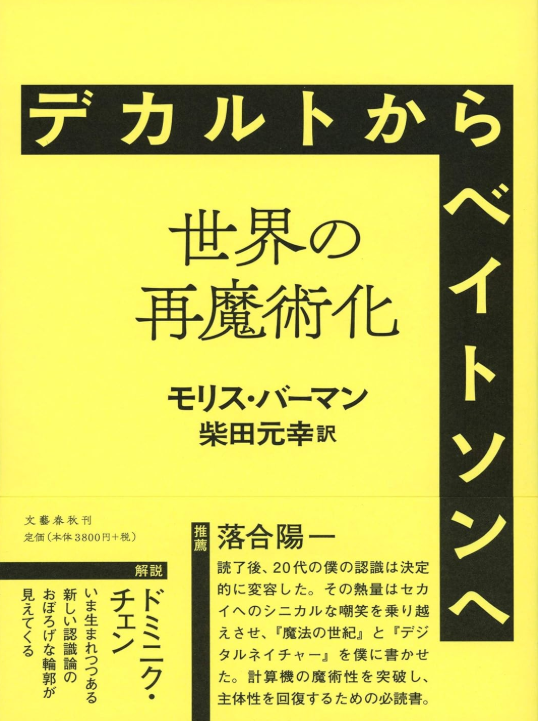この読書ブログ「読書梟」では、日々の読書を通じて考えたことを記録しています。
第2部「文学と孤独の読書」の一篇。
読書は知識や情報の摂取にとどまらない。
そこには「語感」という感覚の世界が広がっている。
ホーソーンの重苦しい物語世界と、ベイトソンのコミュニケーション理論は、
一見遠く離れているようでいて、「言葉が響く」という経験の一点で結びつく。
ホーソーンの重苦しい寓話
ナサニエル・ホーソーンの小説には、罪・孤独・秘密といった重いテーマが繰り返し登場する。
『緋文字』では、罪のしるしを背負った人物が、社会と内面の板挟みに苦しむ。
そこには言葉の重み、沈黙の圧力が刻まれている。
読者は、物語を追うだけではなく、言葉そのものの響きに巻き込まれる。
「読む」というより「響きに触れる」体験。
ベイトソンのメタ・コミュニケーション
一方、グレゴリー・ベイトソンは、言葉が「情報」だけではなく、
「関係」や「文脈」を伝えることを指摘した。
言葉には二重の意味が宿り、ユーモアやズレはその隙間から立ち上がる。
つまり、言葉は意味の容れ物である以上に、
人と人の関係を構成する「場の響き」そのものである。
読書の語感とは何か
ホーソーンの重厚な文体と、ベイトソンの理論を重ね合わせると、
読書は「語感の経験」だと言える。
- 言葉が持つリズムや重さを味わうこと。
- 物語や理論を超えて、響きそのものに耳を澄ますこと。
- 読者自身の身体や感覚に刻まれる残響を大切にすること。
このとき、読書は知識でも情報でもなく「音楽的経験」となる。
梟コメント
「ホーソーン、ベイトソン、そして読書の語感」という取り合わせは、
学問的に整理された関係ではない。
むしろ誤配的で、形式を裏切るような出会いである。
しかし、この偶然の交差点こそが、読書日記アプローチの醍醐味だ。
語感を信じて読むとき、言葉は単なる記号から、
読者に響き続ける余韻へと変わる。
結び
読書は、意味を理解するだけでは終わらない。
言葉のリズム、重さ、ズレ――そうした語感の領域にこそ、
文学と思想は生きている。
この記事もまた、読書梟の読書ブログの一ページとして積み重なっていきます。