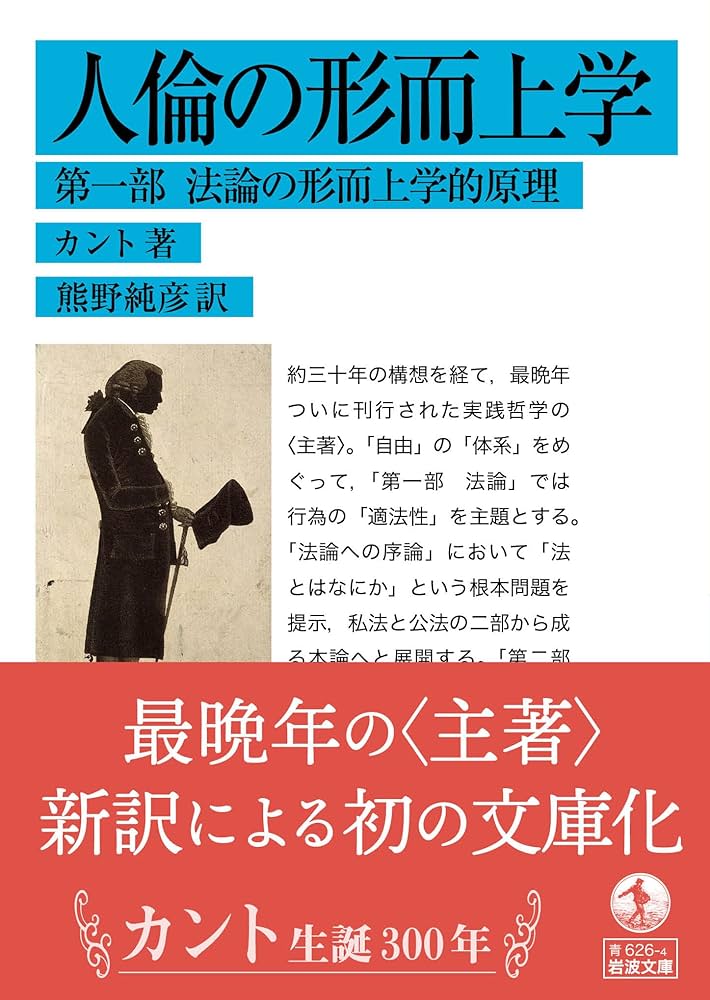この読書ブログ「読書梟」では、日々の読書を通じて考えたことを記録しています。
倫理は、壁でも規範でもない。
むしろ「すきま風」のように吹き込んでくるものだ。
形式が立てた制度やルールの間から、ヒュッと忍び込む。
暖かさを奪うようでいて、むしろ目を覚まさせる。
読書日記とは、この「倫理のすきま風」を記録する営みなのかもしれない。
形式と隙間
本はいつも形式をまとっている。
ジャンル、章立て、注釈、引用。
しかし読者が本当に惹かれるのは、その隙間から吹く風だ。
- 本文よりも余白に書き込んだ落書き。
- 索引に載らない一語。
- 文脈からズレて届く引用。
そこに「倫理的な呼びかけ」がひそんでいる。
読書日記アプローチと「すきま風」
「読書日記アプローチ」は、形式を守ることではなく、形式の隙間を感じ取ることだ。
- 誤配や誤読のすきまから吹き込むものを受け止める。
- 作者の意図ではなく、自分の内に残る微風を記す。
- その微風が他者にも吹くかもしれないと、淡く信じる。
すきま風は、換気口のように読書を呼吸させる。
倫理の隙間に宿るもの
倫理は「正しい答え」ではなく、「隙間の不安」から生じる。
- 「これでよかったのか?」という揺らぎ。
- 「読まれなかった部分」に対する気まずさ。
- 「言わずにおけなかった言葉」の余韻。
それは快適ではない。だが、この不快感こそが倫理を生む。
読書は風通しである
読書は密閉空間ではない。
そこには常に、外からの風が吹き込む。
他者の声、偶然の連想、日常のざわめき。
その風を拒むのではなく、すきまとして開けておくこと。
それが読書日記の呼吸法だ。
結びにかえて
「倫理のすきま風を読む日記」とは、
つまり「倫理を形式化せず、流れ込むものとして受けとめる日記」である。
倫理は返品できない。
誠意と同じように、すきま風として忍び込み、私を揺らす。
その揺らぎを忘れないために、私は今日も日記を書く。
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
次の記事でもまた、読書ブログならではの読後の余韻を記していければ幸いです。