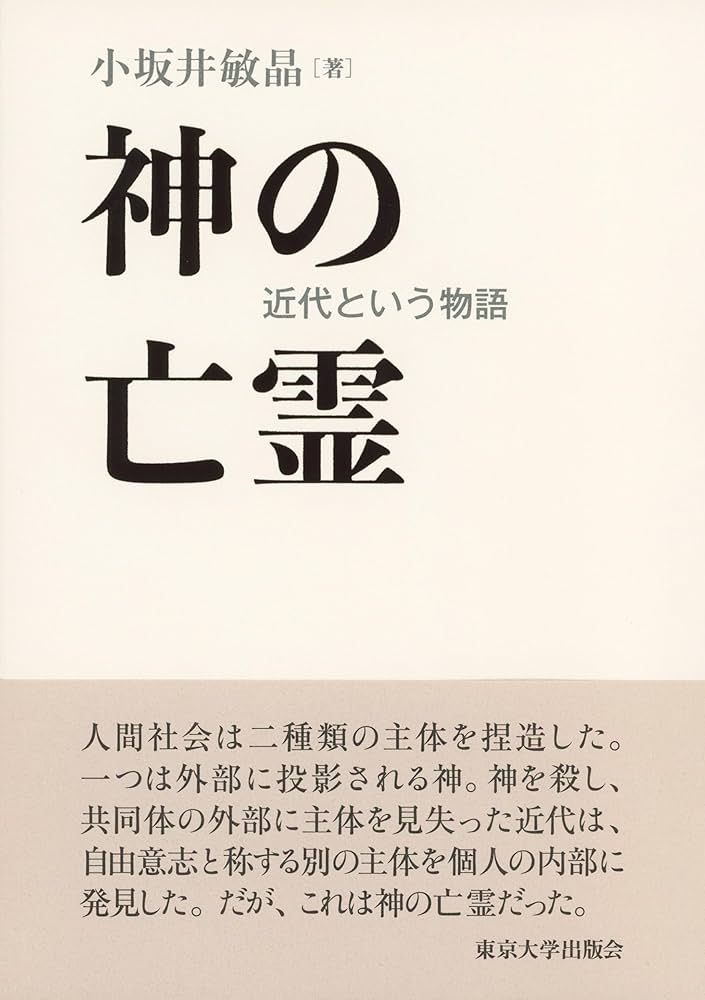■一般財団法人東京大学出版会
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
頭がもやもやするので『神の亡霊』を読んで日々の矛盾と向き合う。
“禁止に根拠はない。(・・・)殺人や強姦など、議論の余地のない犯罪だと認識されるのは、理由が明白だからではない。逆だ。禁止する本当の理由がわからないからである。「悪いに決まっている」。思考が停止するおかげで規範の正しさが信じられる。レヴィ=ストロース説であろうと、エディプス・コンプレックスを持ち出すフロイト説であろうと、近親相姦を忌避する理由が明らかになった瞬間にタブーは相対化され、消滅への道を辿る。法や道徳は虚構だ。だが、その虚構性が同時に隠蔽される。虚構のおかげで社会が機能する事実自体が人間の意識から隠される。” P97-98
矛盾に押しつぶされそうになる感覚が自分にはほどよい刺激となる。
矛盾がなにか、行動の起爆剤になっている感覚がある、矛盾を敢えて歓迎すること。それは、システムを開くことなのか、閉じることなのか。
➡AIの答え
短い答え:どちらでもある。
- 開く場合:矛盾を受容して問いを拡張し、既存の枠組みを横断することでシステムは多様性と創発を取り込む(開いたシステム)。
- 閉じる場合:矛盾を解消するために強い統制やルール、正当化(合理化)を導入すると、外界との接触を遮断して安定化を図る(閉じたシステム)。
どちらに転ぶかはあなたの反応様式とシステムの境界条件(許容できる不確かさの量、時間的余裕、利害関係)によります。矛盾を歓迎する態度そのものは「開き」に近いが、歓迎の仕方(即決で統合しようとするか、長く漂わせるか)によって結果は変わります。
障害年金の診断書を拒絶する医師、歓迎する医師。
振り込まれるころには回復する精神、振り込まれない間は壊れた精神。
精神医療の社会的有用性について500字で述べよ
ChatGPT:
思考時間: 35s
精神医療は個人の苦痛を軽減し日常生活の機能回復を支援するだけでなく、社会全体の安全と生産性を維持する役割を果たす。適切な治療と支援は入院や自傷行為の減少、長期失業やホームレス化の回避につながり、医療費や福祉コストの抑制にも寄与する。また、地域支援やリハビリは家族や地域社会の負担を軽くし、包摂的な社会参加を促す。早期介入や予防は将来の負担を減らし、教育や職場での支援は個々の能力を社会資源へ転換する。多職種による包括的ケアと地域連携は危機対応の迅速化と継続的支援を可能にし、結果的に社会資源の有効活用を実現する。精神医療の投資は短期的なコストを伴うが、長期的には再発防止や孤立解消を通じて公的負担の軽減と社会的結束の強化に資する。何より、当事者の尊厳と権利を守ることで市民社会の成熟を促し、誰も取り残さない社会をつくる基盤となる。研究は有効性と費用対効果を示しており、公的支援の拡充は生産年齢人口の労働参加率向上や家庭の安定に直結する。地域への資源配分と市民教育を組み合わせることで、回復志向のケア文化を根付かせられる。制度設計の中心に据えられるべきだ。具体的な対策を。
あなた:
社会保障の社会的損失について、精神医療の有用性と比較しながら500文字で述べよ
ChatGPT:
思考時間: 6s
社会保障の拡大は福祉を保障する一方で、誤配や不正給付、財政負担の増大、過度な依存の固定化といった社会的損失を伴う可能性がある。税負担の上昇は資源配分の非効率や労働参加のインセンティブ低下を招き、制度の硬直化が長期的な人的資源の活用を阻害することが問題だ。しかし精神医療は、適切な診断・治療と地域支援を通じて症状の軽減と機能回復を促し、入院・自傷・長期離職の抑制によって福祉コストの削減と労働力の回復に寄与する。したがって、社会保障の負の側面を最小化するには、給付の精緻なターゲティングと早期介入、精神医療を核としたリハビリ・職場復帰支援、地域多職種連携を組み合わせる政策設計が有効である。回復志向の投資は短期的コストを要するが、長期的には社会的損失の軽減と包摂的な社会の実現に繋がる。