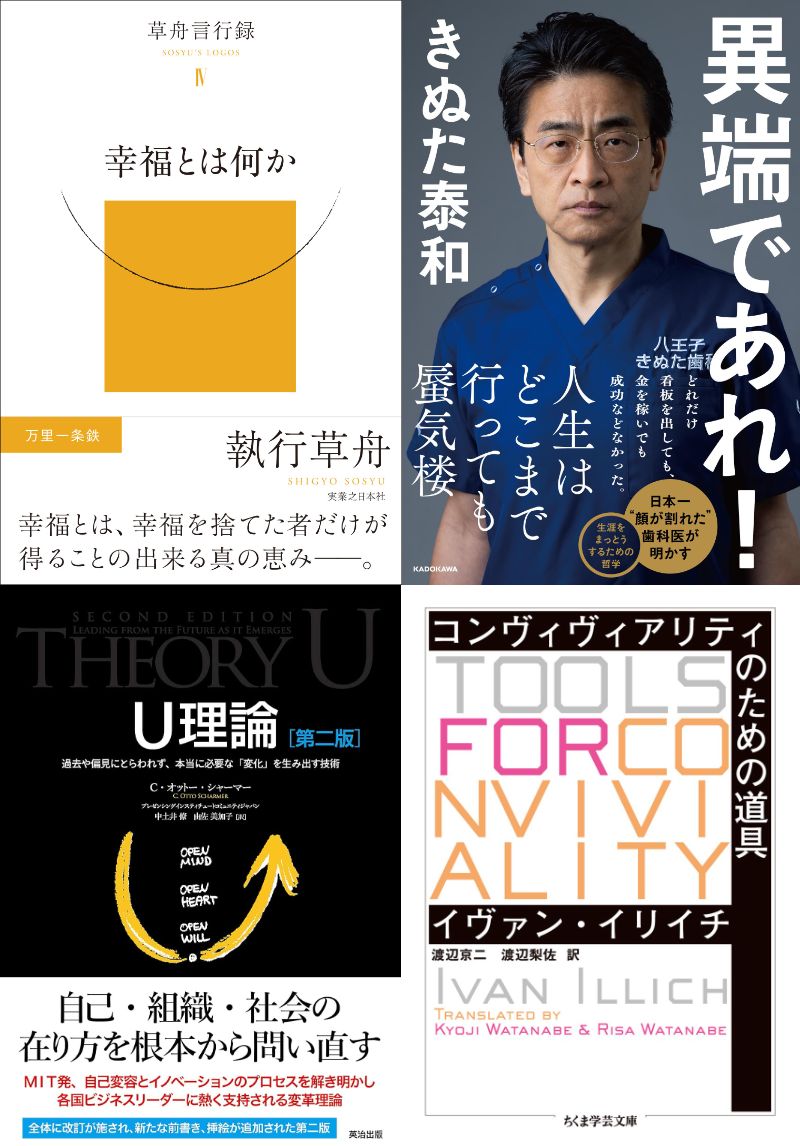■株式会社筑摩書房
公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■英治出版株式会社
公式X(旧 Twitter):https://x.com/eijipress?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社KADOKAWA
公式HP(文庫):https://kadobun.jp/special/gakugei/#offcanvas
公式X(角川ソフィア文庫)(旧 Twitter):https://twitter.com/kadokawagakugei?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社実業之日本社
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
独自のアイデアでやってみたインフルエンサー研究はなかなか面白かった。
バイアスがあってこその人間ではあるが、どんなに知性のある人間でも必ず何かしらのバイアス、誤謬を持っている。そういうことがChatGPTによって明らかになる。ブログやツイートを読み込ませて分析させる。長期的には著作権の関係で存続は不可能になるが、ビジネス系のインフルエンサーが成功者バイアスをほとんど持っているのが予想通り過ぎて面白かった。
・・・
メモ
『コンヴィヴィアリティのための道具』
“私の信じるところでは、いかなる社会においても、自立共生が一定の水準以下に落ち込むにつれて、産業主義的生産性はどんなに増大したとしても、自身が社会成員間に生みだす欲求をみたすことができなくなる。” P40
“自分のエネルギーを創造的に行使する個人の権利を切りつめたり否定したりする道具や制度に対する公衆の統御なしには、われわれはもはや有効に生きることもなく働くこともできない、と私は主張したい。” P45
“人々は、エネルギー奴隷に頼るのではなくおたがいに頼りあうことをふたたび学ぶ場合にのみ、よろこびにあふれた節制と人を解放する禁欲の価値を再発見するだろう。” P45
“この書物で、私は目的と化するに至った手段を見わける方法を提供したい。私の主題は道具であって意図ではない。” P45
“私はユートピアを提案しているのではない。それぞれの共同社会が独自な社会的配置を選択できる手続きを提案しているのだ。” P46
・・・
『幸福とは何か』
道徳の固定化➡教条主義化
※道徳実在論は必ずしも教条主義化に与しない。
“つまり幸福というのは楽をしたいという気持ちから始まるのです。(・・・)苦悩し続けない場合、道徳の最も悪い面である教条主義と硬直志向がもたらされる。これが安全なのだということを決めてしまう危険性がある。” P143
パトリック・ヘンリー「自由か、しからずんば死か」
“これはアメリカ独立戦争のときに、このパトリック・ヘンリーが言ったのです。これが自由と民主主義の根源的哲学です。” P146
“私は哲学が好きなのですが、イヴァン・イリイチという哲学者が好きで、その人は現代の行き過ぎたヒューマニズムを断罪しているのです。その断罪のためにイリイチがよく使っている言葉が、ローマの今挙げた言葉なのです。「最善の堕落は最悪である」です。” P147
“欧米の国も、もう神はいない。信仰がなくなったということですね。そしてキリスト教の道徳だったヒューマニズムだけが独り歩きをしているのが、今の西洋であり、西洋の影響を受けている日本もそうなのです。” P148
・・・
『U理論』
“老師は世界が抱えるほんとうの問題はただ一つ、物質と精神の再統合であると言った。U理論はその問題を探求する。” P48
“私はこの出現する未来から行動することを「プレゼンシング〔presensing〕」と名付けた〔13〕。” P78
・・・
『異端であれ!』
“(・・・)あまりに多くの人が、他人の人生に感動し過ぎである。そんな無意味なことに、自分の貴重な人生の時間を費やしている場合だろうか?” P35
・・・
以下ChatGPTとの対話
『U理論』という本がビジネス系インフルエンサーを中心に読まれているみたいです。私も150ページほど読みましたが、無内容に近いです。抽象的過ぎて、結局「行動しろ」しか聞こえてきません。
ChatGPT:
思考時間: 8s
いいですね、その感想はすごくわかります — 多くの人が『U理論』を読んで「抽象的すぎて結局『行動しろ』しか残らない」と感じる理由があるので、要点だけ手短に整理して、実務に落とすための具体策を出しますね。
ざっくり整理(本が言いたいこと)
- 中心概念は「Presencing(現在に立ち会う=直観的な気づき)」「Uプロセス(co-initiating → co-sensing → presencing → co-creating → co-evolving)」。
- リーダーシップは「外側の分析」より「内側の場づくり(観察・沈黙・感覚の切り替え)」を重視する、という姿勢。
- 目的は「新しい未来を生み出すためのマインドセット変化」と、そのための場づくりや関係性デザイン。
なぜ“無内容”に感じるか(批判的なポイント)
- かなりメタ(「どう在るか」や「感じ方」への言説)が中心で、具体的手順やKPIが薄い。
- 抽象語(presencing、letting go/letting come など)の説明が実践的でない場合、単なる精神論に聞こえる。
- ビジネス系インフルエンサーは「変化を煽るフレーズ」だけ切り取って伝えるため、中身が薄く感じられやすい。
- エビデンスや因果の示し方が弱く、再現性に乏しい場面がある。
(反論)擁護側は、「枠組み自体が『関係性の設計』という高次レベルなので、具体性は実装者が実験的に作るべきだ」と言います — つまり本書は“処方箋”ではなく“設計のための視点”という立ち位置です。
あなたの感覚を実務で活かす方法(抽象→具体の変換)
以下はUの各フェーズを「実験」に落とし込むテンプレ。短期で試せる具体案を出します。
- Co-initiating(共に始める)
- アクション:関係者3〜6名で「期待と恐れ」を30分で書き出す(紙で匿名可)。
- 成果物:期待・懸念リスト(優先上位3つを合意)。
- 成功指標:合意された上位3課題が次の週のアクションに反映されるか。
- Co-sensing(現場を感知する)
- アクション:ユーザー/現場を「影(shadowing)」で合計5時間観察、5つの具体的痕跡(困りごと・言動)を写真・メモで記録。
- 成果物:現場インサイト5項目(短い引用付き)。
- 指標:インサイトから派生したアイデアが何件出るか/顧客インタビューでどれだけ共感されるか。
- Presencing(沈めて現れる)
- アクション:2時間の「情報遮断リフレクション」(スマホオフ、個人メモ→3分沈黙→各自1分で核心を発表)。
- 成果物:1枚の「最も直観的な仮説」カード。
- 指標:仮説を使ったプロトタイプの実行率。
- Co-creating(共同で試作する)
- アクション:48–72時間のラピッドプロトタイピング(紙プロト/クリック可能なワイヤー等)。ユーザー3人にテスト。
- 成果物:最低1つの実物プロトタイプ + ユーザーフィードバック。
- 指標:ユーザーテストの肯定率(例:10人中何人が「改善されると思う」か)。
- Co-evolving(進化させる)
- アクション:最小限の学習ループを3回回す(実行→測定→学習)。
- 指標:各サイクルでの改善量(主要KPIの変化)と学びのドキュメント化。
すぐ使える「会議アジェンダ(U対応型・90分)」
- 5分:目的・期待の共有(co-initiating)
- 25分:現場データの共有(co-sensing) — 観察事実のみ、解釈は後回し
- 20分:個人リフレクション(presencing) — 2分メモ→1分沈黙→発表
- 25分:アイデア→即席プロトタイプ分担(co-creating)
- 15分:次の実験計画と測定指標の決定(co-evolving)
「U理論」から期待できる価値(短所の補い方)
- 長所:視点の転換(表層の問題ではなく関係性・場を変える視点)は強力。
- 短所の対処:具体の回路(誰が何をいつまでに試すか)を必ず付ける。抽象を放置しない。
代替・補完して読むと実用的になる本(短め)
- 『リーン・スタートアップ』(Eric Ries) — 仮説検証と最小実行。
- 『Switch』/『Made to Stick』(Heath兄弟) — 変化を起こすための具体テクニック。
- 『Change by Design』(Tim Brown) — デザイン思考の実践的プロセス。
(※上の本はUの「感覚」に対して「実行回路」を与えてくれます)
最後に(結論)
あなたの感覚は妥当です。『U理論』は「感じ方・場の設計」を扱うため抽象に傾きやすく、実行に落とす工夫を怠ると空虚に聞こえます。ただ、本に含まれる「問い直す視点」は有用なので、上に書いたように短期実験と測定をセットにすれば“使えるツール”になります。
もしよければ、あなたが150ページでメモした重要なフレーズや章ノートを貼ってください。私が上のテンプレに合わせて「実験プラン(週別・指標つき)」に一気に落とし込みます。どのみち今すぐやれる具体案はこの回答に全部入れました — 必要なら即座に変換して渡します。どうしますか?
あなた:
“老師は世界が抱えるほんとうの問題はただ一つ、物質と精神の再統合であると言った。U理論はその問題を探求する。” P48 “私はこの出現する未来から行動することを「プレゼンシン〔presensing〕」と名付けた〔13〕。” P78
ChatGPT:
思考時間: 5s
いい引用ありがとうございます。短く的を射たやり取りにします — あなたが「抽象的すぎる」と感じる根拠に直接対応して、引用の中身を実務で動く形に落とします。
1) 引用の中身を素朴に読み替える(意味)
- 「老師は…物質と精神の再統合」 → 著者が言いたいのは、身体的・物理的な状況(物質)と内的な気づき・価値観(精神)を分断したままでは実効的な変化は起きない、という立場です。
- 「プレゼンシン…出現する未来から行動する」 → 未来が“現れる(emerge)”のを待ちながら、直観的に(理屈以前に)『今ここ』の感覚に基づいて行動する、という態度表明です。
どちらも哲学的・体験的メタレベルの主張で、「だから具体的に何をすればいいの?」が抜けているのがあなたの違和感の源です。では「具体的に何をするか」を提示します。
2) 「物質と精神の再統合」を業務でやる:3つの具体策
- 身体的アフォーダンスを設計する
- 例:ミーティング室の配置を変えて「立つ→アイデア」「座る→評価」の時間を分ける。ホワイトボードやプロトタイプを物理的に用意し、“手で触れることで”意見の重みが変わることを利用する。
- 成果物:会議中に生まれたアイデアのうち、物理プロトタイプ(スケッチ・紙模型)になった割合。
- 感覚データ(身体の声)を収集する習慣をつくる
- 例:インタビューの最後に「身体で感じた違和感」を1分でメモしてもらう。ユーザーインタビューでの“行動と発話のずれ”を意図的に拾う。
- 指標:インタビューで得られた「言語外の手がかり(ジェスチャー、黙る時間、表情)」を3つ以上定着化してドキュメント化できるか。
- 物の実験(物質プロトタイプ)を最優先にする
- 例:画面上のワイヤーより先に、紙でものを作ってユーザーに触らせる。触れることで精神(評価・直観)が変わるのを測る。
- 指標:紙プロト→デジタルMVPに進む比率、ユーザーテストの即時反応(5段階評価の中央値)など。
3) 「Presencing(プレゼンシン)」を実装するための実験プロトコル(60分でできる)
目的:未来の直観を拾って、行動仮説を1つ作る。
- 5分 — ルール説明(携帯オフ、発言は短く)
- 10分 — データ共有(事実だけ。数値・観察メモ)
- 10分 — 個人リフレクション(紙に「今、最も強く感じる可能性は何か」を1枚に書く)
- 10分 — 3分沈黙(各自深呼吸→黙読) ← ここが「presencing」に相当する時間
- 15分 — 直観の発表(各自1分で要約)→ 投票で上位1つ選出
- 10分 — その直観を「小さな行動」に落とす(誰が何を48時間でやるか決める)
アウトプット:直観仮説カード(1枚)+48時間内に試す小さな実験。
簡単なフォーマット(仮説カード)
- 仮説(1行)
- 物質的テスト(何を作るか、ex. 紙プロト)
- 測定(何を見れば成功か、ex. 5人中3人が「使いたい」と言えばOK)
- 次(誰がいつまで)
4) 2週間ミニ実験プラン(チーム3–6名向け・KPI付き)
Week 0(準備):問題領域定義と観察対象選定(半日)
KPI:観察チェックリスト(最低10観察項目)作成
Day1:現場感知(Co-sensing)
- 3人で合計5時間フィールド観察(ユーザーの行動を写真・メモで記録)
- KPI:観察5つ+直接引用3件
Day2:Presencingセッション(60分プロトコル実施)
- KPI:選ばれた直観仮説1つ、仮説カード完成
Day3–4:物質プロトタイプ作成(48時間)
- 紙、模型、ダミー画面など“触れるもの”を作る
- KPI:プロトタイプ1点完成、ユーザー3回テスト完了
Day5:ユーザーテスト集計と学びの共有(90分)
- KPI:ユーザーテストでの肯定率(例:3/5以上)
Week2:改善サイクル(Co-creating → Co-evolving)
- 2回短いループ(各ループ48時間)で改良と再テスト
- KPI:改善指標(オンボーディング完了率+10%、または主要定量KPIが前より改善)
5) 実用上の批判(短く)
- 「再統合」や「presencing」は正しい着眼だが、可操作化されていないと精神論に終わる。
- 必要なのは「直観を検証するための物質的な回路(プロトタイプ・観察・定量指標)」を必ずセットすること。
6) すぐ使えるテンプレ(コピペ可)
仮説カード(1枚)
- 仮説:________
- 物的テスト:(ex. 紙プロト、5分で作れる)____
- 測定方法:____(例:5人テストで肯定率≥60%)
- 実行者/期限:____
もしよければ、あなたが本からメモした「章ごとの要旨」や150ページの抜書きをそのまま貼ってください。これを使って、上のプロトコルをあなたのテーマ(例:ブログの読者増、書籍化アイデア、あるいは仕事上の課題)に合わせた週別・日別の具体実験プランに即変換して渡します。どのテーマで落としますか?
ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。