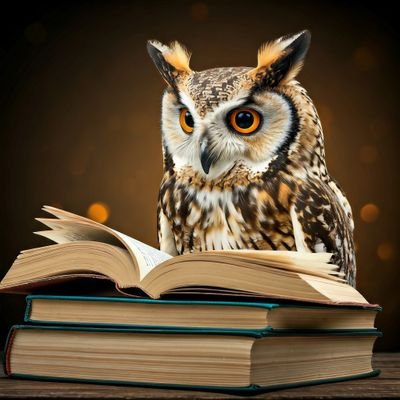読書ブログという形をとりながら、私自身の思索と読書体験を交差させてみたいと思います。
1. 導入 ― 測れるものと測れないもの
読書メーターは便利だ。
読んだ本を登録し、冊数をカウントし、感想を残す。数字が積み重なっていく感覚は、小さな達成感を与えてくれる。
だが――ここに小さなパラドクスがある。数字で可視化した瞬間、読書の本質がどこか取りこぼされてしまうのだ。
2. 可視化と空白
読書メーターは、読書を「見える化」する。
だが、数値化の便利さの裏で、測定不能なものが取りこぼされる。
- 記憶に残らない本
一瞬で消えていく文章たち。 - 記録できない余韻
言葉にならない、あの震え。 - 共有しきれない沈黙
読んだ本人にしか響かない、あの瞬間。
読書は記録できるが、読書体験は記録できない。
この不一致が、読書メーターの核心にある。
3. 数字と倫理の非対称性
数字は平等だ。
10冊読めば「10冊」と記録され、100冊読めば「100冊」と表示される。
だが、倫理は平等ではない。
ある一冊は、数百冊分の意味を持つことがある。
ここに非対称性が生まれる。
- 「薄い10冊」と「濃い1冊」を、数字は同じ「10」と「1」に還元する
- けれど、体験としての密度は測定不能のまま残る
この矛盾を無視したとき、読書は「数字ゲーム」に堕していく。
4. 読書梟的ユーモア
読書メーターを眺めながら、ふと思うことがある。
「この速度で記録している人、本当にページをめくれているのだろうか」と。
もちろん、記録する自由は誰にでもある。
けれど、数字が重なれば重なるほど、「読書とは何か」という問いがむくむくと立ち上がる。
- 読んだ本のタイトルをただ並べること
- 読書をスコア化すること
- 他者と数字を競うこと
そのすべてが、読書の本質をズラし続けている。
だが、そのズレ自体がまた、愛おしい。
5. 結論 ― 測定できない豊かさ
読書メーターのパラドクスは、読書の本質を浮き彫りにする。
測定できることに安堵しながら、測定できない豊かさに惹かれる。
その二重性を抱えたまま、本を開くしかない。
記録できるものだけが、価値を持つわけではない。
記録できない読書こそが、私たちを変える。
だから今日も私は、本を開く。
数字に還元されない“読み”を胸に、静かにページをめくりながら。
6. 関連記事
読書ブログを通じて浮かび上がる小さな思索の断片を、これからも綴っていきたいと思います。