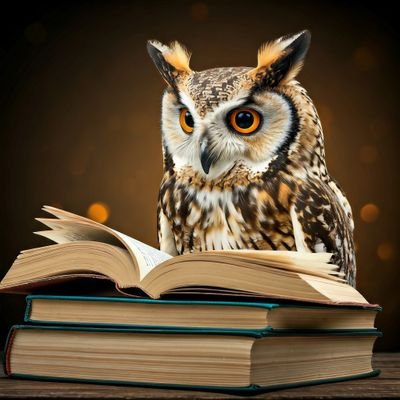全体構成
- 導入:「せきにん」の装置/読書梟の宣言
- 責任の側面(応答可能性=response-ability/“選び取る誠実”)
- 積人(積読)の側面(遅延の倫理/可能性の貯蔵/編集規律)
- 交差点(責任×積人=遅延する応答+選択の規範)
- 教育と制度の批評
- イヴァン・イリイチ:脱学校・学びの自主管理/コンヴィヴィアル・ツール
- 小室直樹:制度設計と規範の整合/責任の形式化・匿名化
- 宮台真司:情報洪水と中間集団の消失/即応圧の中での「熟考の権利」
- 小坂井敏晶:「責任という虚構」—規範の作動と“責任”概念の社会的構築 - 情報社会の知と積人
- 「積む」ことのパブリック性(図書館/コミュニティ・レコメンド)
- 速読・要約経済への批判—冊数の暴力を拒む基準 - 哲学と死の思索
- 池田晶子:言葉と死に向き合う誠実/“読まない時間”の意味 - 芸術と創造倫理
- 岡本太郎:毒と爆発(未読=火薬庫)
- 執行草舟:成果の呪縛を焼く“捨て身”と積人の勇気 - 結語:数えない勇気、選び抜く誠実—「せきにん」の新しい倫理
導入
「せきにん」という音に耳を澄ますと、そこには二つの漢字が潜んでいる。一方は、他者に応答し行為を引き受ける“責任”。もう一方は、未読を積み上げる主体、“積人”。前者は倫理、後者は習慣である。だが二つの字が同じ音に宿ることは、単なる言葉遊びを超える。むしろそれは、現代人の知的生活における緊張そのものを映している。
責任は「読むべきだ」という声となり、積人は「まだ読まなくていい」という誘惑になる。この相克のあいだで、私たちは日々揺れている。積読は恥ずかしいものか、誠実な準備か。答えはひとつではない。だが確かなのは、積読が“無責任”に見えるのは、責任という観念がすでに私たちの背後にあるからだ。責任と積人は、互いに相手を照らし出す影と光なのである。
第一部 導入:「せきにん」という言葉の仕掛け
「せきにん」という音を耳にすると、ほとんどの人は反射的に「責任」という字を思い浮かべるだろう。仕事や家庭、社会生活のあらゆる場面で、責任はつねに私たちを見張っている。やり遂げるべきことを果たさなければならない、失敗すれば誰かが責任を取らねばならない、そうした強い圧力のなかで、責任という言葉は私たちの日常を律している。
ところが、同じ音に別の漢字を当てると、まったく違った光景が立ち上がる。「積人(せきにん)」――本を買い、積み上げながらも、まだ読まずに保留している人のことだ。積読という言葉自体は広く知られるようになったが、積読を行う主体を「積人」と呼ぶのは、私自身の遊び心から始まった造語である。だが、その響きを口にするとき、私は単なる冗談を超えた思索の扉が開くのを感じる。責任(responsibility)と積人(積読者)が同音異義として重なり合うとき、倫理と習慣、義務と自由、応答と保留という二つの次元が不意に交差するからだ。
言葉の仕掛けとしての「せきにん」
日本語はしばしば、同じ音に複数の意味を宿す。これは偶然の一致であると同時に、思考の契機となる。責任と積人は、表面的には何の関係もない。しかし、同じ音に集約されることで、二つの概念は互いを照らし出し、批評的装置として機能し始める。
責任は「応答すること」を求める。ハンナ・アーレントの言葉を借りれば、行為の不可逆性のもとで、私たちは自分の言葉や行為に対して責任を負う。池田晶子が強調したように、人間は死を見つめる存在として、自らの思考や選択を最後まで引き受けざるをえない。その重みは数値に換算できない質的なものだ。
一方で積人は、応答を先送りする主体である。本を積み、まだ開かずに置いておく。読むことを未来に回す。これは一見、責任からの逃避に映る。だが、積人は未来に対する「可能性の保管人」でもある。未読の本の背表紙は、まだ果たされていない問いの約束書であり、応答の延期は応答の否定ではない。
このとき「せきにん」という音が二つの漢字をつなぐことで、私たちは責任と積人を同じ地平に置き直すことができる。読むことの責任と、読まないことの自由。そのせめぎ合いこそが、現代の知的生活を形づくっている。
積読文化の断片史
積人という存在は、決して現代特有のものではない。歴史を振り返れば、未読本を抱えた人々はつねにいた。江戸時代の貸本屋の記録をひもとけば、返却された本の多くがほとんど読まれていなかったという証言が残る。明治期の知識人の日記にも、買ったはいいが読めずに積んでしまった本のことがしばしば書き留められている。
近代の読書家たちにとって、積読は恥でもあったが、同時に知への渇望の痕跡でもあった。大量の翻訳書が流入するなか、読むべき本は雪崩のように増え、積まれた未読本は「時代に追いつこうとする苦闘」の証となった。
現代においては、積読はさらに可視化されている。SNSにアップされる「積ん読タワー」の写真は、笑いと共感を呼ぶ。Amazonの「あとで買うリスト」もまた、デジタル版の積読といえるだろう。つまり積読は、個人の怠惰を超えて、一つの文化的習慣となった。積人は、時代を越えて繰り返し現れる普遍的な存在なのだ。
責任との緊張関係
とはいえ、積読には常に内なる声が付きまとう。「買った以上は読むべきだ」という責任の声である。読まないことは、著者に対する不誠実ではないか。知識に対して無責任ではないか。こうした罪悪感は、多くの読書家を悩ませてきた。
しかし、積人の側から見れば、積読は単なる回避ではない。むしろ「まだ応答しない」という戦略的選択である。問いに即答しないこと、答えを急がないこと。これは責任の放棄ではなく、応答の熟成を意味する。責任が「今ここでの応答」を迫るとすれば、積人は「未来における応答」を準備する。両者は緊張しつつも、同じ地平に立っている。
この緊張関係が、読書をめぐる倫理を豊かにしている。もし責任だけが支配すれば、すべての本を即座に読了することが強迫観念となり、読書は息苦しい義務に変わる。逆に積人だけに傾けば、応答は永遠に延期され、知は可能性のまま凍結されてしまう。責任と積人、二つの「せきにん」が拮抗することで、読書は生きた実践となるのだ。
社会批評への入り口としての「せきにん」
現代社会は「即応」を求める。メールやSNSの通知は、数秒単位の反応を催促する。教育制度は速読や効率的な学習法を推奨し、企業文化は成果を数値化して評価する。そこでは、応答は即時性と数量化に回収される。責任は「どれだけ早く、どれだけ多く反応したか」で測られてしまう。
だが、積人はその流れに逆らう。積んでいる本は、即読を拒否する沈黙の証である。本棚に眠る背表紙は、数値化できない時間を保証し、応答の遅延を守り抜く。積人であることは、情報社会の即応圧に対する小さな抵抗となる。
つまり、「せきにん」という言葉の仕掛けは、単なる語呂合わせではない。責任と積人が交差するとき、そこには現代社会を批評するための視角が生まれる。責任の倫理と積読の習慣を並置することで、教育・制度・情報社会の構造が浮かび上がるのだ。
読書梟の情熱というスパイス
私にとって「せきにん」という発想は、単なる思いつき以上のものだ。積読の山を前にして、私はしばしば自分の無力さを感じる。だが、その無力さの中に、未来の可能性を見ている。積人であることは、責任からの逃避ではなく、責任の新しい形なのだ。
責任と積人、二つの「せきにん」を抱えること。これは、知の時代に生きる私たちに課せられた宿命であり、同時に祝福でもある。誠実に読むことと、未来に備えて積むこと。その両方を引き受けるとき、私たちは「せきにん」という言葉の重みを真に感じることができる。
第二部 責任の系譜
- 責任の哲学的基礎
- 応答可能性(response-ability)
- カント的自律/アーレント的不可逆性との接続 - イリイチの責任
- 脱学校社会における「学びの自己責任」
- コンヴィヴィアル・ツールの使用責任
- 制度に任せず、個が応答する仕組み - 小坂井敏晶の責任論
- 「責任という虚構」=責任は本質的ではなく社会的に構築される
- 法・規範・制度が作る“責任”と、積人が抱える“未読責任”を対比 - 池田晶子の思索
- 死と向き合うことが究極の責任
- 哲学的に「誰も代わってくれない応答」
- 積人=死に至るまで未完であることを受け入れる主体 - まとめ:責任と積人の交点
- 責任は即時の応答だけではなく、未来に持ち越す応答もある
- 積人=責任の時間的拡張を体現する存在
第二部 責任の系譜――応答可能性の歴史と現代的変奏
1. 責任の哲学的基礎
責任という言葉を哲学的に捉えるとき、そこには「行為の結果を引き受ける」という単純な意味を超えた奥行きが見えてくる。西洋哲学の伝統では、カントが自律の倫理を通して「自由であることは責任を負うことである」と強調した。人間が理性に従い自ら選択する存在である以上、その行為の帰結に対しても応答する責任を免れない。
ハンナ・アーレントはさらに一歩進めて、行為の「不可逆性」を強調した。人間の行為は一度外に出れば取り消せない。だからこそ、私たちは予期せぬ結果や副作用に対しても責任を持たざるをえない。責任とは、計算や計画を超えた領域で、他者との共生を引き受けるための概念なのだ。
現代哲学では、責任を「response-ability」――応答可能性と解釈する流れがある。つまり、責任とは義務や罰の分配ではなく、呼びかけに応答する能力である。問いかけや挑発に対して、どのように自分を差し出すのか。その応答の在り方こそが責任を形づくる。
この視座から見れば、読書も責任を孕んでいる。テクストは他者の声であり、読者はそれに応答する義務を負う。だが応答は即時的である必要はない。熟成や逡巡の後にようやく言葉を返すこともある。ここに「積人=積読をする主体」との接点が立ち上がる。責任は遅れて到来する応答もまた含んでいる。
2. イリイチの責任論――脱学校とコンヴィヴィアリティ
イヴァン・イリイチは『脱学校の社会』(1971)で、制度化された教育が学びを管理し、人々の自発的な学習能力を奪っていると批判した。学校は学ぶ権利を保障する装置であると同時に、学習を資格や評価に囲い込み、責任を制度に委譲させる。生徒は「教えられる責任」を果たすだけで、自らの問いに応答する責任を忘れてしまう。
イリイチが構想した「学習ウェブ(learning webs)」は、個々人が自らの関心に基づいて学びを選び取り、応答の責任を自分の手に取り戻すためのネットワークだった。そこでは、知識は供給されるものではなく、対話と交換のなかで生成される。学びは制度的義務ではなく、自発的責任として再構築される。
また『コンヴィヴィアリティのための道具』(1973)でイリイチは、人間が自らの能力を発揮するための「 convivial tools 」の概念を提示した。道具の使用において重要なのは、それが人間を従属させるのではなく、自律的な応答を可能にするかどうかである。学びの道具もまた、応答可能性を奪うのではなく拡張すべきだ。
この視点から見ると、積人は「制度に管理されない学び」を象徴している。積読は評価基準や進度表から解放された自律的な学びの証拠である。未読の山は、制度に委ねられない問いの貯蔵庫であり、応答のタイミングを自分で決める責任の表れだ。積人は無責任ではなく、むしろイリイチ的意味での「責任の再獲得者」として位置づけられる。
3. 小坂井敏晶――「責任という虚構」の社会心理学
小坂井敏晶は『責任という虚構』(筑摩選書、2009/増補版あり)で、責任概念が自然的・本質的なものではなく、社会が構築したフィクションであると論じた。法律や規範は「誰がどこまで責任を負うのか」を制度的に決める。しかし実際には、因果の連鎖は複雑で、責任を明確に切り分けることは不可能だ。だからこそ社会は「責任」という虚構を立ち上げ、それを信じることで秩序を維持している。
この視点を積読に当てはめると興味深い。私たちは「本を買ったら読むべきだ」という暗黙の責任を感じている。だがそれは自然の摂理ではなく、文化的な期待にすぎない。積人を責める声は、社会的に構築された「読書責任」の虚構なのだ。
さらに小坂井は、責任の虚構が人間の心理に深く作用し、罪悪感や義務感を生み出すことを指摘した。積人が抱える罪悪感もまた、社会的に植え込まれた虚構である。ここで重要なのは、この虚構にどう応答するかだ。無責任の烙印を拒否し、積読を自らの戦略として引き受けること。積人は責任の虚構を撹乱し、別の仕方で応答可能性を実践している。
4. 池田晶子――死と応答の責任
池田晶子は『死とは何か さて死んだのは誰なのか』(新潮文庫、2007)などの著作で、死を哲学の中心に据えた。彼女の思索において、死は単なる終末ではなく、人間が本質的に向き合わざるをえない問いである。誰も代わりに死ぬことはできない以上、死は究極の責任である。
池田はまた、哲学の言葉を専門用語ではなく日常語で語り直すことにこだわった。哲学するとは、自分自身に応答すること、逃れられない問いに対して誠実に立ち止まることだった。ここでの責任は、他者への義務というよりも、自分自身への応答の責任である。
積読の倫理を池田的視座で読み替えるなら、未読本は「まだ応答していない問い」の象徴である。人は死に至るまで応答を完了することはできない。だからこそ、積人であることは人間の有限性を引き受けることに等しい。すべてを読み終えることはできないし、すべてに答えることもできない。有限性の中で、どの問いに応答するかを選び続けることが、責任の核心なのだ。
5. 責任と積人の交点
イリイチは責任を制度から個に取り戻そうとし、小坂井は責任が社会的に構築された虚構であることを暴き、池田は死を前にした究極の応答責任を語った。三者をつなぐと、「責任=応答可能性」は単なる義務や罰則を超えて、制度・文化・有限性の三層で揺らぎながら立ち上がってくる。
積人は、この責任の揺らぎを生きる主体である。制度に従うのではなく、社会的虚構を意識しつつ、有限性を受け入れながら、自らのタイミングで応答する。積読は無責任ではない。それは「遅延する応答」の実践であり、「有限性の中で選び取る誠実」の表明なのだ。
責任と積人は、同じ「せきにん」という音を共有することで、互いを映し合う鏡となる。責任がなければ積人の罪悪感も生まれず、積人がなければ責任の本質も浮かび上がらない。両者は対立するのではなく、むしろ相補的に現代人の知的生を形づくっているのである。
第三部 積人の文化史――歴史的実践から情報社会の抵抗線へ
1. 積読の古層――江戸期の貸本文化と知の堆積
積読は現代に限った現象ではない。江戸時代の貸本屋の記録を読むと、返却された本の多くが最後まで読まれていなかったという証言が残っている。当時の庶民にとって、本は高価で貴重な財産であったが、それでも「借りて積む」ことが日常的に行われていた。
寺子屋教育が広がり、読み書きが一般化していくなかで、貸本屋は知識と娯楽の供給源となった。だが、人々は必ずしも本を読破することを目的にしていたわけではない。本を所有し、手元に置くこと自体が知の接触であり、積読の行為には「可能性を保持する」という意味があった。つまり、積読は当初から「読む」だけではなく「持つ」「積む」ことに固有の価値を認められていたのだ。
この段階での積人は、知識社会における新しい階層の誕生を告げていた。読書量や内容にかかわらず、本を所有することで自己の文化資本を表明する。積読は、社会的アイデンティティを示す仕草でもあった。
2. 近代知識人の積読――焦燥と誠実のあいだで
明治以降、西洋からの翻訳書や啓蒙的著作が雪崩のように流入した。夏目漱石や森鴎外ら知識人の日記には、買ったまま読めずに積まれていく書物の記録が散見される。膨大な知の洪水の前で、読みきれないことは恥であると同時に、むしろ誠実な反応でもあった。
この時代の積人は「時代に追いつこうとする苦闘者」だった。国家の近代化、科学技術の進展に応答するために、人々は積読の山を築かざるをえなかった。積読は知の消費の遅れを可視化するが、それはまた「問いに備える誠実」の証でもあった。
3. 戦後から高度経済成長期――積人と自己啓発文化
戦後日本の知識社会では、自己啓発書やビジネス書の大量出版が積読の新しい形を作った。高度経済成長の波に乗って、成功と効率が至上命題となる中、多くの人々が「読めば役に立つ本」を大量に買い込んだ。しかし、実際には読み切れず、積読の山が家庭や職場に築かれた。
この積読は、近代知識人の苦闘とは異なる意味を持つ。ここでは積読は「役立ちの延期」になった。知識は即効性を期待される一方で、実際には消化されずに積まれていく。積人は、成果主義の影で矛盾を抱える存在となった。
4. 現代SNS文化の積人――可視化と共感
現代において積読はさらに可視化され、インターネット文化の一部となった。SNSには「積ん読タワー」の写真が投稿され、笑いや共感を呼ぶ。Amazonの「あとで買うリスト」や電子書籍の未読データも、デジタル化された積読である。
ここでは、積読は「恥」ではなく「共感」を生む文化的記号に変わった。本を積んで読めないことは、もはや個人の怠惰ではなく、情報過多時代に生きる者すべての共通経験とみなされている。積人は孤独ではなく、互いの山を見せ合うことで連帯を築く。
5. 宮台真司と情報社会――即応圧への抵抗としての積人
社会学者・宮台真司は、現代社会を「即応圧」に支配された空間として描いてきた。SNSやメディアの流れの中で、人々は秒単位で反応を求められる。意見や感情はすぐに発信されなければならず、熟考や遅延は「時代遅れ」とされる。
この状況で、積人は静かな抵抗者となる。積んだ本は即読を拒否する沈黙の証であり、「応答を遅らせる権利」を物質的に保証する。積人は、情報社会における熟考の権利を体現する存在だ。宮台が指摘する「中間集団の崩壊」と「個人化」のなかで、積人は孤立ではなく、遅延を選び取る新しい共同性を作り出す。積読をめぐる共感やユーモアの共有は、その萌芽である。
6. 積人の文化史が示すもの
江戸期の貸本屋から現代のSNS文化まで、積人はつねに歴史の陰に存在してきた。その姿は時代ごとに異なる意味を帯びる。
- 江戸期:知の所有と文化資本の表明
- 近代:知の洪水に対する誠実な苦闘
- 戦後:成果主義の影での「役立ちの延期」
- 現代:情報過多社会への抵抗と共感の共有
この流れを踏まえると、積人は単なる読書習慣ではなく、社会の知識環境を批評する存在だと分かる。積人は、制度や市場やテクノロジーに合わせて姿を変えながらも、一貫して「即時の応答」から逃れる自由を守ってきた。
積読は怠惰ではなく、歴史的に繰り返される「応答の遅延」の実践である。宮台的に言えば、それは即応圧に対する「反時間的装置」であり、現代社会における数少ない熟考の保証だ。
第四部 教育と制度――積人が攪乱する責任の構造
1. 教育制度と責任の分配
近代教育は、学びを制度に委ねることで成立してきた。学校は知識を分配し、進度やカリキュラムを管理する。生徒は決められた課題をこなし、教師はその成果に責任を持つ。教育制度における責任は、厳密に割り振られた役割として機能してきた。
だが、この制度的責任は必ずしも「応答可能性」を保障しない。生徒は自らの問いに応答するよりも、制度が要求する課題に従うことを優先する。責任は形式的な履行に変換され、学びそのものへの誠実な応答は脇に追いやられる。教育制度は、責任を「誰が失敗したか」を問う枠組みに縮減し、学びの本質である「何に応答するのか」を見失わせる。
ここで積人の姿を重ねてみよう。本を買い、積んだまま読むことを遅らせる積人は、制度的な進度管理から逸脱する存在である。積人の実践は「課題未提出」の烙印を押されるかもしれない。だが、実際にはそれは応答の遅延であり、自らの問いを熟成させる時間である。積人は、教育制度が与える形式的責任を攪乱し、学びの自由を取り戻す。
2. イリイチ――脱学校と責任の再獲得
イヴァン・イリイチが『脱学校の社会』で批判したのは、まさにこの制度的責任のあり方だった。学校は学びを制度に預け、学習の成否を「教師の責任」「生徒の責任」といった分配可能な単位に変換する。イリイチはこれを「教育の神話」と呼び、それが人間の学びを制度の枠に閉じ込めてしまうと喝破した。
彼の提案する「学習ウェブ」は、責任を制度から個へと取り戻す試みだった。学びは義務ではなく、自発的な選択と応答であり、その責任は自分自身が担う。つまり責任は「制度から割り当てられるもの」ではなく「学びに対する応答可能性」として再定義される。
積人はこのイリイチ的な構想を象徴する存在だ。未読の本を積むことは、制度が与える課題に従わず、自分の関心に基づいて問いを抱え続けることを意味する。積人は「まだ読まない」という選択によって、応答の責任を自分の手に取り戻す。制度が強いる責任を攪乱し、応答を遅延させることで、学びの自由を実践しているのだ。
3. 小室直樹――制度論と責任の形式化
小室直樹は、社会科学を横断する著作で「制度」と「責任」の関係を鋭く分析した。彼の制度論は、社会を秩序づける仕組みがいかに個人の行動を規定するかを明らかにする。制度は行為の因果関係を単純化し、「誰が責任を負うのか」を明確に区切ろうとする。しかしその過程で、責任は形式化され、実質的な応答可能性から切り離されてしまう。
組織の中で働く人々は、自らの判断よりも「制度がどう規定しているか」に従うことで責任を回避する。「マニュアル通りにやったから自分に責任はない」という言葉はその典型だ。責任は応答ではなく、制度の網の目のなかで形式的に処理される。
積人の存在は、この形式化された責任に対するアンチテーゼである。本を積むことは、マニュアルに従った即応を拒否する行為だ。積人は「まだ応答しない」という選択によって、制度が強いる形式的責任から逃れ、実質的な応答可能性を温存する。積人の山は、制度が分配した責任の外部に生まれる「自由の余白」なのである。
4. 教育と積人――制度的評価と誠実な遅延
現代の教育制度は、成果を数値化することで責任を明確にしようとする。テストの点数や偏差値、修了単位の取得は、学びの責任を定量化する装置である。だが、知の応答は必ずしも数値に収まりきらない。むしろ数値化の圧力は、熟考や逡巡といった本来の学びを阻害する。
積人はここで、制度的評価に対抗する別の姿を示す。本を積み、読むことを遅らせることで、数値化できない責任の形を保持する。積人は「未読=未熟」ではなく、「未読=熟考の可能性」として応答する。教育制度が「速さ」と「量」で責任を測るなら、積人は「遅さ」と「選択」で責任を再定義する。
5. 組織と積人――責任回避の構造を攪乱する
企業や官僚制の組織では、責任は常に分散され、時に誰も責任を取らない構造が生まれる。小室直樹が指摘したように、制度は責任を透明化するのではなく、しばしば不透明化する。責任は形式的に割り振られるが、実質的には誰も応答しない。
積人の実践は、この責任回避の構造を映し出す。積読の山は、回避や遅延の象徴に見える。しかし、積人は制度の責任回避とは異なる。積人は「誰かが責任を取るだろう」と委ねるのではなく、「いずれ自分が応答する」という未来への約束を保持している。積読は無限延期ではなく、応答を自己の手に留める装置なのだ。
ここに、制度的責任と積人の責任の違いが浮かび上がる。制度は責任を形式化し、分散させることで誰の責任でもなくしてしまう。積人は責任を遅延させつつも、決して他者に委ねない。積人は未来において応答する責任を引き受ける。制度的責任が無責任を生むのに対して、積人の責任は誠実な遅延としての可能性を保つ。
6. 攪乱としての積人
こうして見ると、積人は教育制度や組織責任に対して攪乱的に働いている。教育制度が数値化によって責任を明確にしようとするとき、積人は数値に換算できない遅延の責任を提示する。組織が責任を分散し、誰も実質的に応答しなくなるとき、積人は「未来における応答」という誠実な遅延を保持する。
積人は制度の内外を漂いながら、責任の形式化を撹乱し、応答可能性を守り抜く存在である。その実践は怠惰ではなく、むしろ制度の圧力に抗して学びと責任を取り戻す倫理的行為なのである。
第五部 芸術と創造の倫理――積人の爆発と捨て身
1. 芸術と責任の逆説
責任と芸術を結びつけるのは一見奇妙に思えるかもしれない。責任は秩序と規律を求めるが、芸術は自由と逸脱を希求する。しかし、この両者は必ずしも対立するわけではない。むしろ芸術は、責任の制度的枠組みを攪乱し、新しい責任の形を提示する。
積人はその意味で、芸術家と同じく「秩序から逸脱する責任」を体現している。未読本の山は混沌の象徴であり、制度的秩序に収まりきらない。だが、その混沌のなかにこそ新しい応答の可能性が潜んでいる。積人は芸術的存在として、未来の爆発や変容を準備する。
2. 岡本太郎――爆発する未読の毒
岡本太郎は「芸術は爆発だ」という言葉で知られるが、その真意は「生命が自己を表現する極限のエネルギー」だった。彼の著作『自分の中に毒を持て』(青春出版社、1993)は、芸術とは「危険を抱え込みながら自らを解放する行為」であると説く。
この「毒」を積読の山に重ねるとどうだろうか。未読本は、まだ解放されていない思考や感情の毒である。本棚に積まれた書物は、未消化の爆薬のように眠っている。読むことは、その毒に火をつけ、爆発させる行為だ。積人は毒を抱え込む存在であり、爆発の予兆を温存している。
岡本太郎にとって、芸術の倫理とは「安全圏に安住しないこと」であった。同じように、積人の倫理とは「読んで理解済みという安全圏にとどまらないこと」である。未読の本を積むことは、未知の毒を抱え込み、自らを危険にさらす勇気にほかならない。積人は、爆発を先送りしながらも、それを回避しない姿勢を貫く芸術家なのである。
3. 執行草舟――捨て身と積人の勇気
執行草舟は現代において「捨て身」の思想を唱える稀有な思想家である。彼は成果や効率を至上とする社会を批判し、むしろ「生のために成果を投げ捨てる勇気」を強調する。著書『生くる』(講談社、2019)や公式サイトの言葉にも繰り返し現れるのは、「全存在を賭けることが真の自由を生む」という信念だ。
積人の実践もまた、一種の捨て身である。本を積むことは、読書の成果をすぐに示すことを拒否する行為だ。知識を効率的に吸収し、アウトプットとして活用することが称賛される社会において、積読は「成果を見せない」という危険な選択である。積人は「役立つ読書」という安全圏を捨て、自らの未読を抱え込む捨て身の存在なのだ。
執行草舟は、芸術や思想を「生命を燃焼させる行為」として語る。そこでは成果や評価は二次的であり、むしろ生き切ること自体が目的となる。積人もまた、読書の成果を超えて、生きることの燃焼に直結する実践である。未読本の山は「まだ出会っていない思想との約束」であり、それを抱えながら生きること自体が、捨て身の勇気に満ちている。
4. 爆発と捨て身の交差点
岡本太郎の「毒」と「爆発」、執行草舟の「捨て身」と「燃焼」。この二つの倫理を積人に重ね合わせると、未読本の山は単なる怠惰ではなく、創造のエネルギーを秘めた危険な装置として立ち現れる。
積人は爆発を準備し、捨て身でその危険を抱え込む。積読の山は、いつ爆発するか分からない思想の火薬庫であり、積人はそれを恐れず抱きかかえる存在だ。彼らの責任は、成果を出すことではなく、可能性を保持し続けることにある。
5. 創造の倫理としての積人
ここで改めて問うべきは、「積人の倫理とは何か」ということである。責任の倫理が「他者に応答すること」であるならば、創造の倫理は「まだ応答しないことを引き受けること」だ。積人は応答を遅らせることで、爆発や捨て身という創造的契機を保持する。
制度が成果を即時に求める時代にあって、積人の実践は創造的な攪乱である。未読は無駄ではなく、可能性の貯蔵庫であり、未来において爆発的に開花するエネルギーである。岡本太郎と執行草舟が提示した芸術と生命の倫理を重ね合わせるとき、積人は単なる読書家ではなく、創造を生きる存在として浮かび上がる。
6. 結語――未読を抱える勇気
芸術は爆発であり、生命は捨て身である。この二つの極端な倫理を結ぶ橋が、積人の実践にある。未読の山を抱えながら、それを恐れず、成果を急がず、可能性として保持し続けること。これこそが創造の倫理としての「せきにん」なのである。
積人は怠惰ではない。むしろ彼らは、未来の爆発と捨て身の勇気を抱える芸術的主体である。制度的責任を超え、社会的虚構を撹乱し、死を見つめながら応答を遅延させる。積人は、現代社会における創造の最後の砦である。
第六部 交差点/社会批評への展開――質的責任と量的積人の同化
1. 質と量のねじれ
責任は本来、質的な概念である。誰かに応答し、問いに誠実に向き合うという応答可能性の問題は、数値で測ることができない。しかし現代社会は、責任をしばしば量的な指標に還元する。どれだけのタスクをこなしたか、どれだけのメールに即座に返信したか、どれだけの会議に参加したか――責任は「数」で管理される。
一方、積人は量の象徴である。積まれた未読本は量的に可視化され、数を増すたびに罪悪感やプレッシャーも増していく。しかし、その量は同時に「質への可能性」を秘めている。積んである本はまだ読まれていないが、それぞれが質的な応答の契機となりうる。ここに「責任(質)と積人(量)」が交差する。
この交差点において、質と量は対立するのではなく、むしろ同化していく。責任は量的に管理され、積人は質的な意味を背負う。現代社会では、責任と積人が互いの属性を交換し、ねじれながら共存しているのだ。
2. SNSと即応圧――責任の数値化
SNSは、責任を数値化する代表的な装置である。発言に対する「いいね」や「リツイート」は応答の尺度を数値化し、どれだけの人に届いたかが評価の基準となる。そこでは、責任ある言葉よりも、即時的で反応を得やすい言葉が優先される。責任の質は量に回収され、応答は即時性によって価値づけられる。
積人の実践は、これに対する沈黙の抵抗である。積読は即応を拒否し、数値化されない応答を準備する。SNSが「即座に反応する責任」を課すのに対して、積人は「まだ応答しない責任」を引き受ける。未読の本は「反応を遅らせる権利」を物質的に保証している。
宮台真司が語るように、情報社会では「熟考の権利」が失われつつある。積人はその権利を守り抜く最後の主体であり、SNS的責任に対するアンチテーゼなのだ。
3. 速読文化と効率至上主義
近年、速読や多読が「効率的な読書法」として広まっている。読書は「何冊読んだか」「どれだけ速く読んだか」で評価され、成果主義の文脈に組み込まれる。責任は「読んだ証拠を示すこと」に変質し、質的な応答よりも量的な達成が重視される。
しかし、速読文化は応答可能性を掘り崩す。本を速く読むことはできても、その問いに誠実に応答することは別問題である。責任は速度や数量に還元されない。
積人はここで、効率至上主義への批評を体現する。積読は速さを拒否し、むしろ「遅延すること」を肯定する。積人は「まだ読まない」という選択によって、読書を再び質的な応答へと引き戻す。未読本の山は、速読文化に対する沈黙の抗議であり、熟考の権利を保障するアーカイブなのだ。
4. 責任と積人の同化
現代社会では、責任と積人は互いの性質を交換し、同化している。
- 責任は質的な概念でありながら、量的に数値化される。
- 積人は量的な存在でありながら、質的な意味を背負う。
この同化は皮肉でもある。責任の質が量に回収される一方で、積人の量は質に転化する。未読の数はそのまま、熟考や誠実さの可能性として解釈される。積人は「遅延する責任」を引き受け、責任は「即応する積人」を求める。両者はねじれ合いながら、現代社会の知的風景を形成している。
5. 社会批評としての積人
このねじれを読み解くと、積人は単なる読書習慣を超えて、社会批評の主体として立ち現れる。積人は、責任の質が量に回収される現代において、量の中に質を保持する存在である。積読の山は「質を奪われた責任」に対する逆照射であり、「数値化されない誠実」を保証する証拠だ。
積人の倫理は、即応圧と効率至上主義に抗して「遅さ」を肯定する。遅延は無責任ではなく、むしろ誠実な応答の一形態である。積人はその実践によって、責任と積人の同化という現代的状況を批評する。
6. 「せきにん」という社会批評の言葉
ここで再び「せきにん」という音の重なりに立ち返ろう。責任と積人が同じ音を持つことは、単なる偶然ではない。現代社会においては、責任と積人が実際に同化し、互いの性質を交換している。この言葉の仕掛けは、社会批評の現場を鮮やかに照らす。
責任が数値化され、積人が誠実を背負うとき、私たちは「せきにん」という言葉に二重の意味を読み取る。そこには、制度と習慣、質と量、即応と遅延のねじれが集約されている。積人は社会批評の主体であり、「せきにん」という言葉はその批評のための装置なのである。
第七部 社会批評への展開――公共性・読書と教育の未来
1. 公共性の危機と積人の可能性
現代社会は、情報の洪水と即応圧に晒され、公共性の基盤が揺らいでいる。議論はしばしば短文化・断片化され、SNSの「いいね」やリツイートが公共的評価の基準とされる。熟考や遅延は排除され、反射的な応答が「民主的参加」と見なされる。
しかしこの構図は、公共性の劣化を招く。意見の交換は単なる情報の応酬に堕し、質的な対話は成立しにくい。責任ある応答が数値に還元されるとき、公共性は深まりではなく拡散に向かう。
ここで積人の実践を思い出そう。積読は即応を拒否し、応答を遅らせる。積人は「まだ答えない」という態度によって、公共性を守る可能性を開く。熟考のための遅延は、公共的討議に不可欠な要素である。積人は、数値化と即応圧に対する「公共性の守護者」として立ち上がる。
2. イリイチと学びの公共性
イヴァン・イリイチが「脱学校の社会」で示したのは、学びの公共性の回復だった。学校という制度が学びを独占することで、学習は制度的評価に縛られる。イリイチは、学びを制度から解放し、自由なネットワークのなかで公共的に共有されるものとして再構想した。
積人の実践は、この構想に通じている。未読本を抱え込むことは、制度の進度や評価に従わず、自分の関心に基づいて学びを選び取ることだ。積読の山は「まだ応答していない公共性」の可能性を宿している。積人は学びを独占から解放し、未来の共有に備える主体なのである。
3. 池田晶子と死の公共性
池田晶子が語った「死の哲学」は、個人の有限性を自覚することが、かえって公共性を開くことを示していた。死は誰も代わりに引き受けられない究極の責任であり、その認識は自分を閉じるのではなく、むしろ他者との真の対話を可能にする。
積人の有限性も同様である。すべての本を読むことはできない。未読は死の比喩であり、有限性の証だ。しかしその有限性を引き受けることは、公共的対話の条件となる。積人は「私はすべてを応答できない」という前提から出発する。その謙虚さこそ、公共性の新しい基盤である。
4. 宮台真司と制度の再構築
宮台真司は、現代社会における「制度の崩壊」と「公共圏の脆弱化」を指摘してきた。中間共同体が弱体化し、個人が孤立するなかで、公共性はメディアや市場に委ねられている。宮台が求めるのは、熟考と遅延を可能にする「厚みある公共性」の再構築である。
積人の実践は、この方向性と響き合う。積読は即応的な公共圏から距離を取り、熟考を可能にする余白を確保する。積人は公共性を消費するのではなく、準備し、保留し、未来に投げ渡す。そこには、情報社会を超えるための公共性の萌芽がある。
5. 教育の未来と積人の倫理
未来の教育は、速さと効率を競うものではなく、遅さと熟考を尊重するものへと転換されるべきだ。積人はその象徴的存在である。未読の山は、未解決の問いを保持するアーカイブであり、生徒や学習者に「まだ答えなくてよい」という権利を保障する。
もし教育が積人の倫理を取り入れるなら、評価は即時的な成果ではなく、問いを持ち続ける能力に基づくものとなる。積読は「怠惰」ではなく「誠実な遅延」として評価され、教育は再び公共性を取り戻すだろう。
6. 公共性の未来を開く積人
積人は、教育や制度の外縁で、公共性の未来を準備している。未読は「まだ語られていない声」を保持し、応答の遅延は「対話の厚み」を保証する。積人の存在は、現代社会における公共性の再生にとって不可欠である。
責任と積人が同じ「せきにん」という音に宿ることは、偶然ではない。質的責任と量的積人が同化する現代において、積人の倫理は公共性の再構築の鍵となる。積読は未来の公共性を準備する沈黙のアーカイブであり、教育の未来を照らす灯火なのだ。
第八部 結語――誠意は数値化できるのか/人を積んで責任を回避する制度の皮肉
1. 誠意と数値の断絶
私たちは日常的に、誠意を「どれだけ行動で示したか」「どれだけ数をこなしたか」で測ろうとする。ビジネスでは成果数値が誠意の証とされ、教育ではテストの点数が努力の証とされる。しかし誠意は本来、数値に還元できない。
誠意とは「応答可能性」の質に関わる。問いや呼びかけにどのように応答するか、その誠実さに関わる。応答の遅延や沈黙もまた、誠意の形でありうる。だが数値化はこの複雑さを切り捨てる。誠意を数値で表そうとするとき、最も大切な「質の深み」が失われてしまう。
積人の実践は、この断絶を可視化する。未読本の数は量的に把握できるが、それが誠意を表すわけではない。むしろ「まだ応答していない」という誠意が、その量の背後に潜んでいる。積人は誠意を数値化できないことの証人なのである。
2. 人を積む制度の皮肉
一方、社会制度はしばしば「人を積む」ことで責任を回避する。企業は委員会やプロジェクトを乱立し、人員を積み上げて「体制を整えた」と説明する。行政は組織図に人を配置することで「責任体制」を示す。だが、実際には誰も実質的な責任を引き受けない。
ここには、積読と似た皮肉が潜んでいる。本が積まれることで「知の体制」が整ったかのように見えるが、実際にはまだ読まれていない。同様に、人が積まれることで「責任体制」が整ったかのように見えるが、実際には応答が欠落している。
積読が誠実な遅延を孕むのに対し、人を積む制度は不誠実な責任回避を孕む。積人は未来に応答する可能性を抱え込むが、制度は未来への応答を他者に押し付ける。両者の差は、誠意の有無にある。
3. 「せきにん」という言葉の二重性
責任(責任)と積人(積読をする人)が同じ音を持つことは、単なる偶然ではない。現代社会では、責任と積人が実際に交差し、相互に照らし合っている。
責任は数値化され、質を失いかけている。その一方で、積人は量を抱え込みながら質的な意味を帯びている。この二重性は、「せきにん」という言葉の響きに象徴的に凝縮されている。
責任が量に還元され、積人が質を背負うとき、私たちは「誠意は数値化できない」という事実に改めて気づく。積人の実践は、責任の本質を言葉の裏側から照らし出している。
4. 誠意の不可算性
ここで最後に確認しておきたいのは、誠意の不可算性である。誠意は「何冊読んだか」「どれだけ速く読んだか」といった数値では測れない。誠意とは「どう応答するか」という一点にかかっている。
積人の山は、誠意の不可算性を物質的に表現している。本が積まれていること自体が「まだ応答していない」という誠意の痕跡なのだ。誠意は成果や即応ではなく、遅延や保留のなかにこそ宿る。
5. 社会批評としての皮肉
最後に、この大論考全体を貫く皮肉を強調しておきたい。
- 制度は人を積むことで責任を回避する。
- 積人は本を積むことで責任を引き受ける。
前者は責任の空洞化、後者は責任の深化である。見かけは似ていても、その内実は正反対だ。社会批評としての皮肉は、この二重性を指摘することにある。
積人は怠惰ではなく、誠実な遅延を体現する存在である。制度は責任を形式化し、数値化し、人を積むことで責任を回避する。積人と制度の対比は、現代社会の倫理的病理を鮮やかに照らし出している。
6. 結語――「せきにん」を生きること
責任と積人、二つの「せきにん」を貫くテーマは、誠意の不可算性であった。誠意は数値化できない。応答の質にかかわるものであり、遅延や沈黙のなかにこそ宿る。
制度は人を積んで責任を回避するが、積人は本を積んで責任を引き受ける。ここに現代社会のアイロニーが凝縮されている。
「せきにん」という言葉を生きるとは、この二重性を自覚し、数値に還元できない誠意を保持することである。積人の倫理は、未来に向けて応答を遅延させる誠実な実践であり、制度の皮肉を批評する最後の砦である。
私たちは今後も「せきにん」を抱え続けるだろう。責任を背負い、積人であり続けること。それが、公共性と誠意を取り戻す唯一の道なのかもしれない。
参考文献
- イリイチ『脱学校の社会』(1971/1972米版)では、学校制度の批判と「学習ウェブ(learning webs)」の発想が中核。分散・自律・平等なアクセスを志向。ウィキペディア
- 「コンヴィヴィアリティ(conviviality)」は『コンヴィヴィアリティのための道具』(1973)で導入。人の自発的能力を引き出す“ツール”と、産業的に人を従属させる“ツール”を対置。ウィキペディアnorthernschool.info
- 小坂井敏晶はパリ第八大(心理学)で教鞭をとり、『増補 責任という虚構』『増補 民族という虚構』『社会心理学講義』などで「規範/責任」の社会的構築性を論じる。筑摩書房の著者ページ・書誌に明記。+2
- 宮台真司:日本の社会学者(学位論文は予期理論関連)。情報社会・中間集団・規範の議論で知られる。ウィキペディア
- 小室直樹:社会学・経済学・法学を横断し、制度論・社会科学の統合を標榜。東京工業大学など歴任。ウィキペディア東洋経済オンライン
- 池田晶子:専門用語に依存しない日常語の哲学。『14歳からの哲学』等。死の思索にも重心。ウィキペディアAmazon版元ドットコム
- 岡本太郎:理念“芸術は爆発だ”。著『自分の中に毒を持て』は青春出版社文庫/文庫新版あり。記念館・美術館の資料でも語録が整備。seishun.co.jptaromuseum.jp
- 執行草舟:実業家・著述家。公式サイトにプロフィール・著作・美術事業の記述。戸嶋靖昌との縁(後援)も記録に残る。ウィキペディア+1しぎょう総集