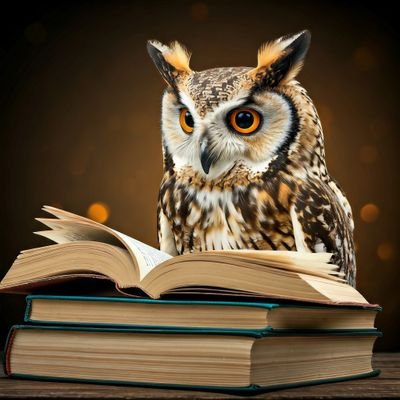Ⅰ 数式の外側で
「(-1)×(-1)=1」。
算数の授業で最初にこれを習ったとき、多くの子どもは違和感を覚える。「マイナスにマイナスを掛けたらプラスになる」と言われても、直感には反する。借金を二回すれば財産が増えるわけではないし、失敗を重ねれば成果が生まれるわけでもない。だがこの数式は、算術の体系を保つために必然的に導かれる。そして大人になってから、ふと立ち止まるときがある。「あの規則性は、単なる数の論理ではなく、人生の局面にも潜んでいるのではないか」と。
私がここで語りたいのは、数学の厳密な証明ではない。むしろ逆に、厳密さからはみ出した生活の思索である。苦悩に次ぐ苦悩をくぐり抜けるとき、単なる減算を超えた「転化」が起こる。それは快楽的な幸福ではなく、深度を持つ肯定、すなわち「正」と呼びうるものだ。
Ⅱ 第一の苦悩
人生における最初のマイナスは、誰にとっても避けられない。失恋かもしれないし、職場での挫折かもしれない。あるいは家庭環境や身体の不調という形で最初から背負わされる場合もある。
この最初の「-1」は、それだけで十分に人を打ちのめす。人は反射的に、その痛みを埋め合わせようとする。美味しいラーメンを食べる、旅行に出かける、SNSで「いいね」を集める。もちろんそれは悪くない。けれども、それはせいぜい「-1+5=4」にすぎない。確かに結果はプラスだが、もとの苦悩は未解決のまま沈殿している。
Ⅲ 二重苦という跳躍
ところが、人は時に二つ目のマイナスを迎える。似た種類の失敗、あるいはまったく別の苦しみ。ここで重要なのは、それを避けるか、背負うか、である。
二度目の苦悩に直面すると、多くは「もうごめんだ」と背を向ける。しかし逃げ切れなかった者は、必然的に二重苦をくぐることになる。逃れられぬ圧迫の中で、ただ身をよじり、もがき、内面の壁にぶつかる。ここで起きることが、単なる加算ではなく「掛け算」だ。
「-1+(-1)=-2」として沈み込むかに見える局面で、実は「-1×-1=+1」という別の論理が顔を出す。二つのマイナスが掛け合わさるとき、そこに転倒が生じるのだ。
Ⅳ 謙虚を超えて、無へ
二重苦の只中で人は謙虚になる。謙虚とは、自分が特別ではないと知ることだ。しかし、これはまだ入口にすぎない。謙虚さをくぐった先に訪れるのは「無」の感覚だ。
「無」とは、何も考えないことではなく、普段の思考が機能しなくなる地点を指す。陽気なとき、成功に酔っているとき、私たちはけっしてこの領域には到達できない。だが二重苦は、人をそこへ強制的に押し込む。
そして不思議なことに、その「無」から新しい思考が芽吹く。普段なら決して思いつかない視点、他者の痛みに対する共感、自己への冷徹なまなざし――。二重苦によって開かれた場所でしか得られない光景がある。
Ⅴ 文学と哲学の証言
この「二重苦による正」は、古今東西の思想にしばしば顔を出す。
ニーチェは「自らの苦悩を愛せ」と言った。彼にとって苦悩は克服すべき障害ではなく、生成の必然条件だった。ドストエフスキーの小説の登場人物たちは、しばしば地獄のような状況をくぐり抜け、その果てに奇妙な光を掴む。高橋和巳の『悲の器』もまた、個人の苦悩と社会的矛盾の二重性を描きながら、どこかで「正」に向かう運動を内包している。
また、仏教においても「二重否定」は悟りに通じる。存在への執着を否定し、その否定すら否定するとき、「空」が立ち現れる。これもまた「(-1)×(-1)=1」の生の論理に近い。
Ⅵ ズレとしてのユーモア
私はここで、少しユーモアを差し込みたい。
「焦りすぎてアリストテレスを読む」とか、「こじれすぎてコジェーヴを読む」といった言葉遊びは、苦悩のなかで生まれる小さな救いだ。ユーモアは、苦悩を単なるマイナスにせず、どこか別の方向へ跳ねさせる。ズレによって笑いが生まれるとき、すでに小さな「正」が芽吹いている。
Ⅶ 血肉化する思考
最終的に重要なのは、二重苦を言語化し、血肉にすることだ。単なる体験として過ぎ去るのではなく、言葉にすることで初めて自分の中に定着する。
「二重苦によって正」という数式めいた表現は、そのプロセスを象徴している。苦しみを二度くぐったあとに見える光景を、数学の規則性を借りて名づけることで、私たちは経験に輪郭を与える。
Ⅷ 結語――深度ある肯定へ
単なる快楽のプラスではなく、二重苦の果てに現れる「正」。
それは、傷を背負った者にしか見えない景色である。
「(-1)×(-1)=1」という算数の規則は、人生の隠喩として響く。マイナスを二度くぐり抜けることは、確かに痛みを伴う。しかし、その転倒によって開かれる肯定は、薄っぺらな幸福とは異なる強度をもつ。
私たちは、ラーメンを食べて一時的に慰められることもあるだろう。だが、真に血肉となるのは、二重苦を言語化し、そこでしか見られない景色を正として抱きしめる経験なのだ。