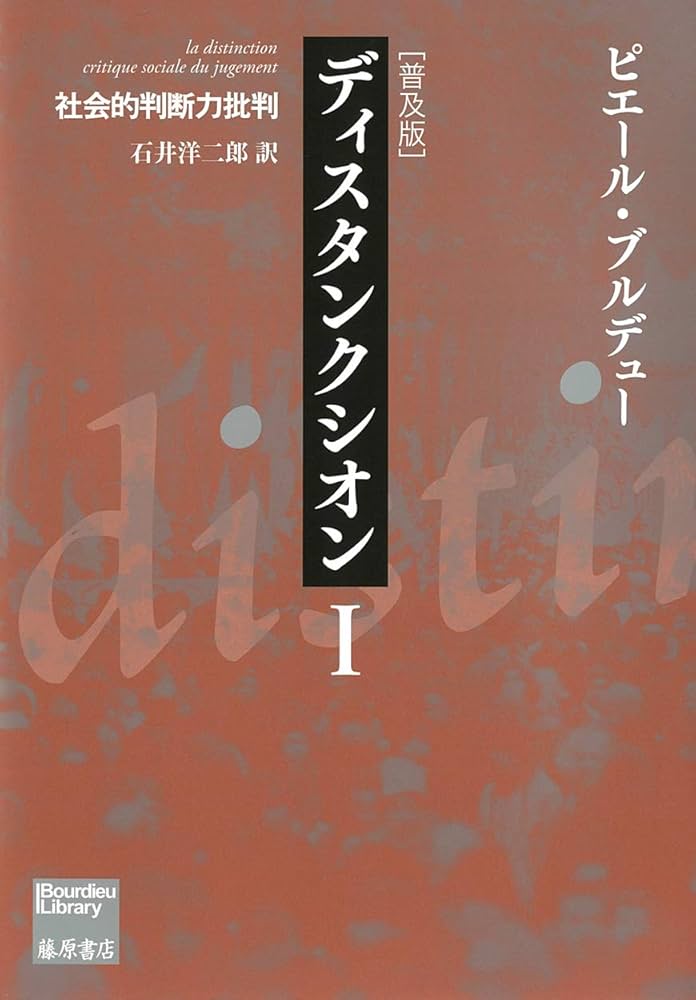■株式会社藤原書店
公式HP:https://www.fujiwara-shoten.co.jp/
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/FujiwaraRSS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
問題意識と背景
中間層(平均的な収入の方)の男性が多数を占める日本において、女性が社会進出すればするほど宮台真司用語「属性主義」(詳しくは宮台真司教授の本へ)によってミスマッチが増え、少子化につながるのえでは、と仮説を立てた。よってこの仮説を検証していくことをこの記事の目的とする。
1. 序
ジュンク堂の5階で、私は二冊の本を抱えた。
ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオン』と、ナシーム・ニコラス・タレブ『反脆弱性』。
この二冊を並べた時、思わず笑みが漏れた。前者は檻の設計図であり、後者はその抜け道である。
文化資本という鉄格子と、不確実性という錆。両者の交錯点にこそ、「脱中間層戦略」の核心が潜んでいる。
2. ブルデューの檻
ブルデューによれば、人間の好みや趣味は、単なる個人の選択ではない。
クラシック音楽を聴くか、演歌を好むか、あるいはどの本を積んでいるか――それらは無意識に社会階層を映し出し、そして再生産する。
「文化資本」と名付けられたこの装置は、中間層を中間層に留め置くための鉄格子である。
私は書棚を眺めながら、自分の本棚そのものが檻の一部であることを思い知らされる。
読書は自由の証ではなく、むしろ習慣化された「ハビトゥス」の鉄筋なのだ。
3. タレブの錆
一方、タレブの声は正反対だ。
彼は告げる――「脆弱性を恐れるな。不確実性に身を晒せ。ショックを糧とせよ」と。
安定を守ろうとするほど、システムは弱くなる。
中間層は「安全」を信じ込むことで、かえってリスクに対して無防備になる。
だが反脆弱な存在は違う。偶然の衝撃を吸収し、むしろ強化されてゆく。
「失敗は資本であり、偶然は抜け道である」と彼は書く。
4. 鉄格子に錆を走らせる
ここで二冊の本が重なる。
文化資本は檻を築き、反脆弱性はその檻に錆を走らせる。
読書という行為は二重性を持つ――檻を強化する鉄筋にもなれば、錆を誘う不確実性にもなりうるのだ。
中間層を抜けるとは、単に高収入を得ることではない。
自らの文化資本を、檻ではなく突破の武器に変えることなのである。
5. 結語
鉄の檻は強固である。
だが、不確実性の錆はゆっくりと、しかし確実にその格子を侵す。
ブルデューとタレブを横断的に読むことは、檻と錆を同時に手にすることだ。
読書梟としての私に残された使命は一つ。
――檻の設計図を抱えつつ、錆を仕込むこと。
それが「脱中間層戦略」の始まりである。