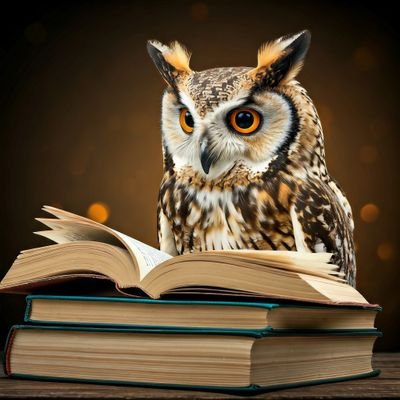読書ブログという形をとりながら、私自身の思索と読書体験を交差させてみたいと思います。
、ビジネス(私的セクター)が果たせることと公共(政府・自治体・市民共同体)が果たすべきことを明確に区別して整理し、最後に活動家として動くための具体アクション(すぐ使えるテンプレ含む)を付けます。
端的な区別(原則)
- ビジネスが得意/やるべきこと
- 利潤動機で効率的に供給できるもの(差別化・イノベーション・迅速なサービス提供)。
- 競争で効率化や顧客向けの付加価値を生む分野(マーケティング、UX改善、カスタマーサービスの工夫など)。
- ユーザーの選好に応じた多様な商品・サービス(プレミアムサービス、ニッチ向けサービス)。
(→ ただし「効率=公正」ではない点は要注意。)OECD
- 公共(政府・自治体・市民共同体)が果たすべきこと
- 公共財・外部性の是正:市場が提供しにくい「非排除性/非競合性」の公共財(治安、街路灯、基礎インフラ、気候対策の一部など)は公共が担う。市場では過少供給になりがち。スタンフォード哲学百科事典Econlib
- 格差是正・社会的セーフティネット:所得再配分、保健・教育の普遍的アクセスなど、基本的な平等(機会の平等)を守る役割。日本の医療の普遍的制度はこの例。OECD
- ルール作り・競争条件の整備:独占・情報非対称・外部不経済に対する規制(独占禁止、消費者保護、環境規制など)。市場の失敗を是正するための監督と法整備。OECD
- 共同管理や市民参加の支援:コミュニティが自律的に資源を管理するモデル(Ostrom が示した共同管理の原理)は、公共と民間の“第三の道”として重要。NobelPrize.org
具体例での振り分け(短く)
- 医療:基礎的普遍提供は公共(ただし民間病院の運営や付加サービスは民間)。OECD
- 教育:義務教育・高等教育の基礎的アクセスは公共、専門コースや補習は民間が担う。
- インフラ(上下水道、道路):公共主体が基本。ただし建設・維持の一部でPPP(公民連携)は有効。OECD
- デジタルプラットフォーム(出会い系やマッチング):民間が提供するが、透明性・差別防止・個人情報保護・対等な手続きは公共(法制度・監督)が担うべき。OECD
判断のためのチェックリスト(政策決定者に問うべきこと)
- このサービス/財の利用は誰にどの程度の害・利益をもたらすか(外部性は?)
- 市場に任せると誰が取り残されるか(格差は拡大するか)
- 民間に任せる透明性・説明責任・救済手段は確保されるか
- コミュニティによる共同管理で代替可能か(Ostrom のルール参照)。NobelPrize.org
活動家として動くための実務プラン(即効で使える)
- 目的を明確に(要求を一文に)
例:「IBJなどマッチングサービスでの透明な応募状況の通知義務化を求める」 - エビデンスを集める(数字・事例・比較)。OECD や学術資料を1枚のファクトシートにまとめる。OECDスタンフォード哲学百科事典
- ターゲットを決める:事業者(IBJ本体/相談所運営)、監督官庁(消費者庁・厚生労働省・自治体)、メディア、市民。
- 同盟を作る:当事者(申し込み側)、消費者団体、自治体議員、弁護士、学者。日本の市民活動は地域ネットワークが鍵。SpringerLinkCambridge University Press & Assessment
- 行動の順序:情報公開請求 → 議員への働きかけ(質問主意書/要望)→ 公聴会で発言 → 市民署名+メディア露出 → 必要なら行政苦情・消費者庁への申立て。
- 市民に分かりやすい訴え方:個人の「不利益事例」をストーリー化し、制度的欠陥(再現可能な問題)として示す。感情に訴えつつも、改善案は制度設計で示す(例:自動通知義務、申込ステータスの標準化、苦情窓口の明確化)。OECD
次の記事でもまた、読書ブログならではの読後の余韻を記していければ幸いです。