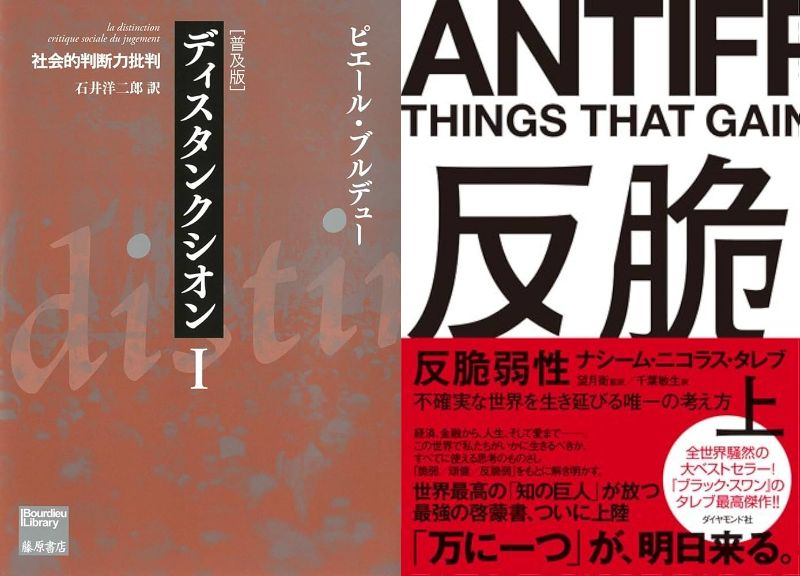つづきを展開
序:錆がもたらす問い
前回までに私は、ピエール・ブルデューの文化資本を「鉄格子」とし、ナシーム・ニコラス・タレブの反脆弱性を「錆」として対置した。
檻を築く理論と、それを腐食させる実践。この二項対立はわかりやすく、痛快ですらあった。
だが読み進めるうちに、より厄介な問いが立ち上がってきた。
錆は、単に檻を壊すのか。それとも、檻を新しい形へと変えるのか。
檻と錆の対立を描いた「02」から一歩進んで、今回は錆の「生成的側面」に焦点を当てる。ブルデューの社会学が見抜いた構造を、タレブの哲学はどう攪乱し、さらに新しい構造へと導いてしまうのか。その矛盾に潜っていきたい。
第一章:錆の正体――小損と偶然の累積
『反脆弱性』をめくると、こんな一節が目を射る。
“社会を脆くし、危機を生み出している主犯は、身銭を切らない人たちだ。”(P25)
タレブが最初に強調するのは、「リスクを共有せず、損を負わない者が社会を歪める」という原理だ。
これはブルデューの「資本を持つ者が構造を維持する」という視点と交差する。どちらも「安全圏にいる者が檻を維持する」と告発しているのだ。
さらにタレブはこう続ける。
“薬理学者の造語である『ホルミシス』とは、少量の有害物質が生物にとって薬の役割を果たし、効能をもたらす現象を指す。”(P71)
偶然や小さな損失は「毒」ではなく「薬」になりうる。
文化資本の檻を思えば、ここに錆の役割が見えてくる。檻は完全に守られたままでは窒息する。小さなひび――それがホルミシスとして働くのだ。
第二章:新しい鉄格子――錆が形づくる構造
ブルデュー的に見れば、錆もまた新しい資本として再生産される。
たとえばタレブのこの指摘。
“歴史を見ればわかるように、社会が豊かになればなるほど、収入相応の暮らしをするのが難しくなる。人間にとっては、欠乏よりも潤沢のほうがずっと扱いづらいのだ。”(P80)
潤沢は人を惑わせ、消費様式は階層を刻む。
私はここに、ブルデューが描いた「趣味の再生産」の影を見る。潤沢に見える文化資本も、結局は新しい鉄格子になる。
さらにタレブは「思考法」そのものを疑う。
“ヒューリスティックとは『単純化されたシンプルな法則』という意味だ。”(P96)
檻を出るどころか、私たちは「単純化」という檻を頭の中に持っている。錆はその思考習慣にも食い込むが、同時に「新しい単純化」をまた生む。
第三章:反脆弱な文化資本
引用を続けよう。
“人生を『プロジェクト』か何かと考えている人類がいる。そういう連中と話すと、しばらく気分が悪くなって、人生が塩味の利いていない料理みたいに感じられてくる。”(P115)
タレブの毒舌に苦笑しつつ、私はブルデューの「生活様式の再生産」を思い出す。
人生をプロジェクトにしてしまうと、それは文化資本の消費と同型になる。味気ない鉄格子だ。
だがタレブはさらに逆説を突きつける。
“システム全体を把握するためには、システム内部に脆い部分が必要なこともあるのだ。”(P118)
“脆いシステムは、物事が計画どおりの針路に従うかどうかに依存している。”(P127)
ここで私は、文化資本を「脆い部分」として扱う可能性を感じる。積んだ本棚は檻の鉄筋であると同時に、計画の破綻を呼ぶ脆さを秘めてもいる。
読書を「公開」する行為は、まさにその脆さを錆へ転じる試みだ。
第四章:脱中間層の「筋トレ」
さらに引用を一つ。
“タクシー運転手、売春婦(大昔からある職業だ)、大工、配管工、仕立屋、歯科医といった職人は、収入面では少し不安定だが、収入がゼロになってしまうような職業上の小さなブラック・スワンに対しては、むしろ頑強だ。”(P149)
ここに私は「反脆弱な中間層像」を見た。
ブルデュー的には職人も階層に埋め込まれている。だがタレブ的には、その不安定さこそが強さにつながる。
私が20万円を投じた行動も、この小さなブラック・スワンへの曝露と考えられる。
確かに失敗の可能性はある。だがその小損は筋肉となり、檻に錆を走らせる。
“システムに変動性があればあるほど、ブラック・スワンの影響を受けにくい。”(P151)
読書もまた変動性を取り込める。
批判や誤解に晒されることで、ブラック・スワンに飲み込まれない体質を作るのだ。
結語:檻は錆びながら動く
ブルデューは文化資本の鉄格子を明らかにし、タレブは不確実性を錆として称揚した。
両者を重ねて読むと見えてくるのは、檻と錆の二項対立ではない。
檻は錆びながら動くという、生成の過程である。
最後にタレブの警句をもう一つ。
“「(有害性の)証拠がないこと」を「(有害性が)ないことの証拠」と勘違いしてしまうことだ。あとで説明するように、この種の間違いは知識人の間で蔓延していて、社会科学の分野にもすっかり根を下ろしている。”(P164)
まさにブルデュー的な「知の再生産」を批判するフレーズだ。
檻を補強する知識人の習慣を、タレブはここで突き崩している。
私は今、読書を「檻」にも「錆」にも変えうる地点に立っている。
だからこそ、読者にも問いたい。
あなたの檻を錆びさせる小さな行動は何か。
誤解を恐れず書くことか。
少額を投じて新しい経験を試すことか。
あるいは、予定を崩して偶然の余地を広げることか。
檻を知ること。錆を仕込むこと。
それが「脱中間層戦略」の本質である。
次回予告
次は、ブルデューとタレブに加えて、フランク・ナイトとハリー・マルコウィッツを参照してみたい。
ナイトは「リスクと不確実性の区別」を提示し、マルコウィッツは「分散投資と効率的フロンティア」を理論化した。
檻を築く理性、錆を誘う偶然。その両者のあいだに「リスク管理」という第三の視点を差し込むことで、読書ログはさらに立体化するだろう。