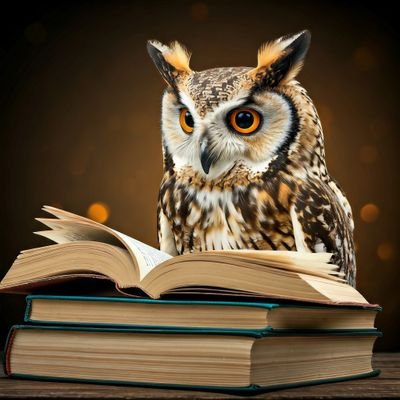の
七年間。決して短い時間ではない。
日々、言葉を積み上げ、読んだ本を記録し、自分の思考を文章にしてきた。だが振り返れば、その労力に見合う「成果」と呼べるものは、ほとんど残っていない。アクセス数は伸びず、収益は雀の涙、誰かから強く注目されることもなかった。
「七年も続けたのに、成果ゼロ」――そう口に出してみると、少しばかり惨めさすら感じる。けれど同時に、これはごく自然なことでもある。「当たり前」なのだ。世界は私の努力を待ってなどいない。インターネットの片隅で言葉を綴ったところで、誰も気に留めてはくれない。
それでも、この虚無にこそ、私の物語はある。
最初の数か月は、淡い期待を抱いていた。記事を更新すれば読まれるはずだ、反応があるはずだ、と。だが現実は冷酷だった。投稿ボタンを押しても、画面の向こうは沈黙のまま。カウンターの数字は増えず、コメント欄は空白のまま、収益化の仕組みにもほとんど触れない。
「努力は報われる」――そんな言葉は、七年もブログを続ければいかに虚しい幻想か、嫌でも理解できる。努力は報われないことの方が圧倒的に多い。報われない努力こそが「標準」であり、「報われる努力」がむしろ例外なのだ。
七年間の更新は、まるで海に石を投げ込み続けるようだった。波紋は一瞬広がっても、次の瞬間には消えて跡形もなくなる。書いた文章は虚空に吸い込まれ、誰の記憶にも残らない。
虚無に耐えるのは容易ではない。
「こんなことを続けて何になるのか」と自問する日が幾度もあった。目に見える成果が出ないと、続ける理由はたちまち揺らぐ。だが、やめなかった。やめたいと思いながら、やめられなかった。むしろ「虚無を抱えたまま生きる」ことに、次第に身体が馴染んでいった。
「成果はなかった」――そう言い切ってしまえば簡単だ。けれど、虚無を抱えて歩いた七年間が、まったくの無だったわけではない。見えにくいだけで、いくつかのものは確かに残っている。
日々、本を読み、その感想を書き留める。最初は単なる備忘録に過ぎなかったが、続けていくうちに、考えを整理するための「型」ができてきた。
文章にすることで、自分の頭の中の曖昧さが露呈する。書くたびに問い返され、書くたびに考え直す。その往復が、思考の深さを少しずつ増していった。
誰も読まない記事を更新することは、孤独そのものだった。承認も称賛もなく、ただ一人で言葉を投げ続ける。だがその孤独は、やがて「常態」になった。他者の反応を期待しすぎず、自分の内面と向き合うことに馴染んでいったのだ。孤独に耐えられる力は、目に見えないが強靭な筋肉のように育っていた。
七年間も文章に取り組めば、嫌でも「自分の言葉の限界」と向き合うことになる。巧みな表現を求めても、しばしば稚拙さが滲む。だがその不全感こそが、次の一歩を促す。完璧にはならない言葉を、それでも書き続ける。これは「失敗を織り込んだ持続性」と呼んでいいかもしれない。
虚無を抱えながら続けてきた七年間、その底に流れていたのは一つの欲望だ。
「中間層から抜けたい」という切実な叫びである。
生活水準を上げたい。経済的に、社会的に、もっと上に行きたい。だが現実には、大きな変化は訪れない。七年のブログが直接的に収入を生むことはなかったし、社会的な立場が変わることもなかった。
だからこそ欲望は、いっそう強く燃え上がった。
「負けたくない」という感情は、時に妬みや焦燥と混ざり合い、心をかき乱す。
「なぜ自分だけがここに留まっているのか」という問いが、夜ごと頭をよぎる。
しかし考えてみれば、この欲望もまた「虚無が残したもの」なのかもしれない。何も得られなかった時間が、逆に「得たい」という切実さを際立たせたのだ。虚無が欲望を磨き、焦燥を鋭くした。
7年間のブログ生活を振り返って、成果はゼロだった。アクセスも、収益も、人脈も。虚無だけが残った。
だが虚無の底をのぞき込むと、そこにはわずかな光が漂っていることに気づく。
それは、習慣化された思考、孤独に耐える筋力、言葉と向き合い続けた痕跡、そして何より「中間層から抜けたい」という切実な欲望だ。
虚無は何も与えない。だが、何も奪いきることもできない。
残ったものは確かに小さく、目に見える成果ではない。けれど、その小さな残滓を手がかりに、私は次の七年を歩むだろう。
「7年の虚無が残したもの」――それは、虚しさに耐えながらも、なお言葉を綴り続ける自分自身だった。