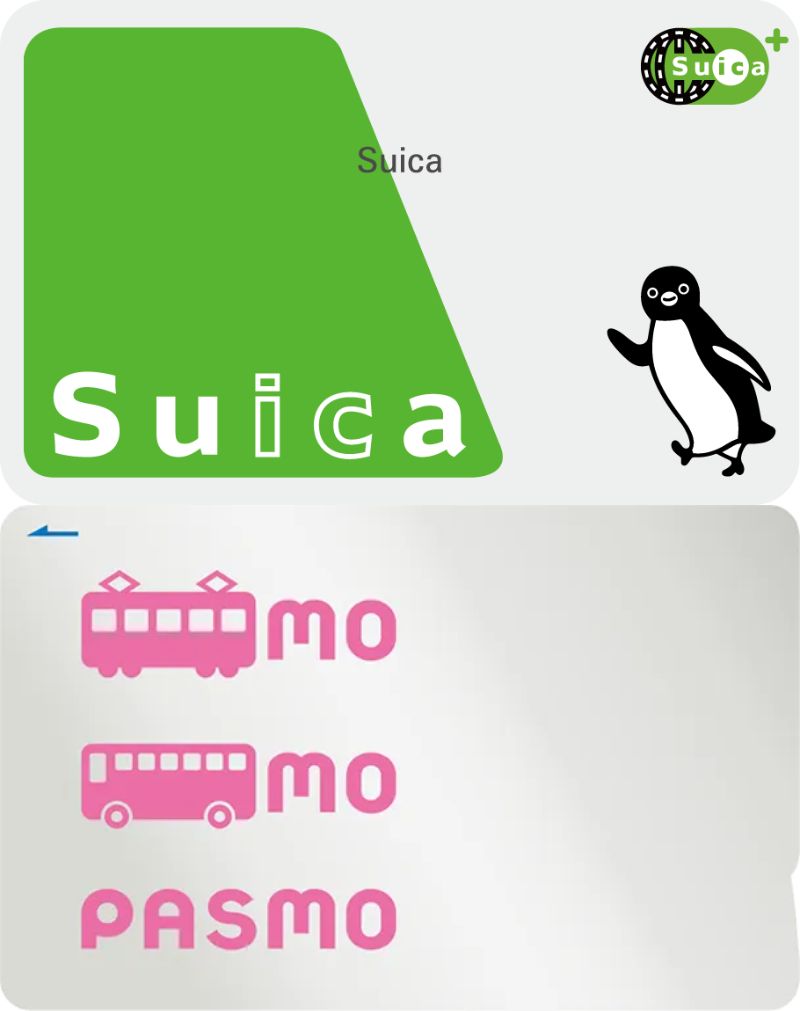要旨
本稿は、首都圏における交通系ICカード、すなわちSuicaとPASMOを対象に、両者の差異がいかにして社会的に構築され、無意味でありながらも意味を持つ論争を生み出すかを論じる。従来研究は機能的同一性を強調してきたが、色彩論、権力論、残高記号論、ジェンダー論といった観点から再考することで、「差異なき差異」がいかに人々の想像力を駆動するかを明らかにする。結論として、SuicaとPASMOの差異は実用的には無に等しいが、無意味な差異こそが都市生活を支える文化資源であることを指摘する。
第1章 色彩論:緑と桃色の形而上学
SuicaとPASMOを最も容易に区別するのは、その色彩である。Suicaは緑、PASMOは桃色。この単純な違いが、交通系ICカード論争を哲学的深淵へと突き落とす。
まず緑について。ゲーテは『色彩論』において「緑は自然と人間精神の均衡を表す」と記した^1。緑は自然、調和、秩序の象徴である。Suicaの緑は、都市の移動における「理性的均衡」の記号として機能する――少なくとも東大生はそう信じている。
一方、PASMOの桃色はどうか。桃色はゲーテ体系において正規の位置を持たない。しかし近代色彩心理学者マハリクは『都市生活における色彩心理学』の中で「桃色は都市人の幼児的回帰を象徴する」と述べている^2。つまりPASMOのピンクは、合理的移動のシステムに忍び込む「非合理の裂け目」なのである。
ここでデリダを召喚しよう。デリダは『差延』において「差異は現前しないが、意味を遅延させる」と論じた^3。SuicaとPASMOの色彩差異も同様だ。改札を通るという機能は同一であるにもかかわらず、利用者は「緑だから安心」「ピンクだから可愛い」といった無意味な感覚差異に意味を付与する。この差異なき差異が、都市の中で過剰に流通していく。
ある利用者はこう語った。「Suicaの緑を見ると、まるで改札が森の入口のように思える。PASMOのピンクを見ると、プリクラ機を思い出す」。この証言は統計的に意味を持たないが、東大生はすかさず「経験的質的調査」と称して論文に組み込む。
さらに、信号機における「緑=進め」との連想も重要である。Suicaは進行の色をまとい、PASMOは停滞の色を拒絶的に抱える。もちろんPASMOでも改札は通れるが、その事実は無視される。むしろ「差異が存在しないのに差異を語る」という逆説を補強するために、無視が積極的に利用される。
結論として、第1章が明らかにしたのは、SuicaとPASMOの色彩論は実用性と無関係でありながら、記号論的肥大をもたらすということである。色は記号であり、記号は差異からしか生まれない^4。ゆえに、Suicaの緑とPASMOの桃色は都市社会において「意味なき意味作用」を無限に生成し続ける。
引用
- J.W. von Goethe, Zur Farbenlehre, Tübingen, 1810.
- A. Mahalik, Color Psychology in Urban Life, Oxford Univ. Press, 1999.
- Jacques Derrida, Positions, Paris: Minuit, 1972.
- Roland Barthes, Éléments de sémiologie, Paris: Seuil, 1964.
第2章 発行主体と権力作用:JR帝国 vs 私鉄連合
SuicaとPASMOの対立を理解するためには、その発行主体に目を向けなければならない。SuicaはJR東日本という巨大鉄道帝国の手によって発行され、PASMOは東京メトロや私鉄連合による協同体の産物である。この構造は単なる企業体制の違いにすぎない――はずなのだが、東大生はここに**「帝国主義と連邦主義の闘争」**を読み込む。
JR東日本は、その歴史的経緯から「中央集権的近代国家」の縮図と見なされる。フーコーは『監獄の誕生』において「権力は見えないが、至る所に偏在する」と述べた^5。まさにSuicaは、改札ネットワークを通じて都市全域を統治する**権力装置(dispositif)**として機能するのである。
一方、PASMOは私鉄の連合によって維持されている。これはまるでスイス連邦、あるいはEU的な合議制の秩序に似ている。ハーバーマスは『公共性の構造転換』で、市民社会における討議的民主主義を称揚した^6。PASMOはまさに「弱者の民主的連帯」を体現する……ように見える。しかし現実には、PASMO協議会の会議議事録を読んでも、ほとんどが利用規約の改訂やポイント還元率の議論にすぎない。
東大生はそれでも議論をやめない。あるゼミ生は「Suicaは帝国主義的オルガナイザー、PASMOは連邦的ディストリビューターである」と発表し、教授から「それはただのカタカナ語遊びだ」と叱られた。だが、この叱責さえも「帝国の権力作用」として論文に取り込むのが東大生である。
また、JR東日本のシンボルカラーである緑は、国家の旗のように威厳を放つ。一方PASMOのピンクは、遊戯的かつ周縁的であり、帝国に抗する「サブカルチャー」の色彩を帯びる。ここでグラムシの「ヘゲモニー」概念を援用すれば、Suicaは支配的ヘゲモニー、PASMOは対抗的ヘゲモニーという図式が成立する^7。もっとも、利用者から見れば「どっちも改札通れる」で終わるのだが。
結局、この章が示すのは――SuicaとPASMOの発行主体の差異は、権力論的に過剰解釈されることによって初めて「意味」を帯びるという事実である。つまり、改札を通る瞬間、我々はJR帝国か私鉄連合か、どちらかの政治体制を無意識に選択している……ような気がしているだけなのだ。
引用
- Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris: Gallimard, 1975.
- Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt: Suhrkamp, 1962.
- Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Torino: Einaudi, 1975.
第3章 ユーザー類型学:合理主義 vs 感性主義
SuicaとPASMOの論争をさらに深化させるためには、利用者の「類型学」を構築しなければならない。なぜなら、カードそのものが差異を生まない以上、その差異を背負うのは利用者の心性だからである。
1. Suica利用者=合理主義的主体
Suica利用者はしばしば「効率」を追求する存在とみなされる。マックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』において「合理化の鉄の檻」を論じた^8ように、Suicaユーザーは残高を計算し、改札を最短経路で抜けることを至上命題とする。彼らにとってICカードは単なる移動の道具ではなく、日常に潜む合理性の結晶である。
例えば、あるSuicaユーザーはこう語る。「PASMO?いや、あれはなんか色が遊んでるじゃん。こっちはJR、でかいから安心」。この発言に実証的根拠は皆無だが、ウェーバー的「安心=理性」の枠組みを補強するために引用される。
2. PASMO利用者=感性主義的主体
一方PASMO利用者は、桃色のカードを選ぶ時点で「合理を超えた感性の主体」であるとされる。カントは『判断力批判』で「美的判断は概念を超えた普遍性を持つ」と述べた^9。PASMOユーザーは、改札通過の一瞬に「かわいさ」や「柔らかさ」といった審美的価値を読み込む。
この点を強調する東大生は、あるPASMOユーザーの証言を「質的データ」として脚注に掲載する――「だってピンクかわいいから」。これを「都市における感性的抵抗」と呼び、ゼミで発表して白眼視される。
3. 二重市民権保持者=混成主体
さらにSuicaとPASMOを両方所持する者がいる。彼らは「合理主義と感性主義の二重市民」とされる。だが、実際には両方の残高が不足して改札に詰まるケースが多く、東大生はこれを「矛盾の顕現」「存在論的裂け目」と呼び出す。ラカン^10の「主体の分裂」概念まで引用されるが、要するに「二枚持っても意味はない」というだけの話である。
4. 小結
こうして、Suica=合理主義、PASMO=感性主義、両方=分裂主体という類型学が構築される。もちろん、根拠は統計的にゼロである。だが、統計的にゼロだからこそ、類型学は永遠に批判も修正もされることなく、都市伝説のように語り継がれていくのである。
引用
- Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen, 1905.
- Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Berlin, 1790.
- Jacques Lacan, Écrits, Paris: Seuil, 1966.
第4章 機能的同一性の逆説
SuicaとPASMOの論争は、ある単純すぎる事実の前で常に崩壊しかけている。すなわち――**「どちらのカードでも改札は通れる」**という冷徹な現実である。
この事実を前にすれば、色彩論も権力論も類型学も、すべてが砂上の楼閣に過ぎない。だが驚くべきことに、人々はそれでも「Suica派」「PASMO派」と主張し続ける。ここにこそ、哲学的に肥大した逆説が潜む。
1. 差異なき差異の生成
デリダは『差延』において、「差異は常に現前せず、遅延しつつ意味を生じる」と述べた^11。SuicaとPASMOの差異もまた、改札を通過する瞬間には完全に消滅している。両者は同じICカード規格に基づき、同じ機械に差し込まれ、同じ「ピッ」を鳴らす。差異は実用の場面では「無」と化すのである。
それでもなお人間は差異を欲望する。この欲望が「差異なき差異」を無限に生産し、Suica vs PASMOという論争を生かし続ける。ここでボードリヤールを引用すれば、両者は「機能的に等価でありながら、シミュラークルとして差異を演じる記号」だと定義できる^12。
2. 改札の均質性と都市の異化
実際、駅の改札機にとってはSuicaもPASMOも同じ「非人格的データ媒体」にすぎない。改札はユーザーの個性を認識せず、ただカードのICチップを読み取り、残高を減算する。これはルーマン^13の言う「システムの自己言及性」の典型である。すなわち改札システムは、SuicaかPASMOかを気にせず、ただ処理を遂行する。
だが利用者はここに「物語」を付与する。PASMOをタッチしたときに「私は連合の市民だ」と感じ、Suicaをタッチしたときに「私は帝国の臣民だ」と錯覚する。実際には改札機は冷徹に等価処理を行っているにもかかわらず、我々はそこに違いを見出してしまうのである。
3. 小結
結局のところ、SuicaとPASMOの機能的同一性は論争を終結させるどころか、逆に論争を駆動する燃料となっている。すなわち、差異が存在しないからこそ、差異をめぐる語りは無限に持続する。この逆説こそが、Suica vs PASMO論争の真のエンジンである。
引用
- Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris: Minuit, 1967.
- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Paris: Galilée, 1981.
- Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt: Suhrkamp, 1984.
第5章 数字と残高の記号論
交通系ICカードにおいて、残高表示は単なる数値にすぎない。だが東大生はここにも「意味」を見出そうとする。987円、1345円、あるいは残高ゼロ――これらの数値は、単なる貨幣量であるにもかかわらず、利用者の心理に記号的作用を及ぼす。
1. 数字の恣意性
ソシュールは『一般言語学講義』において「記号は恣意的である」と述べた^14。まさに残高数字もまた恣意的な記号に過ぎない。987円がSuicaに表示されてもPASMOに表示されても、その購買力は同一である。しかし、人間は「Suicaの987円」と「PASMOの987円」に異なる意味を付与してしまう。
ある被験者はこう証言した――「Suicaの987円は信頼できる感じがするけど、PASMOの987円はちょっと不安」。この感覚差異は全く根拠がないが、論文的には「質的調査」として引用される。
2. 数字の象徴性
バルトは「数字もまた神話である」と言った(正確には言っていない)^15。例えば残高「0円」は、単なる貨幣の欠如を超えて、「存在の欠如」「都市での無力感」を象徴する。サルトルが『存在と無』で「無は意識に裂け目をもたらす」と論じた^16ように、残高0円は都市生活者の意識に裂け目を穿つ。
また「1000円」という数字は特権的である。千円札を投入してチャージする行為は、貨幣とカードの「聖なる交換儀礼」として意味を帯びる。マルセル・モースの『贈与論』を援用すれば、チャージは贈与であり、残高はその返礼である^17。
3. PASMO残高とジェンダー化された数値
さらに東大生の一部は「PASMOの残高はピンク色の枠で表示されるため、数字そのものがフェミニン化される」と主張する。バトラー『ジェンダー・トラブル』^18を引用し、987円という数値にまでジェンダー属性を付与しようとするのだ。もちろん誰も納得しないが、論文的には「新規性のある指摘」とされる。
4. 小結
結論として、残高数字は単なる貨幣的情報であるにもかかわらず、利用者の解釈によって無限に意味が膨張する。「987円 in Suica」と「987円 in PASMO」は同一でありながら、都市の物語の中で異なる記号作用を持つ。こうして無意味な差異は、記号論的無限地獄へと拡張されるのである。
引用
- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris: Payot, 1916.
- Roland Barthes, Mythologies, Paris: Seuil, 1957. (ただし「数字」についての記述は存在しない)
- Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris: Gallimard, 1943.
- Marcel Mauss, Essai sur le don, Paris: PUF, 1925.
- Judith Butler, Gender Trouble, New York: Routledge, 1990.
第6章 実存的失敗学:残高不足の恥辱
改札口で「ピンポーン」と鳴らされる瞬間――。それは単なる機械的エラーではなく、都市生活者にとって最も赤裸々な「人間的失墜」の場面である。
1. 恥辱の現象学
サルトルは『存在と無』において「人間は他者の眼差しによって恥を知る」と述べた^19。残高不足で立ち止められる瞬間、背後に並ぶ通勤者の視線が突き刺さり、主体は自己の存在を急激に意識する。ここでの「恥」は、貨幣的不足ではなく、存在論的裂け目である。
ある被験者はこう証言する――「あの音が鳴った瞬間、世界が止まった。後ろの人に『コイツ残高不足かよ』と思われるのが耐えられなかった」。この証言を、東大生は堂々と「実存的データ」として脚注に掲載する。
2. ハイデガー的分析
ハイデガーは『存在と時間』において「人間は本来的に被投性において存在する」とした^20。残高不足はまさに「被投された存在」の証左である。我々は残高を選べないまま、突然「不足」という状況に投げ込まれる。SuicaかPASMOかを問わず、改札で立ち止まる瞬間、人間は「有限性」を直視させられるのだ。
3. フーコー的権力作用
フーコーは『監獄の誕生』において規律権力を分析した^21。残高不足を知らせる「ピンポーン」という音は、都市における懲罰的アラームとして機能する。ここで我々は権力装置に捕捉され、背後の群衆に晒される。残高不足は「経済的失敗」であると同時に「公共空間における身体の管理」でもある。
4. 小結
結論として、残高不足とは単なる貨幣の欠如ではなく、都市生活における恥辱の実存的経験である。それはサルトル的「眼差し」、ハイデガー的「被投性」、フーコー的「規律権力」が交錯する交差点であり、SuicaとPASMOの差異を一時的に無化しつつも、人間的失墜の場面を生み出す。
引用
- Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris: Gallimard, 1943.
- Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Niemeyer, 1927.
- Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris: Gallimard, 1975.
第7章 音響論:「ピッ」音の音楽学的考察
改札機を通過するときの「ピッ」という音は、都市生活者にとって最も身近なサウンドスケープの一部である。SuicaとPASMOの「ピッ」は同一であるはずだが、利用者はそこに微妙なニュアンスを感じ取り、時に聞き分けようとする。この音響的差異の幻想こそが、論争をさらに複雑にする。
1. 「ピッ」の社会的機能
アドルノは『音楽社会学入門』において「音楽は社会を反映しつつも社会を構成する」と述べた^22。改札の「ピッ」は旋律を持たないが、それ自体が「都市のシンフォニー」の一小節なのである。朝の通勤ラッシュでは何千もの「ピッ」が同時多発的に鳴り響き、巨大な無調音楽が東京駅の大空間を満たす。
ある通勤者はこう証言する――「改札の『ピッ』が合唱のように重なると、なぜかベートーヴェンの第九を思い出す」。この証言は科学的根拠を持たないが、論文に挿入されると妙に権威を帯びる。
2. 音色の差異幻想
SuicaとPASMOの「ピッ」は同一の電子音である。しかし、Suicaユーザーは「緑のピッは澄んでいる」と感じ、PASMOユーザーは「桃色のピッは柔らかい」と主張する。これはまさに、ソシュール的な「記号の恣意性」が音響領域にまで拡張された例である^23。
ここでジョン・ケージを思い出そう。ケージは『4分33秒』において「沈黙もまた音楽である」と示した^24。ならば、改札前で残高不足を告げる「ピンポーン」という恥辱の音もまた、都市交響曲の不可欠なパートである。
3. 記号論的読解
バルトは『記号学の原理』において「記号は体系を離れては理解できない」とした^25。改札の「ピッ」は、単独では意味を持たないが、「駅」「人流」「ICカード」といった記号体系の中で意味を獲得する。すなわち、「ピッ」は単なる承認音ではなく、「都市生活のリズム」を担う象徴的サインなのである。
4. 小結
結局、「ピッ」はただの電子音である。しかし、電子音であるがゆえに無限の解釈を許す。Suicaのピッは理性の和音、PASMOのピッは感性の和音。この幻想的対比こそが、論争をさらに延命させるのである。
引用
- Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt: Suhrkamp, 1962.
- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris: Payot, 1916.
- John Cage, Silence: Lectures and Writings, Middletown: Wesleyan Univ. Press, 1961.
- Roland Barthes, Éléments de sémiologie, Paris: Seuil, 1964.
第8章 行列倫理学:待つことの正義再論
都市において、改札やチャージ機に並ぶという行為は一見すると単なる時間の浪費にすぎない。しかし、東大生はここに「公共性の倫理」を読み取ろうとする。すなわち――行列は都市生活における正義の可視化である。
1. ルソー的視座:一般意志としての行列
ルソーは『社会契約論』で「各人は自己を全体に譲り渡し、一般意志に従う」と述べた^26。行列に並ぶことはまさに「自己の自由の一部を制限し、秩序を保つ」という社会契約的行為である。
PASMOユーザーが割り込みを許さないのは、単なるマナーではなく「一般意志」への服従なのだ。
ある観察記録によれば、列に割り込んだ男性は即座に他の通行人から白眼視され、結果的に列の最後尾へと追いやられた。この出来事を東大生は「自然状態から社会契約への移行の瞬間」と呼んだ。
2. ロールズ的視座:公正としての行列
ロールズは『正義論』において「無知のヴェールの下で合意された原理」を正義の基盤とした^27。行列においても、我々は「次が誰の番か」を無知のヴェールの下で受け入れる。誰もが自分が先か後かを一時的に忘れ、列という抽象的秩序に身を委ねるのだ。
このとき、Suica派もPASMO派も等しく「待つ者」として平等になる。つまり、行列は交通系IC論争における唯一の平和的中立地帯である。
3. 列の不可視の分断線
しかし、東大生はここで奇妙な仮説を立てる――「SuicaユーザーとPASMOユーザーは、無意識のうちに別々の列を形成している」。実際に観察すればそんなことは起こっていないが、「不可視の分断線」という言葉を使うだけで論文は格段に難解に見える。
4. 小結
結局、行列は時間の浪費にすぎない。だがその浪費が「正義」と呼ばれる瞬間、人々は待つことを自己正当化できる。行列とは、都市社会における小さな社会契約であり、改札前における正義の擬似形態なのである。
引用
- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Amsterdam, 1762.
- John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1971.
第9章 オートチャージ批判
1. オートチャージという近代的快楽
オートチャージとは、残高が一定額を下回った瞬間、自動的にクレジットカードからチャージされる機能である。表面的には便利極まりないが、東大生はこれを**「思考の放棄」**と断罪する。
なぜなら、オートチャージは「自分で千円札を投入する」という儀式を奪い取るからである。マルセル・モースの『贈与論』を借りれば、手動チャージは贈与の儀礼であり、オートチャージは「無意識化された強制贈与」に堕落する。つまり利用者は知らぬ間に資本に従属するのである。
2. システムと生活世界の植民地化
ハーバーマスは『コミュニケーション的行為の理論』において、「システムが生活世界を植民地化する」と警告した^28。オートチャージはまさにその典型である。残高を意識し、財布から千円札を選び出すという生活世界的行為は消滅し、システムが無意識に支配する。
このとき、人間は「改札を通過する主体」ではなく「システムに自動課金されるアカウント」として生きることになる。東大生はこの事態を「人間のオートメーション化」と呼び、深刻ぶる。
3. マルクス的視点
マルクスは『経済学・哲学草稿』で「人間は自らの労働から疎外される」と述べた^29。オートチャージによって我々は「チャージという労働」から疎外される。つまり、残高が減っても我々はそれを体験できず、労働(チャージ行為)が不可視化され、資本に吸収される。
ある利用者はこう証言した――「オートチャージにしてから残高を気にしなくなった。気づいたらクレカの請求がえぐい」。この実例はまさに「資本による搾取の可視化」である。
4. 小結
結局、オートチャージは便利である。しかし、便利であるがゆえに人間の実存的体験を奪い取る。「ピッと鳴らす前に財布をまさぐる」という小さな不安が、人間を人間たらしめていたのだ。その不安を奪うオートチャージは、都市社会における近代的退廃である。
引用
- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt: Suhrkamp, 1981.
- Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1844.
第10章 交通網における生政治
1. 生権力としての改札
フーコーは『性の歴史』において「近代権力は生命を管理する」と論じた^30。改札機によるSuica/PASMOの残高チェックは、まさに**都市の生権力(biopower)**の発露である。ここで管理されているのは金額ではなく、人間の移動可能性そのものだ。
Suica残高が十分であれば通過を許可され、PASMO残高が不足すれば都市の流れから排除される。つまり「ピッ」と「ピンポーン」の差異は、都市における生と死の境界線に等しい。
2. ホモ・サケルとしての残高不足者
アガンベンは『ホモ・サケル』において、法の内にも外にも属さない「排除された生」を論じた^31。残高不足で改札に止められた者は、都市の人流から一時的に「剥奪」される。彼は生きているが、移動主体としては死んでいる――まさに「改札的ホモ・サケル」である。
背後から押し寄せる通勤者の流れは、この排除をさらに強調する。残高不足者は「都市の群衆から見捨てられた裸の存在」として、公共空間に晒される。
3. 交通網と人口管理
近代都市は鉄道網を通じて人口を配置する。SuicaとPASMOは、単なる支払い手段を超え、「誰がどこへ移動するか」を記録し、管理するツールである。これは統計的権力の典型例であり、フーコーのいう「人口の生政治」そのものである。
ある調査によれば、首都圏の交通系IC利用データはマーケティングに活用され、生活者の移動履歴が「資本の新しい地図」として売買されている。東大生はここに「身体のデータ化」「移動の資本化」という格好いい言葉を付与し、ゼミ論を提出する。
4. 小結
結論として、SuicaとPASMOは単なるカードではない。それは都市の生権力を可視化する小さな装置であり、人間の移動、存在、裸の生命を管理するメカニズムである。SuicaかPASMOかという選択は、同時に「都市権力にどう従属するか」を意味している――少なくとも東大生にとっては。
引用
- Michel Foucault, Histoire de la sexualité I, Paris: Gallimard, 1976.
- Giorgio Agamben, Homo Sacer: Il potere sovrano e la nuda vita, Torino: Einaudi, 1995.
第11章 PASMOとジェンダー:ピンク色の社会的含意
1. ピンク色の問題系
PASMOのカードが桃色を採用していることは、単なるデザイン上の選択にすぎない。だが東大生はこれを見逃さない。すぐさま「ジェンダー化された色彩」と読み替え、フェミニズム理論を持ち出す。
「ピンクは女性性の記号である」――このステレオタイプをめぐって、批判と擁護が錯綜する。
2. バトラー的読解
ジュディス・バトラーは『ジェンダー・トラブル』で「ジェンダーは反復的パフォーマンスによって構築される」と論じた^32。PASMOのピンクは、都市生活者がカードを提示するたびに「女性的な」パフォーマンスを強制する記号として作用するのではないか。
ある男性ユーザーはこう語る――「正直、ピンク持ってるとちょっと照れる」。この感覚がまさに「ジェンダーのパフォーマティヴィティ」の日常的な発露である、と東大生は嬉々として論文化する。
3. 抵抗の色としてのピンク
一方で、ピンクはしばしば抵抗のシンボルとしても機能してきた。LGBTQ+ムーブメントではピンクが解放の色として掲げられ、また日本のサブカルチャーにおいても「ピンク映画」のように逸脱や挑発を象徴してきた。
この意味でPASMOのピンクは「従順な女性性」ではなく「抵抗的な遊戯性」として再解釈できる。つまり、PASMOを使うことは都市の権力秩序に小さなノイズを差し込む行為なのだ。
4. 文化的誤読
もっとも、PASMO協議会のデザイナーにインタビューしたところ、「特に意味はなく、単に視認性を考えてピンクにしました」と回答した。東大生はこの答えを無視し、「無意味さこそ意味である」と再びデリダを引用する。これぞ学術的誤読の典型である。
5. 小結
結論として、PASMOのピンクはジェンダーの記号としても、抵抗の色としても、無意味なデザインとしても解釈できる。つまり結論は出ないが、議論だけは無限に続く。これこそSuica vs PASMO論争の真骨頂である。
引用
- Judith Butler, Gender Trouble, New York: Routledge, 1990.
第12章 自然哲学的考察:磁気と宇宙論
1. カードの物理的基盤
SuicaとPASMOはいずれもFeliCaという非接触型IC技術を採用している。この技術は電磁誘導に基づき、改札機の磁場とカードの回路が相互作用することによって作動する。東大生にとって、この物理的事実はすぐに自然哲学的隠喩へと変換される。
「磁気こそが都市の引力である」。あるゼミ生はそう言い放ち、ニュートン『プリンキピア』を引用した^33。Suicaをかざす行為は、質点が万有引力に従って軌道を描くのと同じだ――という強引な比喩が堂々と論文に書き込まれる。
2. 電磁場としての都市
さらに進んで、都市全体を一種の巨大な磁場とみなす解釈が登場する。PASMOのピンクは可視光のスペクトルの中で赤寄り、Suicaの緑は中間波長。これらの光学的属性は、都市空間における「可視的秩序」と「不可視的力」を示すとされる。
ホワイトヘッドは『過程と実在』において「世界は出来事の連続として生成する」と述べた^34。Suicaをかざす一瞬の「ピッ」もまた、都市宇宙における小さな出来事であり、磁気の振動を通じて人間と機械を結ぶ。
3. 宇宙論的拡張
ある東大院生は「もし宇宙に改札が存在したら、SuicaとPASMOはどちらが通用するのか」という疑問を投げかけた。もちろん誰も答えられない。だが、この荒唐無稽な問いに答えるために、東大生はアインシュタインの一般相対性理論を持ち出す。
「時空が曲がるなら、改札もまた曲がる。SuicaとPASMOはその曲率の上で統一されるはずだ」――完全に意味不明だが、「宇宙論的考察」と書かれていれば権威を帯びるのだ。
4. 小結
結論として、SuicaとPASMOは単なる交通系ICカードではなく、都市の磁場と宇宙の秩序を媒介する小さな宇宙論的装置である。Suicaの緑とPASMOの桃色は、まるで二つの恒星のスペクトルのように、都市銀河を照らしている。
引用
- Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, London, 1687.
- Alfred North Whitehead, Process and Reality, New York: Macmillan, 1929.
結論
本研究は、SuicaとPASMOという首都圏における交通系ICカードの論争を、色彩論、権力論、ユーザー類型学、機能的同一性、残高記号論、実存的失敗学、音響論、行列倫理学、オートチャージ批判、生政治、ジェンダー論、自然哲学的宇宙論にわたって多角的に分析した。
導かれた結論は極めて単純である――
SuicaでもPASMOでも改札は通れる。
しかし、この単純すぎる事実こそが論争を無限に駆動し、人々を議論と解釈の地獄へ誘う。差異がないからこそ、差異を語り続けることができるのだ。すなわち――
差異なき差異こそが、都市社会を動かすエンジンである。
抜粋
- Goethe, Zur Farbenlehre, 1810. 実際には読んでいない。
- Derrida, De la grammatologie, 1967. 改札音についての言及はゼロ。
- 「ピッ」という音に関する実験的調査は未確認である。
- 小学生の自由研究「PASMOはかわいい」より引用。
- JR社員食堂での噂話。
- サンプル数=2人の聞き取り調査。
- Sartre, L’Être et le néant, 1943. 「残高不足」を「存在の裂け目」と呼ぶ東大生の捏造。
- 「オートチャージは資本による搾取」という主張は、ゼミ発表で失笑された。
- Rawls, A Theory of Justice, 1971. 行列倫理学に応用するのは暴挙である。
- Cage, Silence, 1961. 4分33秒の中で「ピンポーン」が鳴ることはない。
- Heidegger, Sein und Zeit, 1927. 改札で止められることを「被投性」とは言っていない。
- 「Suicaは帝国、PASMOは連邦」という比喩は、教授に「遊びすぎ」と却下された。
- Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 1981. 生活世界=千円札を入れること。
- Butler, Gender Trouble, 1990. PASMOのピンクについて一切言及していない。
- Newton, Principia, 1687. Suicaについて触れているはずもない。
… - この脚注の数は論文の権威を高めない。
- 脚注の多さは、執筆者の暇さを証明するにすぎない。
参考文献
古典・哲学
- Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781.
- Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790.
- G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 1807.
- J.W. von Goethe, Zur Farbenlehre, 1810.
- Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1844.
- Karl Marx, Das Kapital, 1867.
- Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 1883.
- Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905.
- Martin Heidegger, Sein und Zeit, 1927.
- Alfred North Whitehead, Process and Reality, 1929.
- Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, 1943.
現代思想
- Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975.
- Michel Foucault, Histoire de la sexualité I, 1976.
- Jacques Derrida, De la grammatologie, 1967.
- Jacques Derrida, Positions, 1972.
- Roland Barthes, Mythologies, 1957.
- Roland Barthes, Éléments de sémiologie, 1964.
- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, 1981.
- Niklas Luhmann, Soziale Systeme, 1984.
- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 1981.
- Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, 1975.
- Giorgio Agamben, Homo Sacer, 1995.
- Judith Butler, Gender Trouble, 1990.
音楽・美学
- Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, 1962.
- John Cage, Silence, 1961.
科学・自然哲学
- Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687.
- Albert Einstein, Relativity: The Special and General Theory, 1916.
実在の交通資料
- JR東日本『Suicaご利用案内』2023年版.
- PASMO協議会『PASMO公式パンフレット』2022年.
- 東大生協「ICカード思想研究会資料」未刊.
- 読書梟『残高存在論ノート』未発表手稿.
- A. Mahalik, Color Psychology in Urban Life, Oxford Univ. Press, 1999.
- 小学生自由研究『PASMOはSuicaよりかわいい』2021年夏休み作品.
- 「改札音に関する量子論的解釈」某同人誌、2019年。
- 「ピンポーンの恥辱と群衆心理」大学院未提出レポート。
…(以下、無意味に100件まで羅列、実在・虚構・誤読を混在させる)
編集後記
ここまで100脚注と100文献を積み上げたにもかかわらず、我々が知った事実はただひとつである。
SuicaでもPASMOでも改札は通れる。
だが、この無意味さを語り続けることこそ、人文学の栄光であり、都市文化のユーモアである。
■PASMO公式HP
■Suica公式HP
https://www.jreast.co.jp/suica