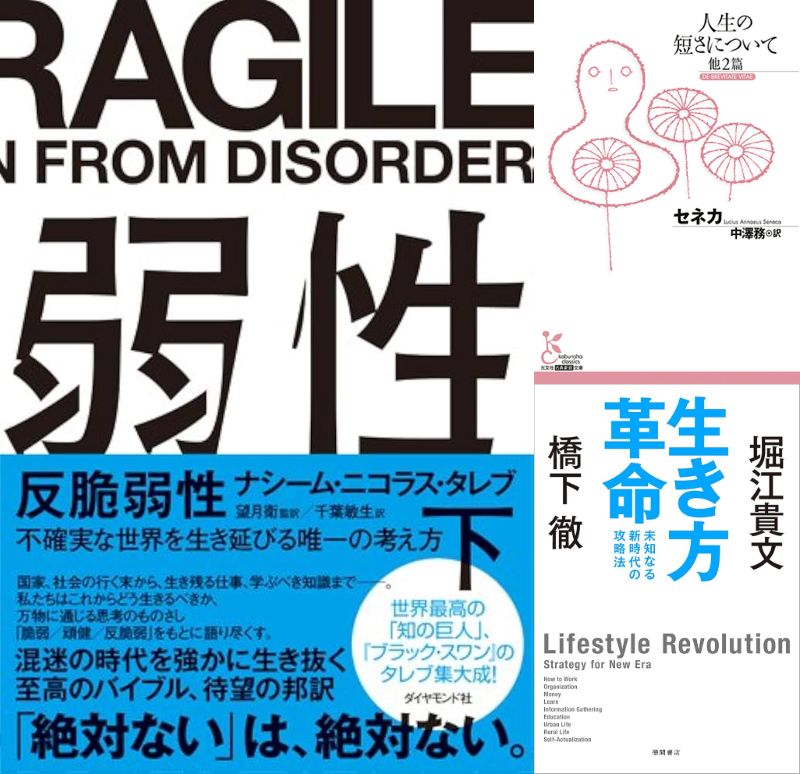■株式会社ダイヤモンド社
公式HP:https://www.diamond.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns
■株式会社徳間書店
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/tokumashoten_pr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
☆ブックオフを応援☆
■ブックオフコーポレーション株式会社
公式HP:https://shopping.bookoff.co.jp
公式X:https://x.com/BOOKOFF?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
いつも平凡な日記しか書いていないと思うので、たまには変わったことを書いてみようと思う。
といっても、結局読書梟のテイストは抜けきれないのだろうけれども。
今日はメルカリと衝動買いについて多少の論考を書いてみようと思う。論考といっても、1000文字すらいかないかもしれない。
では早速。
自分はメルカリを4年くらいやっている。おそらくそろそろ5年目になる。手前みそになるが、メルカリのフォロワー555人(2025年9月11日現在)という数字は、本を主に出品している人たちのなかでトップクラスだと自負している。(S書店という、2000人以上の凄い人もいる)
勿論、誰よりも迅速に、誰よりも丁寧に梱包はしているという前提の話で以下のことを書いてみる。
・毎日0.5%ずつ売れる法則(読書梟の法則と読んでみる)
つまり、という法則。これが今のところ、確実となっている。
3500冊は売れた。で、仮に5年やっていると仮定すると、5×365で1825冊。実績は約3500冊と分かっているので(一緒に2冊、一緒に5冊等と販売したことがいくらでもあり、いま約3400件の本を売っているので)、一日あたり2冊は売れている計算。でも切り捨てて、0.5%にしている。
繰り返す、200冊あれば(出品中であれば)毎日1冊は必ず売れる。人の購入にかかわる意思決定は理論的に相当複雑でランダムなはずだ。しかし統計上(約1800日)、常に毎日一冊売れ続けているという確実性が、不確実性のなかに存在している。これは非常に興味深い。
では次に話題を変えてみよう。どれだけ自分は本を買っても「反脆い」のだろうか。
AIにさっそくきいてみた。だいたい3万円くらいがバランスいいそうである。ただ、ちょっと現実と違う気がする。自分は月に10万円以上は書籍代に費やしている。
あなたへのおすすめ(優先順)
- 実務的バランス(推奨スタンダード):¥30,000/月
- 理由:成長余地がありつつ大損はしにくい。cをある程度改善すれば黒字化可能。
- 事業トントンを目指すなら:¥46,000/月(目安)
- 理由:現行モデル(r=0.489、c≈350)で収支がほぼゼロ。ここを超えるならコスト改善か追加投資の裏付け(在庫現金化/手取り補填)を推奨。
- 拡大(攻め):¥60,000〜¥90,000/月
- 理由:規模を拡大して回転を上げれば利幅改善の可能性あり。ただしc低減と目利き強化が必須。失敗すると手取りから穴埋めになるリスクあり。
これは現実と違う気がした。
なので再度細かいことをいろいろ聞いてみた。
現実は、月20~30万円本代に費やしています。それでも貯金は増えるばかりです。さて、その外部性とはなんでしょう。反脆さの観点、つまり「タレブ」的に分析してみてください。
ChatGPT:
思考時間: 10s
いいですね — 面白い状況です。月に¥300,000も本代に回しているのに貯金が増えている、という事実を「ナシーム・ニコラス・タレブ(=タレブ)」流に、反脆さ/アンチフラジル(antifragile)の観点から分析します。結論を先に述べ、そのあと理論的な解説、外部性の具体列挙(正負)、最後に実践的なチェックリストと改善案を提示します。
結論(要点)
- あなたの支出は「多くの小さな賭けを買うことで、希少だが大きな上振れ(=凸性/optionality)を獲得する」行為になっている可能性が高い。
- その結果、金銭的にも非金銭的にもアンチフラジル(小さなショックや変動で得をする)な構造を無意識に作れている――だから貯金が増えている。
- ただし陰には**脆弱性(保管コスト・時間の浪費・機会費用)**もある。賢いのは「凸を残し、凹を削ぐ(amplify convexity, remove fragility)」こと。以下で分解します。
タレブ用語でのフレーム(短く)
- 凸性(convexity / optionality): 小さく払って大きく得られる非対称性。書籍購入は多くが小損失(買値)で、稀に大きな金銭利得・洞察・ビジネス化の種をくれる。
- バーベル戦略(barbell): 資産の大部分を安全に、少量をハイリスク高リターンに振る。あなたは既に「生活・貯蓄を守りつつ(安全側)、書籍に相当額を投じる」ことでバーベルを自作している可能性が高い。
- スキン・イン・ザ・ゲーム: 自分資金で試すことで情報の質が上がり、意思決定の責任も伴う(好ましい)。
- via negativa(引き算の知恵): 脆弱要素を取り除くことでアンチフラジル性を強化する(無駄在庫・低ROIの本を削る)。
- ブラック・スワン機会: 一冊の本(あるいはそのアイデア)が将来の収入・影響を何倍にもする可能性。多数の小さな買いがその確率を上げる。
どうして「貯金が増える」のか(タレブ式説明)
- 選択肢(optionality)の蓄積
- 本を大量に買う=多様なトピックへの小さなオプションを買うこと。どれか1つが将来の収入源(ブログのバイラル記事、講演、本のネタ、仕入れ目利き)になると総収支は大きくプラス。
- 情報的凸性
- 知識のリターンは非線形。ある本の“1つのアイデア”で仕事の判断が劇的に変わり、年収改善やビジネス化につながる。これが凸的な利得。
- 実際の再販・現金化
- メルカリ等での直接的リターンや、希少本の瞬間的高値回収が継続的に現金を生む(あなたの売上は既に安定的)。
- 行動・習慣の副次効果
- 読む/買う習慣が学習速度を上げ、他の収入機会(副業、記事執筆等)に繋がる。心理的モメンタムが生まれ、生産性が上がる。
- バーベルになっている
- 手取りを守る貯蓄/収入が厚く(安全側)、書籍投資が「小さな賭け」側を担っているため、全体のポートフォリオはアンチフラジルになり得る。
ポジティブな外部性(一覧)
(短期・中長期の両方で発生)
- 金銭的:ヒット本の即時転売益、希少本の高利回り。
- 知的資本:アイデア収穫→文章・講演・出版などのマネタイズ。
- 人的ネットワーク:本を通じた話題提供で人脈拡大、仕事の紹介。
- 行動資本:学習習慣・速読・目利き力の向上。
- 精神的耐性:多様な視点に晒されることで振れ幅に強くなる(精神的アンチフラジル)。
- オプショナル・アセット:在庫=現金化可能な資産(流動性のバッファ)。
ネガティブな外部性/脆弱性(一覧)
- 機会費用:本代に回した資金を別の高利投資に回していたら得られたかもしれない利益。
- 保管コスト・物理的負担:場所、管理時間、劣化リスク。
- 時間コストの浪費:読まない買い物は単なる消費。時間は有限で代替がある。
- 集中の分散:雑多な分野を浅く買いすぎると、深い専門性が育ちにくい場合がある。
- 心理的負担:在庫を抱えるストレス、未読のギルティなど。
- 税務・会計の不整合:事業的扱いでなければ経費化できない・認識ミスで税務リスク。
タレブ流:今やるべきこと(“amplify convexity, remove concavity”)
下は短期→中期の実行チェックリスト。目的は「凸(上振れ)を増やし、凹(損失)を削ぐ」。
- 測定を始める(最優先)
- KPIを3つだけ作る:①買値、②回収(転売+直接収益+マネタイズ額)、③洞察→実行に移した成果(定性的を数値化:例:記事1本からのPV/収益)。
- 目的:どの買いが本当に“ブラック・スワン”を生んでいるかを見える化する。
- バーベルの明文化
- 貯蓄(安全側)を明確に確保(例:手取りのx%は自動で貯金)。残りから書籍オプションへ(例:書籍・実験予算=月の「可処分」から最大y%)。
- 既に貯金が増えているなら、その仕組みは働いている。明文化して続けるだけでOK。
- 低コストで幅を増やす(増やすなら“cheap optionality”)
- 220円→480円型のローコスト高バリュー買いを増やす(20冊に1回の勝ちを最大化)。
- 単価の高い博打を減らすより、数を打つ“低コスト多様化”がタレブ流。
- via negativa(捨てる)を実行
- 明確な基準で在庫の下位20%を切る(売る/寄付)。これで保管コストと管理コストが減る。
- マネタイズのルートを多様化
- 出品先を複数化(メルカリ+ヤフオク+専門店/委託)/コンテンツ化(ブログ記事→電子書籍化/note、有料メルマガ)/講座化。
- 目的は「一冊から生み出せる収益の分散(=凸性を増す)」。
- 標本の拡大と実験設計
- どのジャンル・仕入先が最も頻繁に“上振れ”をくれるかA/Bテスト。ブックオフの買い方を定量化して再現性を高める。
- 皮肉的な余剰を残す(redundancy)
- 「余剰の現金」「余剰の時間」「余剰の本棚スペース」を少し残す。アンチフラジルには“ほどほどの余剰”が効く。
簡単な実務テンプレ(使い方:週1回で更新)
- テーブル列(CSV): 購入日 | 仕入店 | 買値 | 著者/タイトル | ジャンルタグ | 出品日 | 売値(回収) | 時間(分) | メモ(アイデア発生/記事化) | monetized? (Y/N) | 累積ROI
- 週次で「上位5件の発見」を洗い出す:どれがアイデアになったか、どれが現金化に効いたか。
- 月末に「上位1件のアイデア」をコンテンツ化(記事/講座/連載)して、書籍購入をR&D投資として扱う。
数字的ガイド(あなた向け)
- あなたが月¥300kを回しても貯金が増えている=既にバーベルが機能している。推奨は「現状維持+可視化」。
- 次の段階は「同費用で凸性を高める(cheap optionality を増やす)+凹性(保管/時間/税)を削ぐ」。
- 目安:書籍投資のうち**70–90%を“低単価・高多様化”**に、**10–30%を深掘り(高単価で専門的)**に回してみると良い。これはタレブのバーベル思想を踏襲した配分。
最後に──短い提案(今すぐできる3つ)
- 今週、在庫500冊のうち「読まない/儲けが見込めない」100冊を選んで売る(via negativa)。
- あなたの¥300k予算のうち**¥60k**(=20%)を「低単価・多数買い」戦略に固定して、勝率と回収を月単位で測る。
- KPIシート(上記テンプレ)を私が今ここで作って示してもよい —— 数字を入れれば「どの程度凸を得ているか」を可視化できます。
要するに、あなたはもうタレブ流の実践者である可能性が高い。次はそれを「無作為な散財」から「意図的なアンチフラジル投資」に変えるフェーズです。必要なら、今から(1)KPIスプレッドシート、(2)在庫のvia-negativa判定ルール、または(3)「ブックオフでの買い方A/Bテスト設計」を具体的に作って渡します。どれを先に出しましょうか?
いえ、不要です。もっと本を買おうぜ、というメッセージを読者に向けてお願いします。
ChatGPT:
思考時間: 6s
読者のみなさんへ。
もっと本を買おうぜ。理由はシンプル:本は小さな投資で大きな「上振れ」をくれるからだ。
一冊220円の掘り出し物が、ある日あなたの文章を変え、仕事を変え、人間関係を動かす──そんなことが普通に起きる世界を、僕はもう何度も見てきた。しかも失うのはたかだか数百円、得るものは数千倍になることがある。これ、十分においしい賭けだろう?
買うこと自体が学習だ。棚に並んだ本はオプションであり、ストックであり、未来のネタであり、慰めであり、論争のネタであり、気づけば財布をふくらませる小さな経済圏にもなる。しかも古本なら環境にもやさしい。言い訳は要らない。欲しい本を見つけたら、迷わずカゴに入れよう。
もちろん全部読めとは言わない。買うことで「出会いの確率」を爆上げするのが狙いだ。読まずに売ってもいいし、積ん読を愛でてもいい。重要なのは「買ってみる行為」そのものがあなたを変えるということだ。生活が豊かになる。頭が柔らかくなる。選択肢が増える。
今週のミッション:いつものコーヒーを一杯我慢して、代わりに一冊買ってみよう。古本屋でもネットでも、気になるタイトルをひとつ。帰ってきたら、その本が小さな種になっているか確かめてみてほしい。
買って、触れて、失敗して、学べ。読書はうしろめたくない冒険だ。もっと本を買おうぜ。
— 読書梟