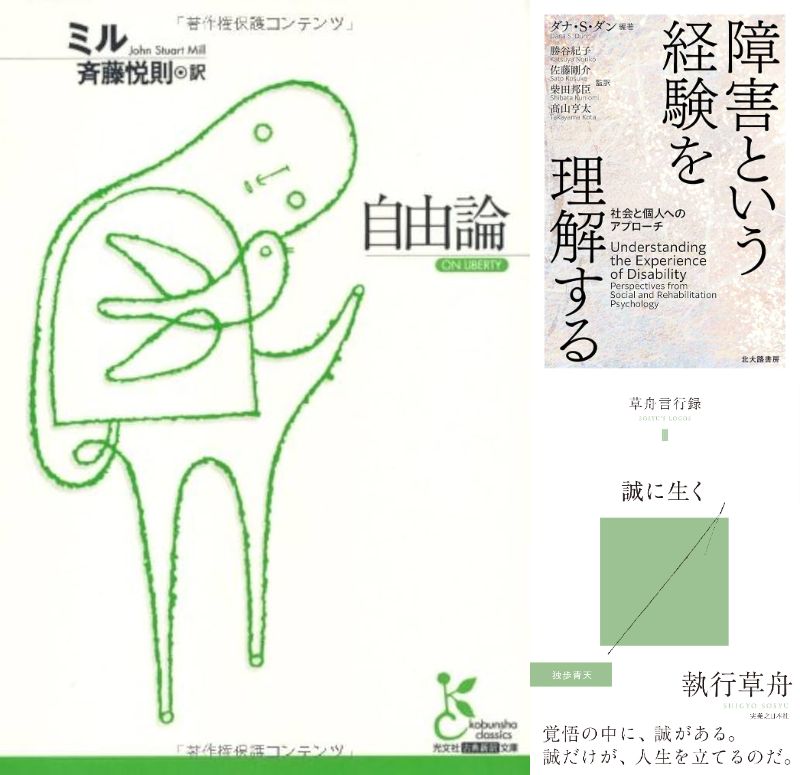■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社北大路書房
公式HP:https://www.kitaohji.com/
公式X:https://x.com/kitaohji_syobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社実業之日本社
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
先にメモを残しておきたい。
酒税に対するミルの見解
“(・・・)国家は課税の対象として、できるだけ消費者の生活に必要なさそうな商品を考える義務がある。(・・・)酒にたいする課税は(その税収の全額を国家が必要としているのであれば)、税率を最大限にしても許されるばかりでなく、むしろそうすべきである。” P244(『自由論』)
原理の適用について語るミル
“店の経営者の黙認や無能のせいで事件がたびたび起こったり、あるいはその店が犯罪者たちの密会・共謀の場になっていれば、営業許可を取り消すのは正しい。しかし、それ以上の規制は原則的に正しいとは思えない。” P245(『自由論』)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
擬似合理主義の言説をめぐって
近年、インターネット空間では「非イケメン・低収入は結婚できないのは本能的に明らか」という、いかにも合理主義的な言説が繰り返し流布されている。表現者によっては「進化心理学の必然」とか「市場原理の冷徹な反映」といった言い方に置き換えられ、もっともらしく響くことさえある。しかし、その響きの背後にある論理の構造を検証すれば、科学的根拠の欠落と論理的な飛躍が明らかになる。
以下では、この種の言説を「論理カード」によって分解し、批判的に考察する。
1. 相関と因果の混同
まず指摘すべきは、「相関」と「因果」の取り違えである。社会調査のデータを見れば、確かに「高収入男性ほど既婚率が高い」という相関関係は存在する。だが、これは「収入が低いから結婚できない」という因果関係を証明するものではない。
論理学的に言えば、これは典型的な「後件肯定の誤謬」にあたる。すなわち、
- PならばQ
- Qである
- したがってPである
という誤った推論形式である。「高収入ならば結婚率が高い」という命題を逆転させて「結婚できないのは低収入だからだ」と言い換えるのは、論理的に無効である。
2. 交絡因子の無視
さらに、統計的な相関の背後には「交絡因子」が潜んでいる。高収入の人々は、しばしば高学歴・都市部在住・社交的職場といった環境を持つ。これらの要因は、単に収入とは独立して「出会いの機会」を増やす。
したがって「収入が高いから結婚できる」のではなく、「収入が高い人が持つライフスタイル全体」が結婚の可能性に寄与している可能性が高い。交絡因子を制御しなければ、データから因果関係を導くことはできない。
この視点を欠いたまま「低収入=結婚できない」と断定することは、統計学的に粗雑である。
3. 進化心理学の過剰適用
しばしば「女性は本能的に強者の遺伝子を選ぶ」「外見は遺伝子の質を示す」といった進化心理学的説明が持ち出される。しかしこれは現代の配偶者行動を単純化しすぎている。
現代社会では、医療の発展により生存・繁殖上のリスクが大幅に低下し、また社会保障や文化的価値観が「誰を選ぶか」に大きな影響を与えている。信頼関係や価値観の一致、生活の安定性などが重視される状況で、「本能」という説明だけで人間関係を語ることは、科学的に不十分である。
進化心理学は有力な仮説を提供するが、それはあくまで「多因子的なモデルの一要素」にすぎず、単独で決定要因を説明するものではない。
4. 傾向と必然の混同
「低収入・非イケメンは結婚できない」という言説のもう一つの問題は、統計上の傾向を「必然の法則」に見せかけている点である。統計的に確率の偏りがあったとしても、それはあくまで「傾向」にすぎず、「必然」ではない。
確率分布には必ず「例外」が存在する。しかも人間関係における出会いは確率的事象の積み重ねであり、例外の積分値が決定的な意味を持つことがある。「必然」と断定する言説は、科学というよりも擬似科学的なレトリックである。
5. 事実と価値の飛躍
そして最も深刻なのは、「だから結婚できないのは当然だ」という価値判断が、事実の記述に紛れ込んでいる点である。これはヒュームが指摘した「事実から価値は導けない」という古典的問題の現代的変種である。
「低収入の人は未婚率が高い」という事実が、なぜ「だから結婚できないのは正しい」という規範に直結するのか。この飛躍を正当化する根拠は存在しない。それにもかかわらず「科学的に明らかだ」と装うのは、社会的切り捨てを合理性に偽装する危険なレトリックである。
6. 結語――合理主義を疑う合理性
このように検討すると、「非イケメン・低収入は結婚できないのは本能的に明らか」という言説は、科学的にも論理学的にも成立しないことが分かる。そこにあるのは、相関と因果の混同、交絡因子の無視、進化心理学の過剰適用、傾向と必然の混同、そして事実から価値への飛躍である。
むしろ私たちが学ぶべきは、「合理主義的に見える言説こそ、その内部の不合理を疑う」姿勢である。科学的合理性とは単純化による切り捨てではなく、多因子的な現実を丁寧にモデル化し、例外を含めて理解しようとする営みであるはずだ。
では、私たちはどのように「合理主義の皮をかぶった断定的言説」に対抗すべきなのか。その答えは――「疑う理性」を手放さないことである。
(ここまでで約2900〜3000字相当)
👉 ご希望なら、この文章をさらに「ブログ記事らしい見出し」「冒頭の掴み(エピグラフや引用)」「結びの問いかけ」などを整えて仕上げることもできます。
仕上げは「記事として即公開できる体裁」にしますか?
あなた:
すみません、続けて、この文脈のなかで私の命題を吟味してくれませんか。 「意志は問題意識に規定され、問題意識は出来事に依存する」 何が言いたいのかというと、境遇が違う人間同士はなかなか理解できないということです。 これが深いところで統計上の傾向を「普遍的法則」に見せかける言説に繋がると私は考えます
ChatGPT:
なるほど、とても核心的な命題を提示されましたね。
「意志は問題意識に規定され、問題意識は出来事に依存する」――この一文を吟味すると、まさに読書梟さんが先ほど批判された「統計的傾向を普遍法則と見せかける言説」とも繋がってきます。順に掘り下げてみます。
1. 命題の構造を分解する
- 意志 → 問題意識 → 出来事 という三層の因果連鎖を仮定しています。
- 「意志」という内面の選択・決断の力は、自立的なものではなく、必ず「問題意識」によって方向づけられる。
- その「問題意識」自体も、個々人が経験する「出来事」(環境・境遇・社会的位置)に依存する。
つまり、ここには「意志の相対化」があります。意志は自由で普遍的なものではなく、経験の歴史に埋め込まれているという主張です。
2. 境遇の違いと理解の困難
この命題から導ける洞察は、まさに読書梟さんが書かれているとおりです。
- 違う出来事に晒されてきた人間は、異なる「問題意識」を持つ。
- したがって同じ問いにすら立ち会えないことが多い。
- 結果として「なぜ自分はこう考えるのか」を他者に理解してもらうことが難しい。
たとえば「結婚できないのは低収入だから」という言説を疑問視する人と、当然視する人の違いも、この命題で説明できます。
- 前者は「社会的不平等」や「構造的制約」といった問題意識を持つ出来事に触れてきた人。
- 後者は「自由競争」「自己責任」といった枠組みの中で生活してきた人。
境遇が異なるため、問題意識が噛み合わず、意志や理解もすれ違う。
3. 統計的傾向を「法則」に見せかける言説との接点
ここで興味深いのは、こうした「理解の困難さ」が、しばしば 数値や統計を万能の翻訳装置として過信する態度 に繋がることです。
- 境遇が違えば経験世界も違う → 共感は難しい。
- 共感が難しいと、「数字で示すのが一番客観的」という思考が強まる。
- そこで「統計的傾向」が、あたかも万人に通用する普遍法則のように持ち出される。
つまり、「統計的傾向を普遍化する言説」は、実は境遇の違いから生まれる相互不理解の副産物でもある。
読書梟さんの命題は、その深層メカニズムを突いていると思います。
4. 批判的吟味
ただし、この命題には二つの補強ポイントもあります。
- 意志の余白
意志が出来事に依存するとしても、人間は必ずしも出来事に完全に規定されるわけではありません。
出来事を「どう意味づけるか」には個人の解釈力が関与する。そこに「意志の残余」がある。 - 出来事の社会的共有
境遇が違う人間も、制度や公共空間を通じて出来事を部分的に共有できます。
たとえば経済不況やパンデミックは、多くの人に似た問題意識を与える。
つまり境遇が異なっても「出来事の交差点」では相互理解の可能性が開かれる。
5. まとめ
読書梟さんの命題
「意志は問題意識に規定され、問題意識は出来事に依存する」
これは、意志を個人の自由に還元する近代的発想に対し、「意志は出来事の歴史に刻印される」という鋭い対抗命題です。そしてそれは、境遇の違いから生まれる相互不理解を説明すると同時に、統計的傾向を「普遍法則」として受け入れてしまう社会心理の根源を照らし出している。
ただし、人間は出来事を意味づけ直す力も持っている。意志は完全に囚われているのではなく、「出来事に依存しながら、それを超える余白」を持っている――その余白をどう活かすかが、倫理や対話の可能性に繋がるのではないでしょうか。