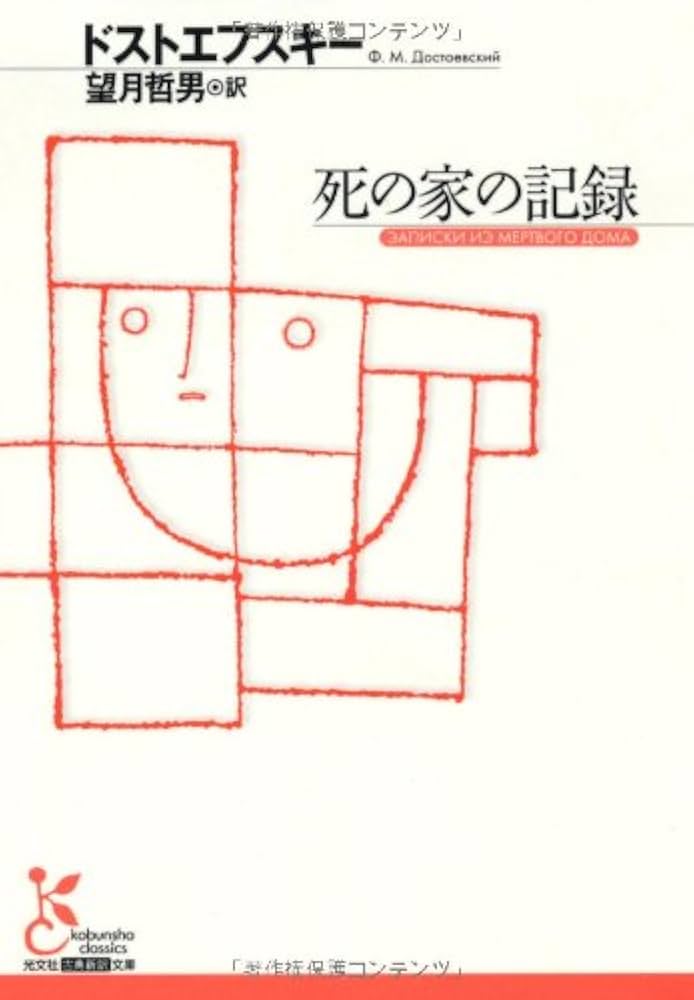■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
法が遅いとき、人間は何を信じるか。行政の返事を待つ時間は、ある種の「法的な無音」の中にいるようなものだ。
こちらが送った文面は整いすぎていて、条文の裏づけも倫理的配慮も揃っている。だからこそ、沈黙が余計に重く響く。誠実に向き合うことが、なぜこれほど報われないのか。正しくあることが、なぜここまで孤独を強いるのか。
法は遅い。
それは誰もが知っている。だが、法の遅さが「生身の人間の時間」をどれほど侵食するかを、体感する者は少ない。書面の一通、メールの一往復。その間に流れる日常は、たった数行の行政文書のために静止する。人は、正義を待つという名の無限待機に閉じ込められる。
私は、この遅延を倫理的にどう受け止めるべきかを考える。
怒りは簡単だ。制度批判も容易だ。しかし、「遅い正義」を許容することこそ、文明の最小単位ではないかという考えもまた、私の中で離れない。
もしもすべての正義が即時であったなら、それは法ではなく、感情の支配になる。法が遅いことには、暴力の抑制という側面がある。だがその遅さが、誠実な人を削っていくとき、私たちはどう生きるのか。
法における「誠実」は、手続きの中でしか確認されない。
だが、人間の誠実はもっと速い。
謝罪、連絡、理解、信頼――そうした倫理的反応の速度と、制度の速度がまったく噛み合わない。誠実は速すぎ、法は遅すぎる。その間に生まれる隙間こそ、現代人の「孤独の場所」なのだと思う。
私はその隙間で、言葉を使って自分を支えている。
たとえば「誠実」という言葉を、単なる道徳ではなく、制度を越える可能性として捉える。誠実さは、相手に届かなくても、形式にすり潰されても、それ自体で生き残る。返信が来なくても、沈黙に押しつぶされても、誠実はそのまま存在できる。
だが問題は――その「存在できる誠実」を、どう信じるかだ。
法が遅いとき、人間が失うのは「信頼の速度」である。
一度送った誠実な文書は、行政のフォルダのどこかに保留される。自分の言葉は宙づりになる。まるで、郵便ポストに手紙を入れた瞬間、その手紙がどこか別の宇宙に転送されてしまったかのような感覚だ。
それでも私は書く。なぜなら、書くことだけが「信じること」に近いからだ。
信じるとは、結果を期待しないことだと、最近思うようになった。
信じるとは、応答を前提としない誠実さを持つことだ。
行政が応答しないのは制度の問題だが、人間が応答しないのは、倫理の問題である。法は倫理を裁けない。だが、倫理は法を超えて存在できる。私がそれを信じられる限り、この沈黙の時間にも意味が生まれる。
ただ、正直に言えば、意味を見いだすのは容易ではない。
夜、メールの受信トレイを開いても、何も届いていない。
それを見た瞬間、心の奥底でなにかが崩れる音がする。
「誠実に生きること」と「生き延びること」は、いつも一致しない。誠実であるほど、社会は遅く見える。ルールに従うほど、孤独になる。
それでも、人はなぜ法を信じるのか。
おそらく、それは法の中に、わずかに“人間らしい余白”があるからだ。
条文の隙間、文書の遅延、制度の鈍さ――それらの中に、暴力を抑えるための「間(ま)」がある。
法が遅い社会とは、怒りが即座に正義になることを防ぐ社会でもある。
もし、すべての判断が感情によって即時に下されるなら、そこにはもう人間の尊厳は残らない。法の遅さは、信頼を壊すが、同時に復讐を止める。
では、人間は何を信じるべきか。
私はいま、行政の返信よりも、書いた文書の整合性を信じている。
感情ではなく、文体を信じる。
自分が書いた一文が、いかなる制度にも耐えうる透明さを持っているかどうかを信じる。
法は遅くても、言葉は瞬時に届く。届かないとしても、書くことは残る。
誠実が制度に届かないとき、誠実は書く者自身を救う。
それでも、心は時折折れそうになる。
「何のために正しくいようとしたのか」と自問する夜がある。
しかし、その問いを立てられること自体が、まだ倫理が死んでいない証拠でもある。
もし、すべてを諦めてしまえば、人間は制度と同化してしまう。
法の遅さを責めながらも、その遅さの中で自分を見つめ直す――その不安定さこそ、倫理の呼吸だ。
結局のところ、法が遅い社会で人間が信じるべきものは、「反応のない誠実」だと思う。
反応を前提にした誠実は、取引の一種にすぎない。
反応のない誠実は、無償の信頼のかたちであり、倫理の核である。
それは報われないかもしれないが、報われなさを通じて人間の dignitas(尊厳)を保つ。
行政が遅くても、倫理は先に進める。法が届かなくても、誠実は生き延びる。
いつか、返信が届くかもしれない。届かないかもしれない。
だが、そのどちらでも、人間は書き続ける。
法が遅いとき、私たちが信じるのは「返事ではなく、書いたという事実」だ。
沈黙のなかで書くこと。それが、唯一、遅さに耐える方法なのかもしれない。