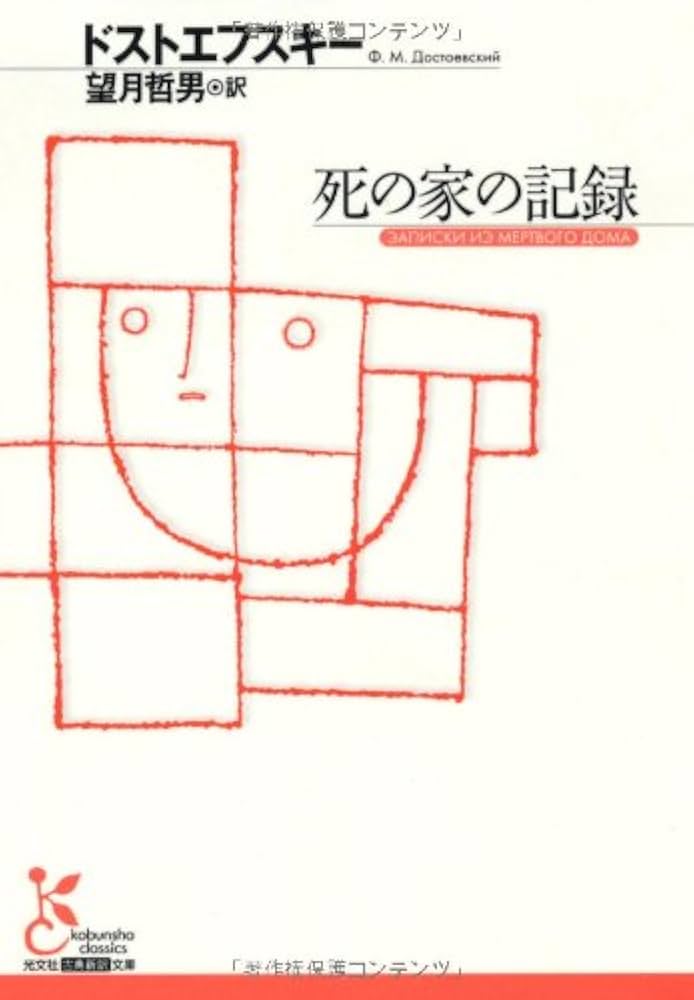■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
「文学は生活に役に立たない」。それを、私は腹を立てながらも認めるほかない。役に立たないのに読み継がれる。理解のために読んでいるはずなのに、読み終えればむしろ「わからなさ」が濃くなる。私は企画立案もできないし、リーダーにも向かない。けれど机に向かうと、わからないまま言葉を並べたくなる。この衝動はどこから来るのか。ブランショは「語り得ない」と言った。だが、その言い方がときに免罪符に見える。「語り得ない」と言い切るだけなら、単なる無知の開き直りになりかねない。語り得なさの中身をこそ問わなければならない。私はそこで足を止める。役に立たないのに読み継がれる。この意味不明な現象の正体を、腹立ちを燃料にして探りたい。
まず、同じ「役に立たない」でも、なぜ血液型診断の本はすぐ廃れ、文学は残るのか。血液型診断は、人を分類する即席の言語だ。A型は几帳面、O型はおおらか。これらは読むそばから安堵を与える。なぜなら、理解が即座に完結するからだ。読んだ瞬間に「わかったつもり」が手に入る。だが、その完結は読後と同時に死ぬ。再読の必要がない。次の場面で役に立つように見えて、実は「もう使われ尽くした言葉」の再配置にすぎない。ここでの快楽は消費の快楽だ。「わかった」に酔うが、翌朝には酔いが冷める。
文学はこれと逆方向に組まれている。文学は理解を未完のまま維持する。登場人物を理解したとたん、別の文脈が現れてその理解を裏切る。物語の核に手が届いた気がした瞬間、核は形を変える。言葉が対象を掌握したと思うと、言葉そのものが自壊を始める。文学は「わからなさを持続させる装置」であり、読書はその装置を回転させる手つきだ。だから再読が要請される。読むたびに新しい誤解が生まれ、誤解がまた理解のふりをして立ち上がり、次の段落で打ち砕かれる。ここで手に入るのは「わかったつもり」の安堵ではなく、わからなさと共存する筋力である。言い換えれば、文学の実用性は実用の枠組みを崩すことにある。「使える知識」を与えるのではなく、「使えない不安」を引き受けさせる。しかもこの不安は、すぐれた作品ほど読者の知的自尊心を破壊するやり方で訪れる。私が腹を立てるのは、まさにここに触れた兆候でもある。
では「語り得ない」は何を指すのか。語ることによって失われる何かが確かにある。体験をスローガンに置き換えるとき、その体験の温度は落ちる。比喩は現実を照らすが、同時に影を深くする。語りは世界を明確にするが、明確にする手つきがこぼれ落とす領域を必ず生む。語り得なさとは、その「こぼれ」を可視化する試みだ。つまり、文学がやっているのは沈黙の賛美ではない。沈黙を保つために語る、という逆説の運動である。沈黙にとどまることは簡単だ。けれど沈黙に触れたまま、なお言葉を選び直すのは難しい。文学の難しさはそこにある。語るほどに語り得なさが露出する。この露出のしかたが作品ごとに異なるため、読書は更新され続ける。だからこそ読み継がれる。語り得なさは「価値」か? 私にはわからない。ただ、価値の基準を決めてしまう機械に抗う抵抗としての効用はある。決定不能を保ち続けることで、他者への乱暴な短絡(きっと彼はA型だから、の類)を遅延させる。その遅延こそが倫理の最小単位ではないか。
「努力すれば報われる」とか「自分らしく生きよ」といった常套句も、理解の欲望を即席に満たす。これらの文句は、読者の不安をいったん眠らせる。だが眠った不安は別のかたちで身体のどこかに溜まる。常套句が効かなくなったとき、ひとはふたたび未知の前で裸になる。文学はその裸の状態に耐えるための反復練習である。役に立たないというより、役に立つことを急がない練習、と言った方がいい。急がないことは仕事の現場で最も嫌われる。しかし、急がないことが可能でない社会ほど、急がない場の希少性は高まる。文学が持続するのは、その希少性のためでもある。効率が上がれば上がるほど、効率では掬えない残りかすが濃くなる。文学はその残りかすの保存法だ。
さらに言えば、理解の欲望は二重だ。ひとは世界を理解したい。だが同時に「理解したい自分」を理解したい。文学は後者を露出させる。物語を追っているようで、いつのまにか自分の反応の癖を読まされている。誰に肩入れし、どこで退屈し、どの比喩に救われ、どの沈黙に苛立つか。読書とは、自分の理解欲求の輪郭線をなぞる作業である。だから読み継がれる。世界が変われば輪郭線も変わる。同じ作品が「別の私」を描き出すから、再読に意味が生まれる。血液型診断は読者の側を変数にしない。枠組みが先にあり、読者は分類の客体に過ぎない。文学は逆に、読者の側を変数化する。読み手が揺れるたびに、作品の相貌も揺れる。ここに反復の快楽が宿る。
私は、「わからない」という感情そのものが希少だと感じている。わからなさは不安であり、同時に自由の密度でもある。わからなさを抱えたまま言葉を選ぶとき、私は他者を一気に断定する権利をいったん手放す。断定する権利を手放すことは弱さかもしれないが、その弱さが関係を壊さずに保つための余白を作る。文学は余白の製造装置であり、余白があるからこそ生活は続行可能になる。役に立たないように見えて、生活の「続行可能性」を底で支える。この支えは、指で触れられないほど薄い。薄いが、薄さゆえに網の目のどこにでも入り込む。仕事の現場で私は役に立たない。しかし、役に立たないという自覚を抱えた者だけが開ける視野がある。完璧な要約や指標で覆い尽くされる前に、まだ名付けられていない違和感を拾う視野だ。文学はその違和感の保管庫であり、保管庫に通ううちに、私は自分の苛立ちの純度を見極められるようになる。苛立ちが他者への攻撃ではなく、言葉の手つきへの要求であるように、何度でも練り直す。その練り直しが、生活に遅い呼吸を導入する。
「語り得ない」は免罪符ではない。語ればこぼれる、そのこぼれを受け止めるために、もういちど語る。その二往復目以降の手つきこそ、私が文学と呼びたいものだ。そこでは、意味は固定されず、価値は遅れて到着し、判断は保留される。保留は臆病ではない。保留は、世界の複数性に対する礼儀である。礼儀は即効薬ではないが、関係の破壊を遅くする。遅くすることは軽蔑される。しかし遅くする技術がなければ、私たちはすぐに世界を単純化の牢屋へ押し込めるだろう。血液型診断は牢屋の鍵の形をしている。文学は、鍵穴の彫りの複雑さを見せてしまう。それを見てしまった者は、たぶんもう簡単には鍵を信じられない。信じられないまま、それでも扉の前に立ち続ける練習をする。この不器用さが人間らしさの最後の砦なのだと、私はいまは信じたい。
だから、私は役に立たない文学に向き合い続ける。向き合うたびに、理解が少し壊れ、壊れた理解の破片がまた次の理解の足場になる。完璧な足場ではなく、仮設の足場だ。風が吹けば揺れる。けれど、揺れるからこそ私は自分の身体の重さを知る。私は怒っている。高尚ぶる言葉に、万能の価値論に、すぐに効く理解の処方箋に。だが同時に、怒りのおかげで私はまだ読む。怒りは読むことの入口であり、出口でもある。読み終えても、何も解決しない。けれど頁を閉じる前と後で、私の「わからない」は質を変えている。わからないまま、少しだけ丁寧になる。その丁寧さは生活の即戦力ではないが、関係を壊さないための鈍い力になる。役に立たないが、続行可能性を支える——この妙な差し引きの中で、文学は今日もなんとか存続しているのだろう。