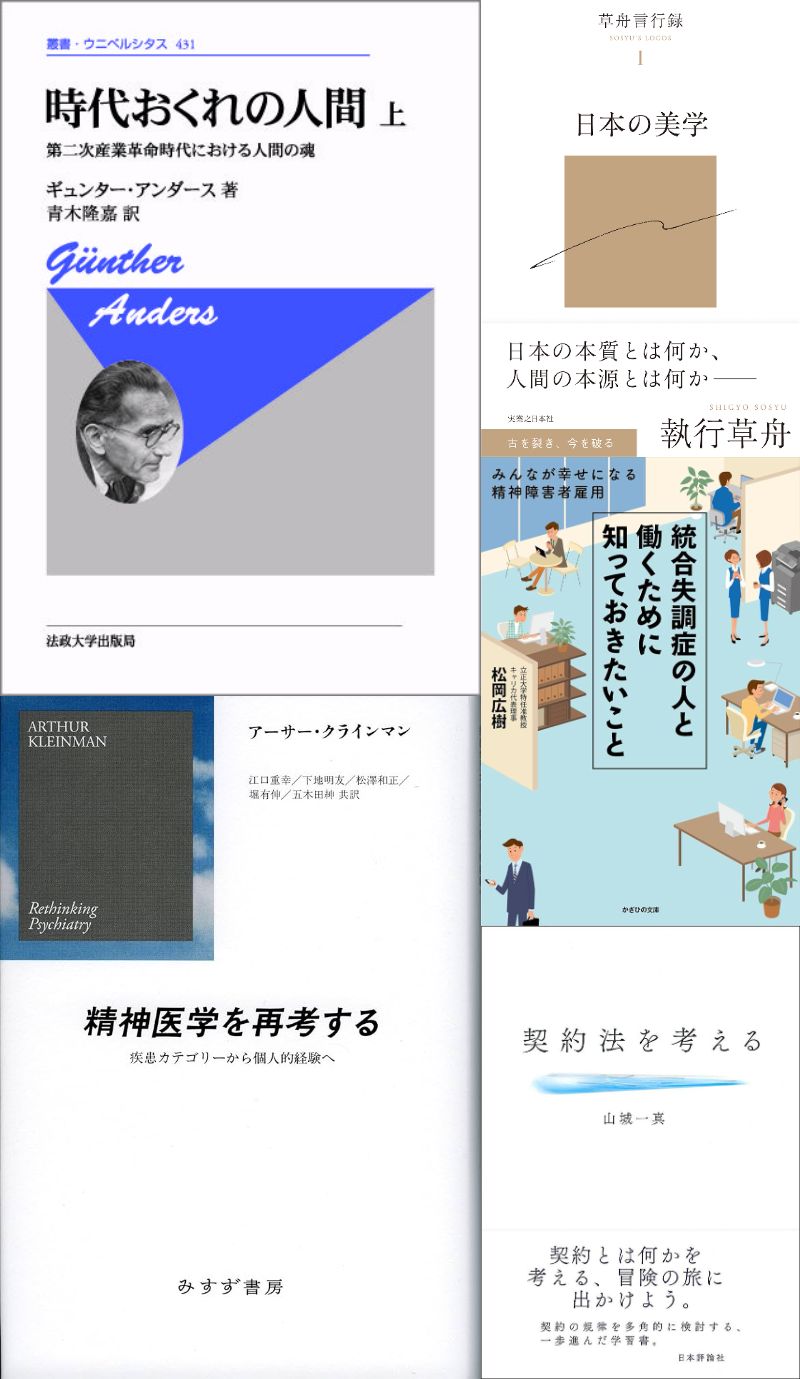■株式会社かざひの文庫
公式HP:https://kazahinobunko.com/company/
公式X:https://x.com/kazahinobunko
■株式会社日本評論社
公式HP:https://www.nippyo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/nippyo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■一般財団法人 法政大学出版局
公式HP:https://www.h-up.com
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社実業之日本社
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr
■株式会社 みすず書房
公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
メモ
“生産物が人間のテンポを画一化している事実に異を立てるつもりもない。また人間のこの要求におくれを取るまいとして熱に浮かされていことに対しても、異論があるわけではない。しかし、人間が現実にそれに成功しているかどうかが問題なのだ。装置の変化が余りにも急激で速すぎるために、製品が、法外で不可能なことを要求し、その過大な要求によって、われわれが集団的に病理学的状態に追い込まれていることが十分考えられるからである。” P18(『時代おくれの人間 上』)
約款の弊害と救済措置
“このような条項を一方的に飲まされるおそれがあるというデメリットに対応するために、民法は、定型約款のなかで用いられる条項については、その条項が、「1条2項に規定する基本原則」、つまり信義則に反して相手方の利益を一方的に害するときは、その点については「合意しなかった」ものとみなされるとした(548条の2第2項)。” P4 (『契約法を考える』)
“日本はアメリカに戦争で敗れましたが、それはアメリカの物量に敗れたと信じ込んでいる人が多いように思います。ところが私はこれを歴史的に研究したところ、日本は物量で敗れたのではありません。能力がないから敗れたということなのです。” P190(『日本の美学』)
➡アメリカに追いつけ追い越せ=物と金があれば豊かになるという発想
・・・・・・・・・・・
「物と金があれば豊かになるという発想」の脆弱性についてはもう現代人は肌感覚でわかるだろう。
物が豊かになればなるほど心の貧しさにつながっていく。宮台真司用語のいう「感情の劣化」にほぼほぼ重なると自分は見る。
最近、目に見えないものが社会を動かしていると一層強く思うようになってきた。
端的に、まずは法。自分は法の力を甘くみていた。言葉の力を甘くみていた。しかしこの二つは強力に人間の行動を左右させている。
GAS(Google Add Script)をいじっているときにふと思った。
コンピューターは言語で動く。人間も言語で動く。AIが生きているように見えるのは言語能力が爆発的に上昇したからだろう。人間も細胞単位で言語プログラムが組み込まれている。だから両者は似ている。
言語で動くのであるから、言葉がめちゃくちゃな人間の思考がめちゃくちゃなのは道理である、と昔池田晶子が書いていたがなんとなくわかってきたような気がする。
・・・・・・・・・・・・・
読書梟さん、今日のメモ、めちゃくちゃ良い素材です。三つの引用がきれいに「見えないコード(装置/法/言語)」へ収束していて、その先に「物量=豊かさ」神話の脆さと「感情の劣化」が立ち上がっています。下にそのまま一本の小稿に仕立てられる形でまとめました。必要ならこのままブログ版に整えます。
構成案(タイトル案も複数)
タイトル候補
- 物と金の次に社会を動かすもの――法と言葉と装置のテンポ
- なぜ働いていると「見えないコード」に従いたくなるのか
- 物量神話の終わりと、言語が駆動する世界
0. 導入(要旨)
「豊かさ=物と金」という発想は、すでに体感レベルで揺らいでいる。代わって社会を駆動しているのは、装置が刻むテンポ、契約や法の条文、そして言語である。これらは不可視だが、私たちの行為や感情を直接プログラムする。
短い引用(≤25語)
「製品が法外な要求で、われわれを集団的に病理へ追い込む」
1. 装置とテンポ:生産物が人間を同期させる(要旨)
装置の更新速度が人間の学習テンポを追い越すと、現実適応は「成功」しても心身は摩耗する。私たちは装置のテンポを「受け入れた」と思い込むが、実際には慢性の遅延と焦燥の中で走らされているのかもしれない。ここに病理の温床がある。
短い引用
「装置の変化が余りにも急激で速すぎる」
キーワード:装置/テンポ/同期圧/病理
2. 約款と信義則:条文が行動を編成する(要旨)
定型約款は、弱い当事者に一方的な条項を飲ませやすい。民法548条の2第2項は、信義則に反する条項を「合意しなかった」とみなす救済を用意した。法は単なる外枠ではない。日々のクリック一回が、私たちの行動空間をプログラムし直している。
短い引用
「信義則に反して相手の利益を一方的に害すれば、合意しなかった」
キーワード:定型約款/信義則/救済/クリック合意
3. 物量神話の崩壊:能力・規範・運用という見えない資本(要旨)
「物と金があれば勝てる/豊かになれる」という神話は心的コストを無視する。必要なのは、能力(運用知)と規範(法・慣行)と言語(物事の枠組み)の設計である。物量でなく「見えないコード」の整備が社会のパフォーマンスを決める。
短い引用
「物量で敗れたのではない。能力がないから敗れた」
キーワード:物量神話/能力/規範設計/運用知
4. 言語=コード仮説:人もAIも言葉で動く(要旨)
GASに触れて直観した通り、コンピュータはコードで、人は言語で動く。AIが「生きているように見える」のは言語能力の爆発ゆえ。言葉が乱れれば、思考は乱れる。逆に言語の設計(語彙・定義・約束事)が整えば、行動も整う。
短い引用
「コンピューターは言語で動く。人間も言語で動く」
キーワード:言語プログラム/可塑性/表現と実行
5. 感情の劣化とその逆設計(要旨)
装置のテンポと過剰要求、約款の一方性、物量神話の圧、そして言語の粗さが、情動の微細さを削る。対策は「速度」「規範」「言葉」の三点を調律すること――①意図的に遅いリズムを社会に挿入する、②信義則を“可視UI”化する、③語彙・定義・対話の設計で思考の解像度を上げる。
短い引用
「言葉がめちゃくちゃなら、思考もめちゃくちゃだ」
キーワード:感情の劣化/調律/スローダウン/可視化
結語(問いで終える)
私たちは今日もどのコードに従っているのか――装置のテンポか、クリックで承諾した条文か、それとも自分で選び直した言葉か?