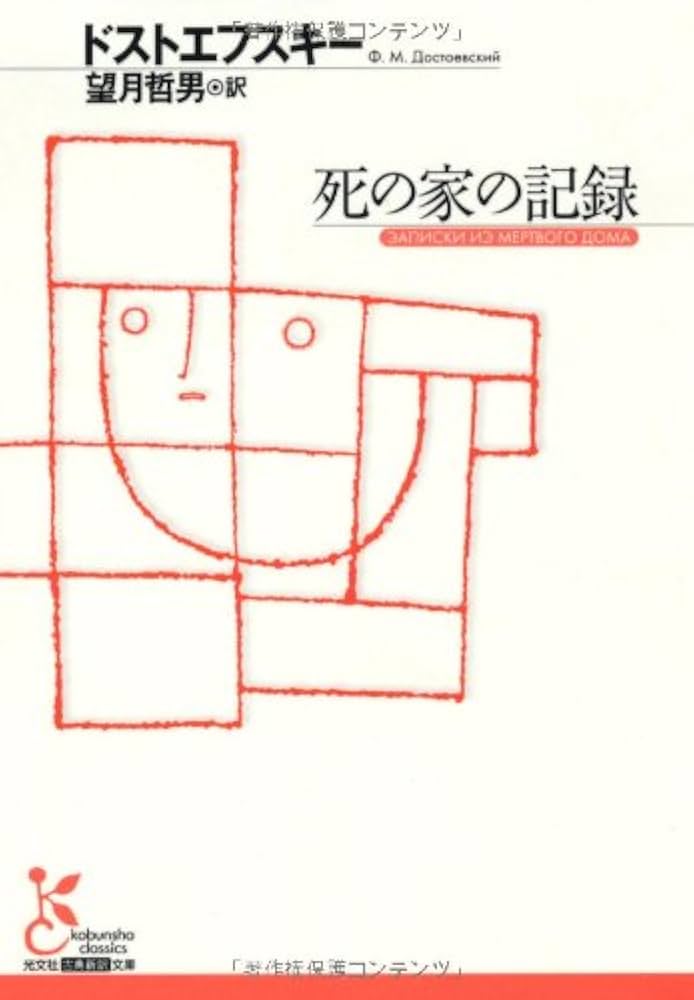■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
要求の妥当性のみを限定的に扱うために
人はしばしば、「要求すること」を自分の権利だと信じている。
要求の発露には、正当なものもあれば、感情にまかせたものもある。だが現代社会では、両者の区別がますます曖昧になっている。誰もが「意見を言う自由」を誇りながら、他者の負担を見落とす。SNSの投稿欄から行政窓口まで、「要求」はあふれ、そこに秩序をもたらすべき判断の力――妥当性の意識――は著しく希薄になった。
それでも、誰かがその線を引かねばならない。要求の「妥当性」を見極め、受け止めるか否かを決める者がいる。彼は感情に反応せず、また相手を否定もせず、ただ要求の内容を吟味する。しかし、その冷静さこそが、ときに「冷たい」と見なされる。社会は往々にして、明晰な線引きをする人を「非人間的」と感じるものだ。
だが、ほんとうに非人間的なのはどちらなのか。無制限な要求を「人間味」と呼び、責任の所在を溶かしてしまう風潮のほうに、私はむしろ人間への敬意の欠如を見る。
「要求の妥当性のみを限定的に扱う」とは、単に冷淡であれという意味ではない。むしろ、その逆だ。要求の妥当性を見極めるとは、相手の尊厳を守るために、要求と人格を切り離すことを意味する。人の言葉はしばしば、怒りや不安や劣等感に覆われて発せられる。だが、そこに混じるノイズをすべて「その人の本心」とみなしてしまえば、対話は成立しない。誠実さとは、言葉の背後にある雑音をいったん留保し、内容を抽出する努力のことだ。
しかし、それを実践するのは容易ではない。わがままな要求に直面するとき、私たちはしばしば二つの極端に引き裂かれる。一方は「迎合」であり、もう一方は「拒絶」だ。迎合すれば相手の感情は一時的に和らぐが、依存を強め、問題は再生産される。拒絶すれば自尊を保てるが、関係は断絶する。その中間を探ること――つまり「限定的に扱う」こと――は、感情の嵐の中で境界線を引く、緊張を伴う行為だ。まるで荒れた海の上に、細い線を引こうとするようなものだ。
このとき、最も大切なのは、「判断の根拠を言語化しておくこと」だ。要求を受け入れない理由を説明できなければ、それは単なる拒絶に見える。説明とは、相手に理解されるためでなく、自分が逸脱しないための防波堤である。説明できない判断は、やがて感情に侵食される。だから、言葉をもたない誠実さは、脆い。
同時に、言葉だけの誠実さも、空虚だ。弁明が自己正当化に転じた瞬間、誠実さは自己保身になる。境界を保つとは、言葉の重さを引き受けつつ、自己正当化に堕さないバランスをとることだ。そこに、倫理の難所がある。
現代の倫理は「やさしさの強迫」に支配されているように思う。相手を否定してはならない、拒絶してはならない、傷つけてはならない――。だが、それは同時に、他者の“要求の無限化”を許す構造でもある。やさしさは、境界を失うと暴力に変わる。相手を尊重するとは、相手の要求をすべて受け入れることではなく、どこまでが対話可能であるかを判断することだ。
対話とは、無限の応答ではない。有限な時間と感情と体力のなかで、どこまでを「応答可能」と見なすか、その見極めが倫理をつくる。
「要求の妥当性のみを扱う」という姿勢は、一見すると官僚的にも思える。だが、その限定性こそが、人と人との関係を長く保たせる。なぜなら、無制限の関与は、やがて双方を疲弊させるからだ。私たちは無限の理解を約束できない。誠実さは、理解の量ではなく、理解の形に宿る。つまり、「これ以上はできません」と伝えることもまた、誠実な応答の一形態である。
私はしばしば思う。要求とは、鏡のようなものだ。相手が何を求めるかには、その人が何を恐れているかが映っている。要求の過剰さは、恐怖の過剰さであり、自己不信の裏返しだ。だから、その要求に応じるか否かを判断する以前に、「この要求はどんな恐れから発しているのか」を考えることが、もっとも実践的な思考法である。
しかし同時に、すべての恐れを癒やすことはできない。そこに限界を見据えること――その「できなさ」を自覚することこそ、支える側の成熟ではないかと思う。
私たちは、無限の理解を目指すべきではない。むしろ、有限の理解をどこまで正確に引くか、その線の引き方にこそ倫理がある。要求の妥当性を限定的に扱うとは、人を切り捨てることではなく、人の不完全さを受け入れることだ。誠実さとは、万能であることの放棄である。
要求が正当か否かを判断するたびに、私はいつも少しだけ自分の中の「人間らしさ」を削られるような感覚を覚える。だが同時に、その削られた部分に、奇妙な清澄さが残る。感情を燃やし尽くした後の灰のような、静かな透明さ。そこに残るのは、善悪ではなく、「限界を自覚した人間」の姿だ。私はその姿を、倫理と呼びたい。
この社会では、あらゆる場面で「もっと応答せよ」「もっと柔軟にせよ」と求められる。だが、応答を拒む権利こそ、成熟した自由の証ではないだろうか。自由とは、すべてに答えることではなく、答えるべきことを選び取る力だ。
要求を限定的に扱うという行為は、まさにその選択の実践である。
誠実とは、拒絶の形をとる勇気でもある。
他者の要求を無条件に受け入れず、それでもなお人間関係を断たないために――私たちはどんな言葉を選べばよいのだろうか。