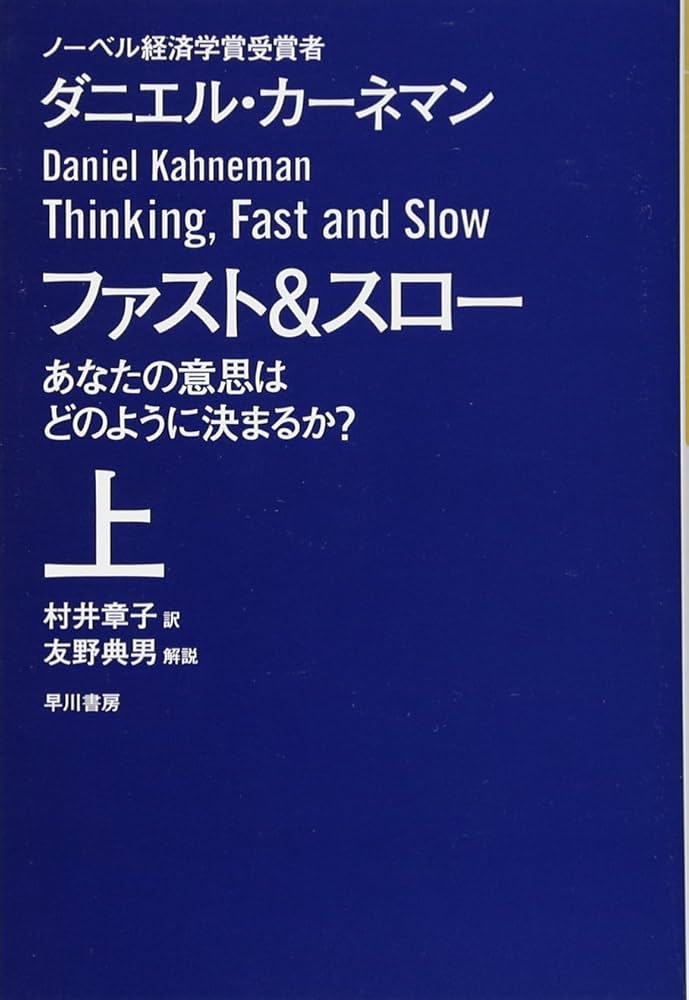■株式会社早川書房
公式HP:https://www.hayakawa-online.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Hayakawashobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
今日はカーネマン『ファスト&スロー』文庫版の上巻を、ようやく腰を据えて読みはじめた。といっても、進んだのはまだ60ページほどである。しかしこの本の性格上、ページ数よりも「どのように自分の頭が連れ回されたか」の方が、読書の手応えを測る指標になるのだと思う。
冒頭近くで提示されるのが、システム1とシステム2という二つの思考モードである。2+2=? これはほとんど反射のように「4」と浮かぶ。あるいは「これはペンです」というレベルの認知も、わざわざ頭をひねる必要はない。ここを担っているのが「ファスト」な思考、すなわちシステム1である。一方、「17×24=?」となると、さすがに指折り数えるか、暗算ルーチンを起動するか、あるいは電卓を探しはじめる。こちらは「スロー」な思考、システム2の領域である。
カーネマンは、この二つを単なる「速い/遅い」ではなく、「自動的に立ち上がる心」と「努力して立ち上げる心」として対比しているように思える。システム1は、勝手に走り出す。システム2は、腰が重いが、いったん動き出すと計算や論理をこなしてくれる。問題は、人間がふだんほとんどシステム1に身を預けたまま生きていることである。
そのことを象徴的に示すのが、あの有名な実験である。バスケットボールをパスし合うチームを見せ、「何回パスが行き交ったか数えてください」と指示する。真面目に数えようとすると、こちらのシステム2はパスの行方に全集中する。そのあいだに、画面の中にゴリラが登場しても、多くの人はまったく気づかない。ひたすら「パスの回数」というタスクにシステム2を取られ、視野に入っているはずのゴリラをシステム1が拾いそこねるのである。
ここで示されているのは、「人は注意の配分をコントロールしているつもりで、かなり不器用に偏らせている」という事実である。しかも、バイアスにかかっている当人ほど、その偏りに気づかない。これは、タレブが『ブラック・スワン』や『反脆弱性』で繰り返し指摘する、「人間の認識は世界の不確実性に対してあまりにも心もとない」という認識と地続きである。
タレブは、こうした脆い認識から人が完全に逃れることはできない、だからこそ「世界をどう認識するか」より「世界にどう構えるか」を問題にする。予測の精度を上げようとするのではなく、予測不能性を前提に、損を限定し、得を開いておく構造をつくる。それが彼の言う「反脆弱性」であり、衝撃によって壊れるのではなく、むしろ強くなっていくシステムである。
今日、『ファスト&スロー』を読みながら、わたしの頭にはずっと、タレブと、自分が考えている「可逆性」のことが同時に浮かんでいた。タレブは「世界の側の不確実性」に賭ける。わたしは「制度や契約の側の可逆性」にこだわっている。両者は別々の話のようでいて、実は同じテーブルに置けるのではないか。そう感じたのである。
わたしが言いたい「可逆性」とは、簡潔に言えば「間違っても戻れるようにしておくこと」である。もう少し真面目に定義すると、力や制度や市場や言説が誤ったときに、弱い側の人間でも、自力と最小限の支援で回復できる余地を残しておくような設計の倫理である。もっと砕けば、「言えば戻る社会」である。
この「言えば戻る」が成立していない領域は、世の中にあまりにも多い。黙っていれば返金しない。質問しなければ説明しない。苦情がこなければ是正しない。これは、個々人の悪意というより、構造としての「不可逆性」が生み出す悪である。わたしはそのことを、あるサービスとの返金交渉を通じて嫌というほど味わった。何も言わなければ、支払った金は一方的に向こう側の「既成事実」として固定される。異議を申し立てた瞬間に、態度も説明も、提示される条件も変わる。そこにあるのは「誠実さ」ではなく、「不可逆性を盾に取り続けるわけにはいかなくなったから」という、きわめて計算的なリアクションである。
このとき、わたしの頭の中では、カーネマンのシステム1とシステム2が、制度側にも置き換えられていた。企業や組織の「デフォルト運転」は、システム1的である。つまり、「苦情がなければコストを払わない」という自動運転モードで動いている。そこに行政や法律、あるいは粘り強い交渉といった「外部からのシステム2」が割り込んだとき、初めて彼らは計算し直す。どこまで返金した方が得か、どのラインで折り合うべきか――。
ここまでは、よくある話である。しかし、その経験をただの「嫌な思い出」で終わらせず、コンセプトとして立ち上げることが、わたしにとっての読書日記2000への道筋になると思っている。つまり、わたしは「損をした人」で止まりたくない。不可逆性の被害者としての自分から、可逆性という概念を発見する人間へと、立場を変えたいのである。
そのときに必要なのが、「消費しない読書日記」という発想である。
これまでの読書日記は、ある意味で「読書体験の消費記録」になりやすかった。読んだ本の要約を書き、気になった引用を貼り付け、印象や評価を残していく。それはそれで大切な営みである。しかし、このスタイルだけだと、本も日記も、読み捨て・書き捨てになっていく危険がある。読み終わった瞬間、経験は「済んだもの」として過去に押し込められ、蓄積というより、流通に近い。
わたしがめざしたいのは、そうではない読書日記である。本を読みながら、その内容を自分の概念装置と組み合わせ、次の作品や思考に「変換」していくためのノートとしての読書日記である。これは、感想文ではなく、概念の実験室である。
たとえば、今日読んだカーネマンのシステム1/システム2を、そのまま「へえ、面白い」で終わらせるのではなく、「可逆性」の視点で読み替える。人間の認知は不可逆である。見落としたゴリラは、もうその瞬間には戻ってこない。そこで起きた判断ミスも、その場では取り消せない。ゆえに、わたしたちは「人間がミスをしない世界」を夢見るべきではなく、「人間がミスをしてもやり直せる制度」を設計すべきである。
この一歩だけで、同じ60ページの読書が「単なる知識の摂取」から「自分の概念の補強」へと性格を変える。消費される読書ではなく、将来の本や論文や有料コンテンツのための下地となる読書である。
わたしは、自分のオリジナリティを単に無料で流し続けるつもりはない。安売りをしたいわけではないし、「アクセス数のために中身を薄める」ような読書日記を書きたくもない。むしろ、これまで積み上げてきた読書と経験と交渉の実録を、「可逆性」という一本の軸で束ね、そのうえで「お金を払ってでも読みたい」と思ってもらえる形にしていきたいのである。
その意味で、「消費しない読書日記」は、わたしにとって一種の投資口座である。ここに書き残した思考断片や怒りの整形済みバージョンは、いずれ「読書梟『可逆性』」という一冊の本に再編される。その本は、正義を語る大きな物語ではなく、「黙っていれば損をする」現代社会において、弱い立場にいる人間がどこまで取り返しを効かせられるか、そのための具体的な技法と倫理を示すものにしたい。
タレブが、不確実な世界で損を最小にし、得を最大にするための「ポジションの取り方」を語ったように、わたしは「不可逆性だらけの社会で、どこまで可逆性を捻り出せるか」という設計の話をしたいのである。カーネマンが、人の直感がどのように誤り、どこまで頼れ、どこで危険になるかを精密に解剖したように、わたしは「制度や慣行のデフォルト運転」がどこで人を傷つけ、どのように設計し直せばいいかを、できる限り具体的に書きたい。
そのためには、読書日記そのものもまた、不可逆的に垂れ流されるコンテンツであってはならない。書いたものがすぐに「過去ログ」として沈んでいくのではなく、後から何度でも取り出し、再編集し、噛み直し、別の文脈へ貼り替えられること。つまり、読書日記の運用自体を「可逆的」にする必要がある。
ブログに公開するテキストと、有料化してまとめるテキスト、その中間にある「概念メモ」としての読書日記。これらをどう配置し、どこにどのレベルのオリジナリティを置くか。それを意識しながら書き進めることで、「消費される読書日記」から「発電する読書日記」へと変えていけるのではないかと考えている。
『ファスト&スロー』の読書は、まだ序章もいいところである。それでも、システム1とシステム2の話はすでに、「可逆性」を考える上での強力な補助線になりつつある。人はなぜミスに気づかないのか。なぜ、ゴリラを見落とし続けるのか。なぜ、黙っているだけで損をさせてしまう制度が温存されるのか。こうした問いを、認知心理学と制度設計のあいだで往復させながら、読書日記2000に向けて書き溜めていきたい。
わたしがこれから書く一つ一つの読書日記は、本当に「可逆的な社会」への足がかりになりうるのか、それともまた別のかたちで消費されてしまうのか――その行方を、どのように自分で引き受けていけばよいのだろうか。