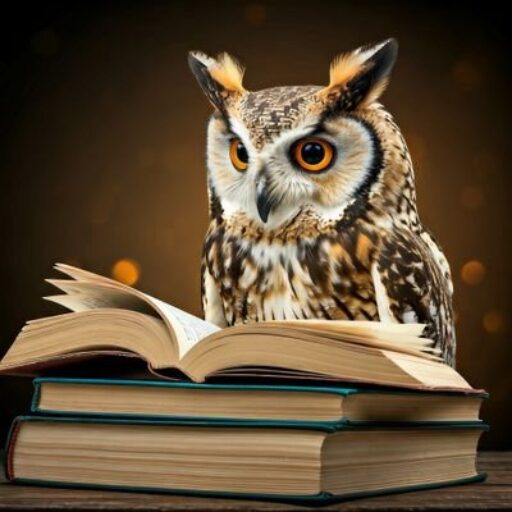「うしろめたい読書日記」という言葉には、最初から二つの矛盾が同居している。読書は本来、誰にも迷惑をかけないはずの行為である。にもかかわらず、そこに「うしろめたさ」が差し込む。しかもそれを、わざわざ日記にして公開する。内省と露出の同居である。私はこの矛盾を、弱点ではなく入口として扱いたい。なぜなら、うしろめたさは読書の敵ではなく、読書を「生」に接続し直す回路だからである。
うしろめたさの正体は、たいてい二種類に分かれる。第一に、読書が現実逃避であるという疑いである。働いているのに、家事があるのに、返信すべき連絡があるのに、本を開く。世界からの要請をいったん棚上げして紙の世界へ潜る。そのときの背徳感が、うしろめたさになる。第二に、読書が自己正当化であるという疑いである。本を読んでいる自分は、何か良いことをしている気がする。だが本当に良いことをしているのか。単に「読んでいる自分」というイメージを消費しているだけではないのか。これらは、自己啓発の明るい照明の裏にできる影である。明るければ明るいほど、影は濃くなる。
しかし、うしろめたさには妙な効能もある。うしろめたい読書は、読書の「形式」と「内容」のズレを敏感にする。形式としての読書は、静かで、清潔で、秩序正しい。だが内容としての読書は、しばしば泥だらけで、乱暴で、矛盾だらけである。トルストイ『復活』を通勤電車で読み続けていると、このズレが容赦なく露呈する。登場人物の相関図は、毎日読まないと崩れる。つまり、読書とは「理解した」ではなく「関係の線を毎日なぞる」実践である。論争、ぶつかり合い、葛藤、企み、刑罰。そこには生きた人間がつまっている。清潔な形式で読んでいるつもりが、内容がこちらの手を汚してくる。ここで、うしろめたさは後退するどころか、別の形で深化する。「こんな人間の泥を、私は安全な席から読んでよいのか」といううしろめたさである。だがこのうしろめたさは、逃避や自己正当化のそれとは違う。むしろ、現実に近づくうしろめたさである。
この「現実に近づくうしろめたさ」が、私をローゼンツヴァイク『救済の星』へ押し流す。正直に言えば、最初の数十ページで私は苛立った。さっぱりわからない。メタ論理学という造語めいた言葉が出てきて、学術的な顔をしながら、比喩は詩のように跳ねる。「思考は存在と結婚した」などと言われると、私は反射的に言いたくなる。ポエムである、と。文学であって論文ではない、と。だが、ここで引き返すと、うしろめたい読書日記の核心を取り逃がす気がした。なぜなら、私が本当に引っかかっているのは「難しいから」ではなく、「難しさの根が死と無にあるから」だからである。理解が追いつかないのに、底の冷えだけは伝わってくる。これは、普通の難書の感触ではない。
ローゼンツヴァイクにとって死は、主題ではなく出発点である。しかも「死一般」ではなく、「私の死」である。ここが決定的に不穏である。死一般なら、学問は扱える。制度や歴史や宗教や文化の語彙で囲い込み、「死はこう位置づく」と言える。だが「私の死」は囲い込めない。私の死は、最後には私から言葉を奪うからである。だからこそ、死の恐怖は、世界を「きれいな全体」として語って安心する哲学を爆破する。ここで「思考と存在の結婚」という比喩が効いてくる。思考が存在と結婚してしまうと、世界は一枚の布になる。縫い目が消え、裂け目が見えなくなる。全体が理解できれば安心、という鎮静剤が効き始める。だが「私の死」は、その鎮静剤を無効化する。死の恐怖は、世界の外側からではなく、私の身体の内側から来る。だから全体化は、ここでは救いにならない。むしろ危険な麻酔になる。
ここで私は、うしろめたい読書日記の方向が少し変わるのを感じる。うしろめたさとは、単に「読んでいる場合ではない」という後ろめたさではない。もっと根の深い、世界の麻酔に対する後ろめたさである。読書の形式に身を隠して、全体を語った気になって、痛みを見ないふりをすることへの後ろめたさである。ローゼンツヴァイクの苛烈さは、私からその逃げ道を奪う。ポエムに見える文体は、飾りではなく武器である。論文の言葉の整然さは、しばしば死の恐怖を整頓してしまう。整頓した瞬間に、本質が死ぬ。だから彼は、整頓の言葉を壊す。詩になることで、裂け目を塞がない。詩とは、理解の不足を補う飾りではなく、理解が届かない地点をそのまま残す形式である。
だが『救済の星』は、死の本ではあるが、死の賛美の本ではない。むしろ死は、思考を麻痺させ、私を独房に閉じ込める。だから彼は、独り言の思考(モノローグ)ではなく、呼びかけ(対話)へ思考を切り替えようとする。救済とは、死を論破することではなく、死の前で閉じた自己が生へ向かって開かれることである。ここで、読書は再び「関係の線をなぞる」実践に戻ってくる。トルストイが相関図で人間の線を描くなら、ローゼンツヴァイクは神・世界・自己の線を描く。どちらも、線が途切れる地点に注目している。刑罰が人間を切断する地点。死が全体を切断する地点。その切断面に、詩が生まれる。
この切断面が、私の中で「責任」の問題へ接続する。『復活』を読んでいると、刑罰という制度が、人間を「変える」のか「壊す」のか、あるいは「変えるふりをして壊す」のか、問いが立ち上がる。「人間は罰によって変わるのか、それとも罰の外側でしか変わらないのか」という問いである。だが現代の決定論的な世界観を通せば、ここは簡単に裏返る。「責任があるから罰する」のではなく、「罰を与えるために責任という概念が存在する」と言いたくなる。責任は虚構であり、後づけであり、統治の装置である、と。これは冷笑ではなく、運用上の現実である。責任はしばしば、非難と報復のスイッチとして作動する。
しかし、ここで私は一つの分岐を選ぶ。責任を「罰の装置」としてだけ理解すると、読書も人生も二択になる。責任から逃げるか、責任で人を殴るか。逃走か殴打か。これは、うしろめたい読書日記の病理をそのまま増幅する。読むことは逃げだ、読むことは正しい、という粗い往復運動になる。そこで私は、責任を「修復」の技術として読み替える。罰モードが「誰が悪いか」「どれだけ苦しめるべきか」だとしたら、修復モードは「何が壊れたか」「誰が何を失ったか」「どう埋め直すか」「再発の確率をどう下げるか」である。責任とは報復の根拠ではなく、壊れたものを埋め直すための手続きである。ここでは決定論は敵ではない。むしろ原因の理解は、修復の手がかりになる。原因を裁くのではなく、未来へ介入する。責任を過去の断罪から未来の設計へ移す。
そして私がいま強く惹かれているのは、修復のうちでも「個人の内面」の修復である。後悔や贖いというパトスである。詩である。制度の修復は設計できるが、内面の修復は計測できない。人はある瞬間に、自分が自分でいられなくなるほどの悔いに襲われる。どんな因果説明も、その熱を消すことはできない。だがその熱は、自己憎悪へ向かえば焼け野原を広げ、他者への応答へ向かえば、わずかでも世界を埋め直す。贖いとは、罰を受けることではなく、痛みの方向を反転させることである。修復とは、取り返せないものを取り返すことではなく、取り返せなさを抱えたまま、明日を作り直すことである。ここで「責任」は虚構であってもよい。虚構であっても、痛みは残る。残骸は虚構ではない。残骸の前で何をするか。そこに、私の責任が立ち上がる。
ローゼンツヴァイクの死の思考は、私に一つの警告を与える。全体化は麻酔になりうる。制度化も麻酔になりうる。責任論も麻酔になりうる。うしろめたい読書日記も麻酔になりうる。読んで内省して書いた、という形式が、痛みを「処理した気」にさせるからである。だから私は、形式にとって誤配であれ、という自分の合言葉を思い出す。読書の形式に収まらないものを、あえて残す。整理しきれないものを抱えたまま、線をなぞり続ける。トルストイの相関図が毎日なぞらないと崩れるように、私の内面の相関図も、毎日なぞらないと崩れる。うしろめたさは、その「なぞり直し」を促す微かな痛みである。痛みがあるうちは、まだ麻痺していない。
「うしろめたい読書日記から救済の星へ」という題は、出世コースの話ではない。読書が立派になっていく話でもない。むしろ、読書が立派であるという麻酔から目覚め、死と無と刑罰と後悔と贖いの、整理不能な現実へ近づいていく話である。救済とは、整頓された理解ではなく、裂け目を裂け目のまま抱え、なお生へ向かって開くことにある。詩でなければ届かない地点があり、論文でなければ整えられない地点もある。だが私は今、電車の揺れの中で、詩のほうへ少し体重をかけている。生きた人間の姿がそこに確かに感じられるからである。
では私は今日、読書という安全な形式の中で「良いことをしている気」になる代わりに、どんな裂け目を修復へ向けて引き受け直せるのだろうか。