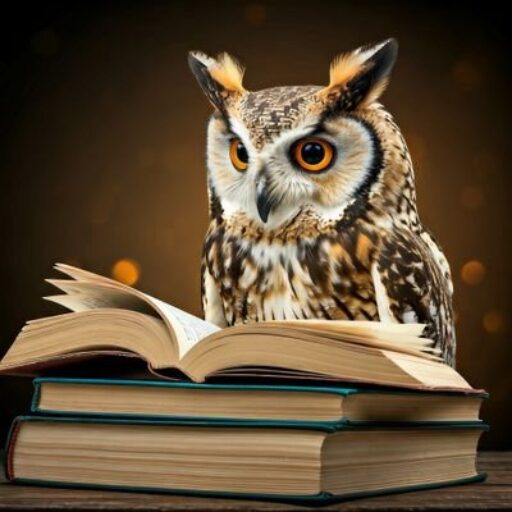うしろめたい、という感情ほど現代的な読書の入口はないと思う。読みたいのに読めていない。読んだのに何も変わっていない。読むほどに自分の人生が立派になっていない。役に立てられていない。そういう「足りなさ」を引きずったまま、ページだけが進んでいく。読書は本来、精神の運動であるはずなのに、いつの間にか読書は成果に換算されるべき活動になり、成果に換算できない瞬間に、うしろめたさが発生する。
だが、ここで言っておきたい。うしろめたさは、あなたが怠惰だから生まれるのではない。世界が読書を物質の尺度で測ろうとするから生まれる。読書は知性のアクセサリーでも、教養の名刺でも、自己投資のレシートでもない。読書が精神の側に属する限り、読書は「回収されないもの」を抱え続ける営みであり、回収されないがゆえに、社会の会計帳簿からはみ出す。はみ出したものは、すぐ「無駄」と呼ばれる。無駄と呼ばれた瞬間、人はうしろめたくなる。つまり、うしろめたさは、精神がまだ生きている証拠でもある。
私は最近、執行草舟『幸福とは何か』を読み終えた。何度も執行さんの本は読みこんできたが、改めて突きつけられたのは、読書とは知性ではなく精神であり、精神とは物質とは無縁の領域に根を張るという感覚であった。世俗的なものが物質的なものだと心の底から思った。もちろん生活は重要で、身体は守られるべきだ。しかし、その「重要さ」がいつの間にか「絶対」に格上げされると、精神は住む場所を失う。読書の価値は、物質の豊かさの延長ではなく、物質がすべてになりかける世界に、別の座標を開くところにある。
ここで一つ、よくある命題を疑ってみたい。「お金がないと心も廃れる」。これは半分は真実で、半分は危険である。生活の不足が人を追い詰め、視野を狭め、余裕を奪い、怒りと疲労を増やす。これは現実だ。だが、そこから「ゆえに心はお金に規定される」と結論してしまうと、話は変質する。その結論は、貧しさの苦しみを救うための言葉ではなく、人間から最後の自由を奪う言葉になる。心が廃れるのは、金がないからだ。だから仕方がない。だから金がある人間が上だ。だから精神は従属物だ。こうして、同情の顔をした物質決定論が出来上がる。
私はこの命題が、深い深い場所で虚偽なのではないかと思った。虚偽とは「現実に起こらない」という意味ではない。むしろ頻繁に起こるからこそ、虚偽は力を持つ。頻繁に起こることを必然にし、人間を必然の檻に閉じ込める。その檻の形が虚偽なのだ。ドン底に落ちながら大文学者となった人物が世界にどれだけいたか。私はドストエフスキーを思う。貧困は人を壊す。壊すのが基本である。それでもなお、精神が「壊され切られない」可能性があることを、彼は文学という形で示してしまった。ここで貧困を美化したいのではない。貧困は悪だ。制度的に解消されるべきだ。しかし、貧困が悪であることと、貧困が精神を定義することは別問題である。別にしておかないと、私たちは「心の貧しさ」を金額で説明し始めてしまう。
書店に行けば、物質礼讃の設計図で溢れている。稼ぐ、増やす、勝つ、伸ばす、最適化する。こうした言葉は、確かに便利だ。だが便利であるほど、言葉は死にやすい。ニーチェは神が死んだと言った。いまは言葉が死んでいる、と私は感じる。言葉が死ぬとは、意味が消えることではない。言葉が世界に触れる能力を失うことだ。言葉が精神を運ぶ舟でなくなり、物質を運ぶコンベアになることだ。評価、成果、数字、肩書き——それらを効率よく運搬する言葉だけが生き残り、痛み、恥、祈り、畏れ、世界愛のような遅い言葉が置き去りにされる。
だから文学は「役に立たない」と判定される。だが裏返せば、世界が文学を必要としていない、という告白でもある。世界とは制度であり、評価であり、会計であり、最適化である。その世界が文学を必要としないのは、文学が「回収不能な価値」を持っているからだ。回収不能とは、利益に換算できないという意味ではない。むしろ、換算した瞬間に失われる価値がある、という意味だ。精神の糧とは、まさにそういう価値である。宇宙のような観察者がいたなら、文学を精神の糧と言うはずである。人間は物質の豊かさだけで生きられない。生きていけないというのは、呼吸が止まることではない。生きているのに生きていない、という状態に落ちることである。
ここで、この記事の主題をはっきりさせたい。「うしろめたい読書日記から脱物質の設計図へ」。つまり、読書日記を「うしろめたい」ものとして抱え込むのではなく、むしろそのうしろめたさを起点にして、物質中心の世界観から抜け出すための設計図へと変換する。その設計図は、資産形成の設計図ではない。自己管理の設計図でもない。脱物質——つまり、物質の語彙だけで世界を説明しようとする癖から離れるための、精神の設計図である。
では、どうやって。
第一に、読書日記の目的を「役に立てる」から「座標を取り戻す」へ移すことである。今日読んだ本が仕事に効いたか、人生に得をもたらしたか、SNSで映えるか。そういう問いを完全に捨てろとは言わない。しかし、それらが第一目的になると、読書は物質の設計図に従属する。読書日記の第一目的は、物質の座標に吸い込まれかけた精神を、いったん別の地点に移動させることだ。読後に「何を得たか」より、「何が崩れたか」「何が恥になったか」「何が怖くなったか」を先に書く。得たものは、後からでいい。
第二に、「うしろめたさ」をデータではなく症状として扱うことである。うしろめたさを「自分がダメだから」と解釈すると、自己啓発の罠に落ちる。うしろめたさは、世界の尺度が読書を誤読しているときに生まれる症状である。症状は、治療の入口になる。つまり、うしろめたさが出た瞬間こそ「いま私は何を物質の尺度で測ってしまったか」と問い返す。それを日記に書く。読書日記は、自己評価ではなく、世界評価の転倒装置になる。
第三に、「言葉が死んでいる」という感覚を、絶望ではなく手触りとして記録することである。言葉が死んだ、と言うのは簡単だ。だが本当に怖いのは、死んだ言葉の中で生きることに慣れてしまうことだ。だから日記は、死んだ言葉を嘆く場ではなく、まだ生きている言葉の微かな脈を探す場になる。読んでいて刺さった一文、意味がまだ定まらない比喩、心に棘として残った言い回し。それらを「役に立つ形」に加工せず、棘のまま置いておく。棘は精神の証拠である。
第四に、ニーチェの「見えない」を隠さないことである。私はニーチェの真価が見えない、触れられない、と感じた。これは恥ではない。むしろ、見えないことを見えないまま書ける人間が、言葉を生かす。理解したふりは、言葉を殺す。見えないものを見えないと言い、その見えなさの輪郭を描くことが、精神の誠実さである。読書日記とは、理解の証明ではなく、理解できなさの誠実な地図である。
第五に、物質と精神を二項対立で固定しすぎないことである。脱物質とは、物質を憎むことではない。物質が必要であることと、物質が絶対であることを切り分けることである。生活は支えられるべきだ。しかし、支えるものが定義になった瞬間、心は縮む。この切り分けの感覚を、読書日記は育てる。たとえば「今日の私は不安だから物質の言葉に逃げた」と書く。逃げたことを責めるより、逃げたことに気づいた感覚を残す。気づきは、精神の再起動である。
以上が、私の「脱物質の設計図」である。設計図は完成品ではない。設計図は、修正され続ける。読書日記も、完成ではなく、更新である。更新とは、精神がまだ生きている証拠だ。
最後に、もう一度、うしろめたさに戻る。うしろめたい読書日記とは、言い換えれば「世界の尺度に完全には屈していない読書日記」である。世界が物質を称賛し、文学を不要と判定し、言葉をコンベアに変えるほど、読書はうしろめたくなる。だが、そのうしろめたさを恥として隠すのではなく、座標として使うなら、読書日記は精神の運動を取り戻しうる。物質の設計図に従属しない設計図を、私たちは書けるのではないか。
では、あなたのうしろめたさは、いまどの瞬間に最も強く立ち上がり、どの言葉を死なせ、どの言葉をまだ生かそうとしているのだろうか。