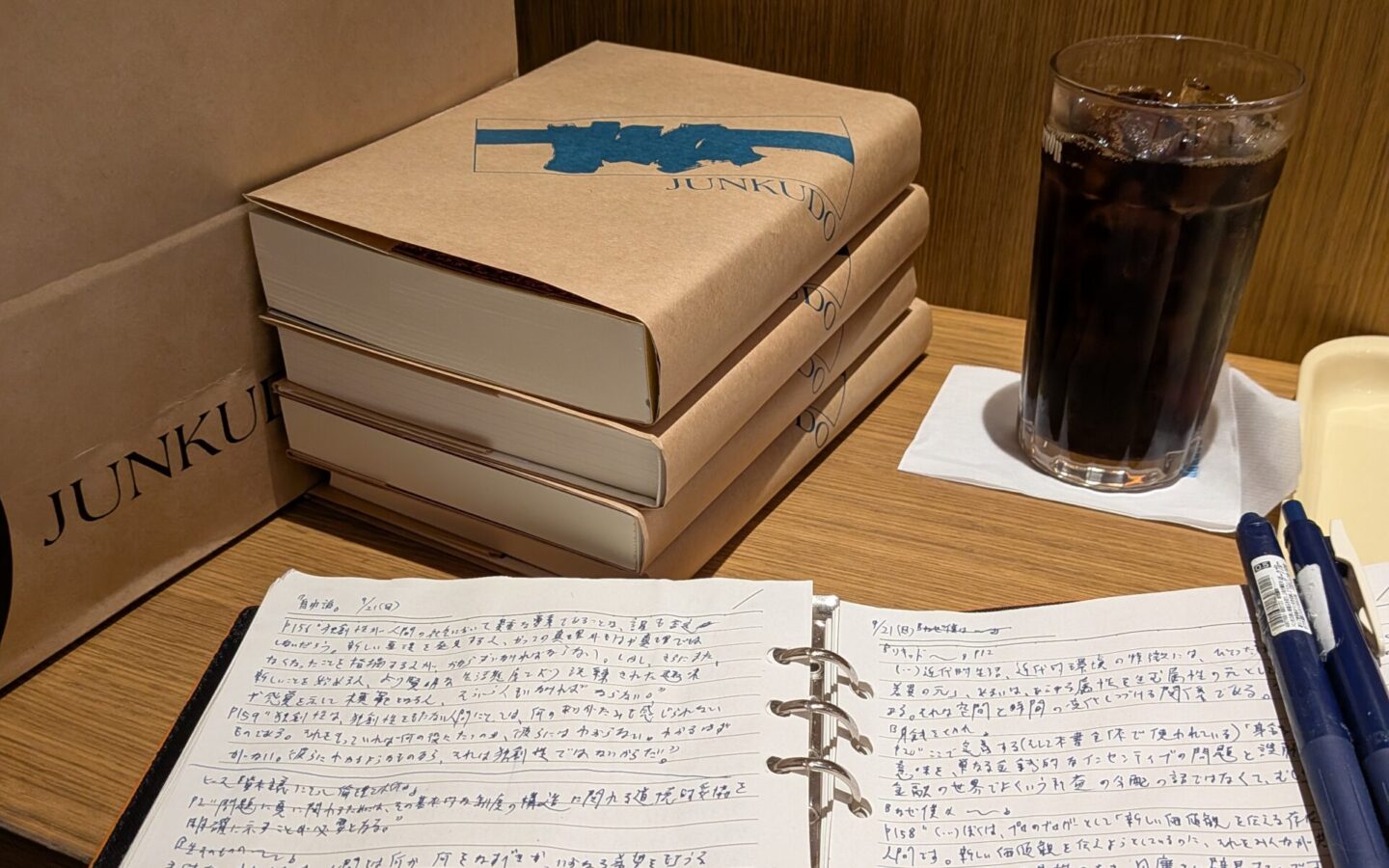今日は好奇心の赴くままに乱読、多読、拾い読み、精読をした。順番も筋も統一感もない。ただ、統一感がないことそのものが、今日の自分の誠実さに近い気がした。歴史を学びたい、と唐突に思ったからである。歴史を知らない人間が未来を語る資格などない、という言葉に刺され、刺された場所がまだ痛んでいる。痛いから、手当のように本を開いた。本を開けば治るわけではないが、少なくとも痛みの輪郭くらいはわかる。
読み終えたのは中公新書『ユダヤ人の歴史』である。新書は便利で、同時に不親切である。便利なのは輪郭を与えるからで、不親切なのは輪郭の外側を置き去りにするからである。読み終えたあと、釈然としなさが残った。釈然としなさは理解不足の証拠であり、同時に、歴史の入口に立った証拠でもある気がする。ユダヤ人の定義が揺れている。宗教(ユダヤ教を信仰する者)であり、血統(ユダヤ人の母を持つ者)であり、共同体(帰属の網)でもある。この揺れが、頭の中でずっと波打っている。
印象に残った箇所を引用する。
「伝統的ユダヤ教は、世俗勢力としてのシオニズムには本来敵対的だった。そもそもパレスチナには、メシアに導かれるまで大挙して移民すべきではないと考えたからだ。ところが、一九四八年以降にイスラエルが既成事実化すると、既存の国家権力には盾突かない、つまり『国の法は法なり』という伝統的な姿勢が始動することになった。そして、現代イスラエル史において大きな転機となるのが一九六七年の第三次中東戦争でのイスラエルの大勝である。この結果、イスラエルは、それまでそれぞれヨルダン、エジプト、シリアが統治していたヨルダン川西岸、ガザ、ゴラン高原を占領し、さらにシナ半島までエジプトから奪った。」
ここで、単純な物語が一度折れる。迫害された民族が祖国を求めた、という一本線の物語ではない。宗教共同体としてのユダヤ教が、世俗政治としてのシオニズムに最初から賛成していたわけではない。むしろ敵対的だった。ところが国家が既成事実になると、「国の法は法なり」という態度が始動する。理念が現実に飲み込まれたのか、理念を守るために現実へ折れたのか、その判定は簡単ではない。共同体は純粋さだけで生き残れない。純粋さを守るために、純粋さをいったん曲げることがある。このねじれを、ただの矛盾として切り捨てたくない。
ここから連想が走った。もし1939年頃のヨーロッパで生き抜く方法があるとしたら、キリスト教に改宗するという手もあったのではないか、と一瞬思った。迫害が宗教に向いているなら宗教を変えればよい、というのは合理的に見える。だが、ここでまた「定義」が立ち上がる。迫害の定義が宗教なのか血統なのか、共同体の登録なのか。定義が動けば、生存戦略は一瞬で無効化される。だからこそ、定義の揺れは学問上の曖昧さである以前に、現実の力学である。
この「定義の揺れ」こそ、今日の読書の中心であった気がする。揺れているから不正確、揺れているから甘い、という話ではない。揺れていること自体が、社会が線を引く装置になりうる。境界が曖昧なまま、裁断の権限だけが制度に握られると、人は「自分がどちら側か」を確信できなくなる。確信できないままに、名簿、書類、噂、登録、婚姻、改宗、居住地といった外部要因に人生が絡め取られていく。曖昧さは弱さではなく、支配の余白になりうる。この感覚は、不穏であるが、歴史を読むときに何度も出会う種類の不穏さである。
ここでロックが差し込まれたのも、偶然ではない気がする。『イギリス思想家書簡集 ロック』から、今日目に留まった一文はこれである。
「ロックは生得的な知識を否定し、経験主義的な知識論を打ち出すとともに、自然法の拘束力は、自然法を定めた神の意志に由来するという主意主義の立場とした。」
経験主義は、生まれつき確かなものがあるという感覚を疑う。しかし、歴史の理解は経験(史料や証言)だけで足りない。経験は部分的で、欠け、偏る。そこで人は、経験を束ねる枠を欲しがる。だがその枠は、経験から自動的に生まれない。自然法の拘束力を神の意志に由来させる主意主義は、その「枠の根拠」を別の場所に置く。つまり、根拠とは、経験の外側から持ち込まれうる。この移動が恐ろしい。歴史でも同じことが起こる。事実の蓄積から価値は出てこない、とヒュームが言うように、事実は事実である。しかし人は、歴史から価値を取り出したい。未来を語りたいからである。語りたいから、枠を作る。枠を作れば、枠の外側が生まれる。枠の外側は、しばしば「なかったこと」にされる。この循環が、歴史の読みを難しくする。
ここで執行草舟『誠に生く』の言葉が、別の角度から刺さってくる。「和を以て貴しと為」についての一節である。
「これを日本人が仲良くするというように単純に解釈すると、自分の意見を持たないとか、何もしないなど愚かなほうに行く場合も多いです。そういう意味では決してない。却って独立自尊といって、自分の思想を徹底的に固めないと本当に他人と和解することは出来ない。徹底的に思想が違う人間がどういう風に一緒に暮らすか、ということが和するということなのです。」
この言葉は、人間関係の話であると同時に、歴史の読み方の話でもある。歴史とは、徹底的に思想が違う人間が、同じ時間と土地に押し込まれた記録である。和するというのは、摩擦を消すことではない。摩擦があることを前提に、どう共存するかという課題を引き受けることである。ならば、歴史と和するとは、過去を都合よく整合させることではない。矛盾する声を同じ紙面に置き、矛盾が矛盾のままで響くのを許しながら、それでも読み進めることである。
ここで自分の中の「うしろめたさ」が形を変える。これまでは、読書しても分からない、歴史に無知だ、語れない、ということがうしろめたかった。だが、分からなさは恥ではなく、入口である。むしろ、分かったふりの方が危険である。歴史の“正しさ”は、単独の視点で確定しにくい。Aが言えばBが否定する。「そんなことは言っていない」。この矛盾を解きほぐすのが歴史学の仕事であり、同時に、矛盾が消えない領域が残るのも歴史である。消えない矛盾は、世界の不親切さではない。世界の複雑さである。
自分は、歴史を文学として、詩として、物語として読みたいと思った。ここで誤解が生まれやすいので言い直す。史実を軽んじたいわけではない。むしろ逆である。史実の手触りを尊重したまま、史実が「価値」へ直結しない断絶を、そのまま置いておきたいのである。断絶を置くことは、怠惰ではない。倫理である。断絶を無理に埋めるとき、物語は暴力になる。断絶を保持するとき、読書は可逆性を持つ。後から学び直せる余白が残る。自分の読みが誤配であったときに、撤退できる余白が残る。これは、読書日記アプローチの核でもある。「形式にとって誤配であれ」。整った結論へ収束させるのではなく、形式が回収しきれない誠意を、あえて残す。
だから、今日の読書日記は「うしろめたい読書日記」から少しだけ離れて、「分からなさの読書日記」へ移る。分からないことを告白して終えるのではない。分からないことを、観察対象にする。定義が揺れるのを、欠陥として責めない。揺れが生まれる条件を眺める。宗教と血統と共同体のあいだに揺れがあるなら、その揺れがどんな政治を生み、どんな制度を生み、どんな人間の生存戦略を無効化し、どんな物語を必要としたのかを読む。ロックの経験主義と主意主義のあいだに緊張があるなら、その緊張が「根拠への渇き」として、歴史の読みの内部にどう現れるのかを読む。和が仲良しではないなら、歴史と和するとは何かを読む。
自分はまだ無知である。無知のまま、トインビー『歴史の研究』を読みたいと思う。巨大な見取り図が欲しい。だが見取り図は、見取り図である以上、切り捨てるものがある。切り捨てられたものの中にこそ、定義の揺れや、矛盾の残骸や、声にならなかった声がある。その残骸を拾うのが、これからの自分の読書日記になればいい。分かったふりをしない。だが、分からないふりもしない。分からなさを抱えたまま、読んだことだけは書く。矛盾が消えないままでも、矛盾が行為を生んだなら、その行為の方へ目を向ける。
歴史は、誤解から始まることがある。誤解が行為を生み、行為が制度を生み、制度が定義を固定し、固定された定義がまた新しい誤解を生む。その循環のどこかで、誰かが「国の法は法なり」と言い、誰かが「そんなことは言っていない」と言い、誰かが「和を以て貴し」と言い、誰かが「それは仲良しの話ではない」と言う。矛盾は消えない。だが、矛盾が消えないこと自体が、歴史のリアリティでもある。
うしろめたい読書日記とは、理解できない自分を恥じる日記であった。分からなさの読書日記とは、理解できないことを起点に、定義の揺れと矛盾の保持を、読書の倫理として引き受ける日記である。今日の自分は、後者に移りたい。移ることで、未来を語る資格が少しでも生まれるとは思わない。だが、未来を語る前に、過去に対して無責任にならない練習にはなる。過去を「分かったこと」にしてしまう誘惑に抵抗する練習にはなる。では、分からなさを抱えたまま読み続けることが、果たして自分にとっての「和する」ということになりうるのだろうか?