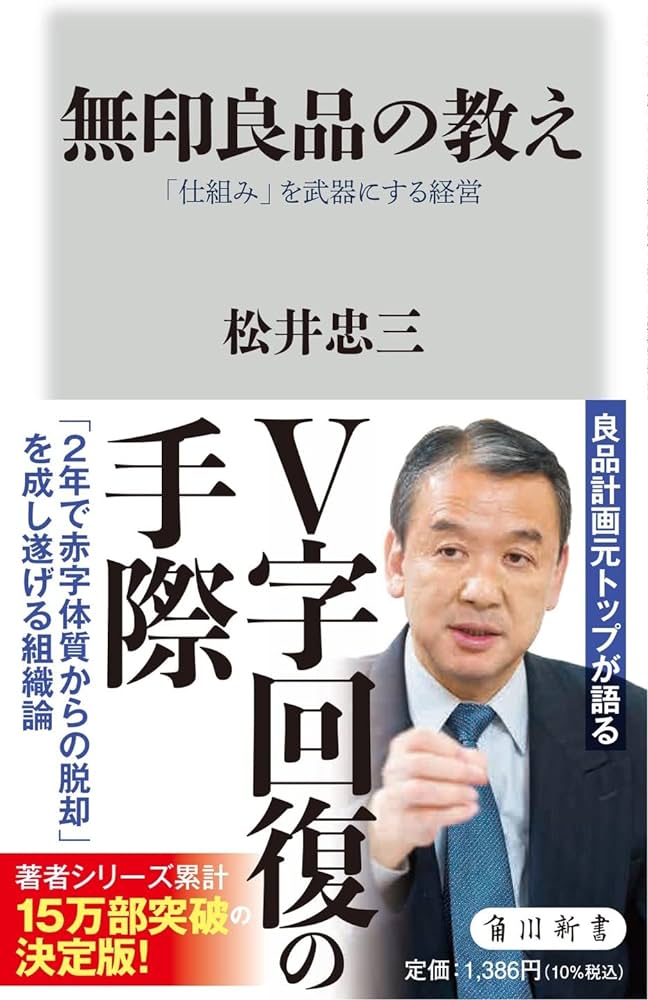
■株式会社KADOKAWA
公式HP(文庫):https://kadobun.jp/special/gakugei/#offcanvas
公式X(角川ソフィア文庫)(旧 Twitter):https://twitter.com/kadokawagakugei?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
松井忠三『無印良品の教え 「仕組み」を武器にする経営』角川新書(2021年)を読む。
僕は前回の記事で生産性と労働時間について少し考えた。
ヒントを得るために、次に僕は民間企業の創意工夫に関して読み漁ってみた。
本書はタイトルの通り、「無印良品は仕組みが9割」という具合に語られている。
V字回復の最たる要因は「仕組み」にあったとのこと。
無印良品はヨーロッパにも出店しているとのことで、無印はラテン系の労働観に影響を少なからず受けてる。
「この仕組みで生産性を3倍にできる」という章では、社員を18時30分に帰宅させることにしていると書いてある。
ラテン系の人たちは往々にして食事やプライベートを存分に楽しむという。
著者は、これが人生にとって重要なことなのではないか、と感想を漏らす。
『ドイツではそんなに働かない』では、日曜日にはスーパーなどを閉めていると書かれていた。(閉店法)
以下は個人的な感想である。
やはり、日本は「精神論」が抜けきっていないようにみえる。
プライベートで何をしようが、食事がどうであろうが、結局は「本人のやる気や能力次第だ」という価値観が残っているのかもしれない。
「うつは甘え」
これはその典型ではないだろうか。
平均的に、働きすぎて日本人は勉強する時間がない。
そして生涯学習の意欲もない。
生産性のない長時間労働の悪循環。
これがいつまで経っても変わらない (ようにみえる) 日本の労働観ではないだろうか。
つづく
公開日2022-04-10