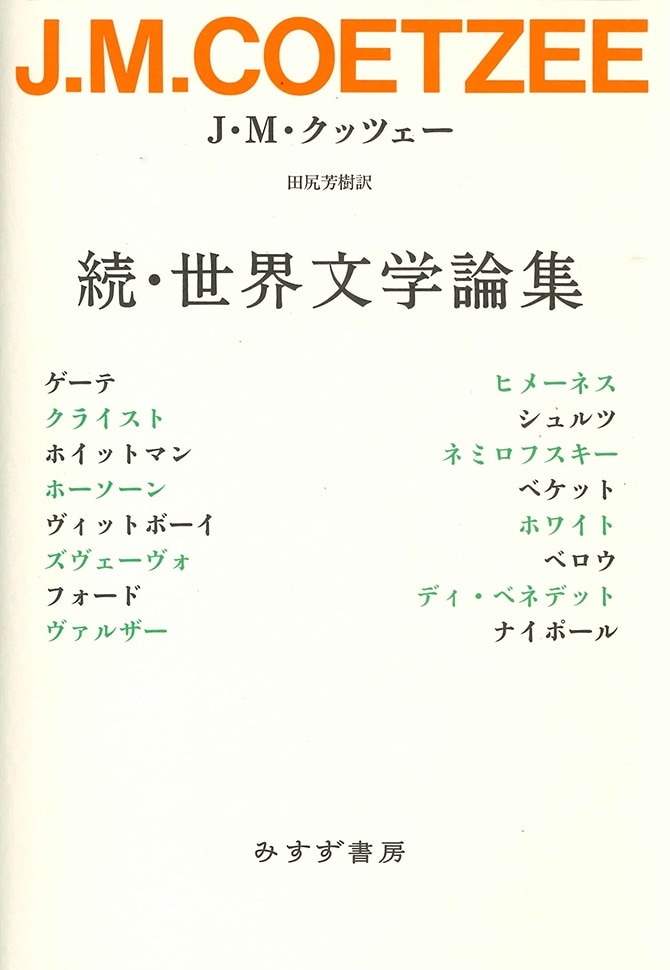
■株式会社 みすず書房
公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社新潮社
公式HP:https://www.shinchosha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/SHINCHOSHA_PR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『言語はこうして生まれる: 「即興する脳」とジェスチャーゲーム』
メモ
・普遍的共鳴説
“この説によると、世界のあらゆるものの属性と、それを呼ぶのに人間が用いる音のあいだには普遍的な調和(もしくは共鳴)が存在する。具体的にいうと、たとえば小さなものをあらわすのには、口の前方に舌をもっていって、発音される母音がよく使われ(teeny-weeny)[ ちっちゃい、ちょっぴり ] のように)、大きなものをあらわすのには口の後方で発音される母音がよく使われる(humongous [ ものすごくでかい ] のように)。” P129
“一九世紀の文献学者でオックスフォードの学監であったマックス・ミュラーは普遍的共鳴説に少々傾いたあと、こう述べている。「私の唯一の疑いは、この一つの説明だけに拘泥してよいのかどうかだ。川はこんなに大きく、広く、深いのだから、言語も源流が一つだけだとは限らないのではないだろうか」” P130-1
本書によると19世紀の言語学は非科学的な手法であったため、どの説も部分的に納得できるものであったが、行き詰まりを迎えた。そのあとにチョムスキーが登場。
“それは、言語学を生物学の一分野と見なすことだった。” P132
・チョムスキー「普遍文法」について
”(・・・)すべての言語は本質的に同じであると結論できたのだ。” P137
“人間の言語の本質は、遺伝的にコードされている。” P137
しかし、現実はそう甘くなかった。
世界のあらゆる部族を対象とした研究では、この想定が通用しなかった。
”その結果として見つかったのは、ただ一つの普遍的なテーマと無限のバリエーションではなく、際限なく出てくる奇妙であっぱれな、いちいち新しい情報伝達のしかただった。” P138
・・・
言葉は奥が深い。
自分は帰り道、なぜ文法が規則的に働く集団とそうでない集団がいるのかを検討した。
これを書くと池田晶子にがっかりさせてしまうかもしれないが、まず文法は「道具」として機能するものだと自分は解釈した。
端的に言えば「チャンク化」。
「education」は1チャンク。
「ivprpyhtg」は9チャンクある。人間のワーキングメモリーでは7~10くらいがせいぜいの限界である。
単語をチャンク化したうえでさらに「文法」までもチャンク化する。
そうすることによって長文がチャンク化され、物語化され、低チャンク化されるので情報の交換、目的の遂行が可能になる。そう考えればいいのではないか。
・・・
言語はやはり往々にして不安定で、意味が不確定である。
問うべきは言語を超えた世界である。
つづく