新・読書日記293(読書日記1633)
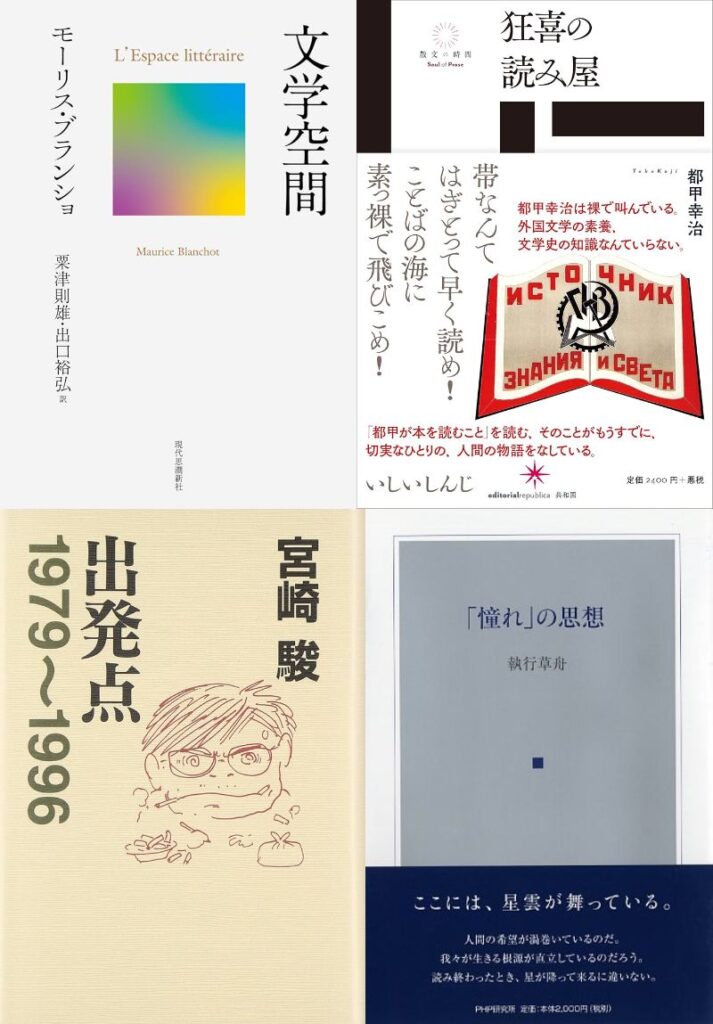
■株式会社現代思潮新社
公式HP:http://www.gendaishicho.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://x.com/gendaishicho
■株式会社徳間書店
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/tokumashoten_pr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社PHP研究所
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/PHPInstitute_PR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社共和国
公式HP:https://www.ed-republica.com/
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/naovalis
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
本が20パーセントなので今日はブックオフを二店舗まわった。
池田夏樹個人編集の世界文学シリーズでトマス・ピンチョンの本があったが、値段が高く、買うのをやめた。
たまにほぼ定価の本がある。これには参る。トーマス・マンの日記もあった。これも欲しくなったが、Amazonのほうが明らかに安く、これもやめた。
お得感がないと買う気になれないのがブックオフだなと思い、なにか良い本はないかとまわって、まわったあげく、『狂喜の読み屋』という面白いタイトルの本を見つけた。
この人の別の本も以前ブックオフで買ったことがある。定評もあり、内容的にも良かったので買って帰った。
翻訳の世界も相当に厳しいことが読んで伝わった。
読み屋という、翻訳する本を決めるための仕事があるらしい。
原文で読み、読んで感じたことなどを端的にレポートする。そして担当者がGOサインを出せば商業用として出版される。
しかしほとんどは採用されない。給料も安い。
ようやく翻訳の仕事をもらったとて、一回きりでは食っていけない。
ブコウスキーも作家で食えるようになったときには50代になっていたと書かれていた。
一冊一冊にどれだけの苦労があるのかを改めて思わされるが、売れる本と価値のある本が比例することもないのが本の奇妙なポイントでもある。
だいたいどこのブックオフも220円コーナーに落ちるような本は決まっている。岩波文庫なんかはもはやどこへ行っても必ず見かける本がある。売れない本ランキングを見ているようで若干悲しくなってくる。(とはいえ、それはブックオフでは売れないという意味で、実際は売れているのかもしれないが)
・・・
『文学空間』
メモ
“芸術はひとつの目的を持つ、芸術とはこの目的そのものなのだ。それは、精神を行使するための単なる手段ではなく、もしそれが作品でないならば何ものでもないところの精神である、ところで、作品とは何か?” P111
ブランショ「作品とは精神における無限なるものの実現に他ならない」
ブランショは文体・文章表現が複雑怪奇ではあるが、案外シンプルなことも書いていて、それが分かるとちょっとスッキリする。
・・・
『「憧れ」の思想』
“小林秀雄は、かつて私に「知性は勇気の下僕である」と語った。知性とは勇気があってこそ、初めて意味をなすものだということだ。” P179
“文学の使命は、永遠に向かう憧れを描くことにあると私は思っている。偉大な文学が、偉大な国家や文明を築き上げるという意味のことを内村鑑三が言っていた。” P182
⇒『イリアス』『オデュッセイア』『詩経』『楚辞』『古事記』『万葉集』
しかし時に辛口になる。
“「存在の使命」の障害となるものは安定・安全・幸福であり、それらが生命の停滞を招いているのだ。” P191
⇒字義通りに解釈してはいけない。この文章について踏まえておくべきことのひとつとして、プラトンのいう徳のある状態が挙げられる。勇気と野蛮を対比してみよ。前者は知識や経験があるので目の前の危険、状況に対して安定、安全である。後者は不安定、危険になる。
小林秀雄は単なる知識よりもプラトン的な徳のほうを重視していたと分かる。(あくまで推測ではあるが)
・・・
宮崎駿がどんな本を読んでいたのかこの本にいろいろと書かれている。
今日はあまり時間がなかったが、歴史ものが多い印象があった。また、新書ばかり読んでいる(とみなされてしまう)世代もあったと書いてあった。
宮崎駿の若いころと現代では明らかに読める本が増えている。新書も気が付けばとんでもない数に増えている。
選択肢が増えすぎるとかえって不自由になるというのがお決まりの逆説であるが、果たしてこの書物が膨大に溢れる今日はディストピアか、ユートピアか。
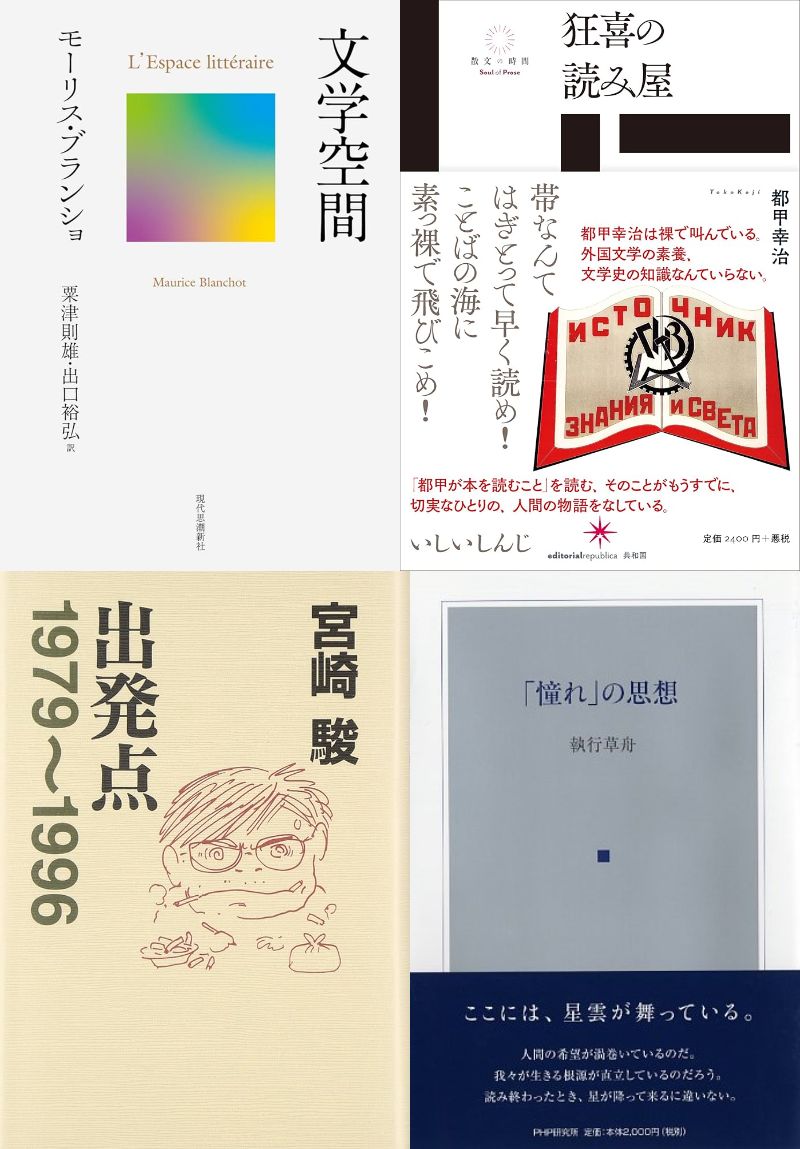
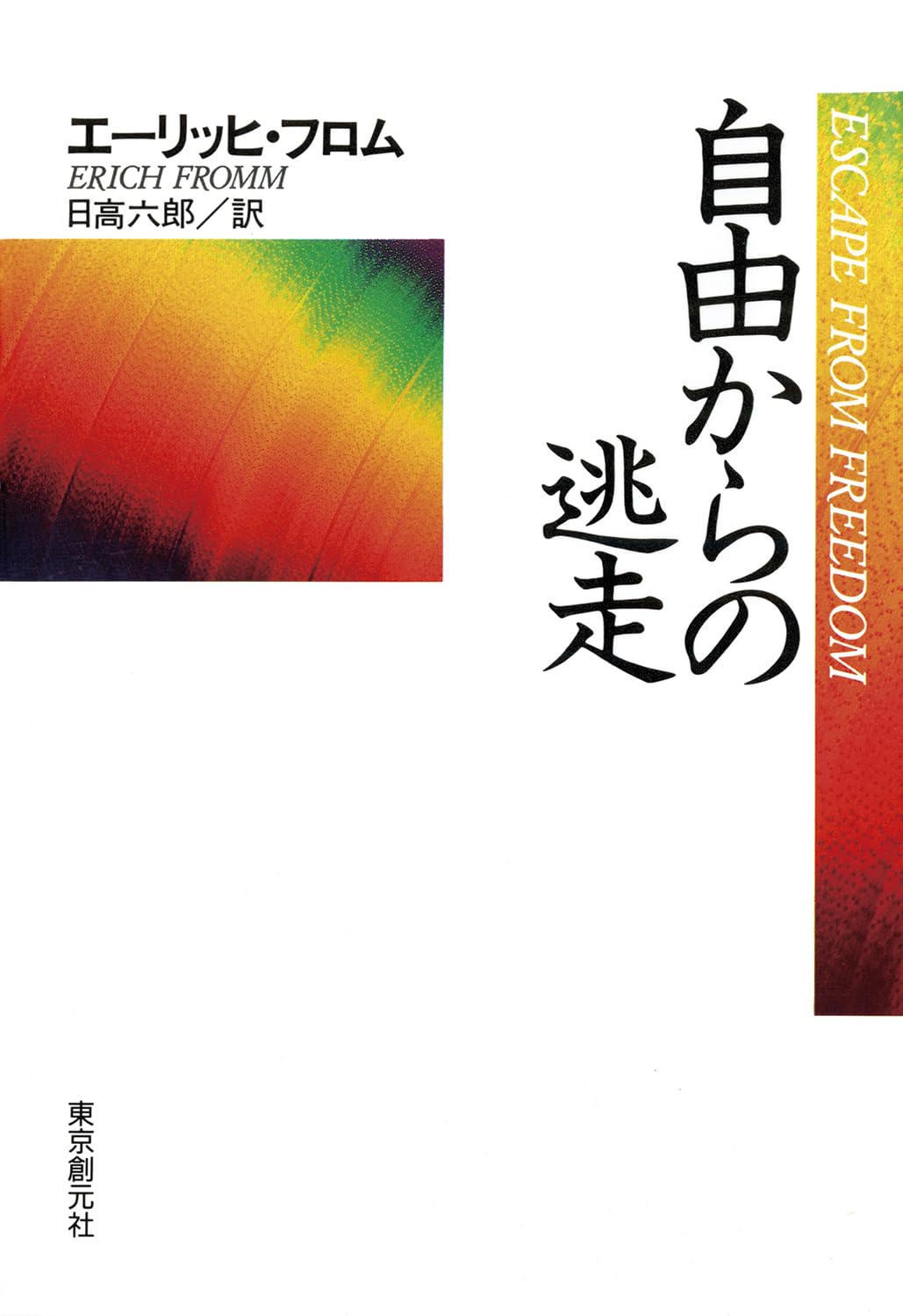
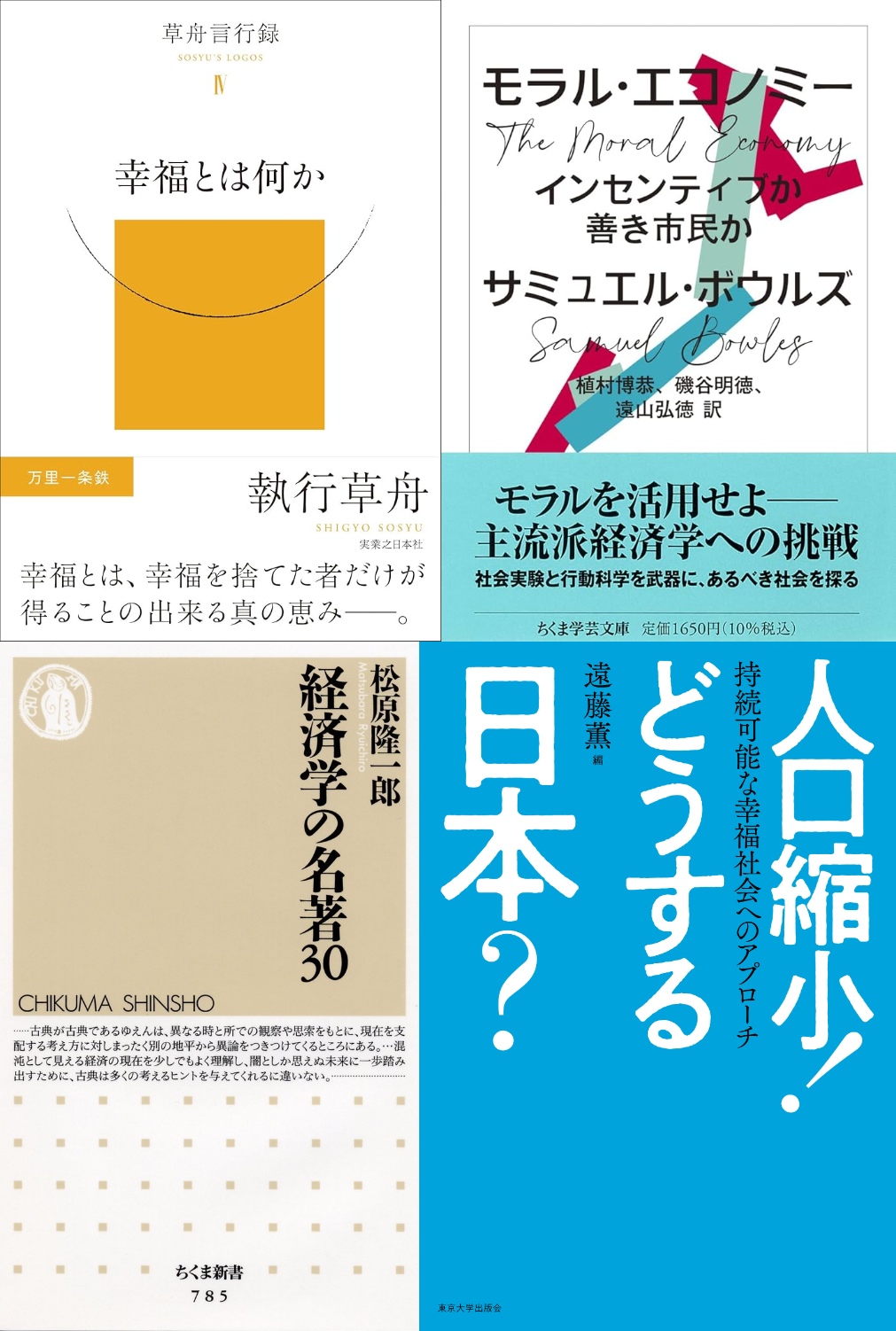
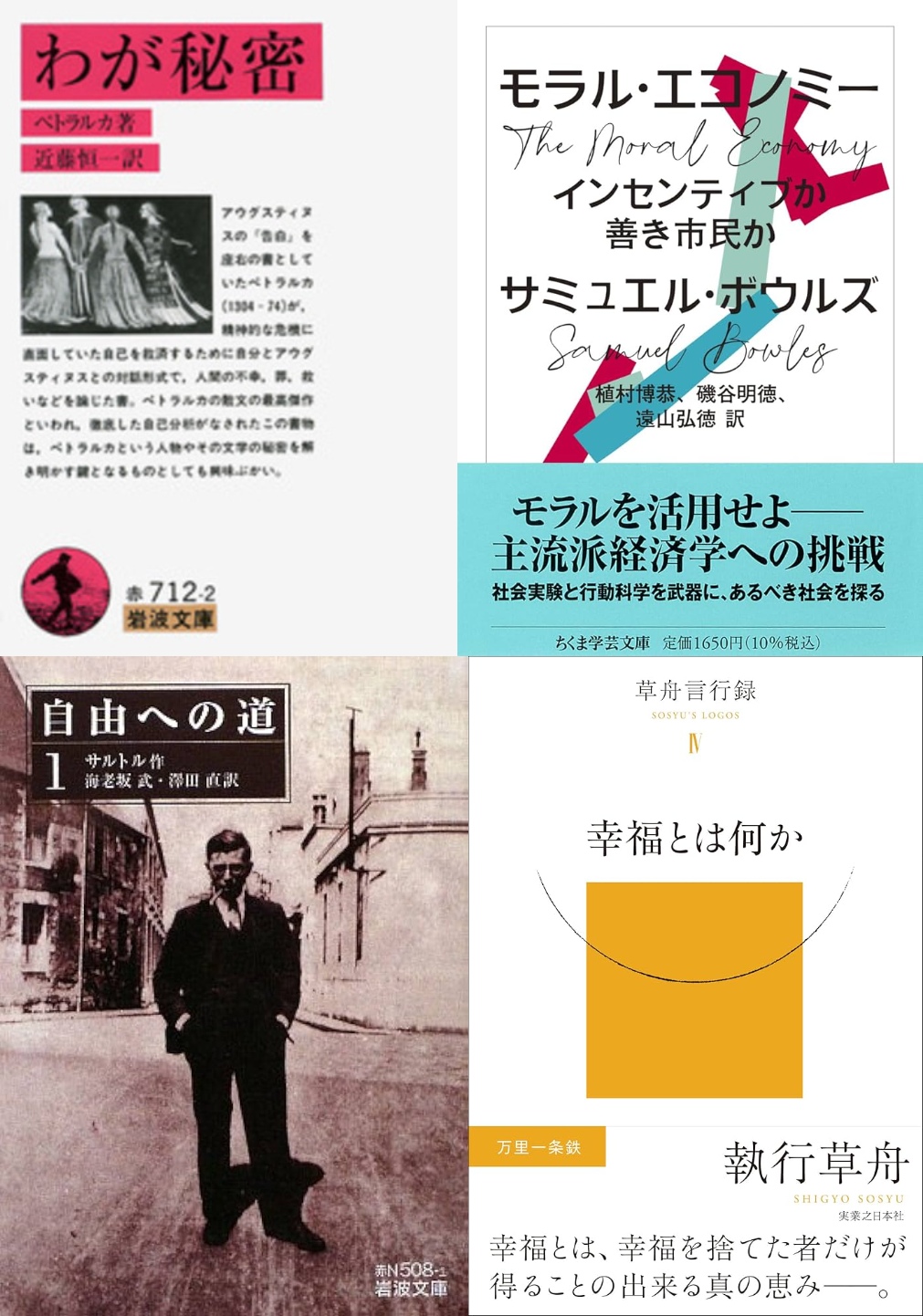
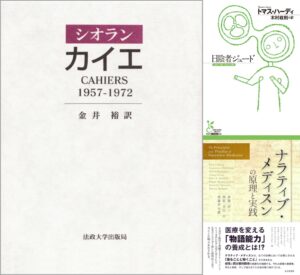

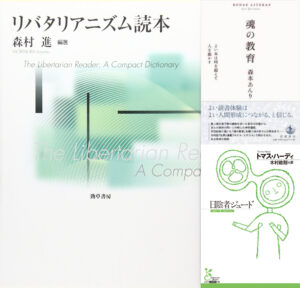
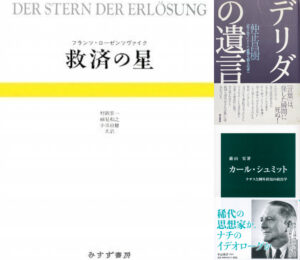
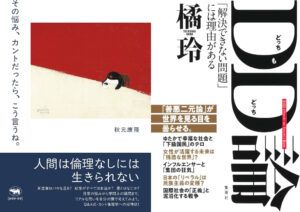

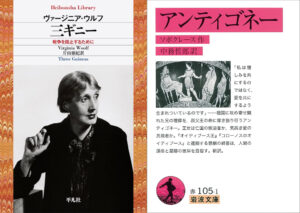
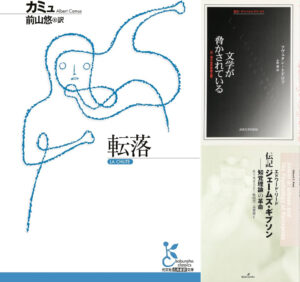
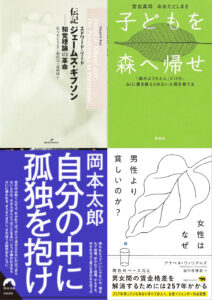
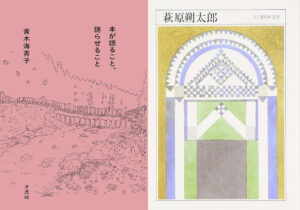
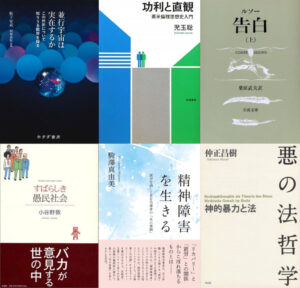
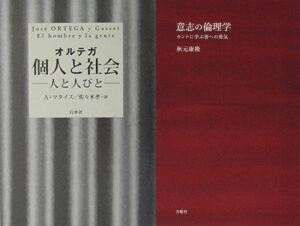
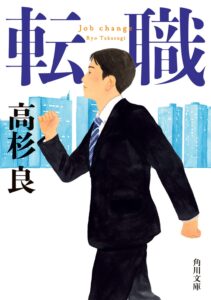
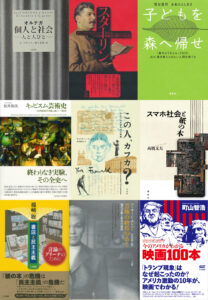
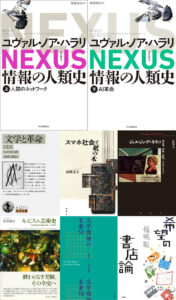
コメントを送信