青木海青子『本が語ること、語らせること』読了+新・読書日記425(読書日記1765)
■夕書房
公式HP:https://www.sekishobo.com/
公式X:https://x.com/yuuka_tkmts?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社筑摩書房
公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
感想
170ページほどの比較的薄い本だったがあっという間に引き込まれ、結局最後まで読んでしまった。図書館を訪れる様々な人との対話の記録がこの本に凝縮されている。本のおすすめの仕方が著者の見識の深さ、物事を視る視野の広さ、人間味の深さを思わせる。「自分の意見というものがなく、自分の考えを持ちたいけれど、どうすればいいのか」といった質問にプラトン『プロタゴラス』を持ち出すところがまたいい。時代はソフィストを求めるが、書物として生き残り、影響を与え続けているのはソクラテスだった、ということまでは『プロタゴラス』を読んだだけでは伝わらないかもしれないが、プロタゴラスを最後まで読めば「獲得するための知」がいかに無意味なものか、空しいものか分かるかもしれない。そして、往々にして「自分の考え」というものがこの「獲得するための知」であるということまでは『プロタゴラス』を読んだだけでは伝わらないかもしれないが、この『本が語ること、語らせること』を読めばのちのち人生のなかできづくきっかけにはなるかもしれない。この本の全てについてここで書くことは出来ないが、この本を買ってよかったと自分は思う。この本がきっかけで萩原朔太郎を真面目に読んでみようと思えたからである。
新・読書日記425(読書日記1765)
メモ
“私の詩を読む人は『聖書』をよむやうな心持で、書いてある文字の通り正直に読んでもらひたい。私は自分の思想や哲学や概念を、少しも他人に知らせたいとは思って居ない。またそんなものには自分でも更に価値を認めて居ない。私はただ私の『感情』だけを信じて居る。『感情』そのものが私の生命である。それさへ完全に表現することが出来ればそれで私の目的は達したのである。” P223
“(・・・)ドストイエフスキの人格は、神と悪魔の著しい対立から成立している。(・・・)同様なる非論理的事実が、トルストイやニイチエや、その他多くの芸術的天才について観察される。実に芸術家の本質的性格は、論理的矛盾の標本である。” P226-227
萩原朔太郎の本を堪能しきったあとに、隣の席から「仕事しなくていいなら一日中ゴロゴロしていたい」という声が聞こえてきた。エン転職だとか、履歴書だとか、転職に関するワードが断片的に聴こえてきた。感覚過敏とまでは自分はいかないが、さすがに読書中にそういったワードは耳に入ってしまう。一日中ゴロゴロしていたいなら、いま何故ゴロゴロしないのかと突っ込みたくなった。また、そんなにゴロゴロしたいなら仕事をやめてゴロゴロすればいいじゃないかとすら思ってしまった。ちょっとイライラしてしまったのかもしれない。スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』では、ヴァージニア・ウルフが「争い、競争、闘争といったものに女性はまったく価値を感じない」と返答(どうしたら戦争を回避できるか?と男性弁護士からの手紙に対して)した話のことが書いてあるが、女性は本質的に競争に興味がないなら、管理職に女性が少ないのは構造のせいもあるだろうが、むしろそれが本質なのではと、うっすら思ってしまった。これ以上書いたらフェミニストから攻撃されそうなのでやめておきたい。
つづく
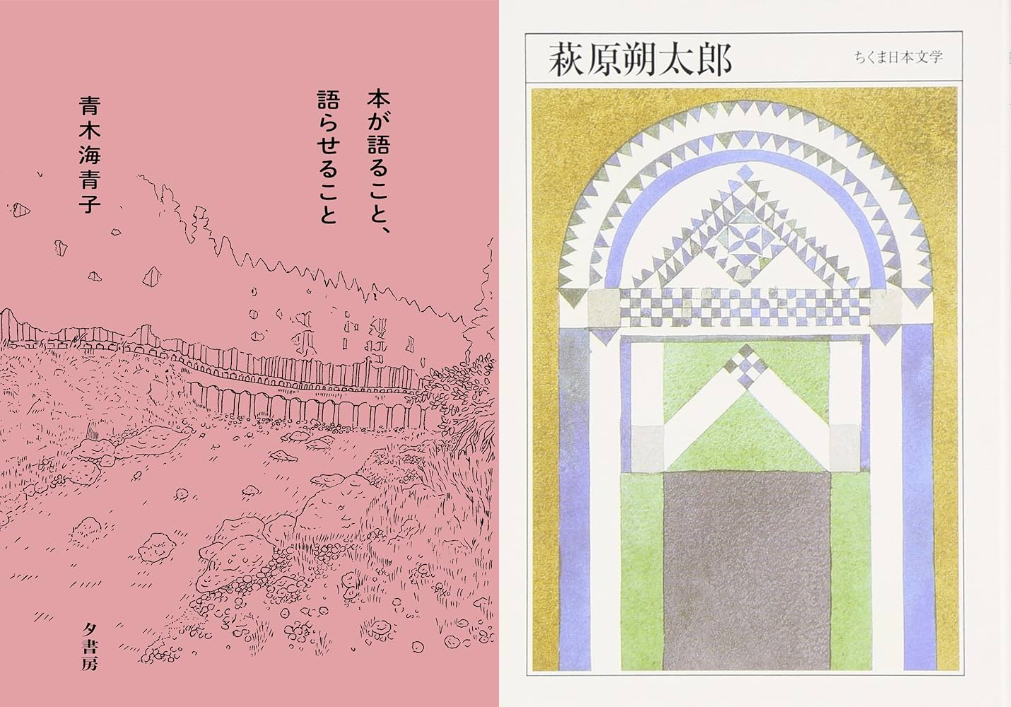
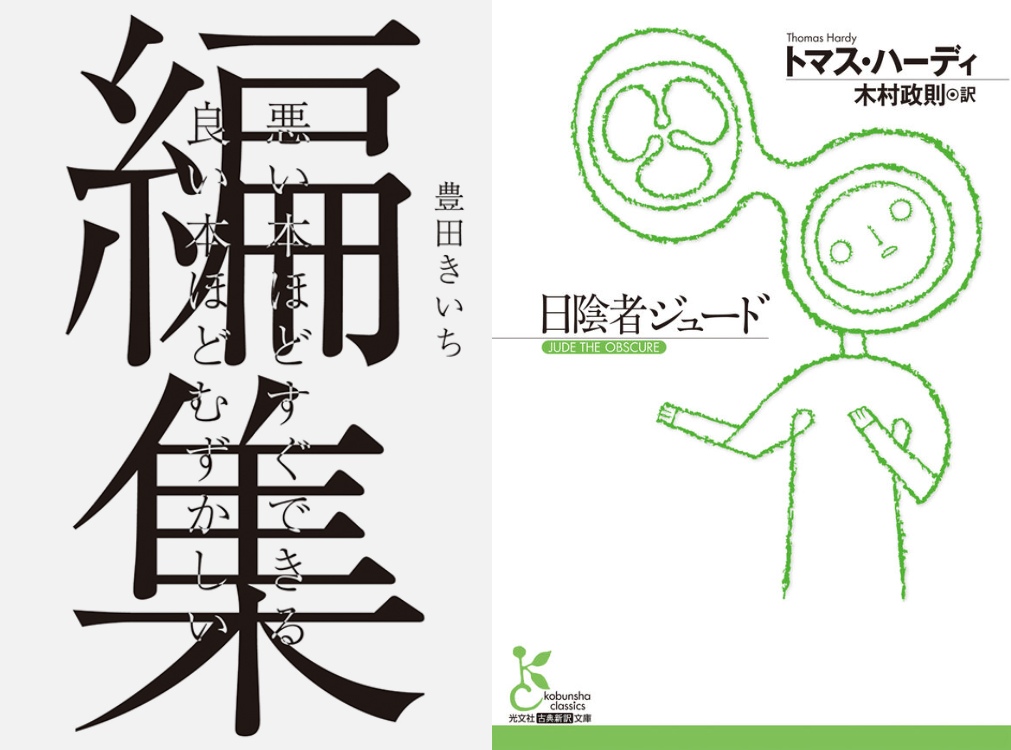

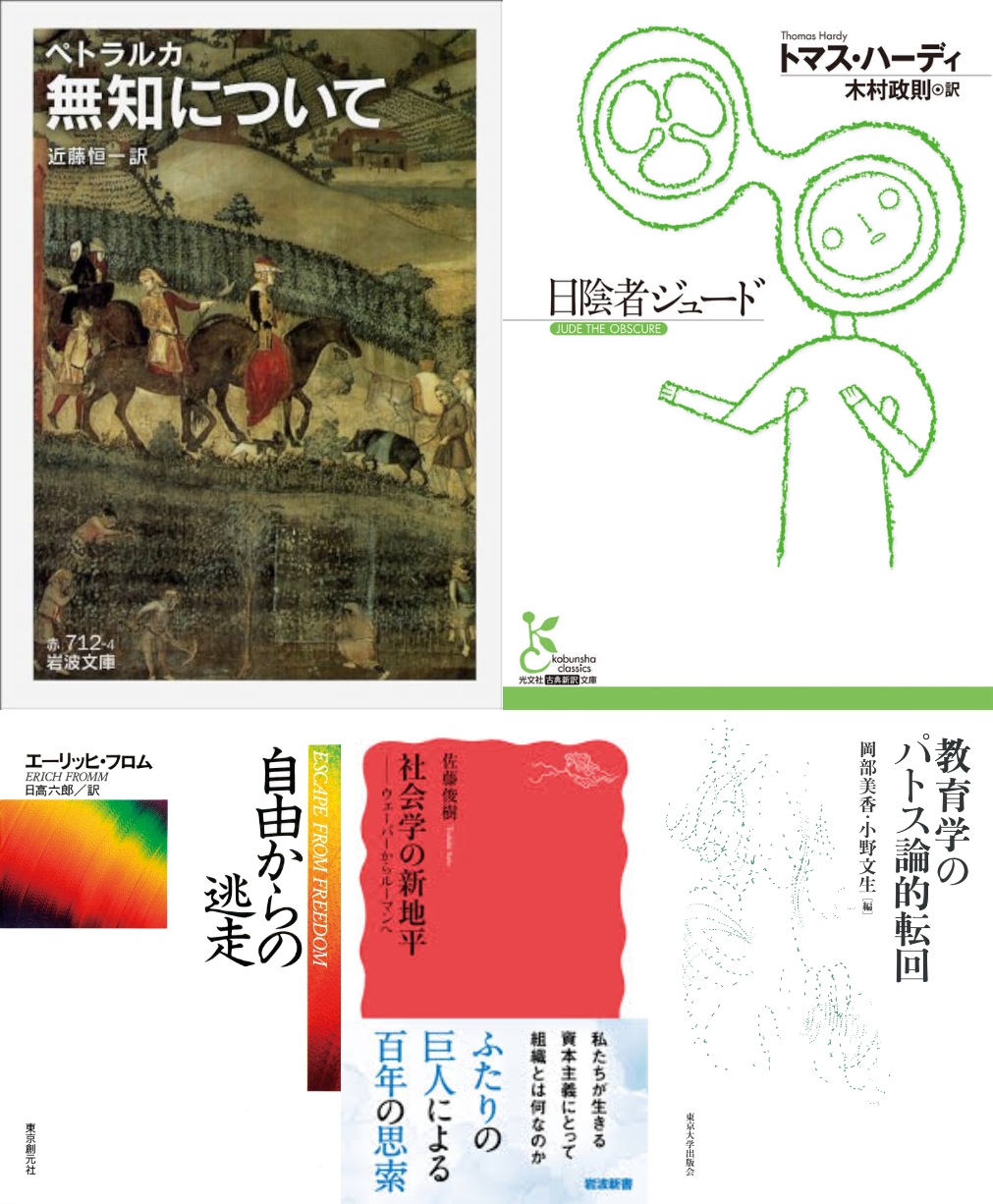
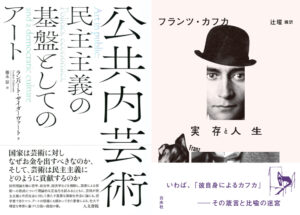

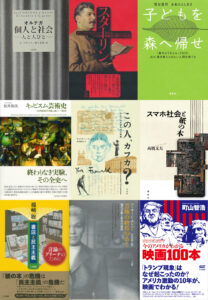
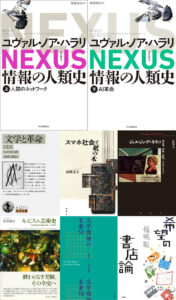
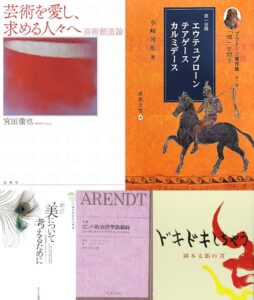
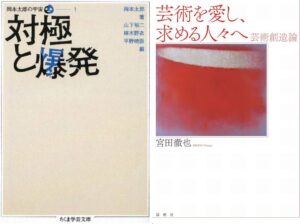
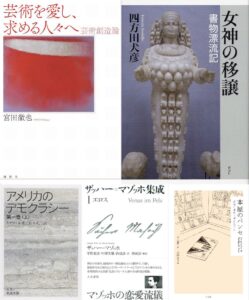

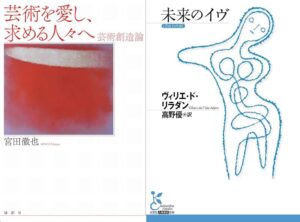

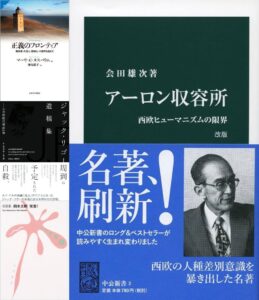
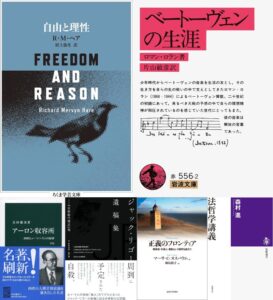

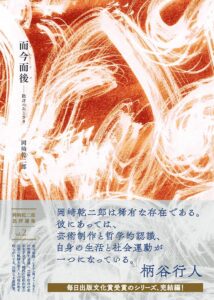
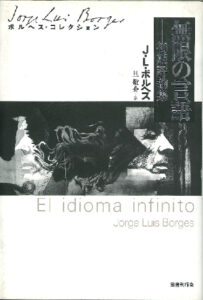
コメントを送信