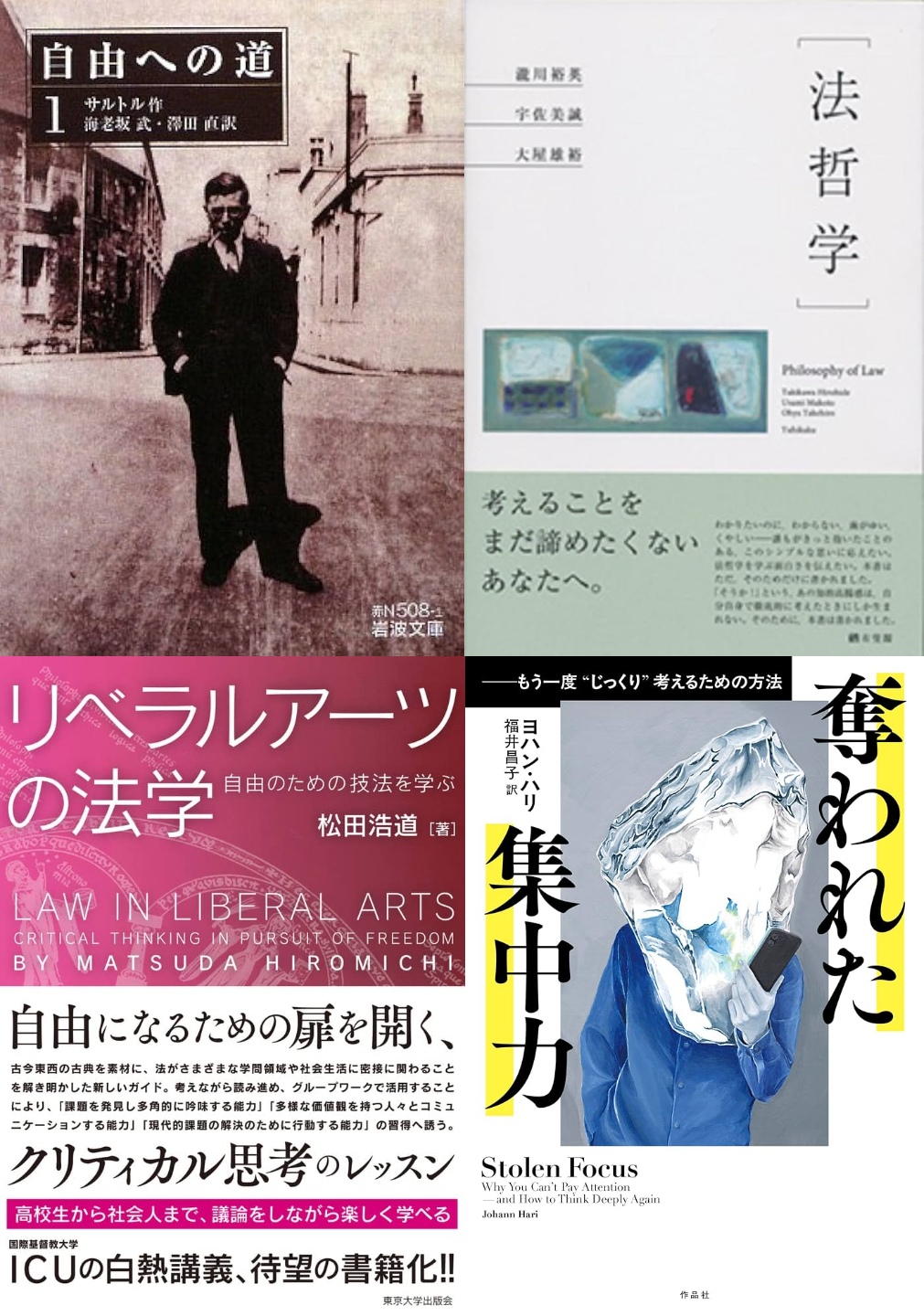■一般財団法人東京大学出版会
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社作品社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/sakuhinsha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社有斐閣
公式HP:https://www.yuhikaku.co.jp/
公式X:https://x.com/YUHIKAKU_eigyo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
メモをいくつかの残し、モヤモヤして今日考えたことをChatGPTと話し合ってみた。さきにメモを、最後にChatGPTとの対話を記す。
・・・
『奪われた集中力』
バズるスピードは年々早くなり、忘れ去られるスピードも早くなっているとのこと。
『法哲学』
厚生主義に対するいくつかの批判
健常者のAさん、半身まひのBさん
➡Bさんの生活レベルは相対的に下がる、よってBさんへの障害給付は正当化される
Aさん「ビールがあれば満足」
Bさん「シャンパンがあれば満足」
➡厚生主義は生活の満足度、充足性に焦点を当てるため、高価なものと安価なものが同等に扱われる
➡”厚生の平等は、本来考慮に入れるべきでない情報まで考慮に入れてしまう。” P100
・・・
満足の障がい者Aさん
不満の健常者Bさん
➡不満足のBさんのためにAさんの財をBさんに移転させることを、厚生主義は正当化させる
➡”厚生の平等は、Bの福祉をAの福祉と同等レベルに引き上げるべく、AからBへの財の移転を正当化する。” P101
・・・
ChatGPTとの対話
経済学の初歩を教えてください。自由経済のなか、福祉や医療の分野では自由競争のなか給付金・補助金が出る一方、大多数の産業ではなにも給付金はありません。どういった線引きがあり、どんな理由、意義があるのでしょうか。経済学では補助金をどういったものとして捉えていますか。
ChatGPT:
経済学では、補助金(subsidy)は「市場の失敗」を是正したり、社会的に望ましい活動を促すための政策手段として捉えられています。以下、なぜ福祉・医療分野で手厚く、他産業では限定的なのか、補助金の線引きや意義について整理します。
✅ なぜ福祉・医療で補助金が多いの?
- 社会的に価値の高い「メリット財」
教育・医療・福祉は個人だけでなく社会全体への恩恵(正の外部性)が大きいため、政府が価格を下げて利用促進する必要があります elibrary.imf.org。 - 市場の失敗(不完全情報・独占的構造)
医療では患者は医療の質を見分けにくく、結果的に過少供給になりやすい。補助金や制度介入で適切な供給を目指します 。 - 所得格差への対応(再分配)
低所得層が高額な医療費を自己負担するのを防ぎ、社会的公正を担保するため、給付・補助制度があります 。
☑ 一般産業には補助金が少ない理由
- 市場メカニズム重視
一般産業は競争が効いていれば、市場が効率的に資源配分を行います。政府介入は価格をゆがめ、市場効率を損なう可能性があります 。 - コストと機会費用が大きい
補助金は税金から支払われるため、別の公共財やインフラに使える資金が減少します 。 - 政治的・圧力的理由
特定の企業・業界への政治的配慮(ロビイング)による偏向もあり、効率的ではない支出につながる危険性があります 。
🎯 線引きの原則と経済学的視点
| 分野 | 線引きの理由・目的 | 補助金の意義 |
|---|---|---|
| 福祉・医療 | 社会的外部性が大きく、所得によるアクセス格差を解消 | ・マーケットの不完全性補填<br>・公平性の確保 |
| 一 般 産 業 | 競争が働けば市場で自然に価格調整が起きる<br>過剰介入で非効率に | 市場競争で自然解決、政府は規制や税制で支援 |
🧠 経済学は補助金をどう見る?
- 修正政策(Pigouvian subsid)
外部効果や公共財の供給不足を是正するため、理論的には有効な手段です lifestyle.sustainability-directory.com+6elibrary.imf.org+6oecd.org+6en.wikipedia.org+3investopedia.com+3elibrary.imf.org+3numberanalytics.com。 - 「幼稚産業」保護
新興産業が国際競争で育つまで一時的に支援するのは理にかなっています 。 - 効率とのトレードオフ
理想的条件(完全競争・情報が完全)では補助金は不要ですが、現実の不完全市場では「第二ベスト理論」によりしばしば補助的役割が支持されます 。 - リスクと代償
補助金による市場ゆがみ、税負担の不正利用、ロビー圧力による非効率など、副作用の管理が常に課題です 。
📝 まとめ
- 補助金は「何に・どれだけ」出すかが重要。外部性・不平等・公共性が強い分野では経済学はその必要性を認めています。
- 一方で無差別な補助は非効率・歪みを招くため、対象と期間を慎重に設計する必要があります。
- 純粋自由市場に反するが、現実の不完全性下では有効な調整手段として位置づけられ、経済政策における「手段の一つ」として経済分析で扱われます。
さらに詳しく知りたい分野があれば、例えば「医療の補助金設計」や「農業補助金の国際比較」など、教えてください!
情報源
あなた:
経済用語の整理をさせてください。社会的外部性とマーケットの不完全性がよくわかりません。
ChatGPT:
社会的外部性と市場の不完全性、どちらも“市場が効率的に働かない状況”を説明する重要な概念です。以下で整理していきます。
1️⃣ 社会的外部性(Externality)
定義
ある経済活動が、取引当事者以外の第三者に意図せず影響(メリットまたはデメリット)を与え、その影響が市場価格に反映されていない状態です。tutor2u.net
| 種類 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 負の外部性(例:工場の大気汚染) | 生産者・消費者はそのコストを負担せず社会に負担を押し付ける | 過剰生産・過剰消費へ → 非効率 economicshelp.org+6britannica.com+6tutor2u.net+6 |
| 正の外部性(例:ワクチン接種、教育) | 社会全体が得る便益が価格に反映されておらず、供給不足に繋がる | 市場での供給不足 → 税金や補助による解決が望ましい |
意義
負の外部性には課税(Pigouvian tax)、正の外部性には補助金(Pigouvian subsidy)を通じて、社会全体の効率を高める政策が経済学上推奨されますeconomicshelp.org+7en.wikipedia.org+7imf.org+7。
2️⃣ マーケットの不完全性(不完全市場)
定義
理想的な「完全競争市場」の条件が満たされない市場のことです。条件とは、無数の売り手・買い手、均一商品、完全情報、自由参入・退出などen.wikipedia.org+2investopedia.com+2investopedia.com+2。
具体例と影響
- 独占・寡占:売り手が価格をコントロールできる。競争が弱く価格が高止まり。
- 情報の非対称性:売手と買手で情報量に差があり、質の低い商品しか出回らない(レモン市場)などen.wikipedia.org。
- 参入障壁:新規企業が入りにくく競争が働かない。
これらの状況では、資源配分が非効率になる「市場失敗(market failure)」が発生しますinvestopedia.com+3en.wikipedia.org+3investopedia.com+3。
3️⃣ 両者の関係と比較
| 観点 | 社会的外部性 | 市場の不完全性 |
|---|---|---|
| 原因 | 取引以外の人に影響が及ぶが、そのコスト・便益が価格に反映されない | 完全競争の前提(情報の完全性、参加自由など)が崩れる |
| 市場への影響 | 負の外部性 → 過剰、生産や消費の矛盾<br>正の外部性 → 不足、社会便益損失 | 価格歪み、選択肢の減少、品質低下など、市場の非効率を招く |
| 政府の介入方法 | Pigouvian tax/subsidy、規制、補助金制度など | 独占禁止法、公正取引、規制緩和、情報開示の義務付けなど |
| 市場失敗の結果 | 社会的厚生の損失(デッドウェイトロス) | 価格・数量・品質に歪みが生じ、社会全体の効用が最適からずれる |
4️⃣ なぜこれらが大切か?
- 社会的外部性と不完全市場は、ともに 自由市場だけでは解決できない「市場の歪み」 の源泉です。
- 経済学では、理論的には市場は効率的でも、現実には様々な障害があり、政策による調整が有効 と考えられます。
- 補助金や課税、規制や情報公開義務は、これらの欠陥を補い、「第二ベスト」的なアプローチとして位置づけられています。
5️⃣ イメージしやすいお話し
- 工場が排煙→近所の空気が汚れる → 本来は工場が治す(Pigouvian税で汚す量に応じて課税)auditingaccounting.comen.wikipedia.org+1economicshelp.org+1。
- ネット通販で初めての購入→商品に自信がない → 情報不確実。返品保証、レビュー制度などが市場の信頼性を支えます。
✅ まとめ
- 社会的外部性:第三者へ無意識に影響を与える構造で、市場価格がそれを反映しない。
→ 負の影響が強ければ課税、正の影響が強ければ補助が入る。 - 不完全市場:完全競争の仮定が崩れた市場で、価格・品質・供給に歪みが生じる。
→ 独占規制や情報整備などで競争環境を改善。 - 両者とも 市場任せでは最適配分に至らない 問題であり、政府・政策による調整が必要とされます。
ご質問ありがとうございます!さらに「具体的な政策事例」や「補助金の設計理論」など、ご興味があればご案内します😊
情報源
あなた:
政府・政策による調整が必要と判断するのは誰でしょうか。
ChatGPT:
経済学で「政府や政策による調整が必要」と判断されるのは、以下のような多層的なプロセスと主体によって行われます:
1️⃣ 経済学者(専門家)による分析
- 市場の働きをミクロ経済学や公共経済学などの理論で評価し、「外部性」「不完全競争」「情報の非対称性」「公共財の不在」など、市場失敗の有無を判別します en.wikipedia.org+2uw.pressbooks.pub+2policymattersinc.org+2。
- 比較可能な実証研究やケーススタディを使い、政府介入(課税、補助金、規制など)が効率性と社会的厚生を高めるかを検討します 。
2️⃣ 政策立案者(政治家・官僚)
- 経済学者の分析や提言を受けて、内閣府や財務省などが、具体的な政策方針(例:環境税・教育補助・独占禁止措置)を策定&実施します 。
- 同時に、公選される議会がその政策を審議・批准し、社会のニーズや価値観に照らして政策を調整します。
3️⃣ 意思決定プロセスと主体
- **Public Choice(公共選択理論)**の観点では、政治家・官僚・有権者それぞれが「合理的に自己利益を追求するプレイヤー」であり、これらに基づく意思決定のゲーム分析が行われます wired.com+15en.wikipedia.org+15cato.org+15。
- 経済学者の提案通りに介入すべきかどうかは、「政府介入による便益」>「政府の失敗や副作用(ロビー圧力、誤った情報、不適切なインセンティブなど)」となるかどうかで評価されます 。
4️⃣ 政府失敗(Government Failure)の考慮
- 政府の介入も万能ではなく、逆に社会的厚生を損なう「政府失敗」が起こりうることが経済学でも指摘されています 。
- 政策の有効性を評価するため、コスト=ベネフィット分析や実証データの活用と共に、官僚・政治家の情報不足・目的のずれ・行政コストなども厳しくチェックされます 。
5️⃣ プロセスのフロー
- 市場・経済データの観察 → 2. 専門家(経済学者)による市場失敗の識別 →
- 政策立案(官僚・政治家) → 4. 議会での審議・採決 →
- 実行(課税・補助金・規制など) → 6. 評価とフィードバック(成功/政府失敗の分析)
✅ 要点まとめ
- 誰が判断するか:経済学者や政策立案者(官僚・政治家)が中心。最終的には議会と有権者の承認を経て実現。
- どうやって判断するか:「市場失敗があるか」「政府介入はより良い成果を生むか」を理論と実証で判断。
- 注意点:「政府失敗」による逆効果を最小化するため、継続的な評価と改善プロセスが不可欠。
政府の介入は「万能」でも「理想通り」でもなく、専門分析+政治選択+実証評価の積み重ねによって初めて『必要』とされ、その後も効果と副作用を管理し続ける動的な仕組みです。
さらに「公共選択理論」や「政府失敗」のメカニズム、具体的制度設計に関心があれば、ぜひお知らせください!
情報源
あなた:
淘汰されていない仕事・ビジネスは、全て社会的意義がある、は真でしょうか。つまり、、、お互いがお互いを苦しめ合っているような状況があるのかを経済学では認識できていますでしょうか。なかなか難しいのですが、、、生き残っている仕事は無条件に社会的に意義のあることをしていると言えますでしょうか、それとも独占に近いから淘汰されないのか。本屋などがその典型と考えます。Amazonが偏在するあらゆる古本屋を駆逐しているようにみえるのですが
ChatGPT:
はい。ご質問は非常に本質的です。すべての「淘汰されていない」仕事やビジネスが、無条件で社会的意義を持つわけではありません。経済学では、いくつかの重要な概念を通じてその構造を説明できます。
🧟♂️ 「ゾンビ企業」(Zombie firms)の存在
ゾンビ企業とは、収益が利払いすらカバーできず、事実上市場の淘汰を受けるべきなのに存続し続ける企業を指します。
- イギリスや日本など先進国では、利払いができない企業が次々に存続しており、それが資源(労働や資本)を効率的な企業から奪い、産業全体の生産性を下げているとの指摘があります 。
- IMFは「こうしたゾンビ企業の増加は、他企業の生産性を恒常的に引き下げる」と警告しています 。
つまり、淘汰されていないこと=「良い」ではなく、経済成長を阻害している「負の構造」もあります。
ガラパゴス化?守られて残った産業の実例
あなたが挙げた本屋はまさにその典型的ケースです:
- Amazon の出現以降、収益性が低下した多くの独立系書店は淘汰されず、存在し続けていますが、その理由は
1. 地域顧客との結びつき(固定客)
2. レンタルやイベントなどの代替的ビジネスモデル
3. 資金余力や家族経営が利払いで厳しくない
これらは企業が生き残るための**遮蔽(バリア)**が働いている例で、必ずしも「社会全体として価値が高い」とは限りません。
🧠 経済学的整理
- クリエイティブ・ディストラクション(創造的破壊):シュンペーターが提唱。非効率なものが淘汰され、新しいものに資源が移ることで経済成長が進む 。
- 過剰な保護・低金利環境:政府補助や低金利政策は市場の自然な淘汰メカニズムを阻害し、ゾンビ企業を生む要因となる blogs.lse.ac.uk+4bis.org+4reddit.com+4。
✅ 結論
| テーゼ | 経済的視点 |
|---|---|
| 淘汰されない = 社会的意義がある? | ✕ ⇒ ゾンビ企業の存在が示す通り、非効率で害にもなり得る |
| 独占に近いから残っている? | ◯ ⇒ 保護・バリアが働き、競争を避けて存在し続けるケースあり |
| 本屋など文化的価値は? | △ ⇒ 地域・文化的価値はあるが、経済的に効率かは別評価 |
💡 補足と今後
- ゾンビ企業問題:多くの国で注目されており、金融引き締めや倒産制度の現代化(例:日本のM&A活用)が議論されています 。
- 政策への示唆:市場メカニズムと保護とのバランス、政府や金融機関の資源配分のあり方は非常に重要です。
ご指摘の通り、「淘汰されずに残っている=社会的意義がある」は誤りです。経済学はこのような非効率を明示的に認識し、それに対処する政策の策定と評価を行っています。
このテーマに興味がある場合、たとえば「ゾンビ企業がなぜ増えるのか」「倒産制度による構造調整のメカニズム」「創造的破壊と文化保護の兼ね合い」など、さらに深掘りできますので、ぜひ教えてください😊
情報源
あなた:
ありがとうございます。モヤモヤしていまして。これらのことを考えさせられる本、考えるための本がありましたら10冊ほど挙げて頂けると幸いです。
ChatGPT:
以下は、経済の非効率・市場失敗・ゾンビ企業・創造的破壊などを多面的に学べる、示唆深い10冊の書籍リストです。ご関心のテーマに沿って選ばれています。
📘 市場失敗・政府と公共選択
- Government Failure: A Primer in Public Choice(Gordon Tullockほか)
公共選択理論に基づき、政府介入の副作用(政府失敗)を体系的に解説しています amazon.com+1econlib.org+1。 - The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and Competition(Julian Le Grand)
政府サービス提供に市場的な「選択と競争」の仕組みを導入する提案。公共経済学の実務的議論が学べます link.springer.com+11en.wikipedia.org+11en.wikipedia.org+11。
🧟♂️ ゾンビ企業と創造的破壊
- Economics of the Living Dead(Hoshi & Kashyap 論文収録)
日本におけるゾンビ企業を分析し、生産性低下への影響も論じています link.springer.com+1chicagobooth.edu+1。 - Creative Destruction: Business Survival Strategies in the Global Internet Economy(Raul Katzほか編)
シュンペーターの「創造的破壊」をインターネット時代の産業構造に応用した理論と実例の解説書 en.wikipedia.org+8direct.mit.edu+8en.wikipedia.org+8。 - Capitalism, Socialism and Democracy(Joseph Schumpeter)
創造的破壊を提唱した古典的名著。今なお引用され続ける重要文献です en.wikipedia.org+1direct.mit.edu+1。 - The Innovator’s Dilemma(Clayton Christensen)
既存企業がイノベーションに敗れるメカニズムと対策を『破壊的技術』理論で明快に解説 en.wikipedia.org。
📉 金融と市場の崩壊・失敗
- How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities(John Cassidy)
自由市場原理の限界を歴史と実例から描き、なぜ市場失敗が起きるかを解説 en.wikipedia.org+5goodreads.com+5goodreads.com+5。 - The Price Is Wrong: Why Capitalism Won’t Save the Planet(Brett Christophers)
再エネ市場での政府役割と市場失敗の構造を鋭く分析。補助金と政策支援の必要性を論じています arxiv.org+9ft.com+9en.wikipedia.org+9。
💡 競争・独占・市場限界
- The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition(Jonathan Tepper, Denise Hearn)
独占・寡占の実態とその社会的影響を掘り下げた現代的分析書 amazon.com。 - Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society(E. Glen Weyl, Eric Posner)
市場の歪みや不完全性に対応する大胆な制度改革案を提案。経済制度の根本を問い直します fivebooks.com。
🔎 おまけ(応用編)
- Capitalism and Freedom(Milton Friedman): 自由市場と政府の範囲をめぐる古典的論争を学べます en.wikipedia.org。
📊 総まとめ
| テーマ | 主な書籍 | 内容の焦点 |
|---|---|---|
| 公共選択・政府の限界 | #1, #2 | 政策と選好、市場補完の限界 |
| ゾンビ企業と産業構造 | #3, #4, #5, #6 | 非効率の維持と破壊的競争 |
| 市場失敗と金融危機 | #7, #8 | 危機・再エネ・制度的課題 |
| 独占・競争制度の再考 | #9, #10 | 現代資本主義の制度設計 |
これらの書籍は、ビジネスや政策における“残っている仕事や企業”の意義を掘り下げつつ、競争や制度設計の視点から深く考えるための良質な知見を提供します。ご興味ある分野があれば、さらに詳しくご案内できます!

情報源
あなた:
すみません、日本語の本でお願いします。
ChatGPT:
以下の10冊は、日本語で読める「市場失敗」「不完全競争」「ゾンビ企業」「創造的破壊」などを深く考えるのに最適な良書です。それぞれのテーマとおすすめポイントをまとめました。
📘 市場失敗・情報の非対称性・公共選択
- 『非対称情報の経済学—スティグリッツと新しい経済学』(光文社新書)
市場における情報の不完全性・逆選択・モラルハザードの問題を、ノーベル賞受賞者スティグリッツの理論をもとにわかりやすく解説 shohyoubookreview.com+1shohyoubookreview.com+1。 - 『良き社会のための経済学』(日本経済新聞出版)
効率だけなく公平性も重視する経済政策のあり方を、非効率性の判断軸として提示 。
🧟♂️ ゾンビ企業・競争・創造的破壊
- 『日本経済の死角――収奪的システムを解き明かす』(河野龍太郎、ちくま新書, 2025)
日本企業の不健全構造と資源配分の歪みを鋭く分析 retsu-business.com。 - 『ミクロ経済学〈1〉市場の失敗と政府の失敗への対策』(八田達夫)
理論+日本事例で市場失敗とその調整策を丁寧に解説 retsu-business.com+11echosympathy.blog3.fc2.com+11shohyoubookreview.com+11。
🏛 ゾンビ企業・日本経済構造
- 『戦後日本経済史』(猪木武徳、中公新書)
戦後の成長・停滞・制度構造を歴史視点で整理。ゾンビ企業の背景理解に有用 eigo-books.com+1zh.wikipedia.org+1。 - 『戦後日本経済史』(野口悠紀雄、東洋経済新報社)
精度高い時代分析で、バブルや長期停滞の構造的要因を論じる zh.wikipedia.org+6eigo-books.com+6zh.wikipedia.org+6。
🌱 政府と市場の関係
- 『日本の経済政策:「失われた30年」をいかに克服するか』(小林慶一郎)
政策の選択と結果を体系的に分析し、市場失敗と政府対応を検証 zh.wikipedia.org+7frontlab.jp+7zh.wikipedia.org+7。 - 『日本経済30年史:バブルからアベノミクスまで』(山家悠紀夫、岩波新書)
制度転換点と政策決定の流れを把握できる現代日本経済への総合ガイド frontlab.jp+1zh.wikipedia.org+1。
🤖 行動経済・制度設計
- 『NUDGE 実践 行動経済学 完全版』(リチャード・セイラー, キャス・サンスティーン/訳)
人の非合理性を「市場失敗」の原因と捉え、ナッジなどの制度設計理論の理解に最適 alfistanao.com+1globis.jp+1shohyoubookreview.com+3globis.jp+3note.com+3。 - 『リスク、不確実性、利潤』(フランク・H・ナイト)
不確実性と市場での利益の関係を深堀。市場構造を考えるうえで不可欠な古典書 note.com。
📋 書籍一覧
| タイトル | 著者 | ポイント |
|---|---|---|
| 非対称情報の経済学 | — | 情報格差の市場影響を体系的に解説 |
| 良き社会のための経済学 | — | 公平・効率のバランス視点 |
| 日本経済の死角 | 河野龍太郎 | ゾンビ企業と構造課題の現代分析 |
| ミクロ経済学〈1〉 | 八田達夫 | 市場失敗と政府介入の理論と実例 |
| 戦後日本経済史 | 猪木武徳 | 歴史視点から制度・成長・停滞を理解 |
| 戦後日本経済史 | 野口悠紀雄 | バブル崩壊後の構造的課題分析 |
| 日本の経済政策 | 小林慶一郎 | 政策選択とその帰結を学ぶ |
| 日本経済30年史 | 山家悠紀夫 | アベノミクス以前の政策変遷把握 |
| NUDGE 実践行動経済学 | セイラー他 | 行動を含めた制度設計理論 |
| リスク、不確実性、利潤 | ナイト | 不確実性の本質と市場構造理解 |
これらの本を通じて、資源配分の歪みや非効率・構造的硬直の背景とその解決に向けた理論・制度設計を立体的に理解できます。気になるテーマがあれば、さらに詳しくご紹介も可能です😊
情報源
あなた:
ありがとうございます。もう少し専門的な、少し価格帯の高めの本もお願いします
ChatGPT:
以下は、より専門的で少し価格帯の高めな日本語の書籍10冊です。いずれも“市場の歪み”“公共政策”“創造的破壊”“ゾンビ企業”“制度や財政構造”など、学術・実務観点から深掘りしたい方に適した良書です。
🧠 公共経済・市場失敗の理論と制度
- 『スティグリッツ 公共経済学(第3版 上・下)』
ノーベル賞受賞者スティグリッツによる決定版の公共経済学テキスト。厚生経済学、外部性、課税制度から医療・教育・社会保障まで網羅された重厚な一冊。定価4,950円 str.toyokeizai.net+2str.toyokeizai.net+2web.econ.keio.ac.jp+2 - 『<サピエンティア>公共経済学』小塩隆士著
不完全競争や外部性、情報の非対称性を大学院初級レベルで解説する中級テキスト。理論と直観のバランスが秀逸。定価3,080円 str.toyokeizai.net - 『公共経済学』(麻生良文/奥野信宏/加藤寛・浜田文雅/柴田弘文ほか)
数式ベースで公共経済学を深く学びたい方に。標準的上級テキストとしてお薦め web.econ.keio.ac.jp
🏛 財政制度・公共政策設計
- 『財政学―制度と組織を学ぶ』佐々木伯朗編著
国家・地方・社会保障を貫く制度・財政組織の構造を経済学的に分析。定価3,190円 - 『公共政策学事典』日本公共政策学会編
A5判600頁超、最新の公共政策理論・手法・実務を網羅。27,500円の大型辞典 maruzen-publishing.co.jp
🔬 産業組織・イノベーション政策
- 『研究開発支援の経済学―エビデンスに基づく政策立案に向けて』岡室博之・西村淳一
R&D補助の制度設計をミクロ実証データで評価。産業政策のエビデンス志向に対応。定価4,840円 - 『産業組織のエッセンス』明城聡・大西宏一郎
GAFAや規制緩和を踏まえた現代的産業組織論を平易かつ網羅的に整理。定価2,530円
💥 創造的破壊・資本主義の制度的進化
- 『創造的破壊とは何か 日本産業の再挑戦』今井賢一
シュンペーター理論を現代日本産業に応用し実効性を検証。定価3,520円 str.toyokeizai.net - 『創造的破壊の力―資本主義を改革する22世紀の国富論』アギヨン他/村井章子訳
世界的な創造的破壊論の最前線。経済成長・不平等・雇用への影響まで学術的かつ先進的な分析。定価4,620円 str.toyokeizai.net
📚 日本経済の構造・歴史分析
- 『日本経済の死角――収奪的システムを解き明かす』河野龍太郎
日本社会・制度の構造的歪みをゾンビ企業やコーポレート・ガバナンスの視点で掘り下げた2025年刊行の新書。
📋 本一覧と価格帯
| 項目 | タイトル | 主なテーマ | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 理論編 | スティグリッツ公共経済学 | 公共財・外部性・課税 | 4,950円 |
| 理論編 | <サピエンティア>公共経済学 | 中級公共経済学 | 3,080円 |
| 理論編 | 公共経済学(麻生他) | 上級理論書 | 約4,000円前後 |
| 制度編 | 財政学―制度と組織 | 制度構造分析 | 3,190円 |
| 制度編 | 公共政策学事典 | 政策理論全体像 | 27,500円 |
| 産業編 | 研究開発支援の経済学 | R&D補助の実証分析 | 4,840円 |
| 産業編 | 産業組織のエッセンス | 現代構造分析 | 2,530円 |
| 破壊論 | 創造的破壊とは何か | 日本の再挑戦 | 3,520円 |
| 破壊論 | 創造的破壊の力 | 世界最先端論 | 4,620円 |
| 日本経済 | 日本経済の死角 | 歴史と制度分析 | 約1,400円(新書) |
これらは学術・政策・制度設計の観点から非常に充実した書籍群です。各分野でさらに深掘りしたいテーマがあれば、関連書や論文もご案内できます😊